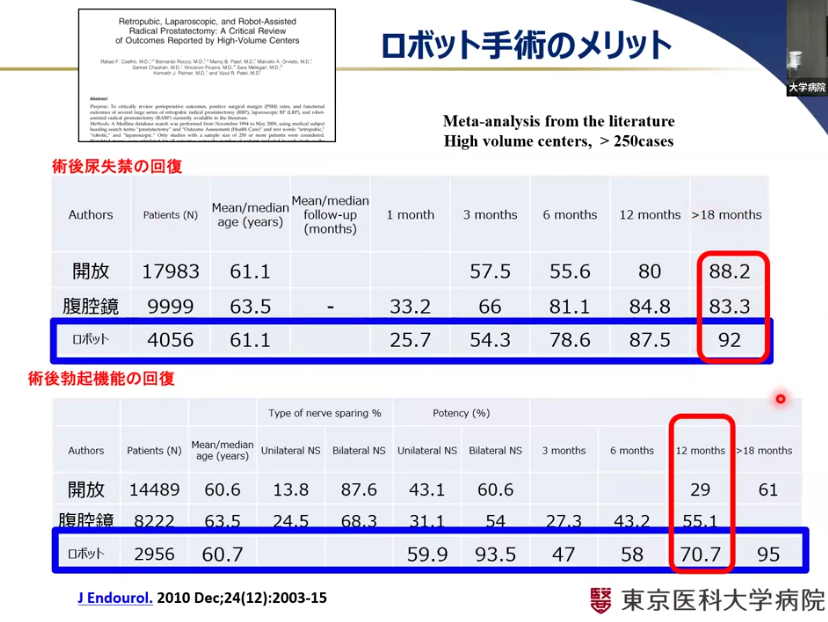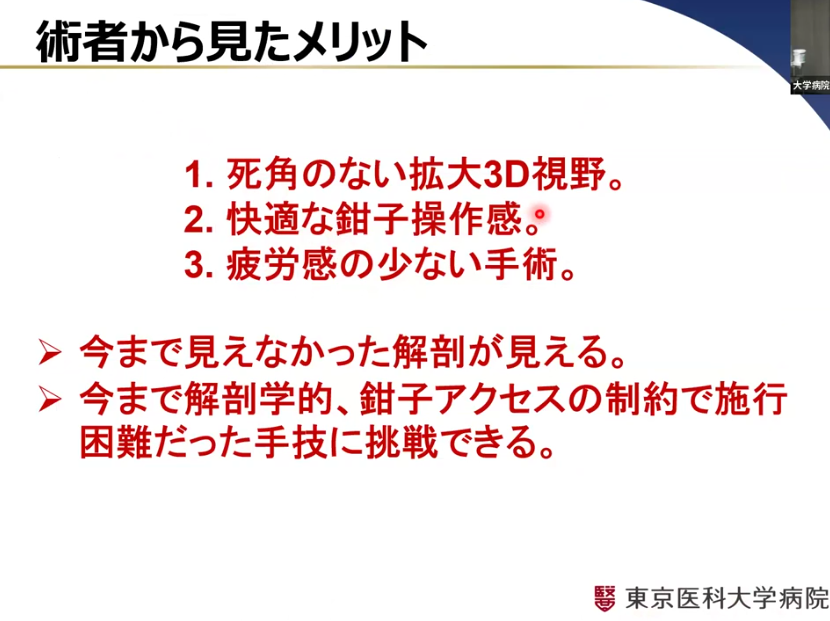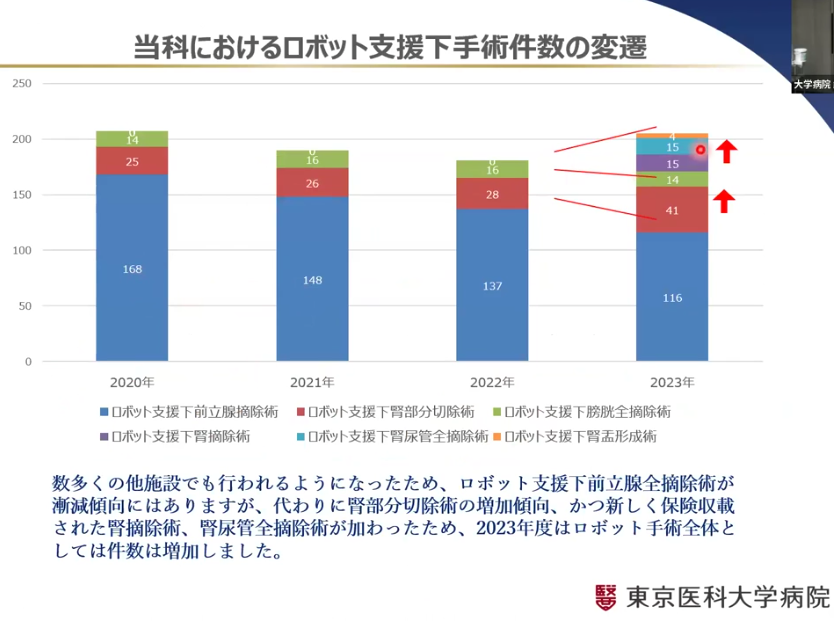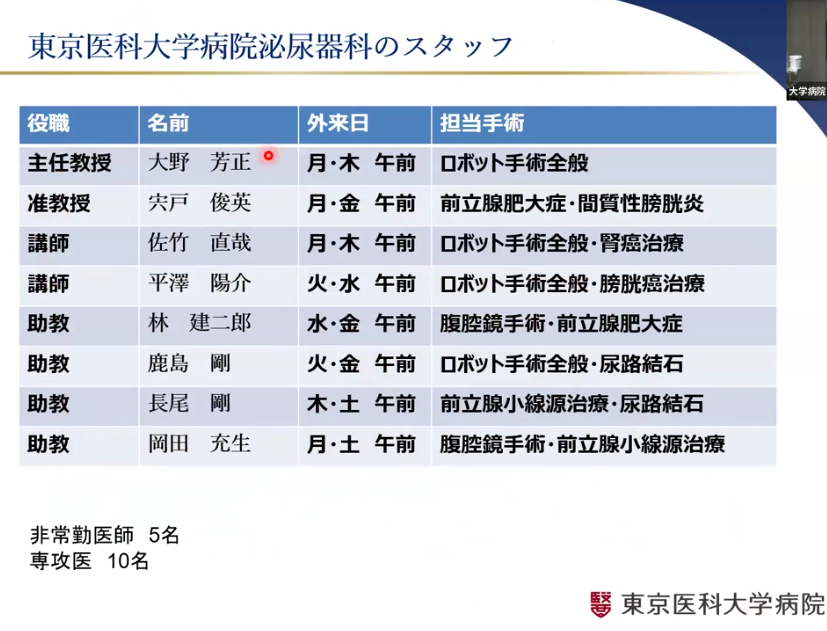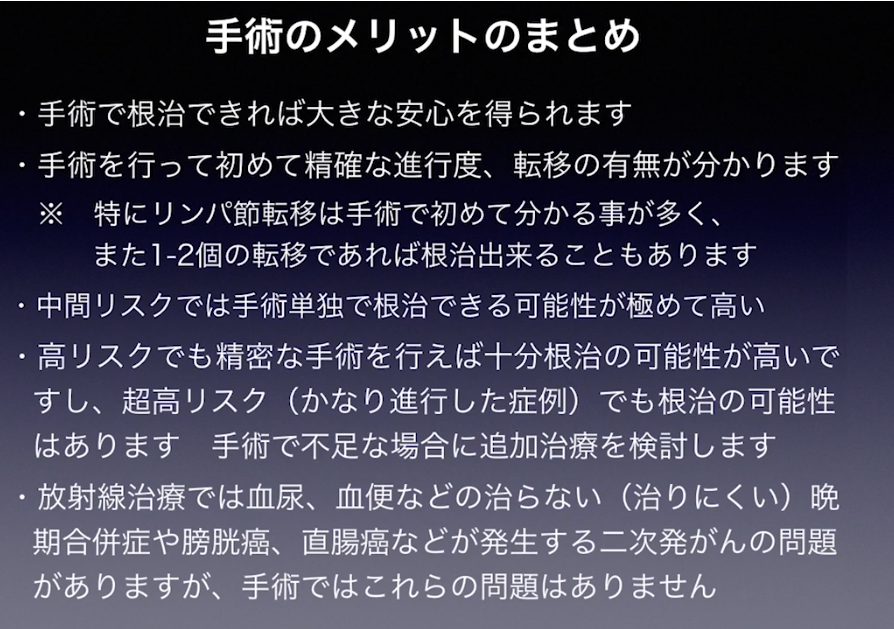
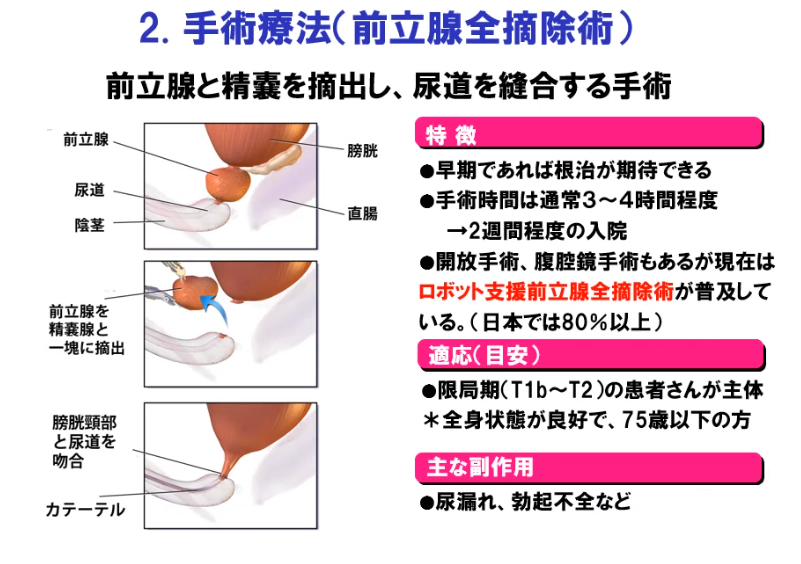
■手術の評価
・リンパ節転移
⇒事前にはほとんど分からない(手術して初めて分かる)
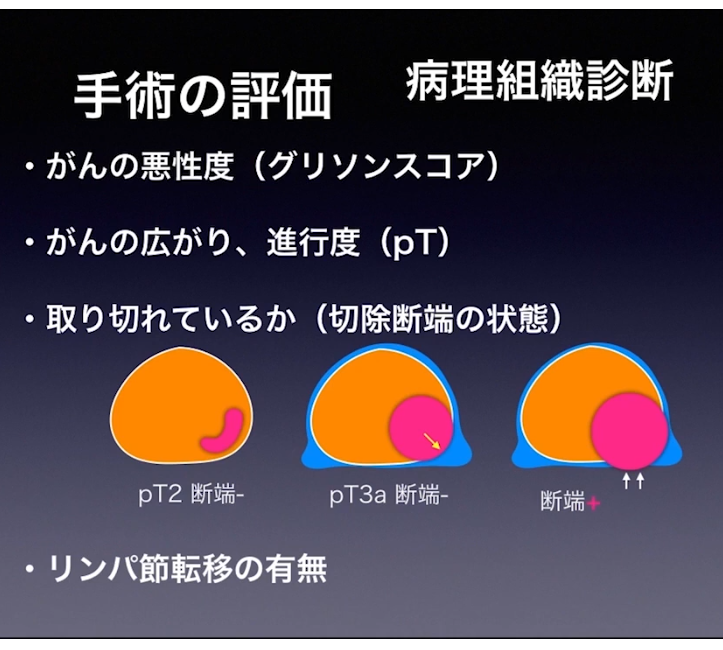
※高リスクにおけるリンパ節転移の率
⇒23.7%
※転移の平均的大きさ:1.8mm
⇒大半のリンパ節転移をCT検査で見逃している(再発因子)
※CTでは8mm以上でないと映らない
■追加治療
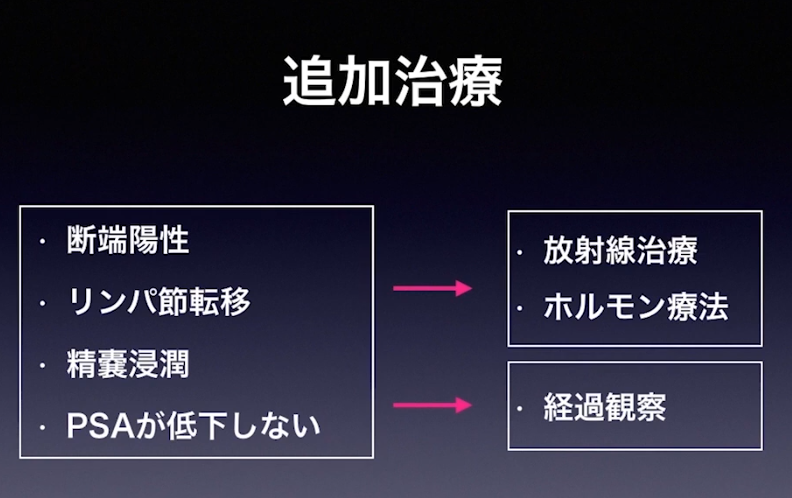
・術後のフォローアップ
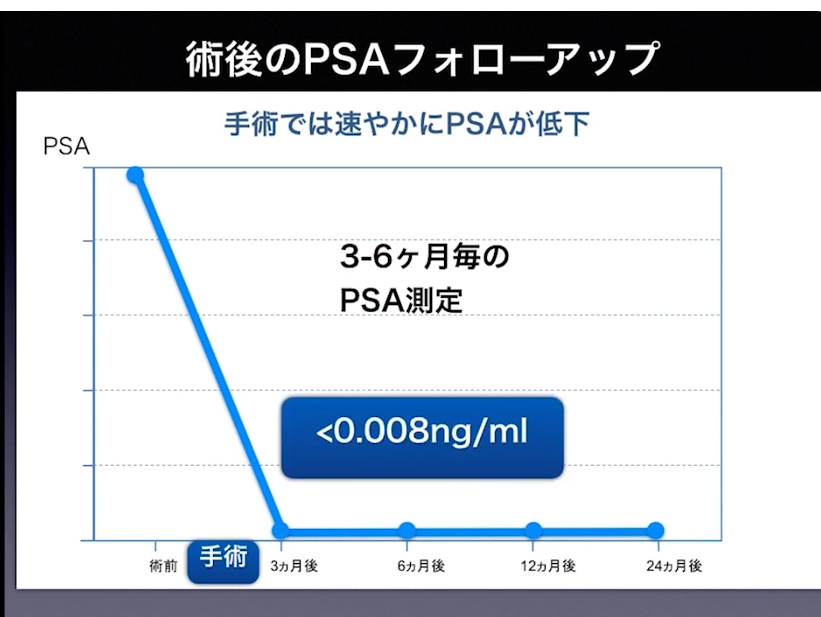
・再発
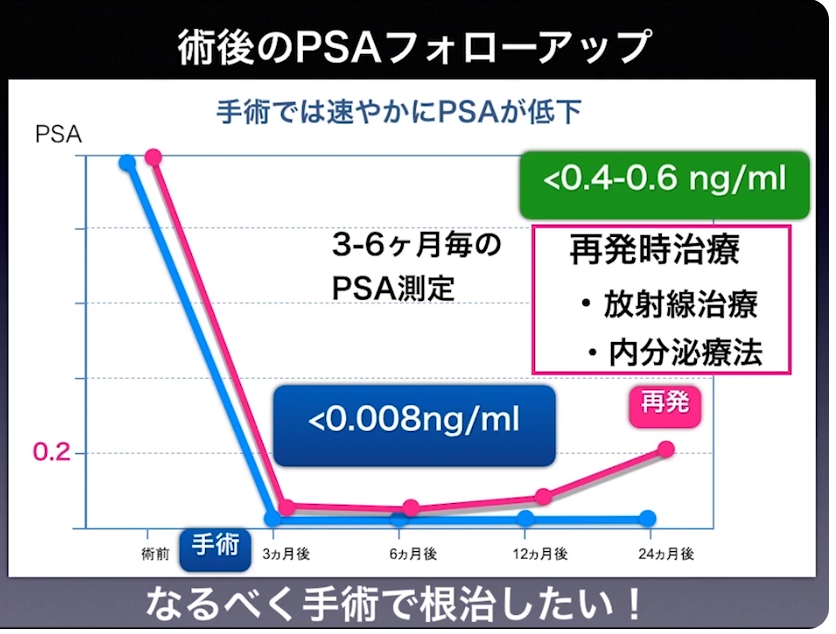
・まとめ
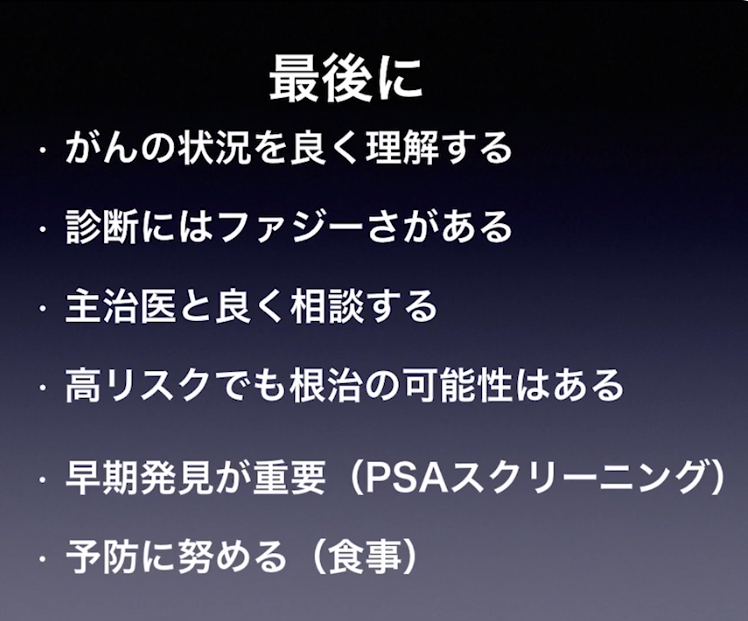
■PSA検査から確定診断・手術選択の流れ
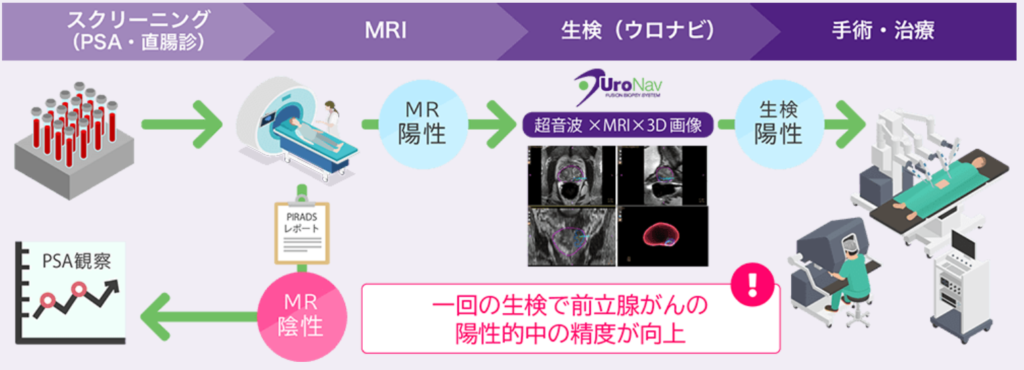
・MRI/超音波融合生検
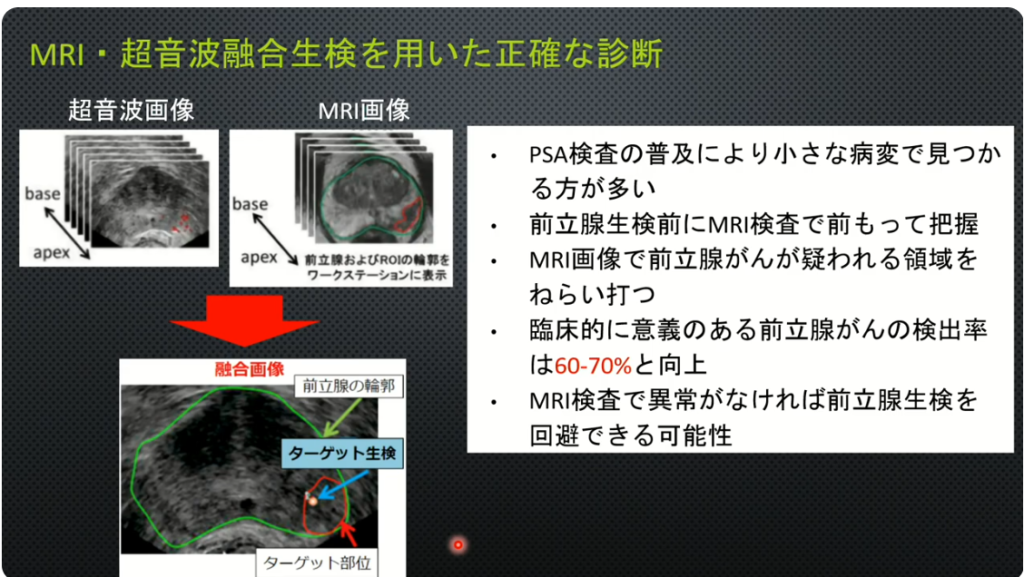
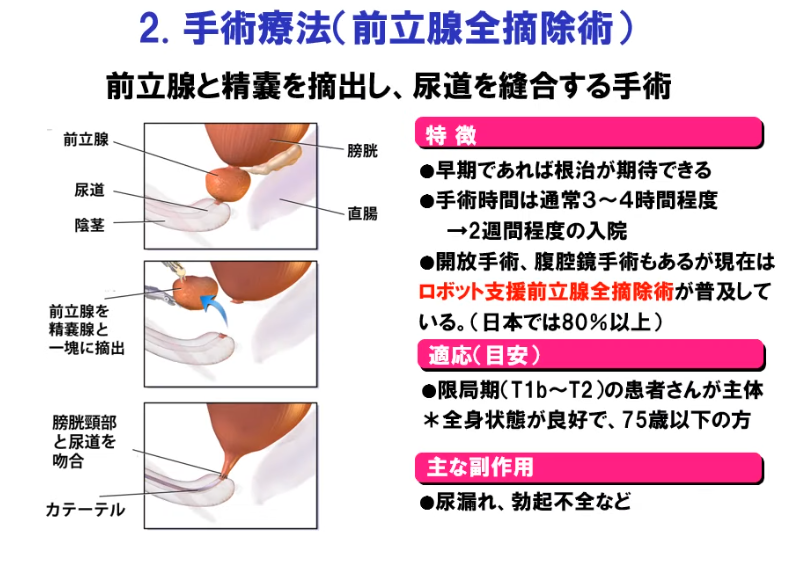

■手術の質の評価項目
■切断断端(断端陽性率)
・pT2の場合:断端陽性は-
※但し、手術ミスでガン細胞領域を斜めに切除すると
⇒断端陽性は+になる
⇒pT3の場合:断端陽性は-と+(膜外浸潤部位)の混在
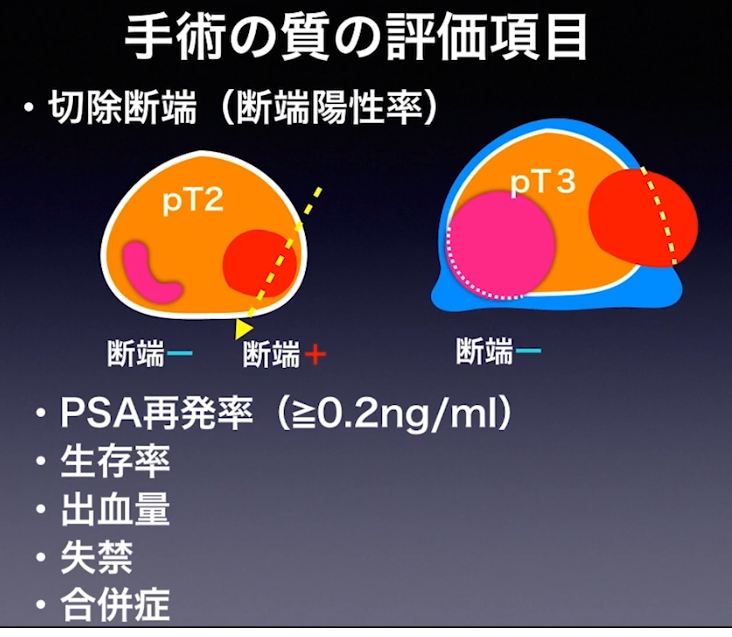
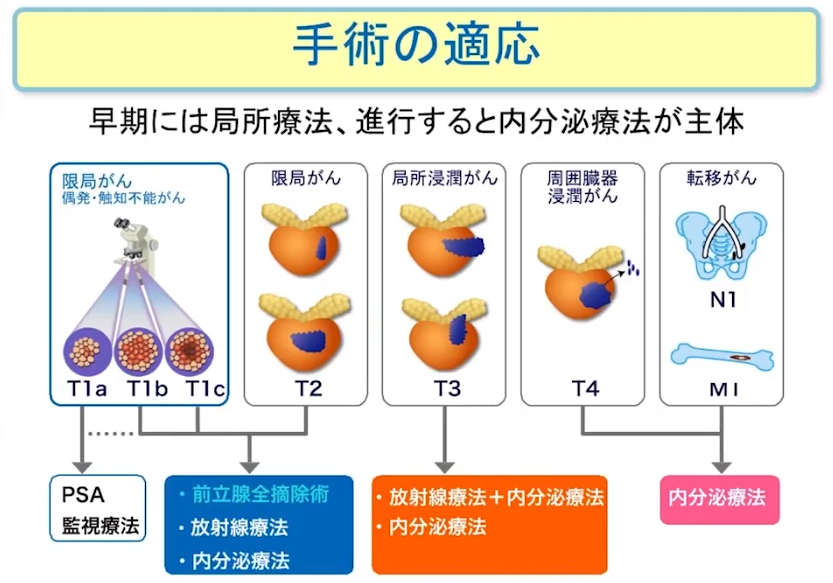
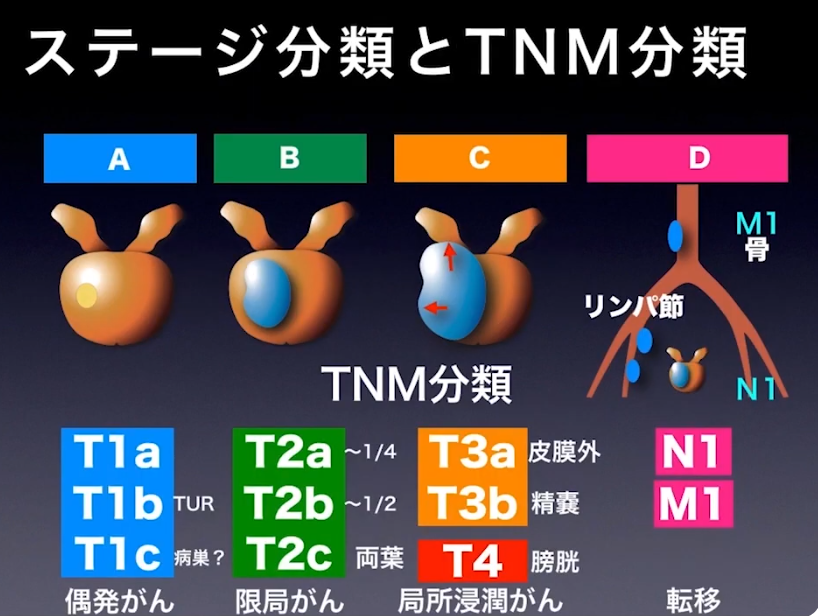

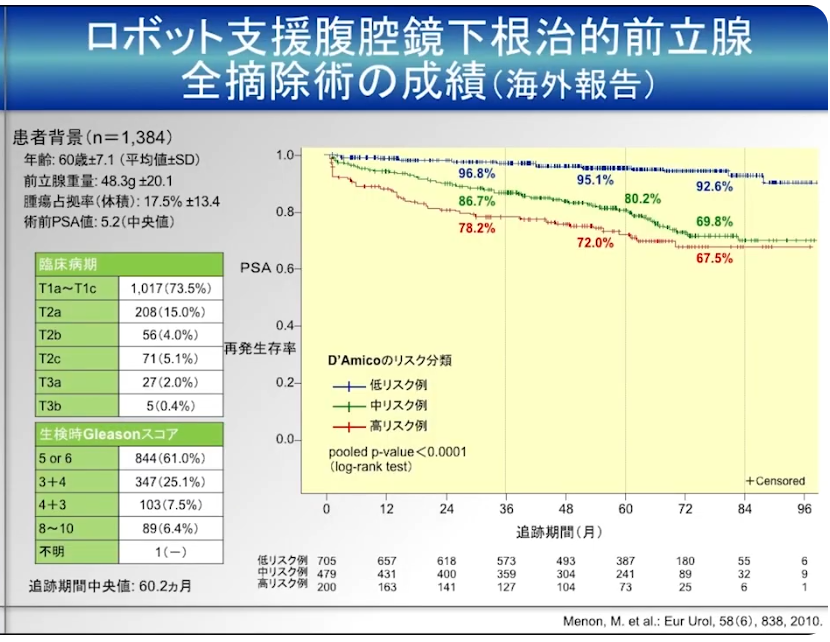
■ロボット支援下手術
※手術時に病院の設備仕様により
⇒MRI/超音波融合生検時のデータとの同期の有無の差はある

■再発(PSA値上昇)を意識して確定診断を行う
・PSMA-PET(保険外診療:自己負担/¥30万円程度)
⇒小さな病変を検出できる
⇒具体的な行動・意識決定が出来る
※CT、骨シンチでは検出できない小さな病変
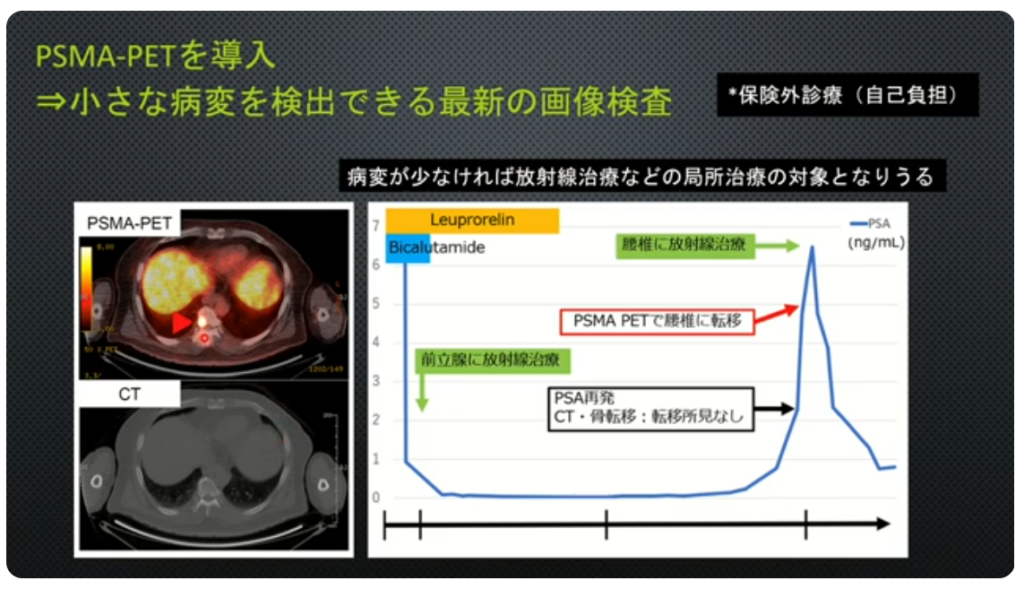
・前立腺特異的膜抗原
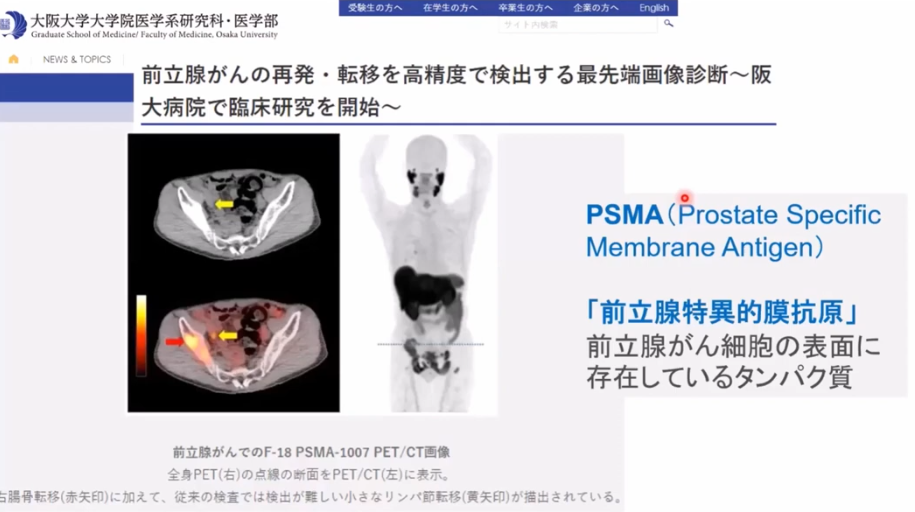
■PSMA-PET検査
・初期病気診断をより正確に
⇒再発部位をより正確に診断
・PSMA-PETによるPSAの値<0.5未満
⇒再発の発見率:約40%
注:再発の閾値(手術:0.2,放射線:2.0)
※PSMAーPETとは前立腺ガン特異タンパク質を検出するPET検査
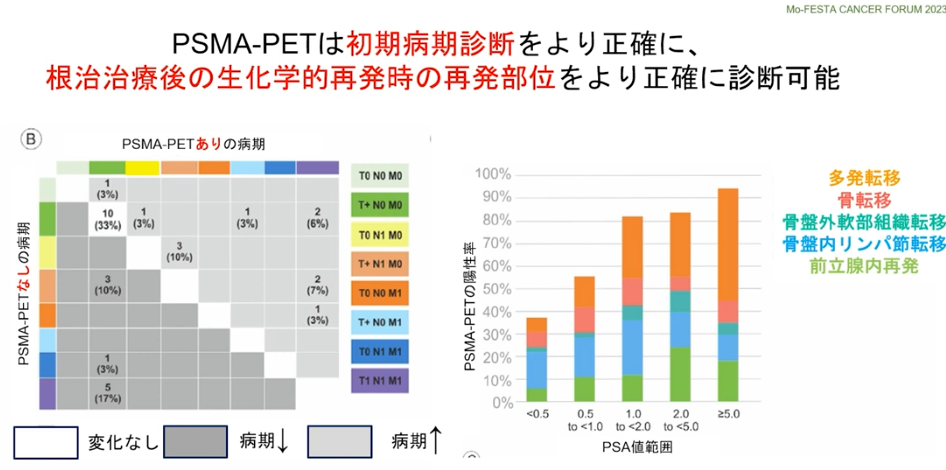
・事例
・CTではリンパ節転移が発見できず
⇒PSMA-PETでは矢印部の転移部位を発見
※全医者が待ち望んでいる検査
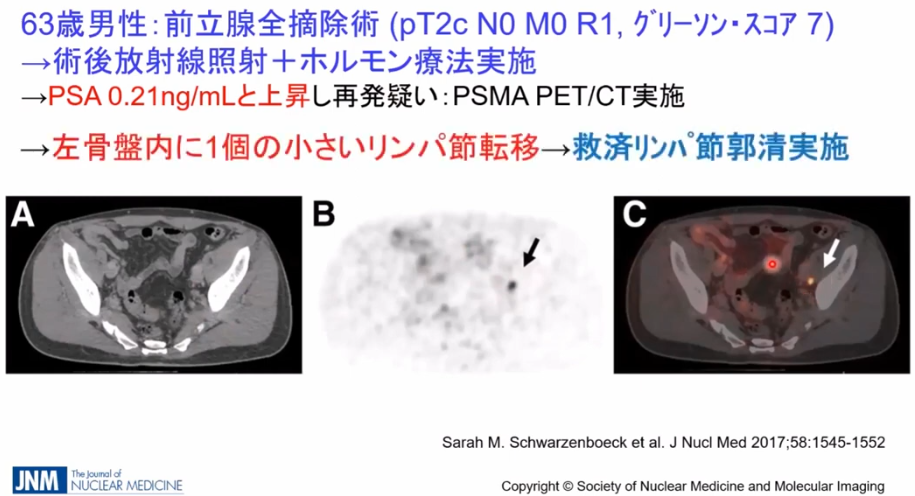
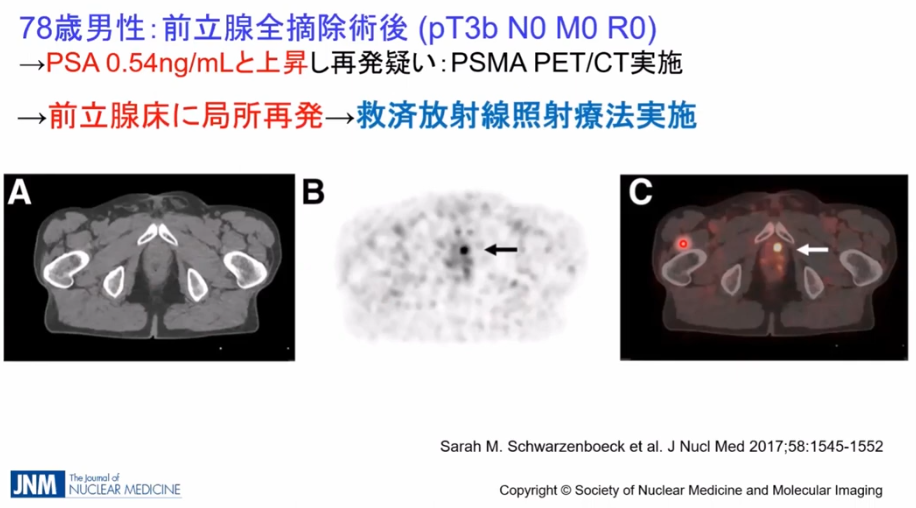
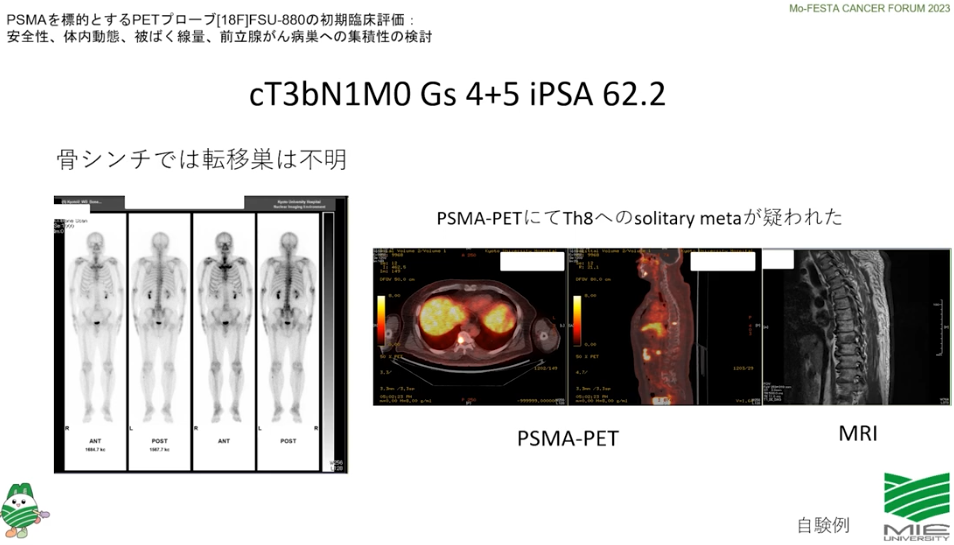
■放射線治療の選択肢が取れる
・ガン細胞の部位が特定できる
⇒ガン細胞の部位が特定できなければホルモン療法になる
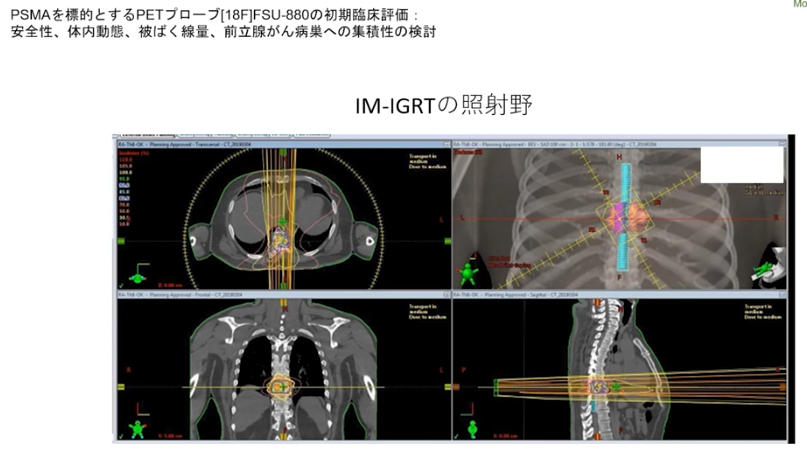
■手術後の補助放射線療法 vs 早期救済放射線療法 ランダム比較調査
・差は無かった
⇒PSAが上昇してきたら治療するとなっているが
⇒参加者に特性が雑多(放射線治療を必要とする/しない)な為
⇒整理された患者特性で比較調査する必要がある
※このランダム比較調査は海外の事例である
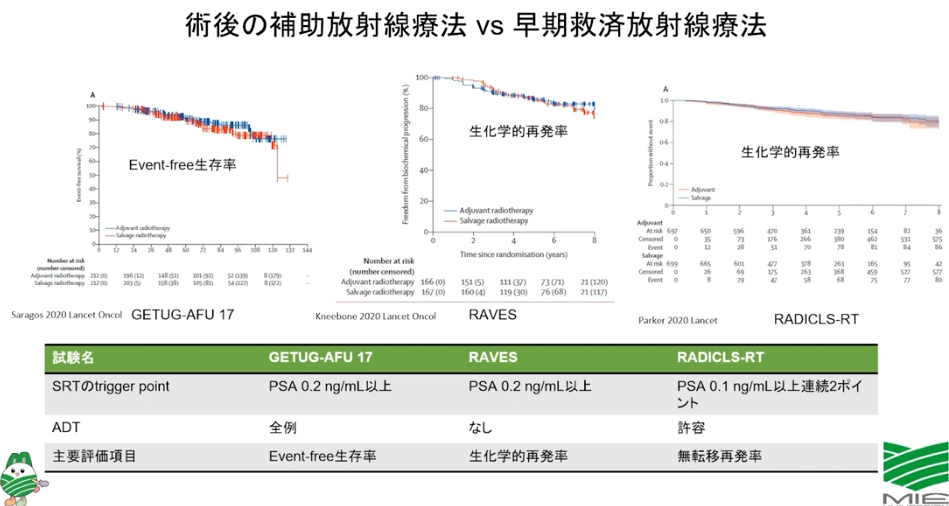
■手術:前立腺全摘術
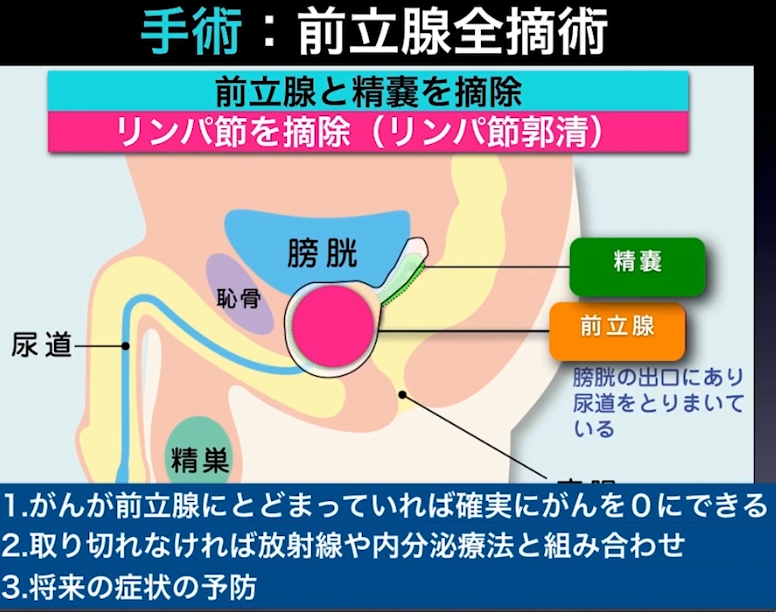
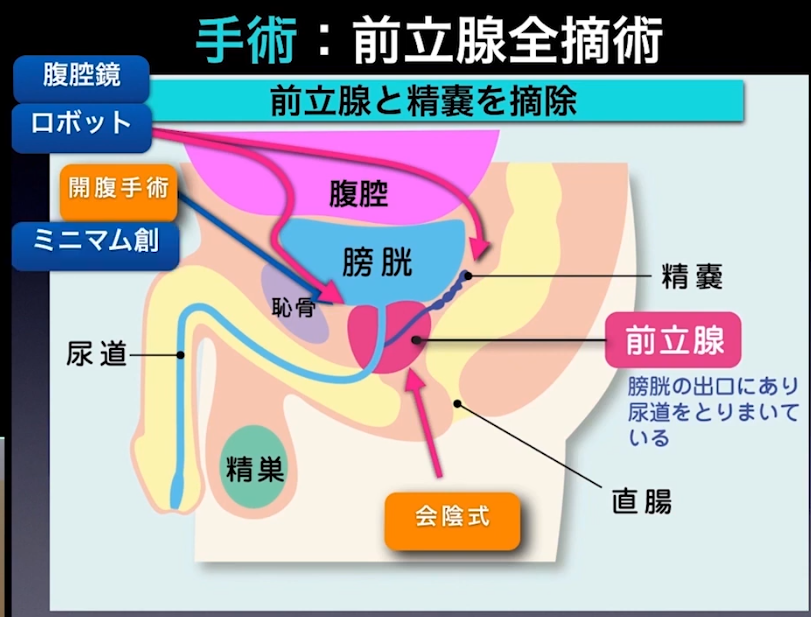
■生検による高リスク前立腺ガン評価格差
⇒診断医間格差
⇒生検の再現性
※ダウングレード、ダウンステージもあり、
一方、リンパ節転移が隠れている
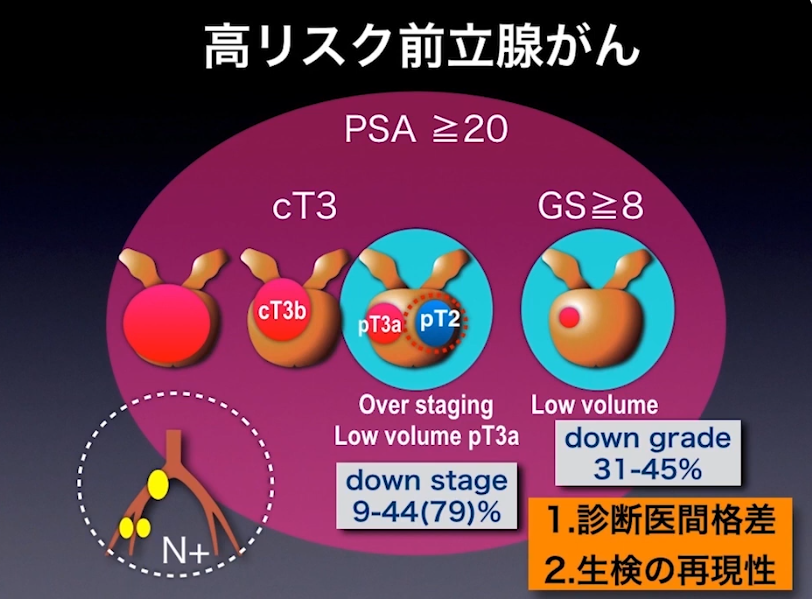
■治療方針
・高リスク・超高リスク
⇒拡大郭清(リンパ節転移を取り除く)を行うべき
※日本では医者まかせ
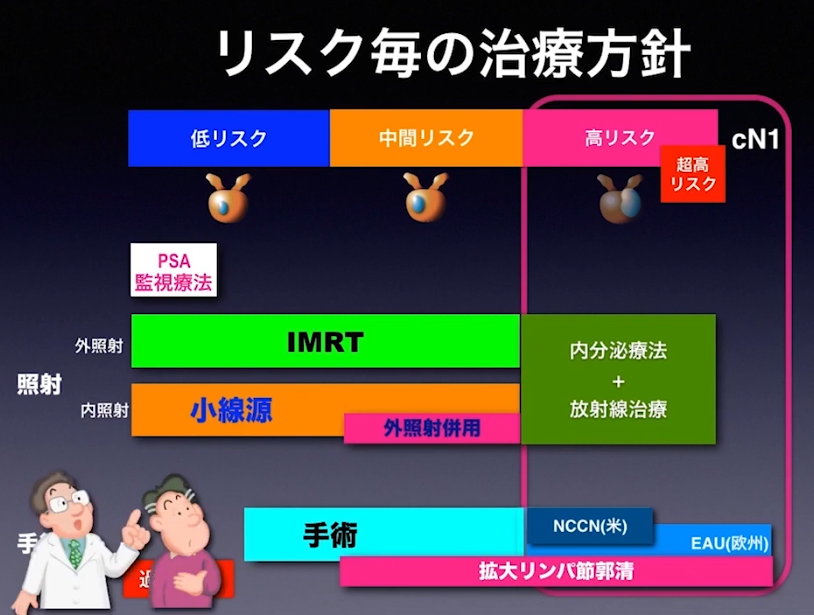

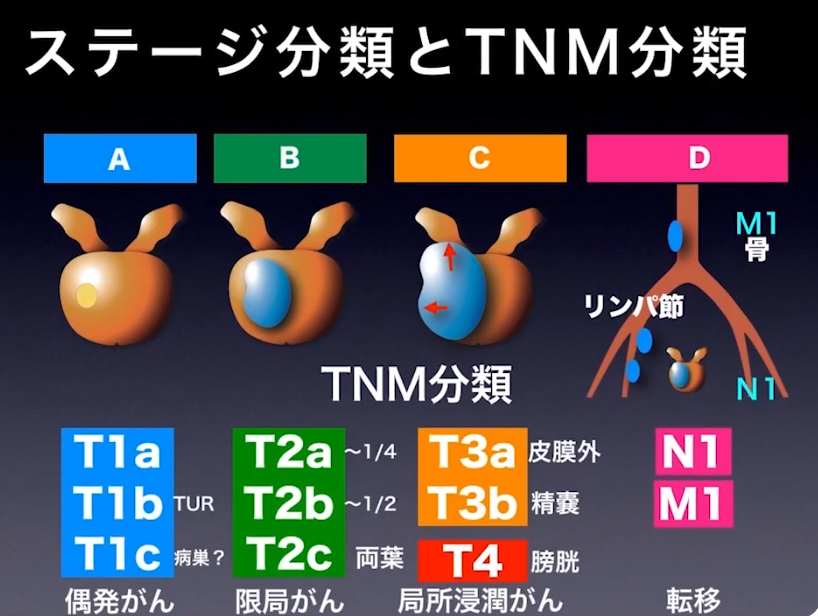
■中間・高リスク(cN1まで)の手術(再発リスクの低減を願い)
・拡大リンパ節郭清は行われるべき
⇒主治医に手術前に確認すべき
⇒医師によっては限局リンパ節郭清だけにしているケースもある
※高い手術スキルがないと拡大リンパ節郭清ができない
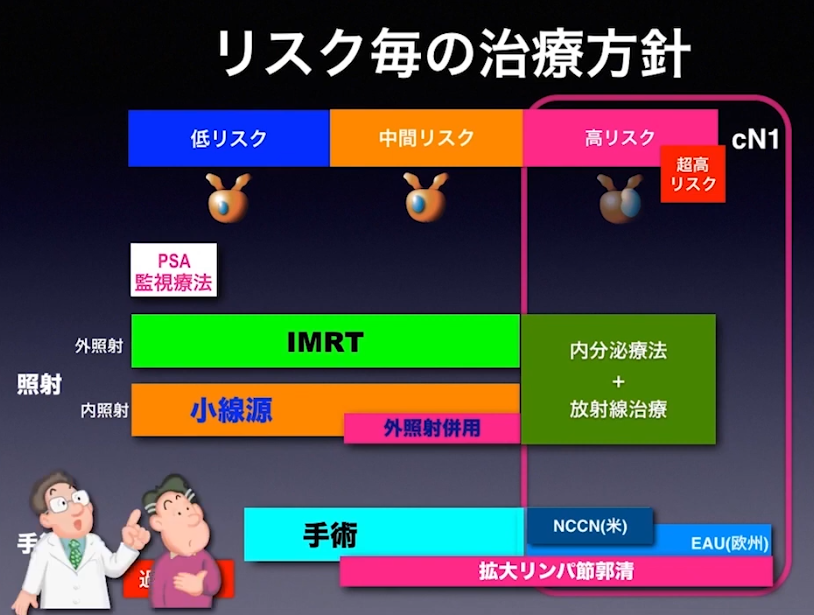
※診断の問題点・治療の問題点を含めて主治医と要確認が必要だ
※高リスクにおけるリンパ節転移の率
⇒23.7%
※転移の平均的大きさ:1.8mm
⇒大半のリンパ節転移をCT検査で見逃している(再発因子)
※CTでは8mm以上でないと映らない
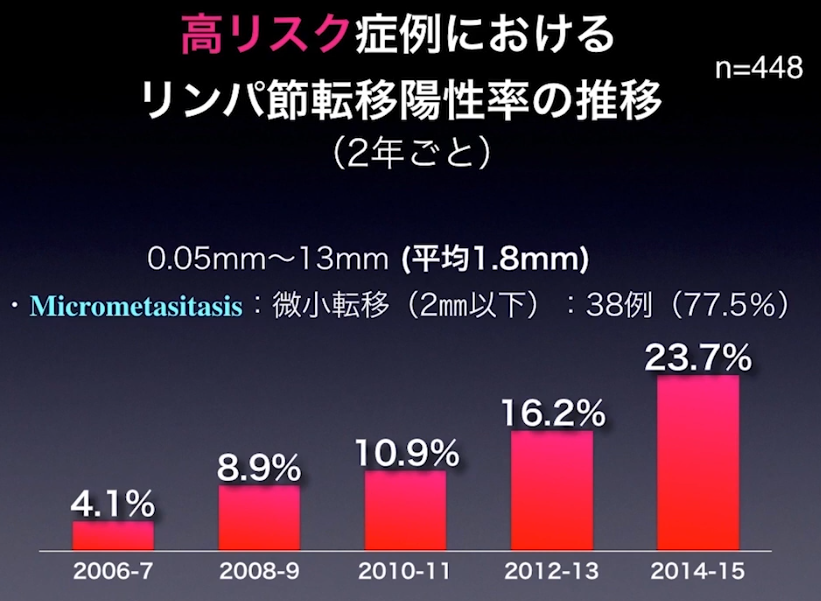

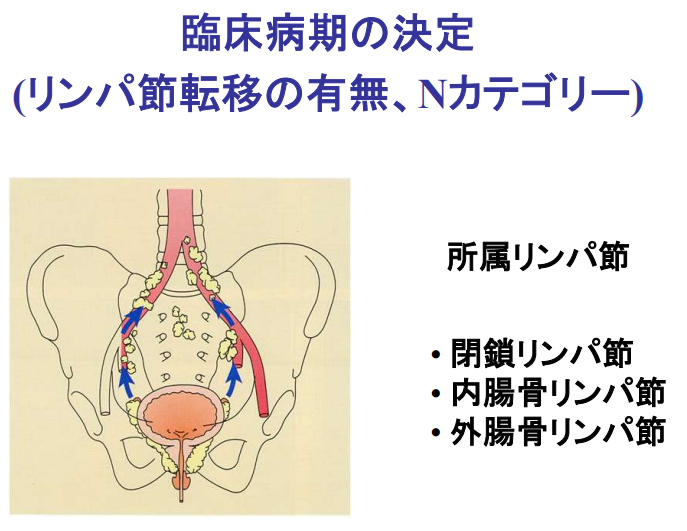
■リンパ節郭清
・拡大郭清すると40個も発見
・転移性陽性率の推移
⇒15.8%(2015年)
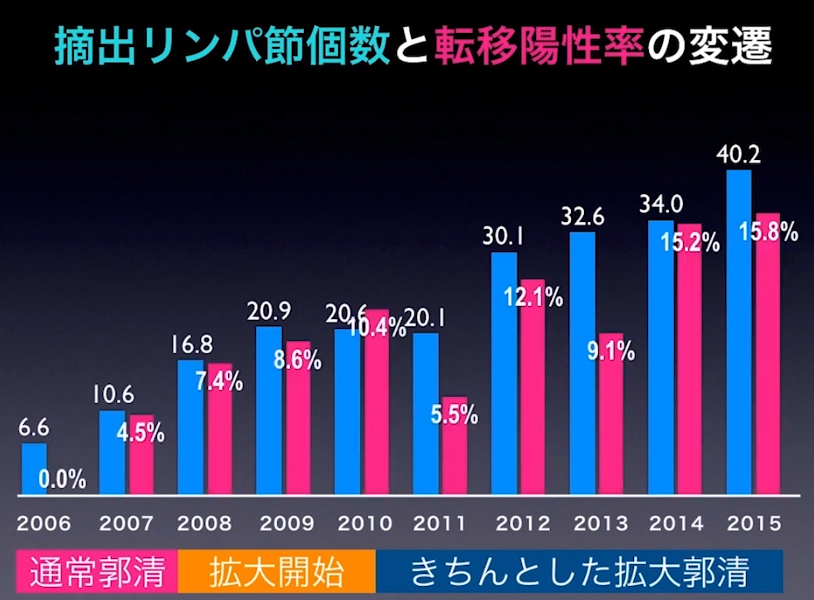
・低リスク以外は
⇒骨盤リンパ節郭清を多くの場合に実施(ミニマム創)
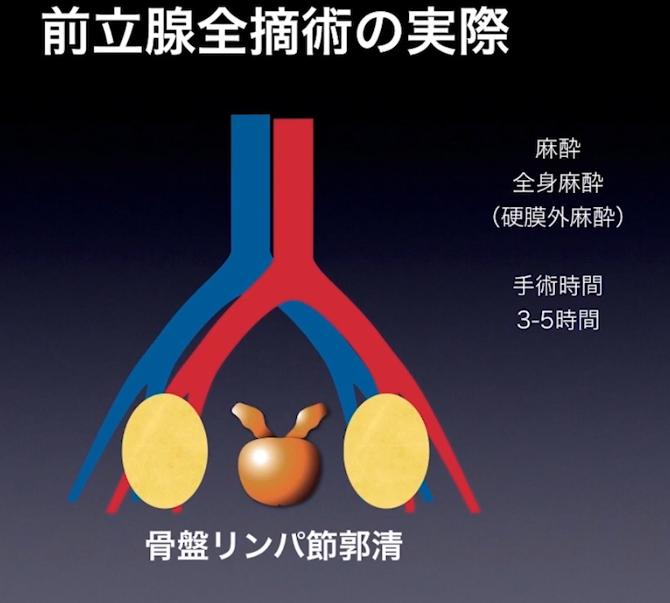
・手術のステップ(概要)
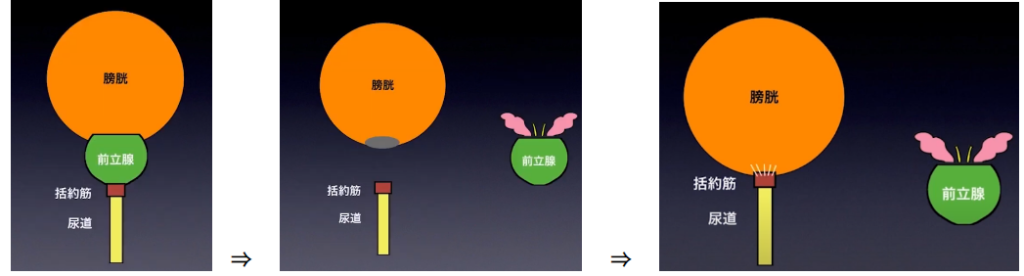
・前立腺の手術は難易度が高い
⇒高いスキルが求められる(多くの経験も含む)
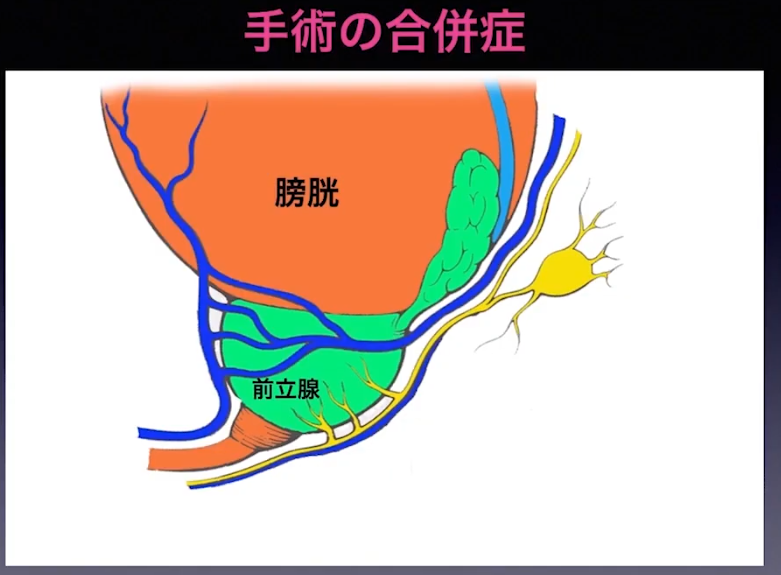
・多い出血の中での手術
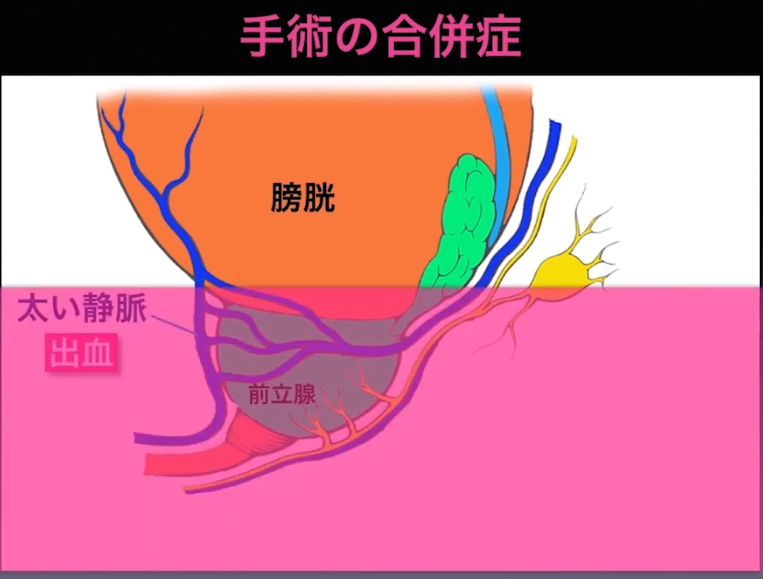
・手術の合併症
⇒根治性と機能温存の両立が難しい
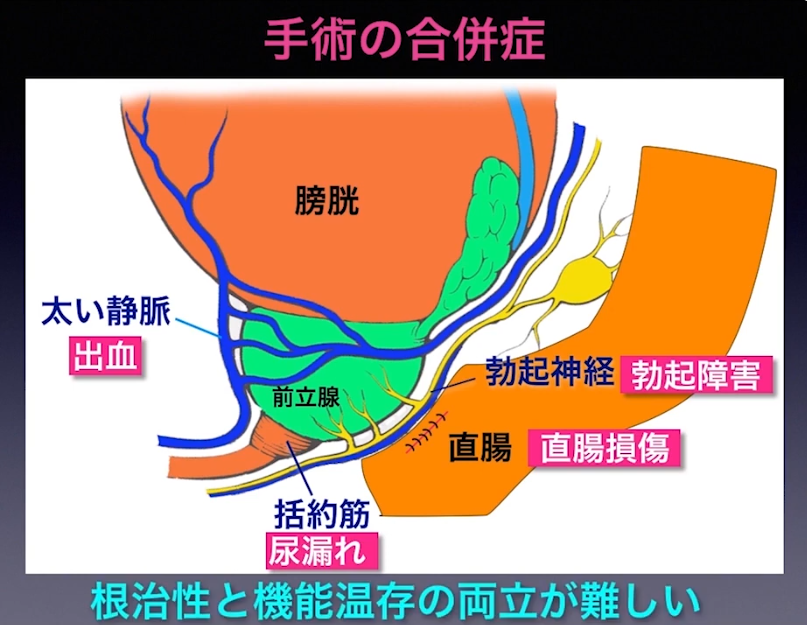
・神経温存術
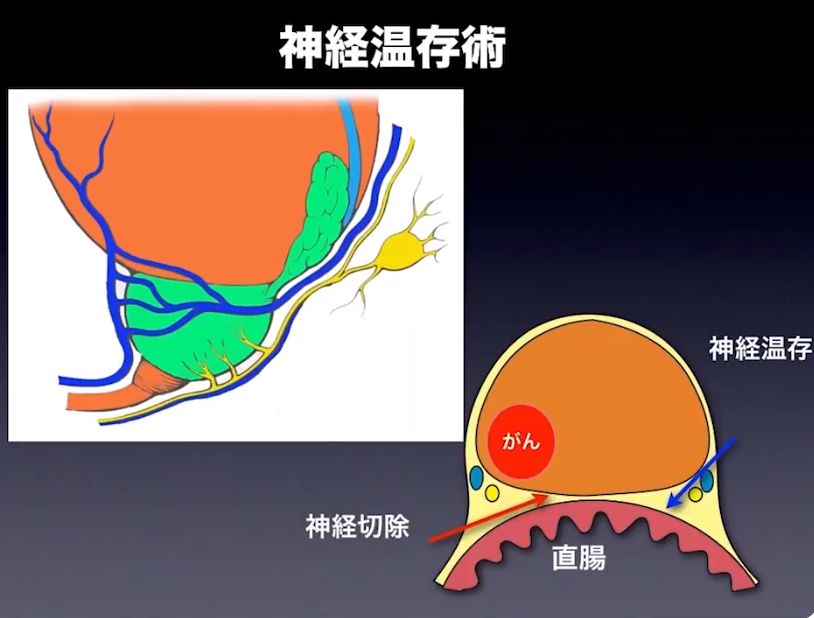
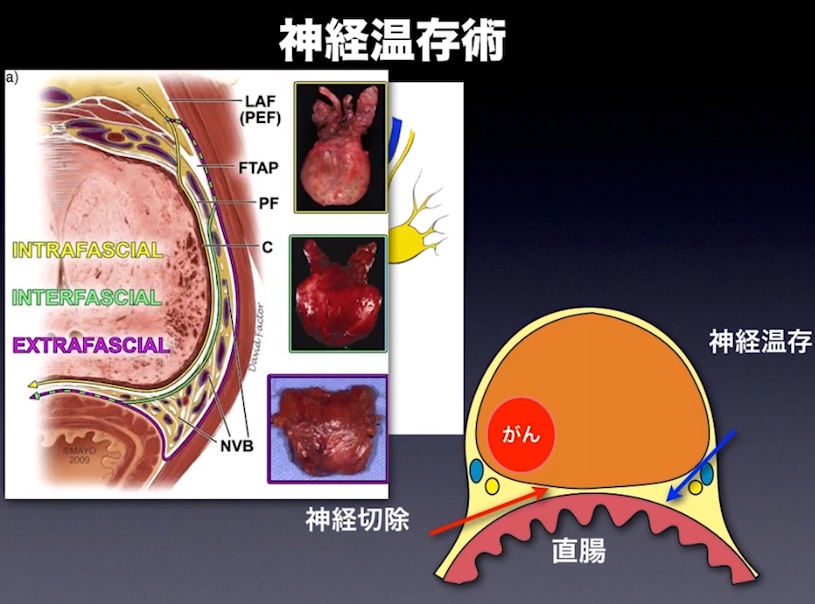
・勃起神経の温存パターン
⇒ガン細胞が占める領域によって
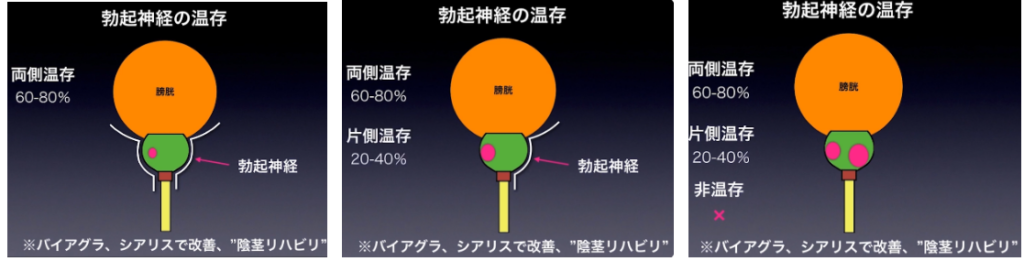
・勃起神経の走行(シート状)
※動画にて詳細に説明されている
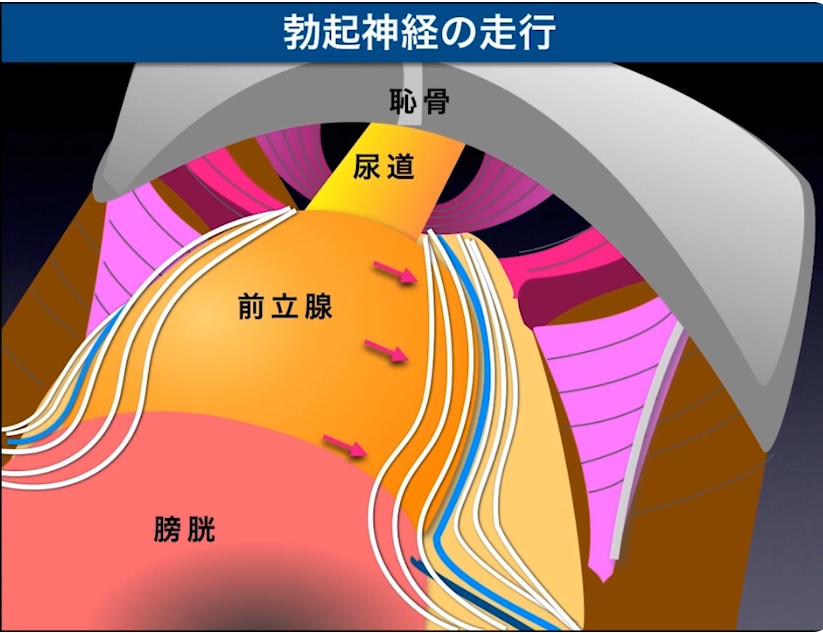
■施設間、術者間で成績の差が大きい(手術方式・病院の選択)
<<事前確認項目>>
・根治性
⇒断端陽性率、再発率
・出血量
⇒輸血の有無
・神経温存の成績
・失禁の割合
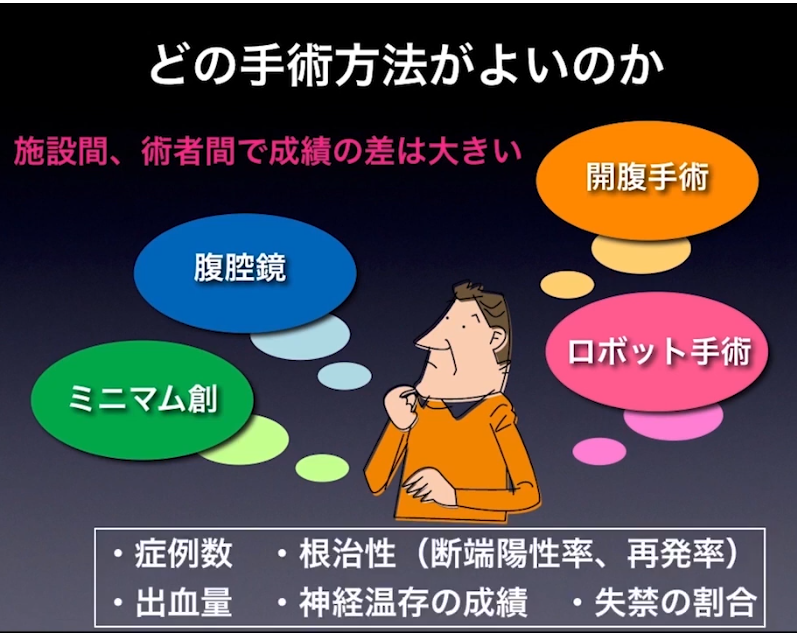
・ミニマム創手術の専門家(熊谷総合病院 泌尿器科 川島清隆氏)
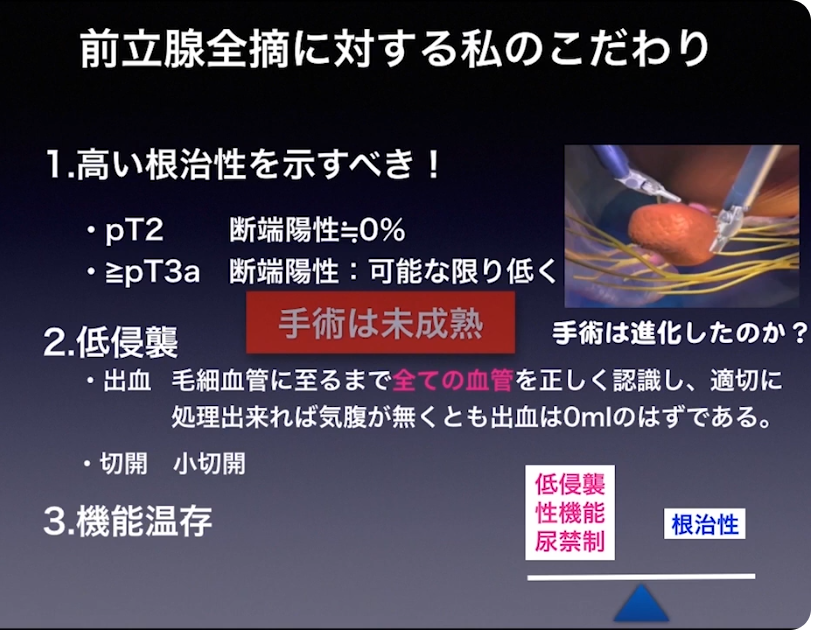
・NCCN(全米総合がん情報ネットワーク)ガイドライン2017
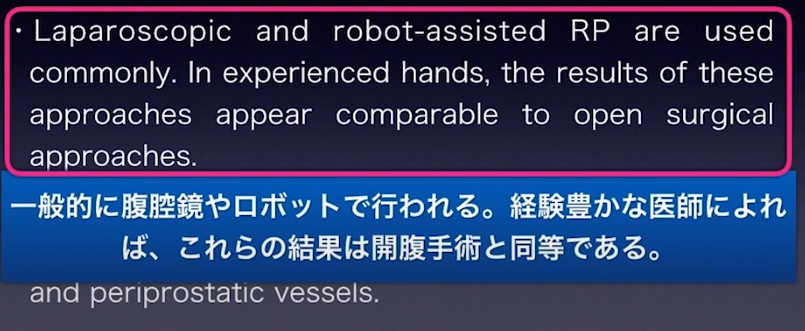
・合意できない内容(熊谷総合病院 泌尿器科 川島清隆氏)
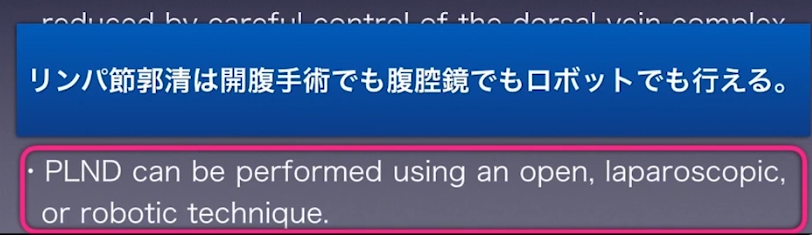
・豊富な経験・熟練の医師を見つけるは至難の業
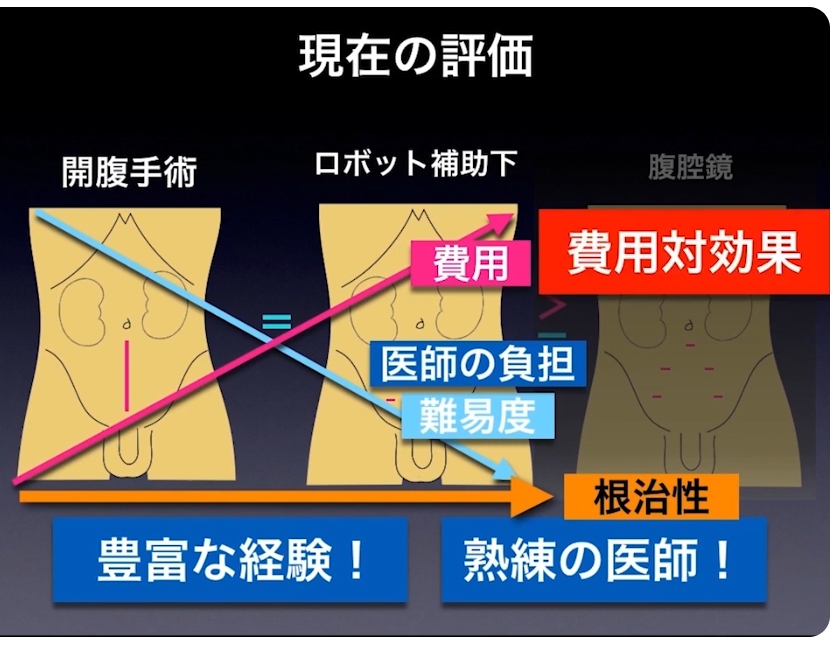
■根治の難しさ
・拡大リンパ節郭清を含めて手技に依存
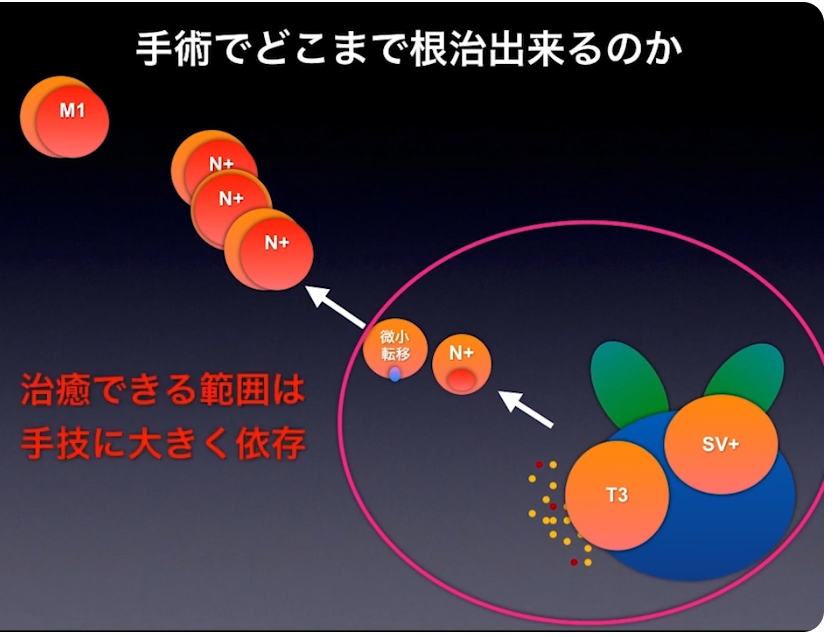
■拡大リンパ節郭清
⇒大変な手術(行われ無い事が多い)
⇒しっかりやらないといけない(根治を目指して)
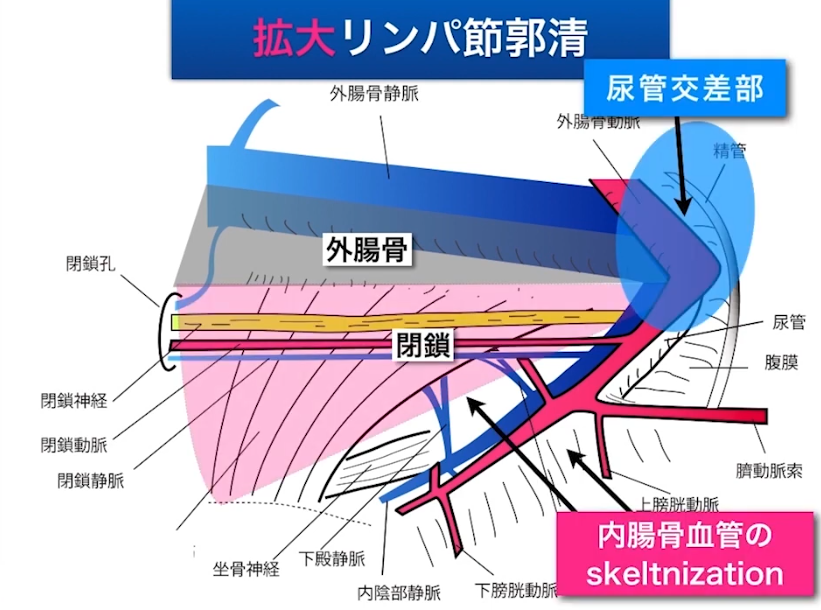
・内腸骨
⇒頻度が多い部位
⇒非常に郭清が難しい
※実際の手術しているシーンとその詳細な内容が説明がされている
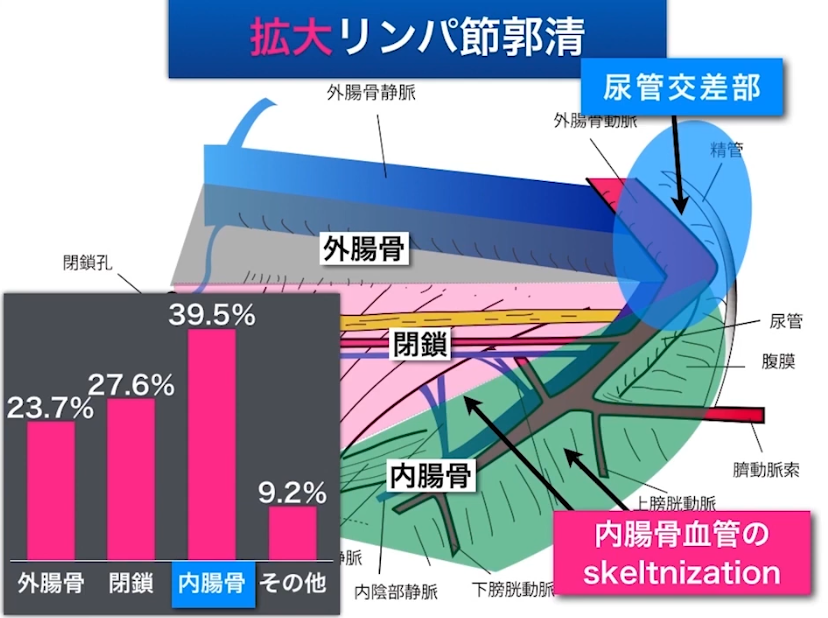
・前立腺周囲の血管の出血を抑える
⇒赤の点線の3箇所
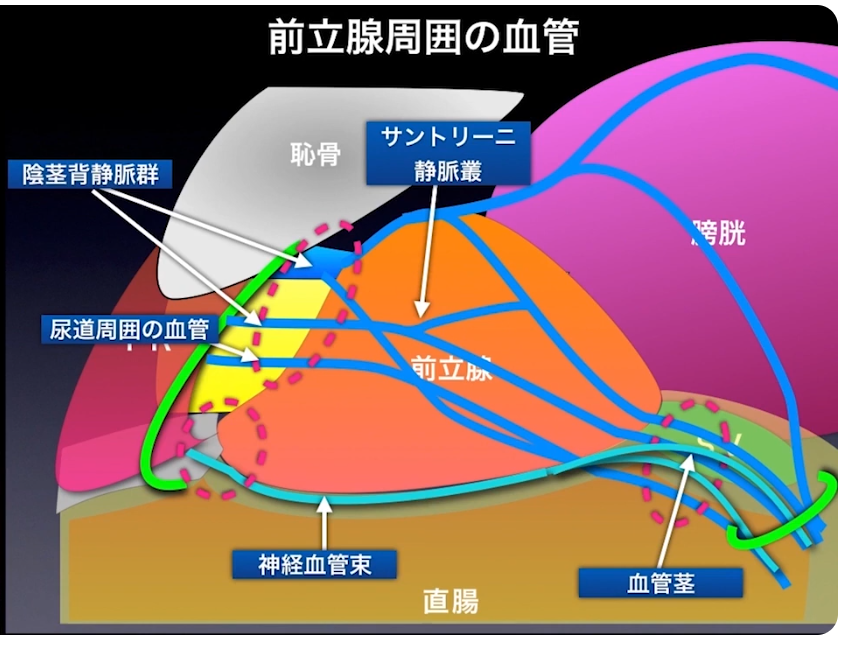
・手術方法(ロボット)
⇒逆行性
⇒順行性
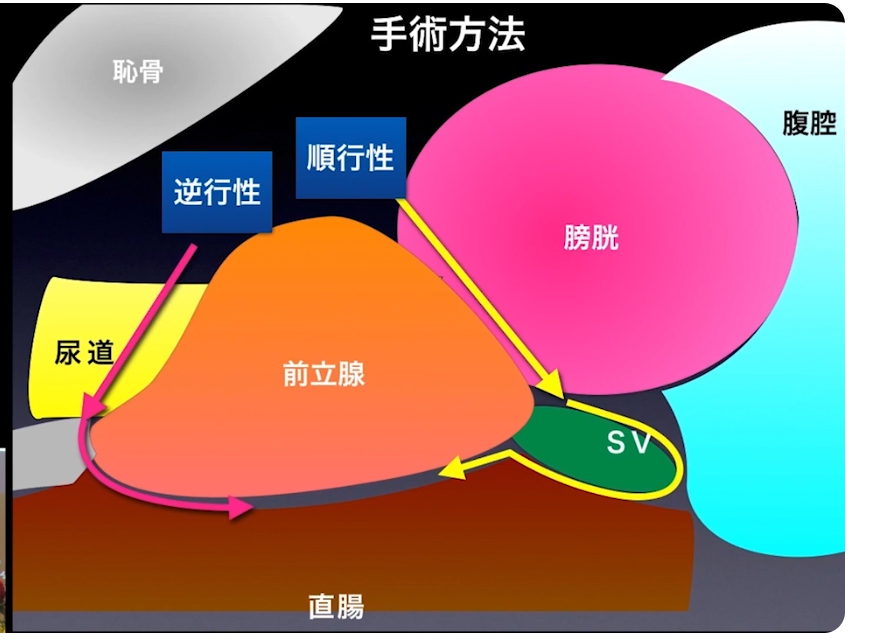
・ミニマム創手術
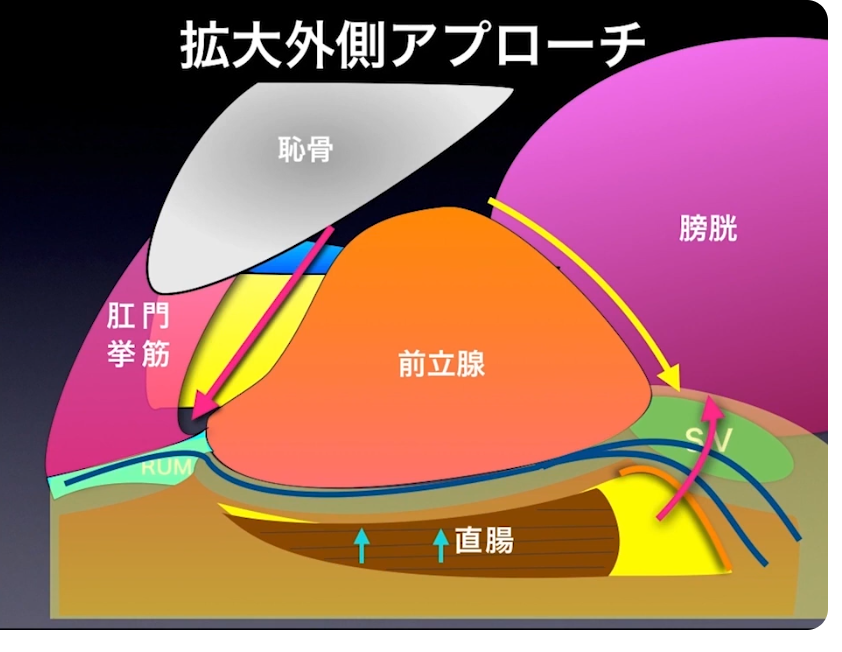
・直腸との間の剥離
※実際の手術しているシーンとその詳細な内容が説明がされている
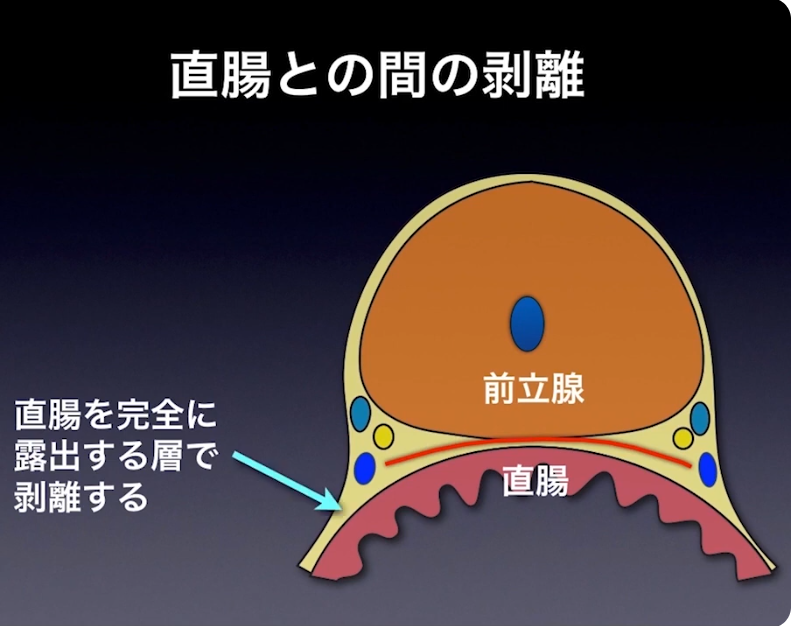
■尿道切離
・ガン細胞が尿道から離れていると
⇒機能温存ができる
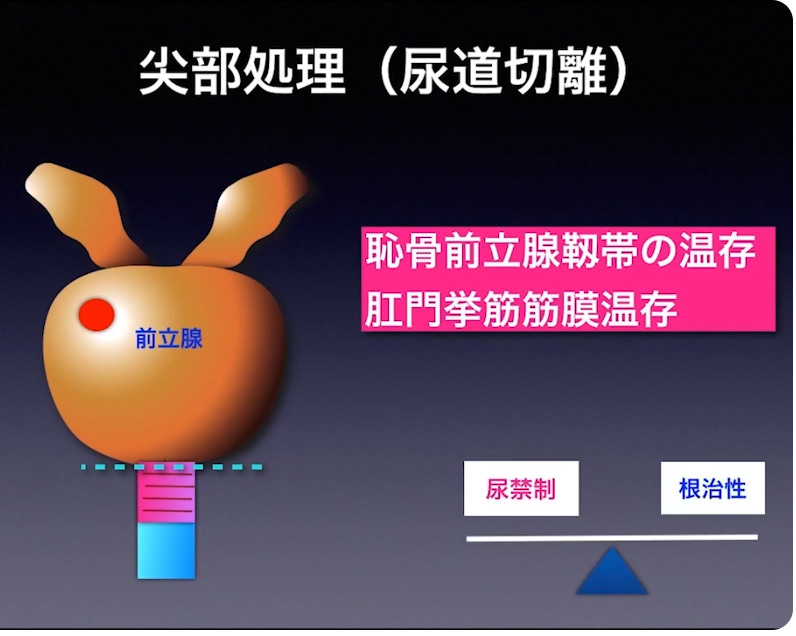
・ガン細胞が尿道から近いと
⇒血管や神経、膜が廻りにあり
⇒回りがよく見えなくなる
⇒見ないで手術するのは難しい
※実際の手術しているシーンとその詳細な内容が説明がされている
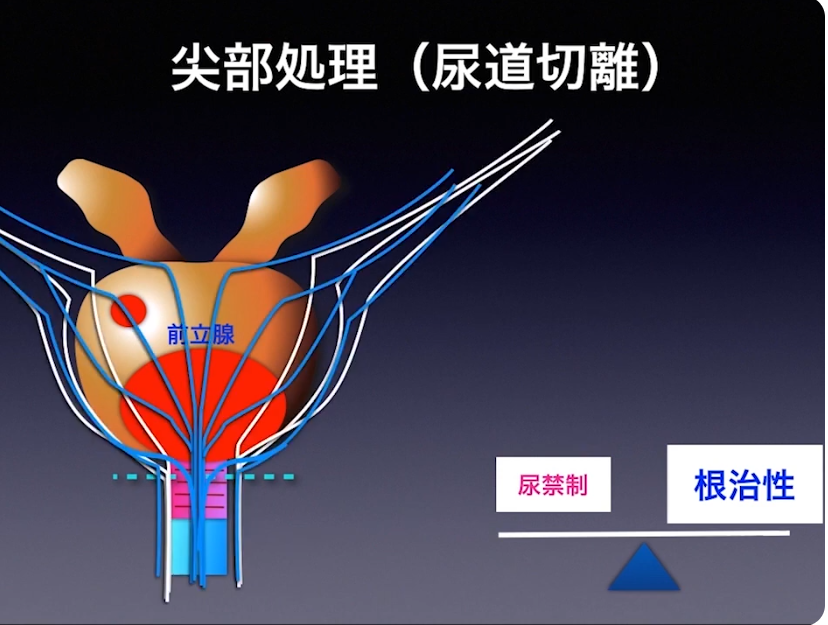
↓
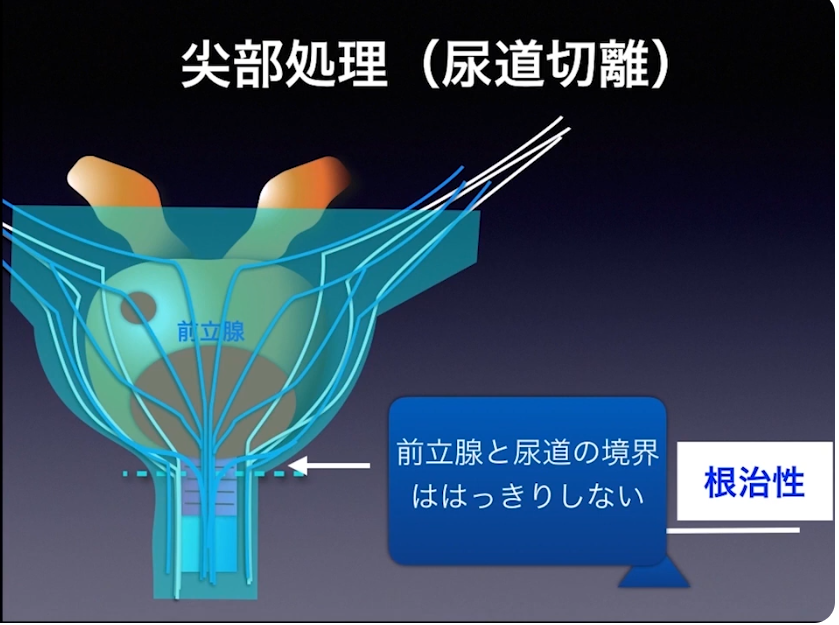
↓
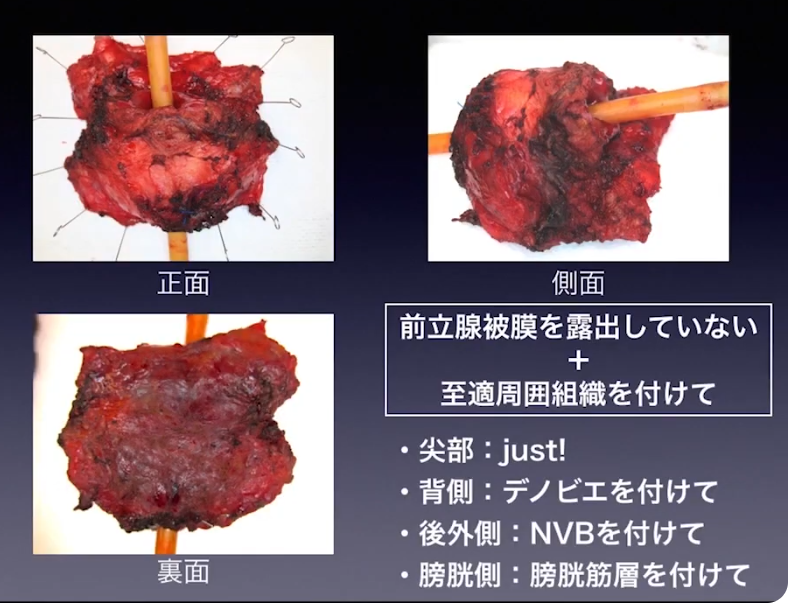
・出血量(ミニマム創手術)
⇒中央値で88㏄(2017年時点)
⇒輸血はしない
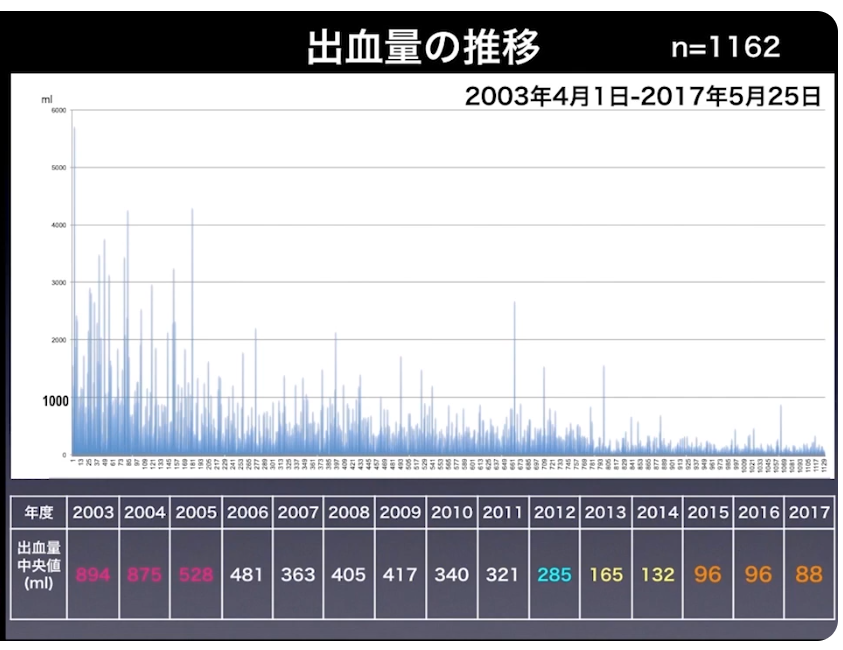
・pT3以上、断端陽性率(RMI)の推移
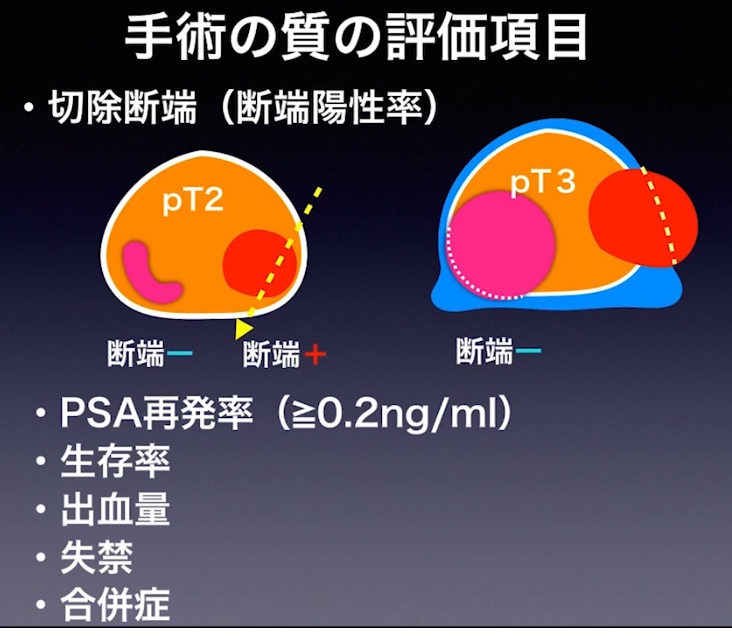
・手技(ミニマム創手術)が安定してきた期間(白枠)
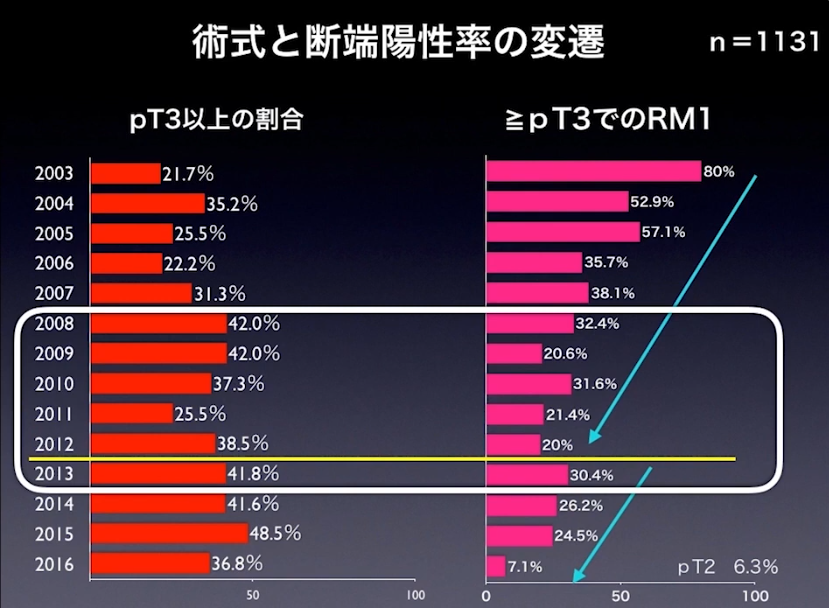
・同期間の再発率の推移(ミニマム創手術)
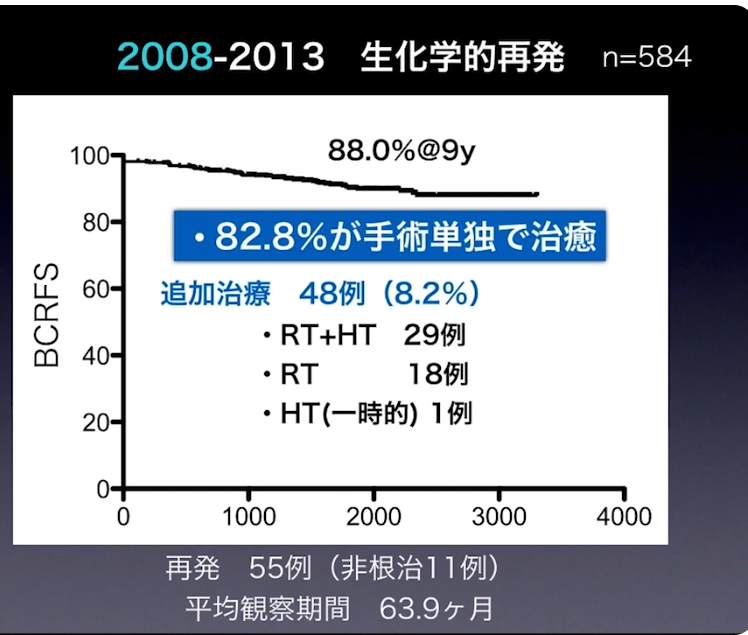
・リスク別比較推移(ミニマム創手術)
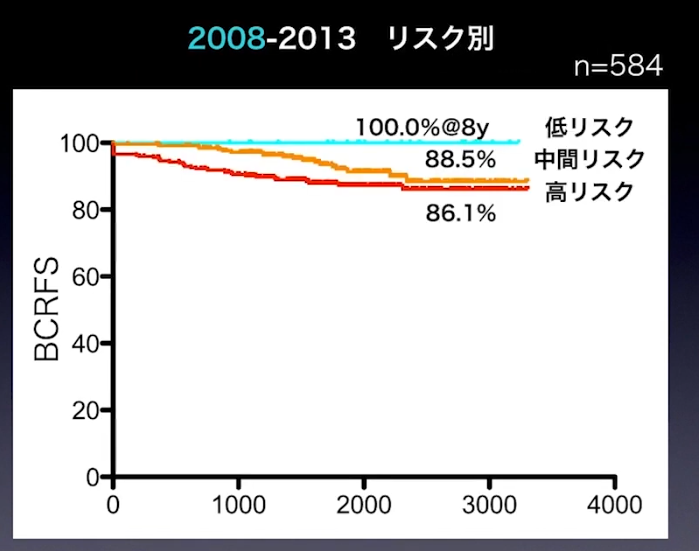
・尿禁制の推移(ミニマム創手術)
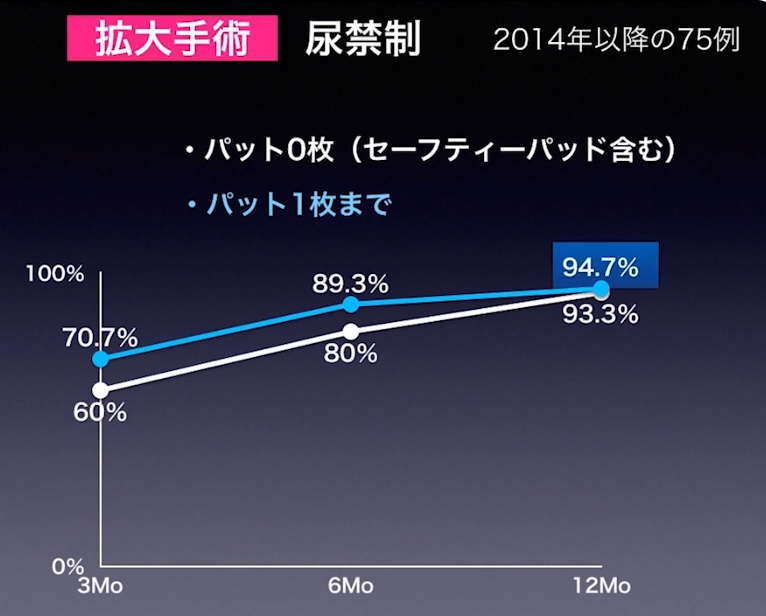
・ロボット手術の場合(文献)
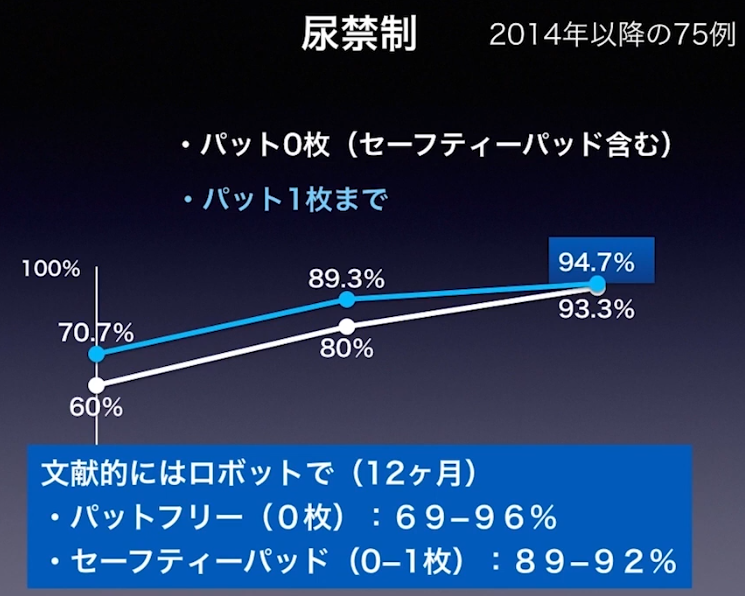
・神経温存
⇒尿禁制に効果
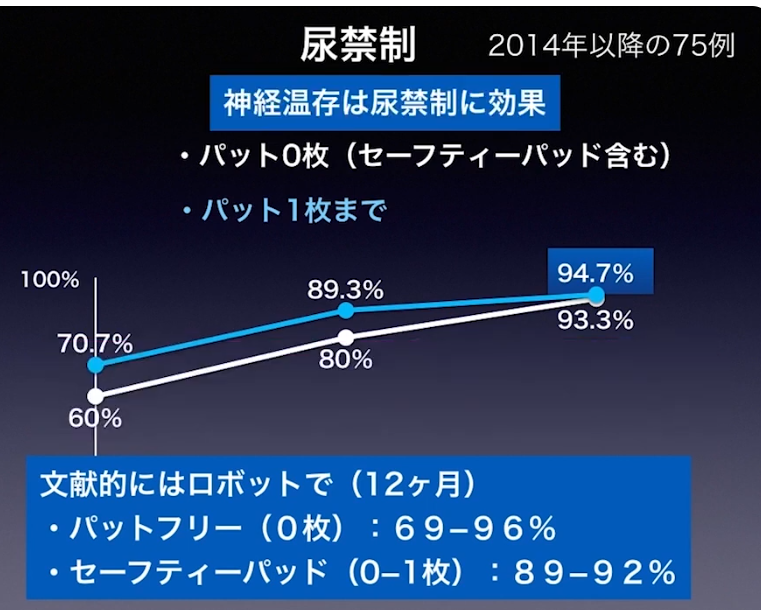
・栃木県立がんセンターの治療方針(ミニマム創手術)
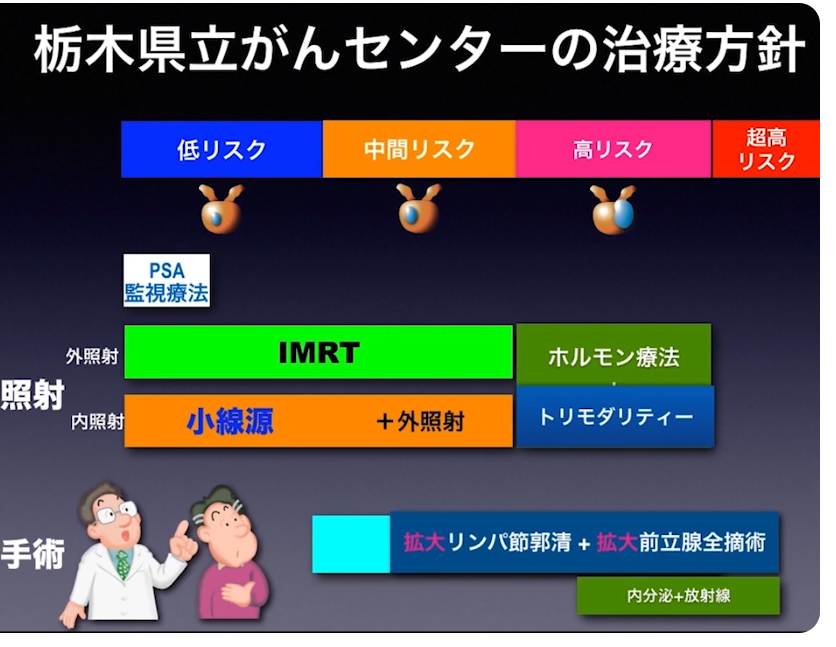
・ミニマム創手術の合併症
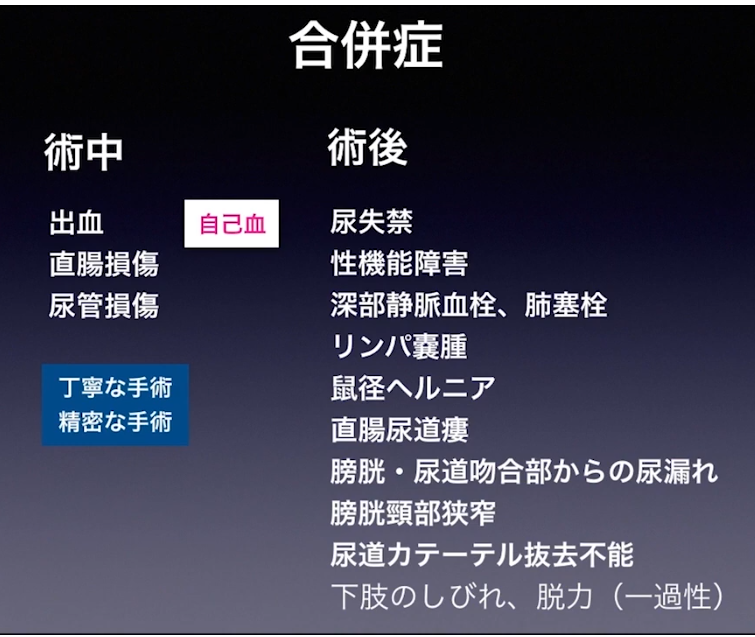
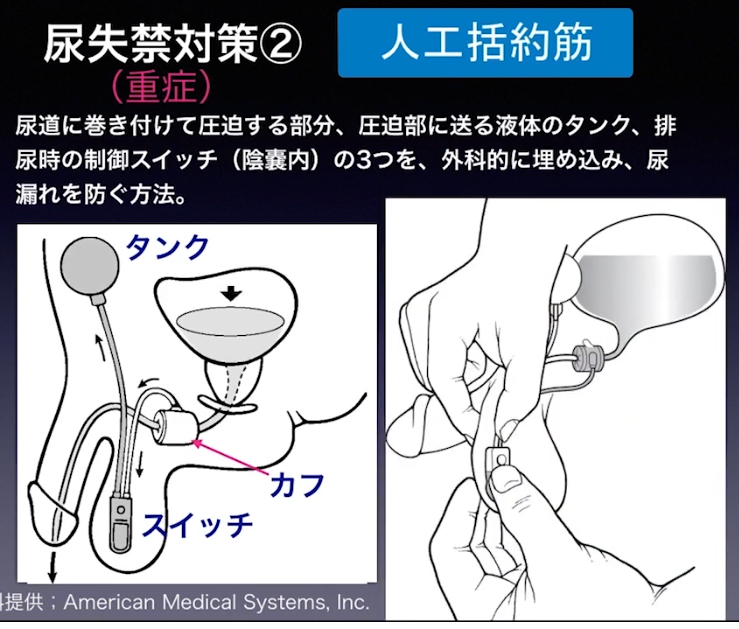
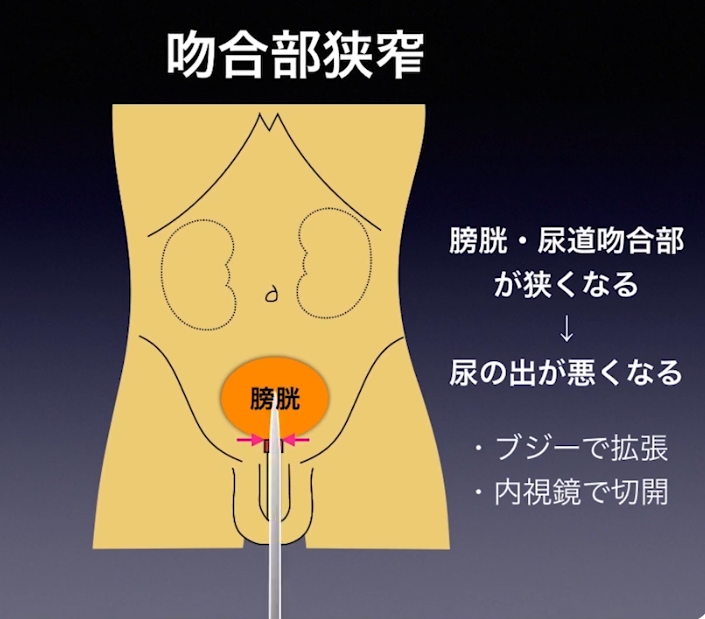
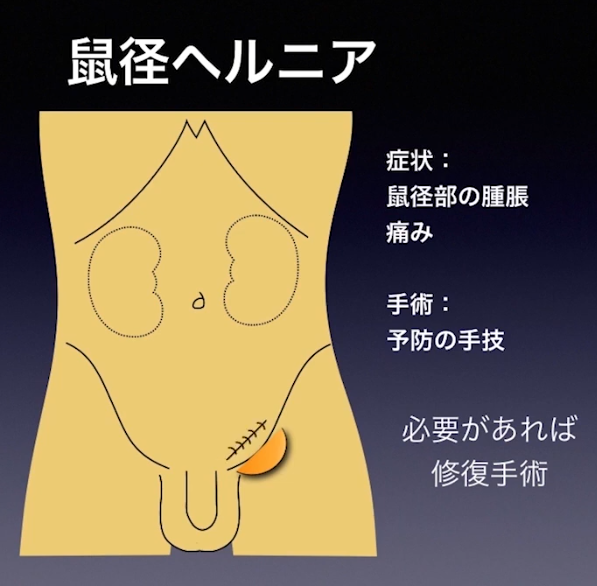
■手術の評価
・リンパ節転移
⇒事前にはほとんど分からない(手術して初めて分かる)
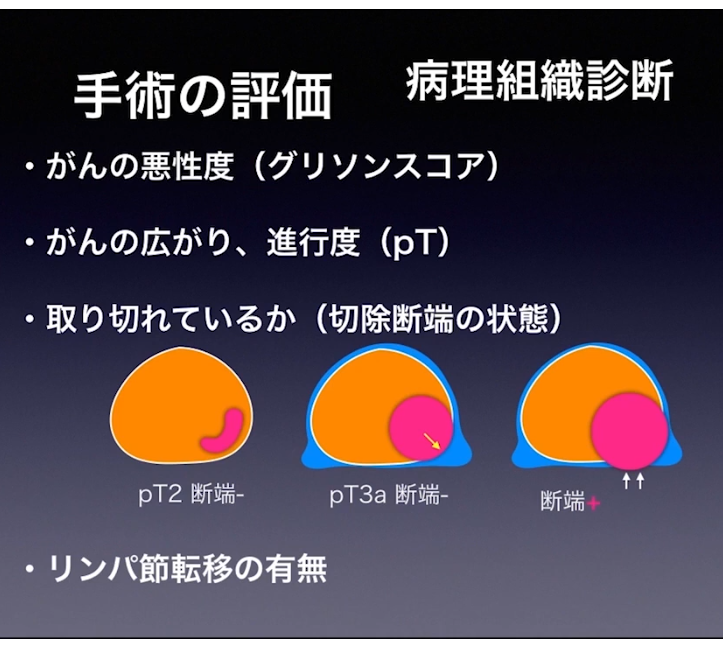
※高リスクにおけるリンパ節転移の率
⇒23.7%
※転移の平均的大きさ:1.8mm
⇒大半のリンパ節転移をCT検査で見逃している(再発因子)
※CTでは8mm以上でないと映らない
■追加治療
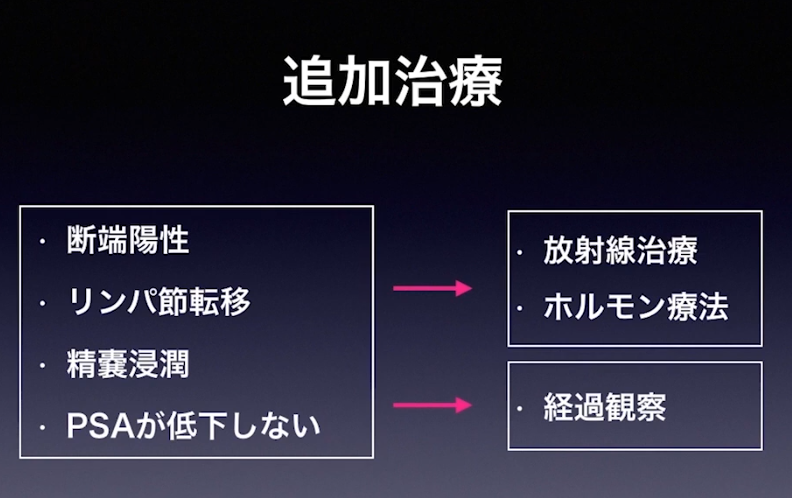
・術後のフォローアップ
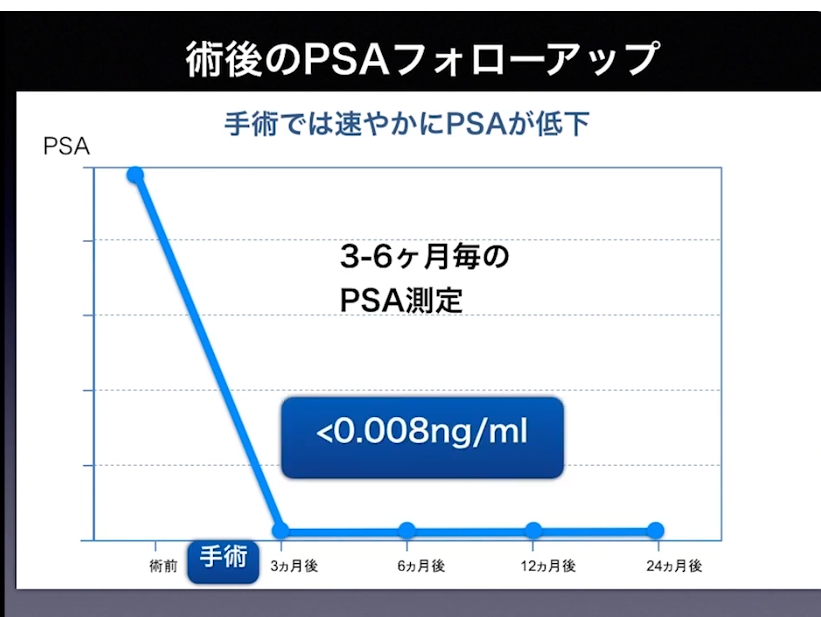
・再発
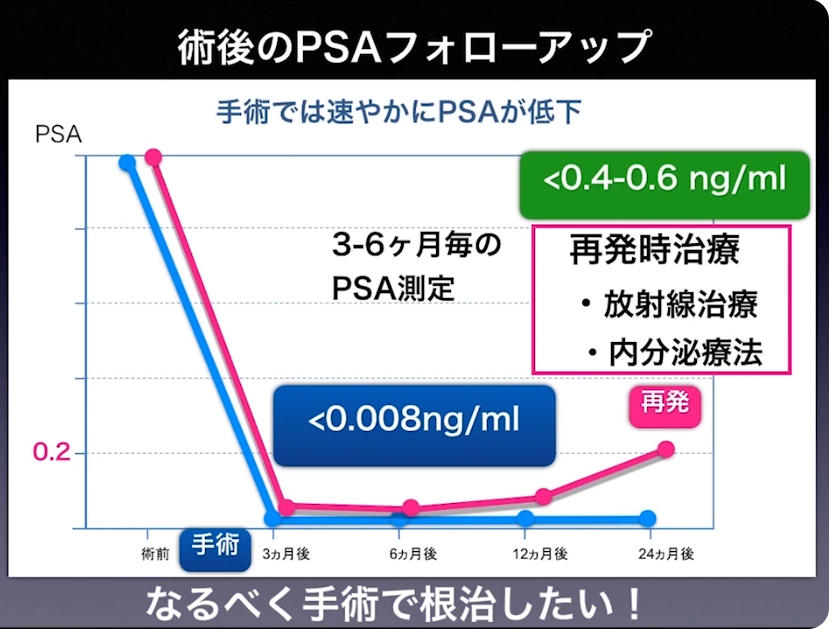
・まとめ
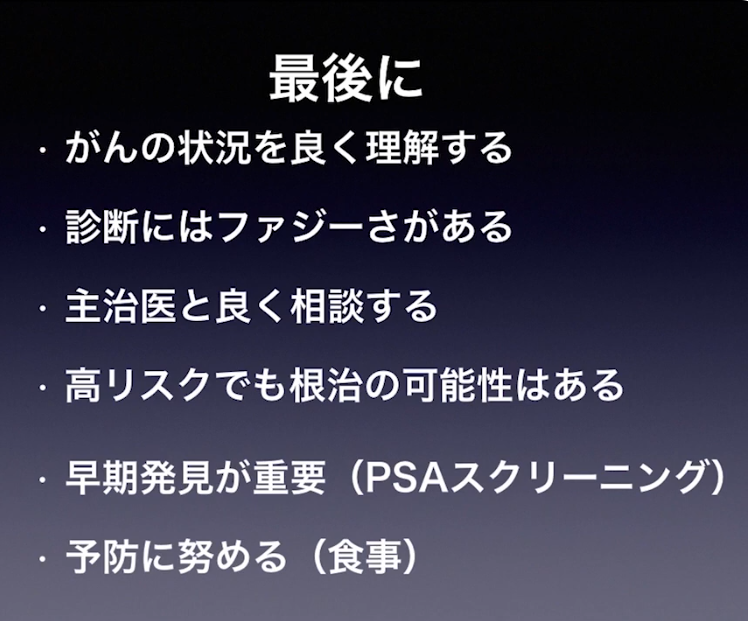
・予防(事前・事後)
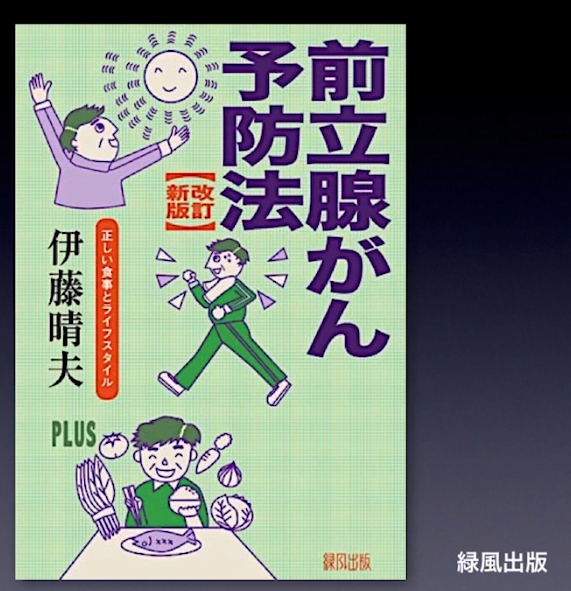
■重要なメッセージ
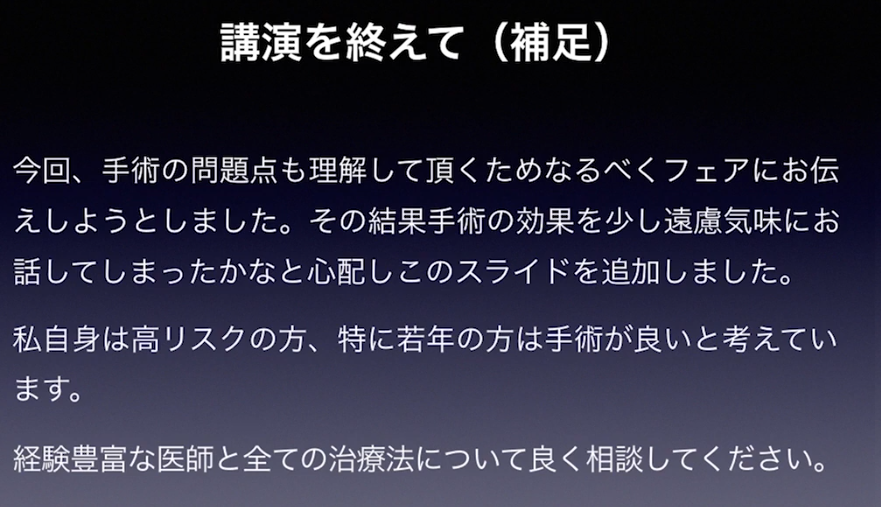
■手術のメリットのまとめ
・特にリンパ節転移は手術で初めて分かる
⇒1~2個の転移であれば根治出来ることもある
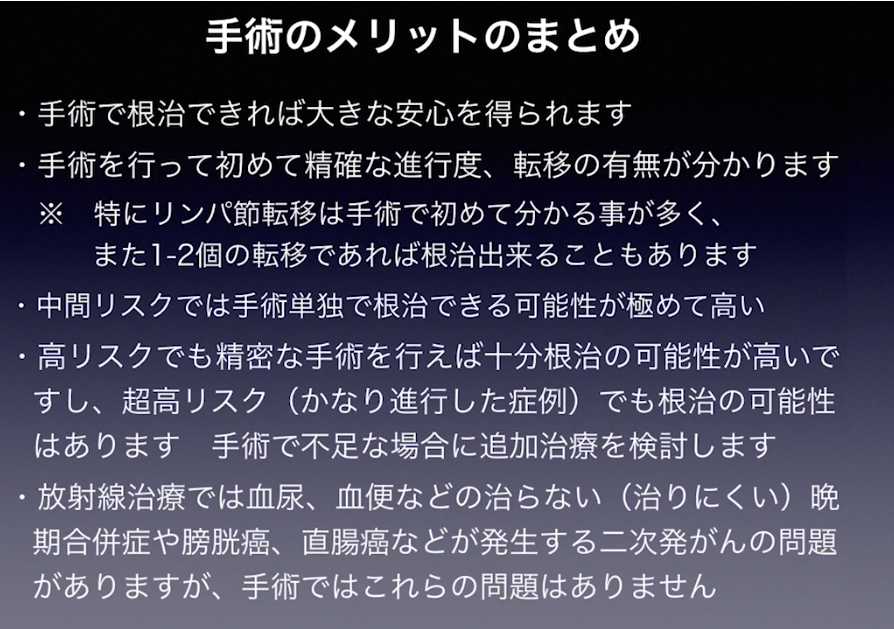
■手術の進化
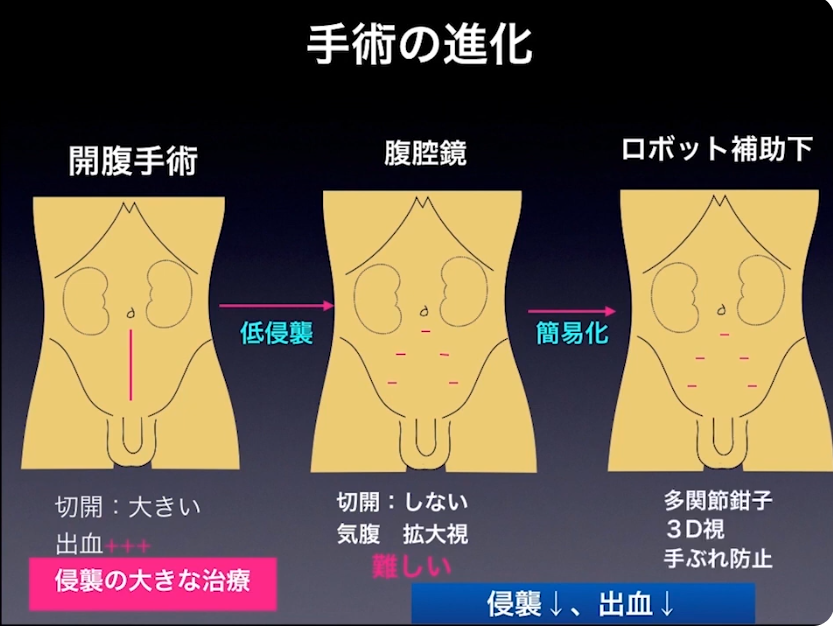
■腹腔鏡下手術
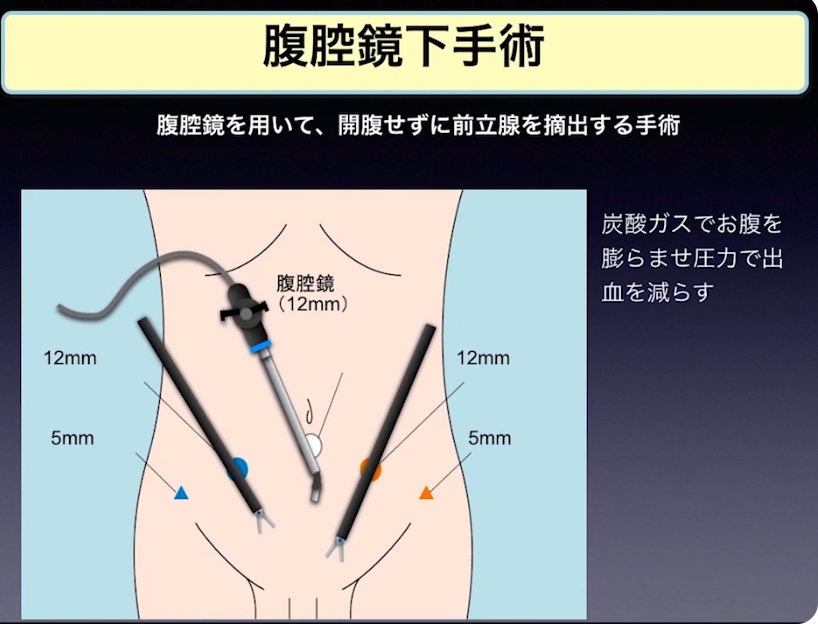
・長所・短所
⇒操作が難しいので熟練者が行うべき(資格制度)
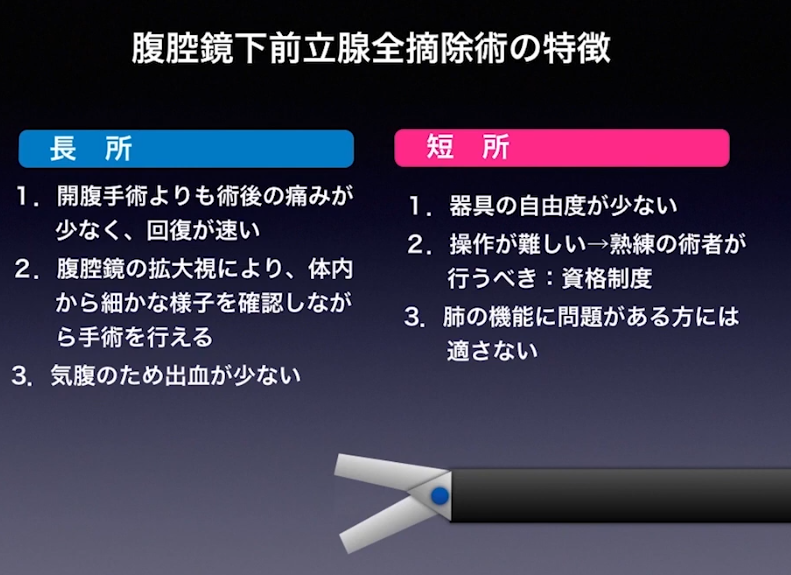
■ロボット支援手術
・操作性が高い

・前立腺全摘に占めるロボット手術の割合
⇒75%(2017年)
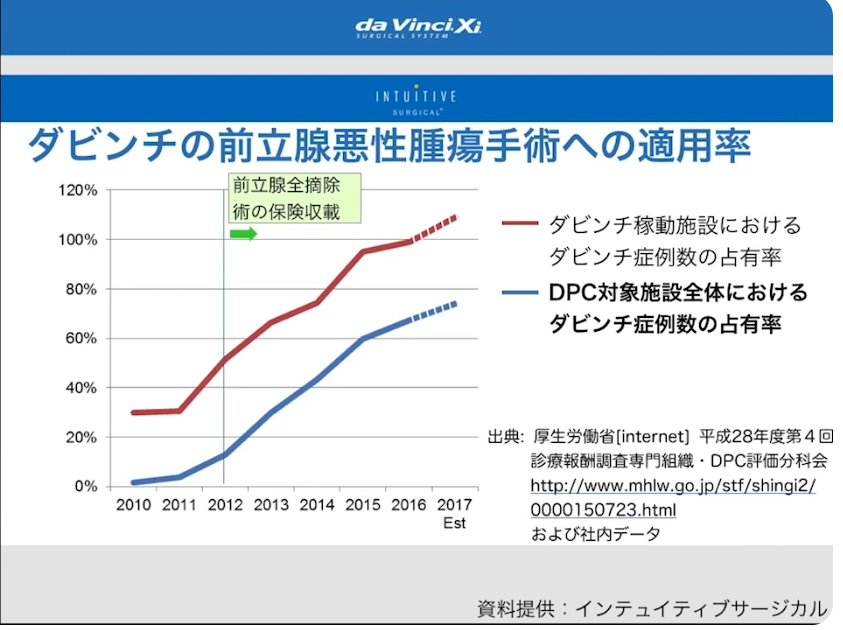
・ダビンチ手術(ロボット手術)の利点(メーカーカタログ)
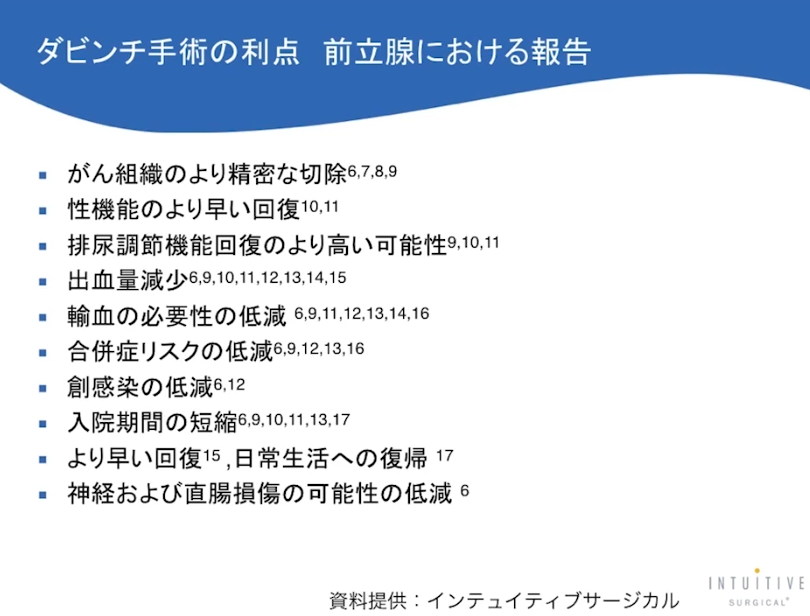
・ダビンチ手術(ロボット手術)の特徴
※動画で紹介されている
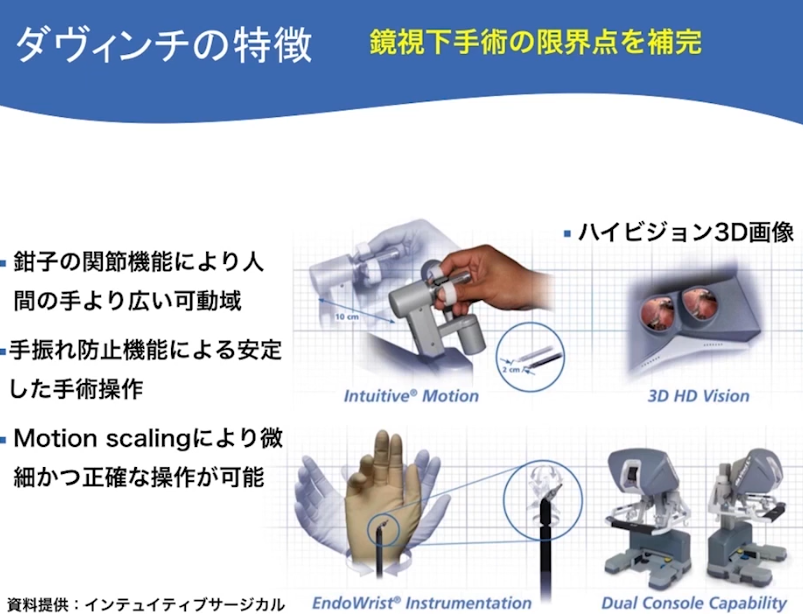
※実際の手術しているシーンとその詳細な内容が説明がされている
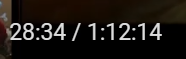
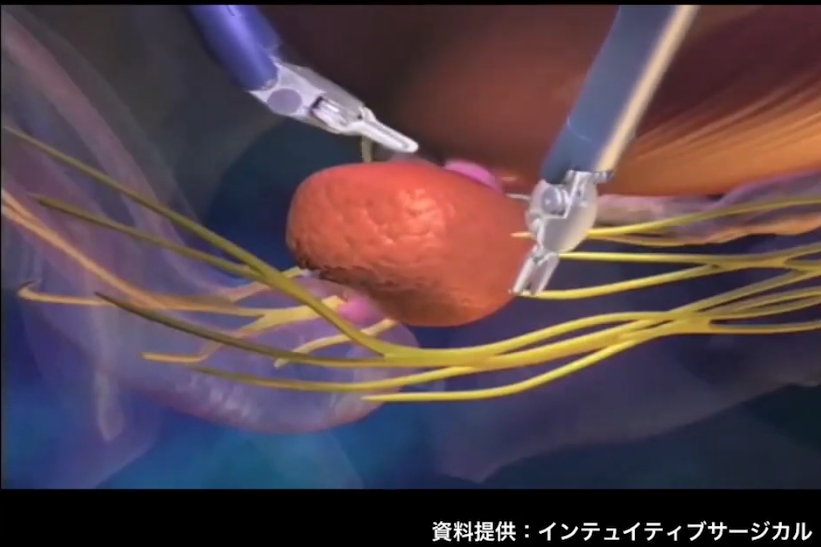
・長所・短所
⇒数年前(2017年の時点で)に
⇒将来ロボット手術が優るであろうと言われている
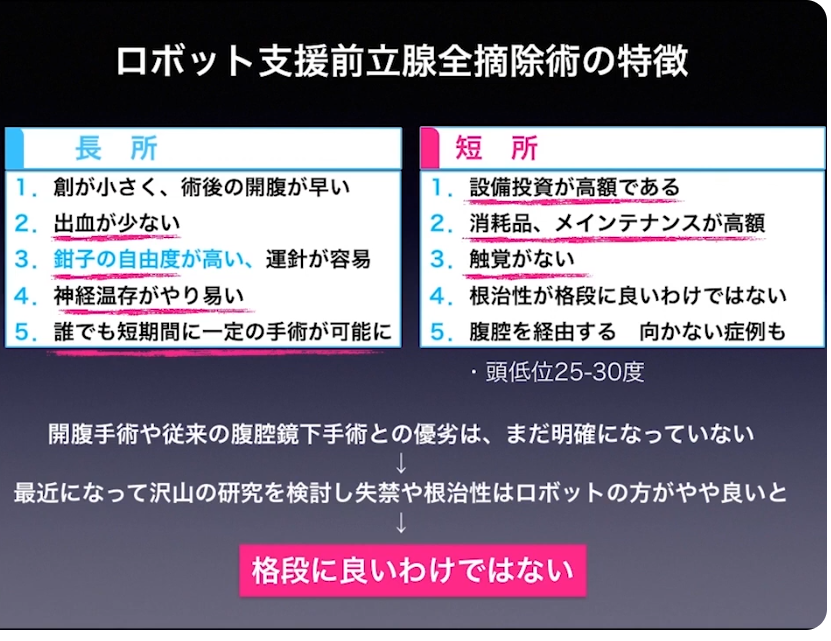
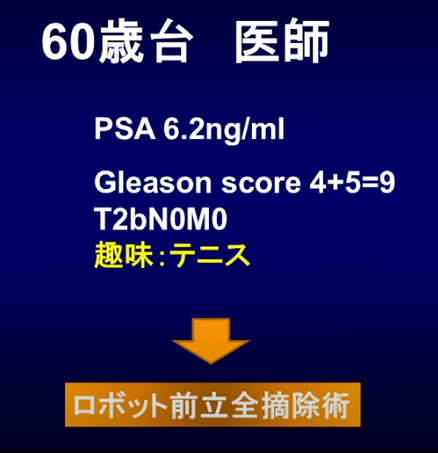
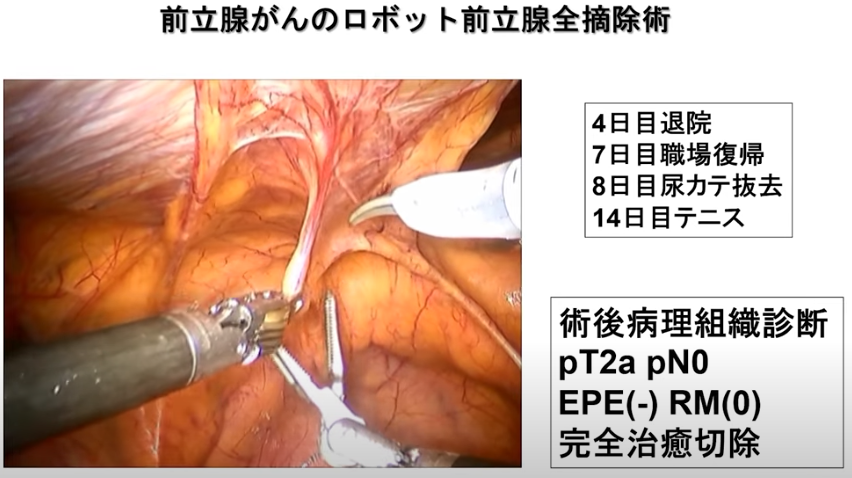
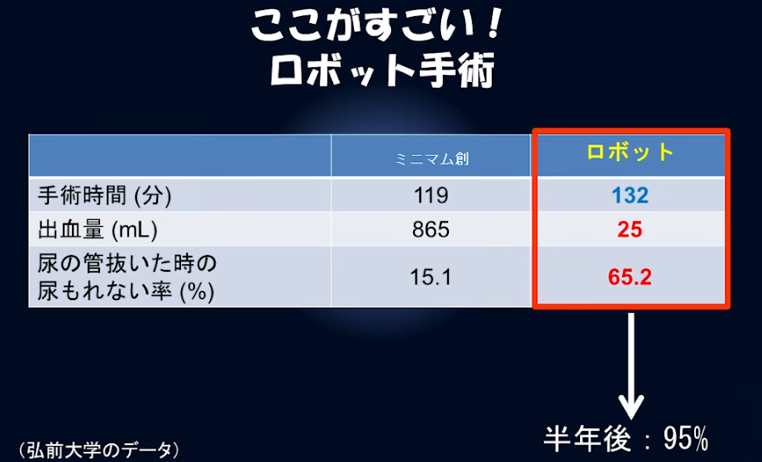
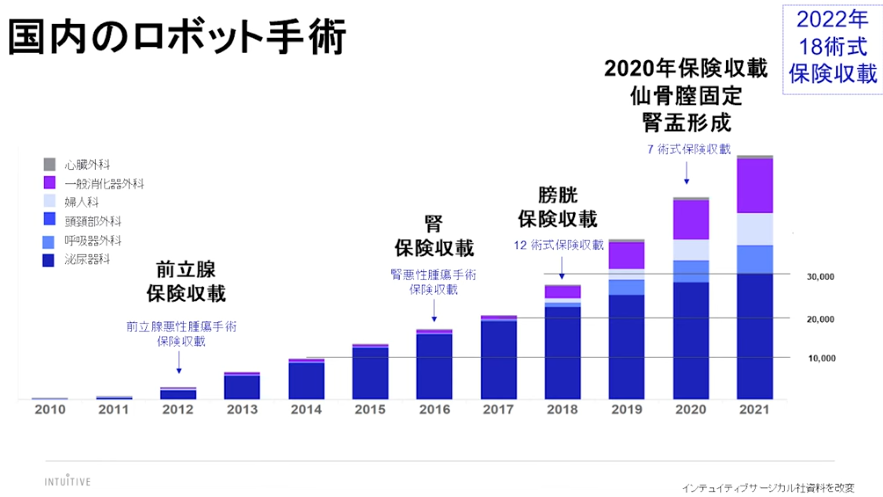
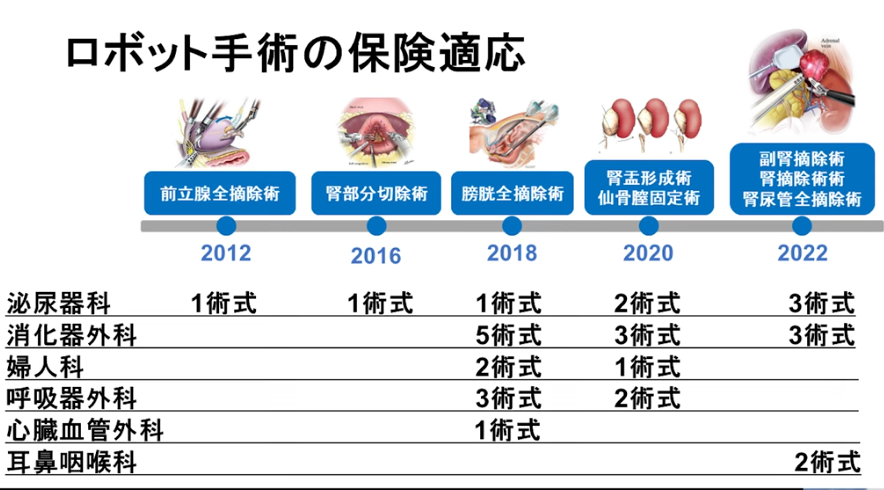
第170回市民公開講座〈第2部〉『前立腺癌ロボット支援下手術について』(開催日:2024年9月5日)
【講師】東京医科大学病院 泌尿器科 助教 鹿島 剛 医師
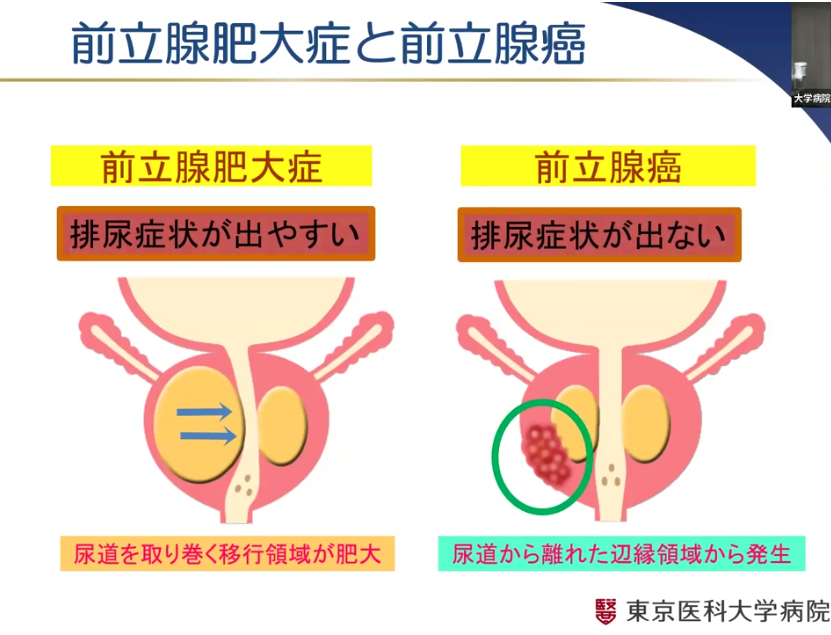
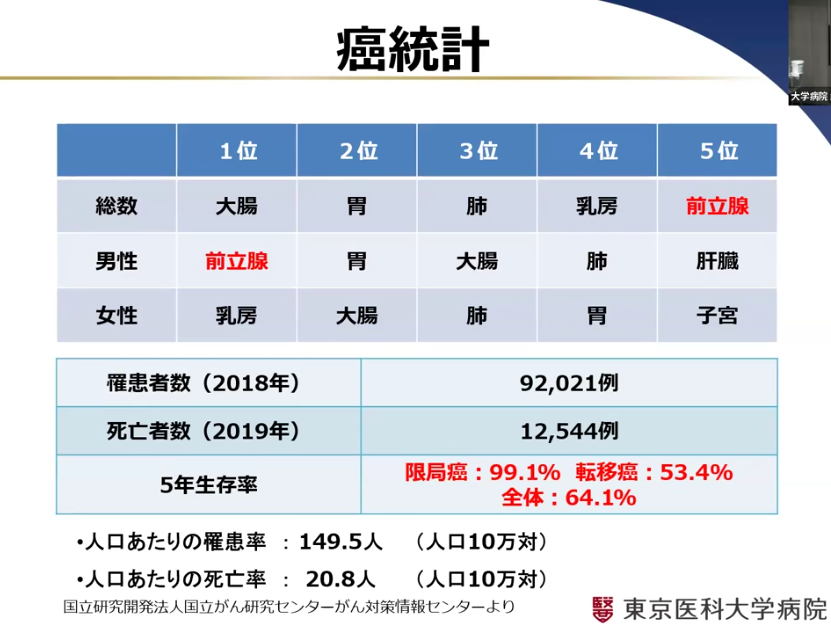
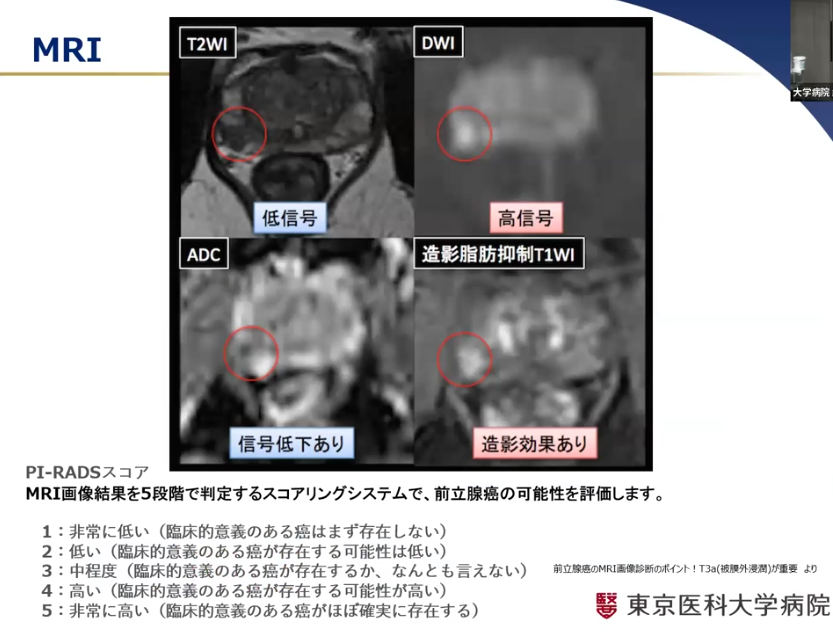
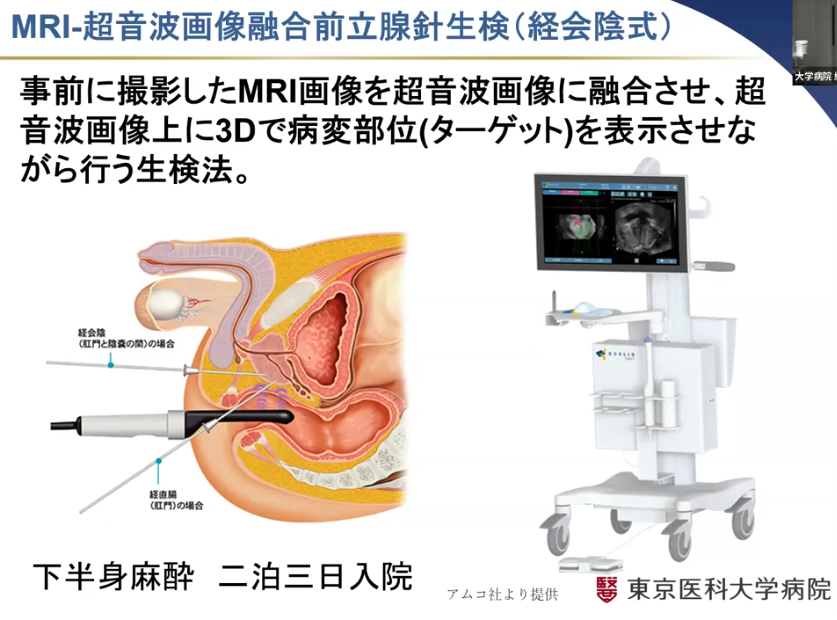
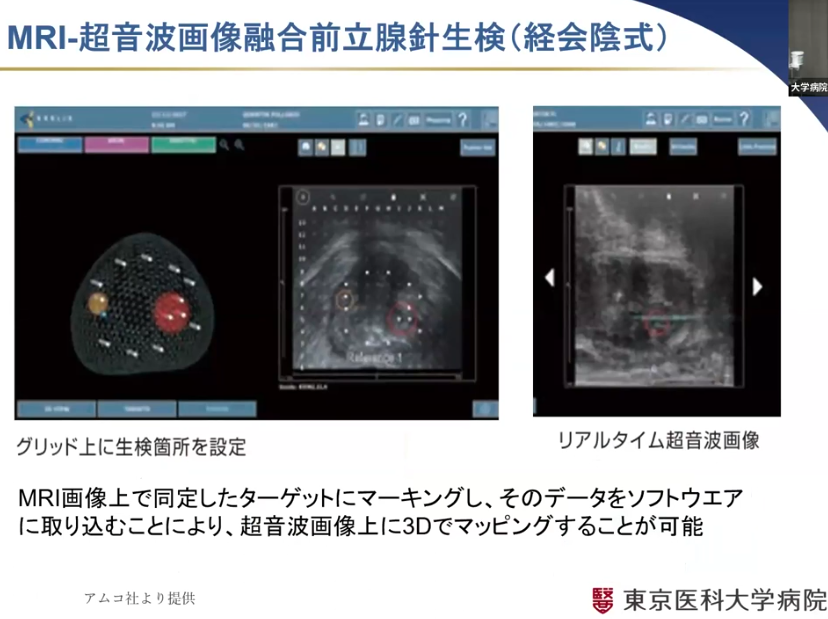
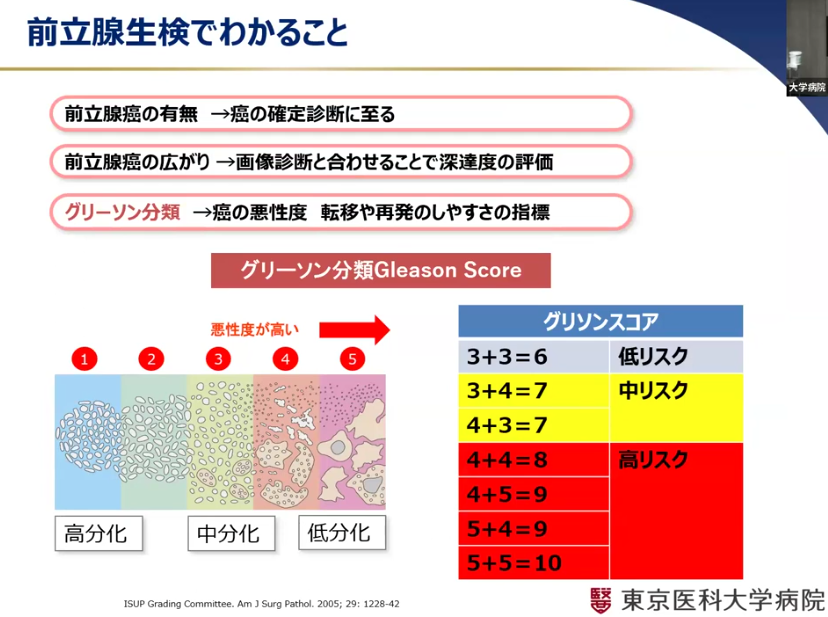
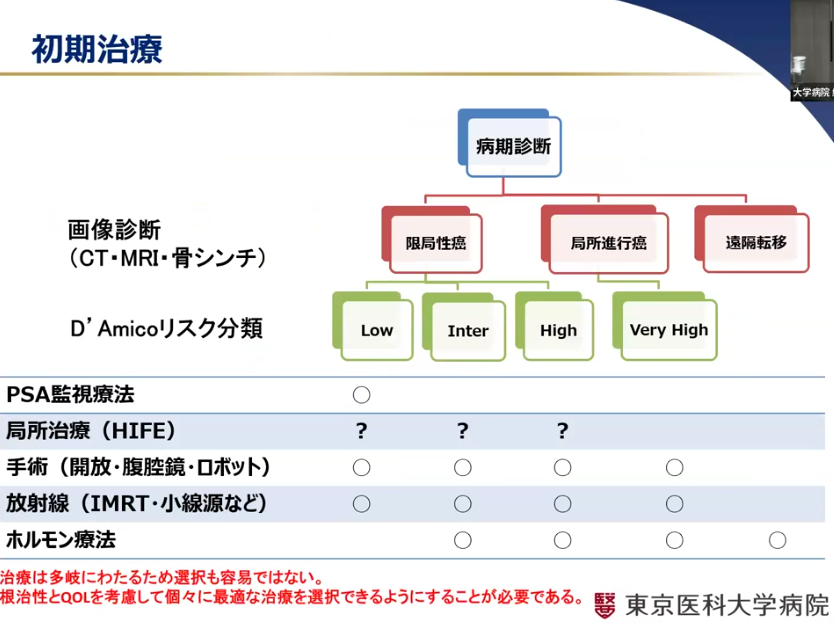
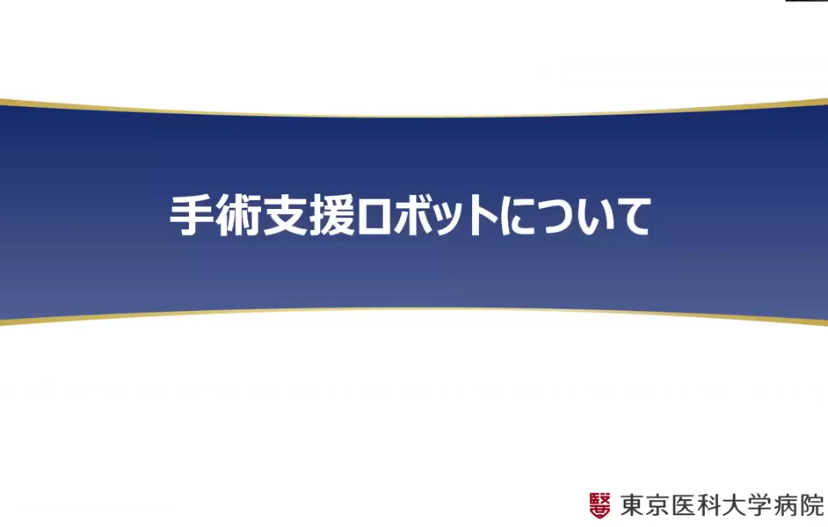

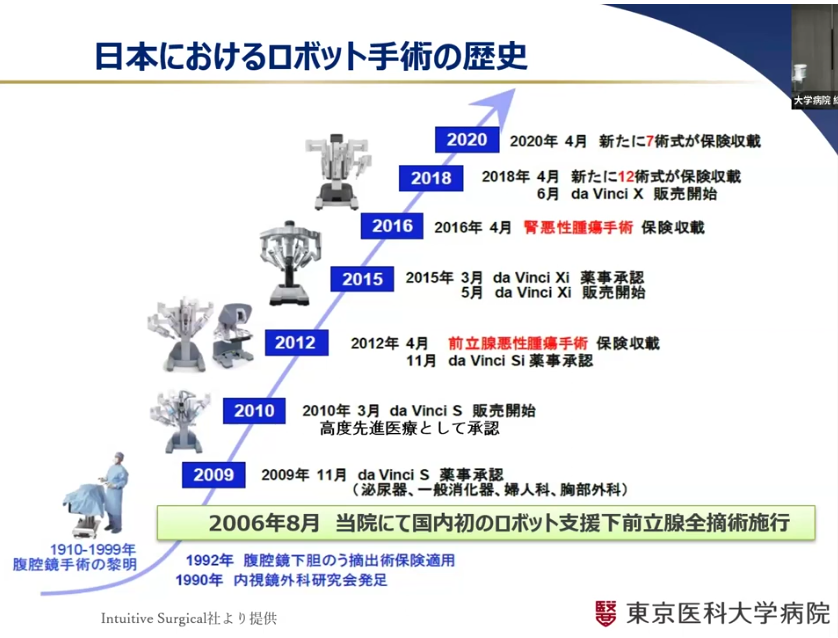
■泌尿器科で開腹手術していた項目
・ほぼロボット支援下手術で対応出来るようになった
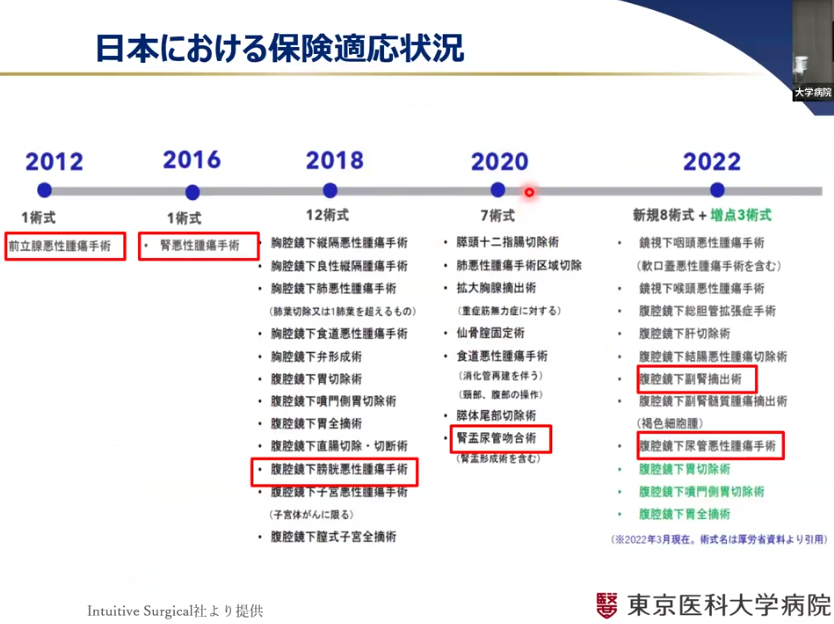
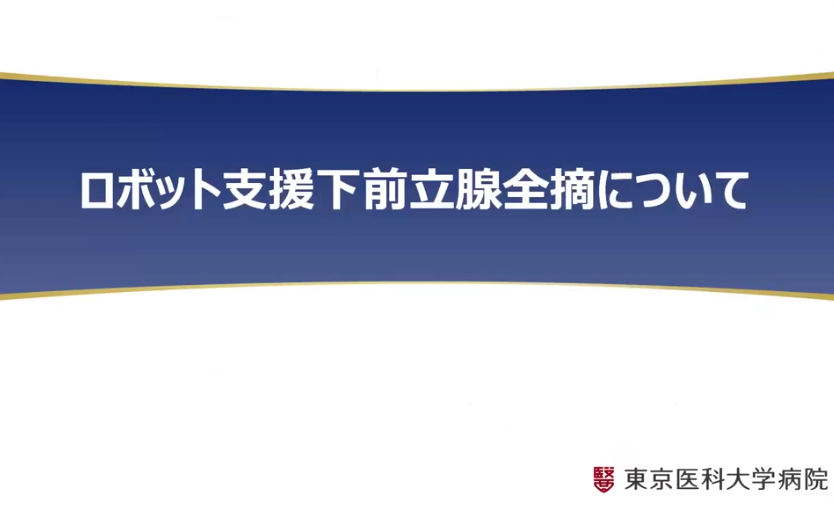
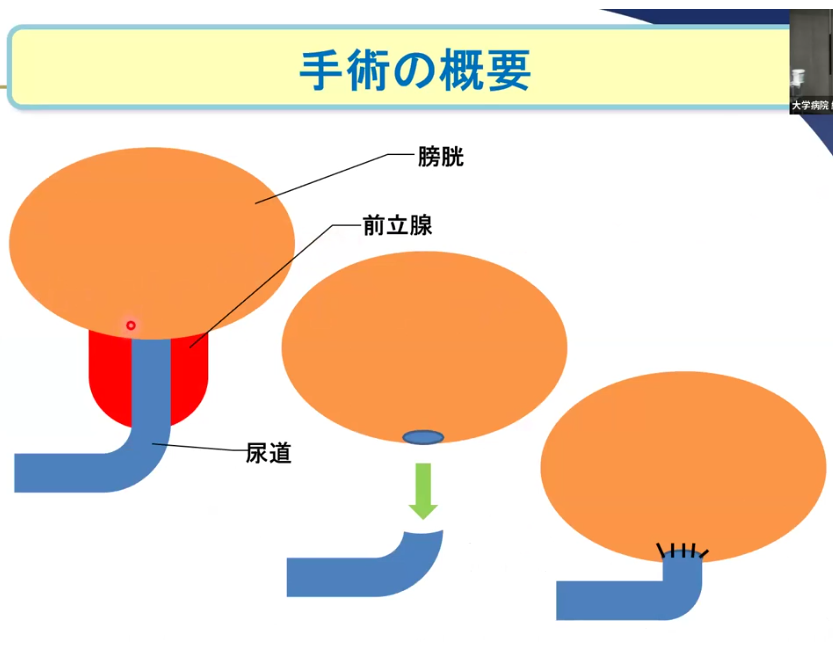
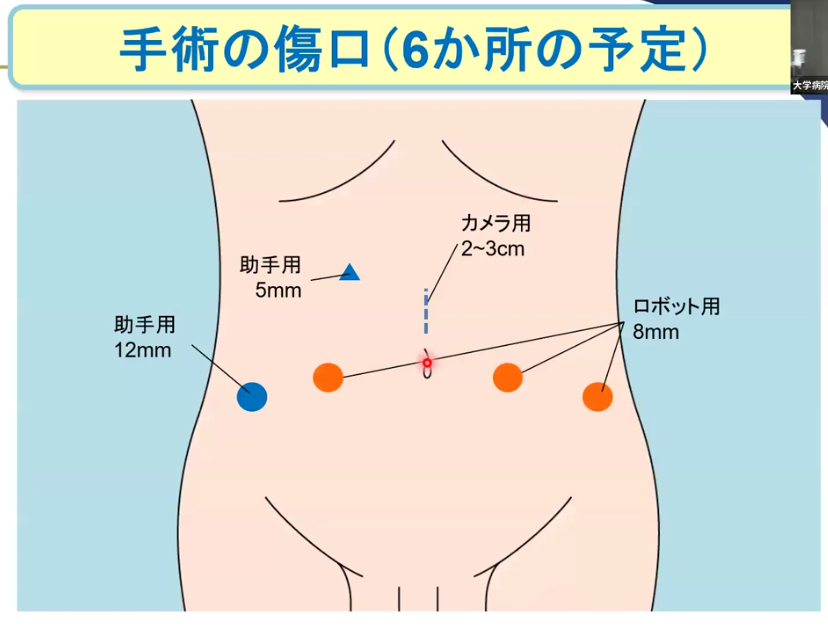
■がん制御
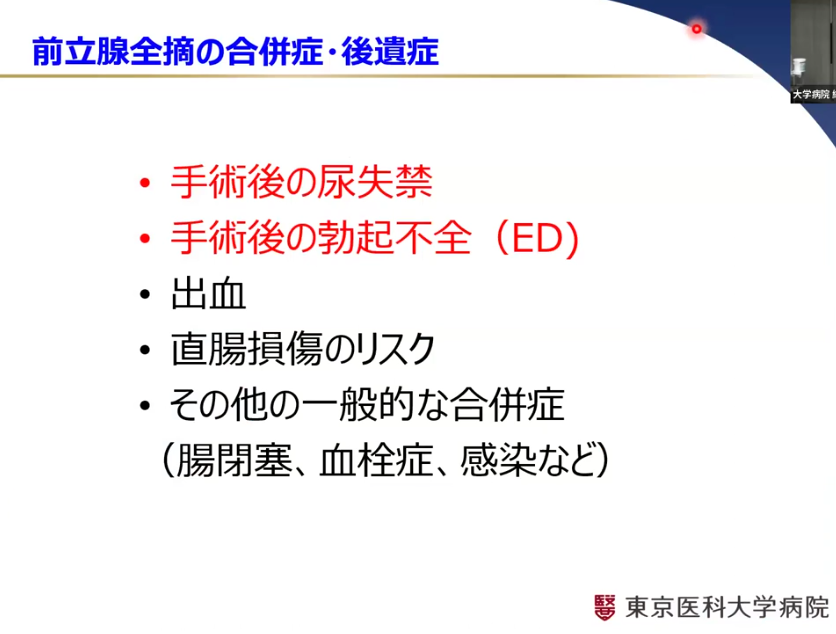
・切除した断面のがん残存率
⇒開腹、腹腔鏡より低い
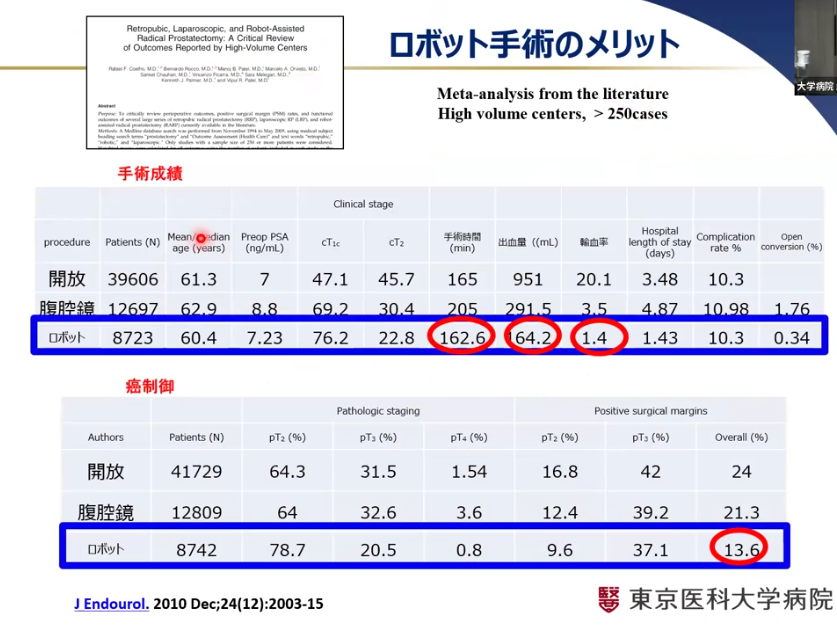
<参考情報>
■切断断端(断端陽性率)
・pT2の場合:断端陽性は-
※但し、手術ミスでガン細胞領域を斜めに切除すると
⇒断端陽性は+になる
⇒pT3の場合:断端陽性は-と+(膜外浸潤部位)の混在
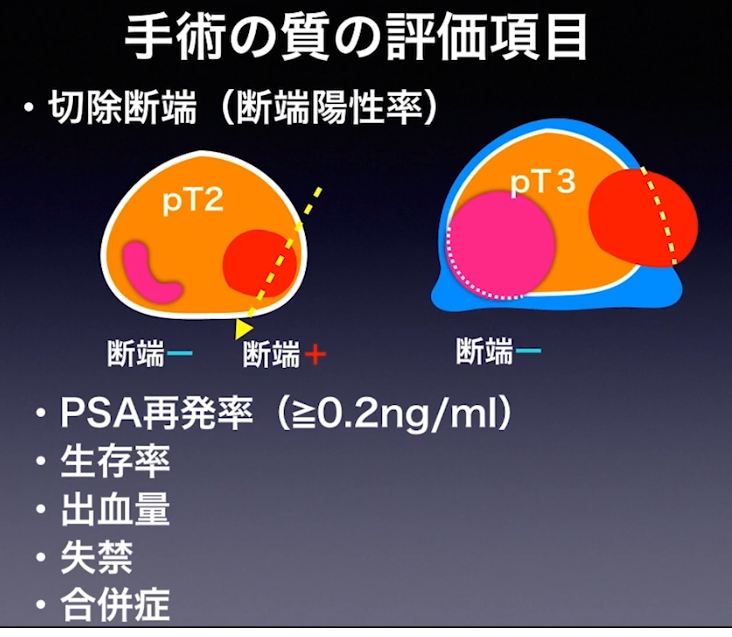
■副作用
・尿失禁
⇒ロボット手術:最近は良くなっている
(下表は少し古いデータ)