出典:
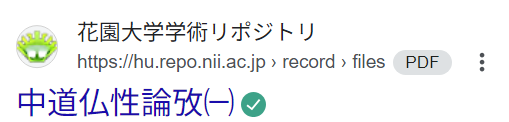
キーワード:中道観(google chrom AI)
中道観(ちゅうどうかん)は、仏教、特に天台宗において重要な概念であり、相対立する二つの極端な立場(二辺)に偏ることなく、その中間をいく真実の道理を観ずることを意味します。
これは単に二つのものの「中間」ではなく、両極端を離れた、矛盾や対立を超える実践的な方法論を指し、仏教における生き方や真理の把握の核心とされています。
■ 一 中道仏性
中道
周知のとおり涅槃経には、仏性とは何かを説明するついで、様々の異名が挙げられている。中道もその一である。しかるに中国仏教において仏性の概念が変化をこうむると、中道という語は、格別な役割をになうようになった。いうまでもなく中道は翻訳語であるが、漢語であるが故に持つ含蓄が、六朝期の中国仏教において、時宜を得たはたらきをしたからである。
吉蔵の大乗玄論第三に次のようにいう。(大45―三五b―c)
古来より相伝して仏性を釈すること同じからず。大いに諸師有るも今は正(た)だ十一家を出だして以て異解と為さん。十一師に就いて皆な名字有るも、今は復た拠列せず、直(た)だ其の義を出だすのみ。
但だ河西の道朗法師は、曇無讖法師と共に涅槃経を翻じ、親しく三蔵に承けて涅槃義疏を作りて、正に中道を以て仏性と為せり。爾後の諸師は皆な朗法師の義疏に依りて、涅槃を講じ乃至仏性の義を釈することを得たり。
この一段について常盤大定博士は「嘉祥は、その後に、河西道朗が親しく曇無讖三蔵に承けて「涅槃義疏」を作り、中道を以て仏性と為せる以後、諸師皆この「義疏」によりて「涅槃」を講じ、乃至、仏性の義を釈するを得たりといふ。これまた一説なるを以て、前の十一家に加へて、十二家となれども、嘉祥が特に之を別出して、破斥を加へざるは、自説に同じきを以てなり。嘉祥の中道仏性説の淵源は、遡りて河西道朗に及び、更に曇無讖を通じて「涅槃経」に及ぶものといふべし」(『仏性の研究』一八七頁)と解説している。
吉蔵自身は次のように述べている。大乗玄論第三(大45―三七c)。
但だ中道の義は識り難きこと、具さに二諦中に辨ぜしが如し。中に非ず辺に非ず、中辺に住せず、中辺平等なるをば仮りに名づけて中と為す。若し是くの如き中道を了すれば、則ち仏性を識らん。若し今の仏性を了すれば、亦た彼の中道を識らん。若し中道を了すれば、即ち第一義空を了せん。補注1
吉蔵が「識り難し」というのは、インド仏教そのままの中道ではない。中国的変容をこうむつた仏性と等置された中道である。仏性がどのように変容したかについては、これまでしばしば論じたところであるが(1)、簡単にいえば、中国思想における「道」の概念に同化し、宇宙論的原理(2)となったということである。
中道という語は、中論二十四章十八偈によって有名である。この偈は「中論偈」とも「三諦偈」とも呼ばれ、中道を問題とする当時のほとんどの学者が取り上げている。まず羅什訳の原文(3)を見ておこう。(大30―三三b)
衆因縁生法、我説即是無、亦為是仮名、亦是中道義。
衆の因縁より生ずる法は、我は説く、即ち是れ無なりと。亦た是れ仮名なりと為すと。亦た是れ中道の義なりと。
青目の釈文にいう、
衆の因縁より生ずる法は、我は説く、即ち是れ空なりと。何を以ての故ぞ。衆縁具足し、和合して而して物は生ず。是の物は衆の因縁に属す、故に自性無く、自性無きが故に空なるも、空も亦復(また)空なり。但だ衆生を引導せんが為の故に、仮名を以て説くのみ。有無の二辺を離するが故に名づけて中道と為す。
もろもろの因縁と和合して生じる法は、無自性であって、存在性がないから空である。しかし空という何物かがあるのではない。他の事柄どうよう、衆生を導くために仮名によって説くまでである。かくして有無(常見断見)の二辺を離却しているから、衆因縁生法は中道である。
是の法は性無きが故に有と言うことを得ず、亦た空無きが故に無と言うことも得ざればなり。
この法は自性がないから有と言うことはできないし、空というものもないから無と言うこともできないからである。
楞伽経巻四(大楞伽経巻四(大16―五〇七c)には
「是くの如く無自生と空等とを応に分別すべし。空なるが故に空なりと説くには非ず。無生なるが故に空なりと説く」といい、
また中論には
「若し物は無自性ならば、是の物は終に不生なり」(大30―二六b)という。
衆因縁生法は無自性であるから「不生」「無生」つまり生じていない。したがって有と言うことはできない。空である。
しかし維摩経入不二法門品にいうように、
色即是空ならば、色の滅して空なるには非ず、色の性自(し ょう)として空なるなり。……
…其中(そこ)において通達する者は、不二の法門に入ると為す。
法は消滅することによって空無となるのではなくて、それ自体のありようとして空無なのであるから、無と言うこともできないのである。「不二法門」とは中道の同意語である(4)。
■ 二諦から三諦へ
仏性思想が中国的変容をこうむるのと平行して、中国仏教は、二諦説から三諦説へと移行していった。
「空」(非有空無)を中心とする教理から、「中道」(非有非無)を中心とする教理へと進んだのである。
むしろ中道を中心とする観想が三諦説を要請したといえる。これらの動きは、すべて仏教の中国化の一環にほかならないが、そのほとんが肇論において構想されていたということを、かつて述べたことがある(5)。とくに三諦説については最近論じたばかりである(6)。
もっとも天台智顗によると、二諦と三諦とのちがいは仏の三身と二身とのように開合の差にすぎないという。維摩経玄疏二に次のようにいう(大38―五二四c)
但だ三身の義は備さに衆経に有りて、理は宛然たりと雖も、名は的として顕われず。楞伽経の如きは具さに三仏の名と義と有り、又た普賢観経は、仏の三種身は方等より生ずと云う。三身は義を明らむれば二身に乖かず。其の開合を識れば豈に定めて偏用せんや。此れ三諦と二諦との開合に類す。
三諦説の中でもっともととのっているのは智顗のものである。維摩玄疏三(大38―五三四c)にいう、
三諦の名義は、具さに瓔珞と仁王との両経に出づ。経に云わく、一には有諦、二には無諦、三には中道第一義諦なりと。
有諦なる者は、世の人心の見る所の理の如き、名づけて有諦と為す。亦た俗諦とも名づく。
無諦なる者は、出世の人心の見る所の理の如き、名づけて無諦と為す。亦た眞諦とも名づく。
中道第一義諦なる者は、諸仏菩薩の見る所の理にして、中道第一義諦と名づく。亦た一実諦とも名づく。
瓔珞経も仁王経も六朝時代に作られた偽経として有名である。偽経の役割が、中国出来の教理に仏説としての権威を与えるためであったことは良く知られている。瓔珞経には次のようにいう(大24―一〇一八b)、
爾の時敬首菩薩は仏に白して言わく、二諦と法性とは為(は)た一なりや為た二なりや。為た有なりや為た無なりや。
第一義諦は復当(はた)云何ん。
仏言わく、仏子よ、所謂る有諦と無諦と、中道第一義諦とは、是れ一切諸仏菩薩の智母なり。乃至一切法も亦た是れ仏菩薩の智母なり。
「法性」とは、地論師のものとされる「眞如法性は一切法を生ず」(維摩玄疏二、大38―五二八b)という言葉から知られるとおり眞如の類語であり、また金剛.には「眞如隨縁は即ち仏性隨縁なり。……当に知るべし、眞如は仏性の異名なり」(大46―七八三b)というから、仏性の類義語でもある。さらに維摩経の経体を明らかにするところで次のようにいう(大38―五五六a)
俗諦は但だ是れ凡人の見る所の理なるのみ、故に此の経の体には非ざるなり。
眞諦は即ち是れ二乗の見る所の理にして、亦た此の経の体には非ざるなり。
中道第一義諦は即ち是れ法性実相にして、即ち此の経の正体なり。
つまり「法性」はまた、第三諦である中道第一義諦にほかならないわけで「実相(7)」とも呼ばれる。すなわち中道仏性である。
この法性と二諦とは一体(一)であるか、別体(二)であるかという問いは、三諦説において、前二諦と第三諦とがいわゆる体用の関係にあることを前提として発せられたものである。
体用論というのは、一個の原理的なものと万物との関係を説明する理論であるが、「体用無二」(大乗止観法門二、大46―六五〇b)つまり原理と万象とは一体不二だということを原則とする。そこのところを踏まえてこの問いは設けられているのである。このことは三諦説がすでになんらかの形で存在していたことを示唆するであろう。この三諦説が肇論において始めて構想されたことは、旧稿「空から眞空へ」において詳説したところである。
また眞諦を「無諦」と呼び、俗諦を「有諦」と呼ぶことも肇論の考えにもとづく発想であろう。瓔珞経は媒介の役目を果たしたのである。
■ 智顗の三諦説
では智顗の三諦説とはどのようなものであったであろうか。それは三観の教理と切り離せない関係にある。維摩玄疏二(大38―五二四c)にいう、
三観を用いて維摩詰の名を釈せば、三観は二諦三諦に迷うの惑を断ち、二諦三諦の妙理を顕わす。眞理皎然たる、之を名づけて浄と為す。惑障斯に尽くる、之を無垢と謂う。観と理と合して大用は無方なり、故に名づけて称と為すなり。
「妙理」も「眞理」も中道仏性を指す。「惑を断ち」「妙理を顕わす」というのは、泥洹経巻四、大12―八八一b)に、
復た比丘有りて、如来蔵経を広説して言わく、一切衆生には皆な仏性の身中に在る有りて、無量の煩悩悉く除滅し己って、仏は便ち明顕なり。
というのと主旨は同じであろう。すなわち智顗の三観説は、見性成仏説の部類に属するものと言わねばならない(8)。玄疏はいう(五二五a)
境智を分別すれば、境は是れ所観、智は是れ能観にて、所観の境は即ち是れ十二因縁なる三諦の理なり。能観の智は即ち三観なり。
玄疏は続けていう(五二五a)、
今、中論偈に約して、正に此の三観の境を明らめん。偈に云わく、因縁所生の法は、我は説く、即ち是れ空なりと。亦た名づけて仮名なりと為すと。亦た中道義と名づくと。
智顗もやはり空仮中三諦の根拠を中論偈に求めるのである。ただ羅什訳に「衆因縁生法」とあるところが、「因縁所生法」と変化している。これは「理無有二(理に二有ること無し)」(維摩玄疏五、大38―五五〇c)という中国仏教の原則に従ってすでに生じていた変化(因果論から体用論へ)であって、智顗の恣意によるのではない。
<参考情報>
例:空観思想(=中道:龍樹/ナーガールジュナ)を基盤にして
『天台思想』
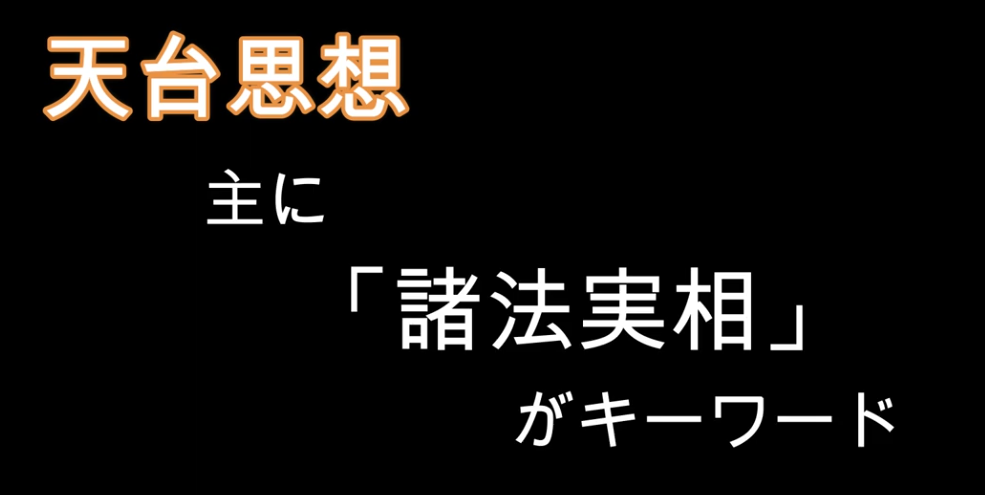
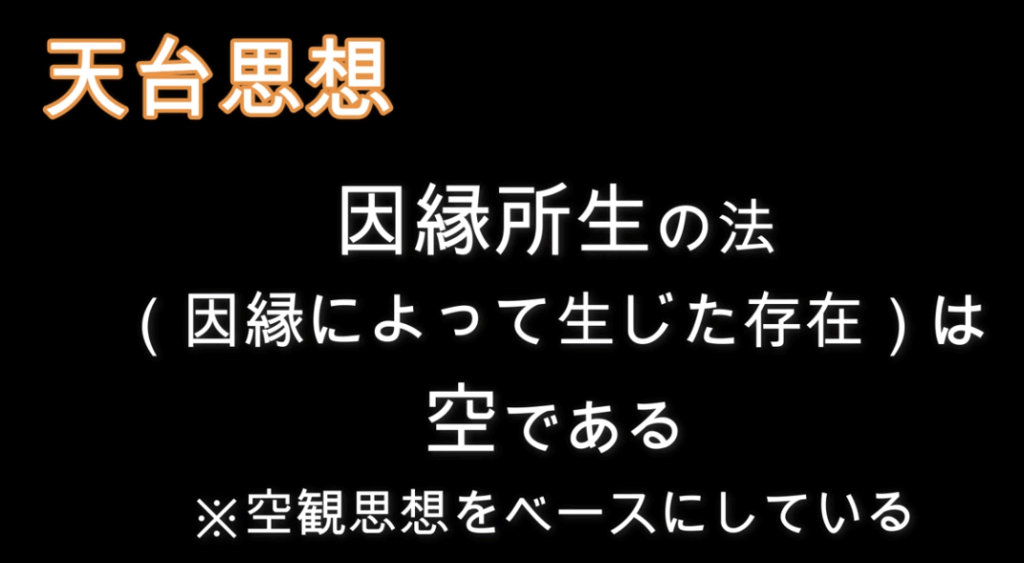
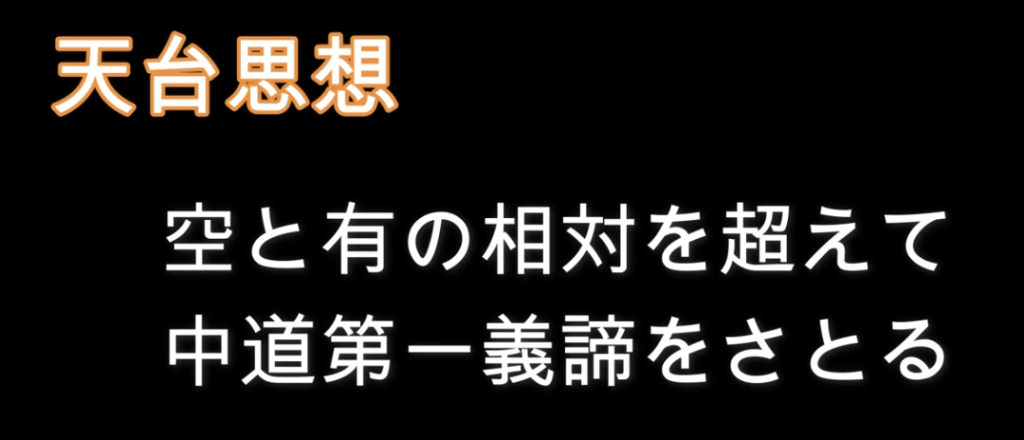
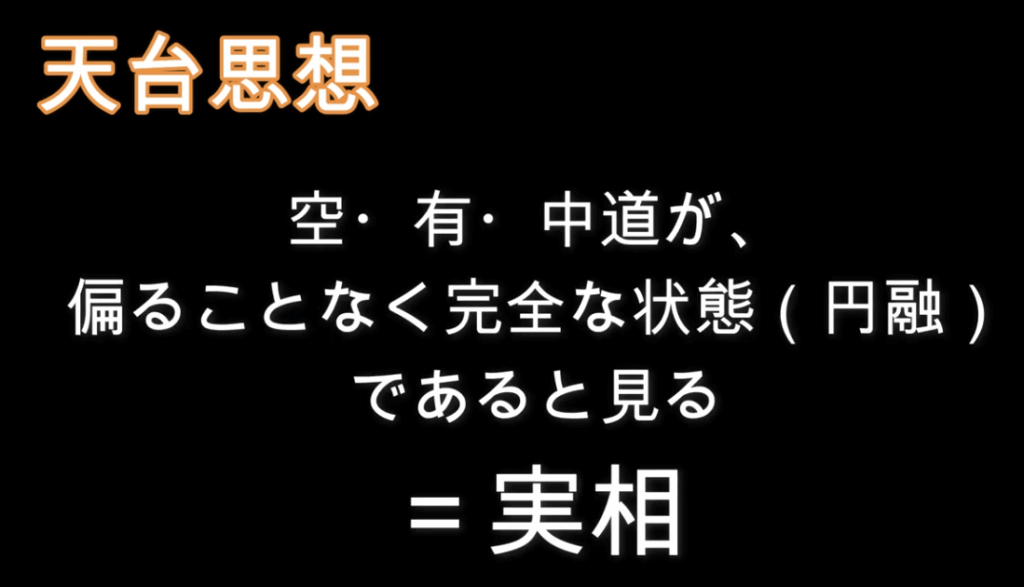
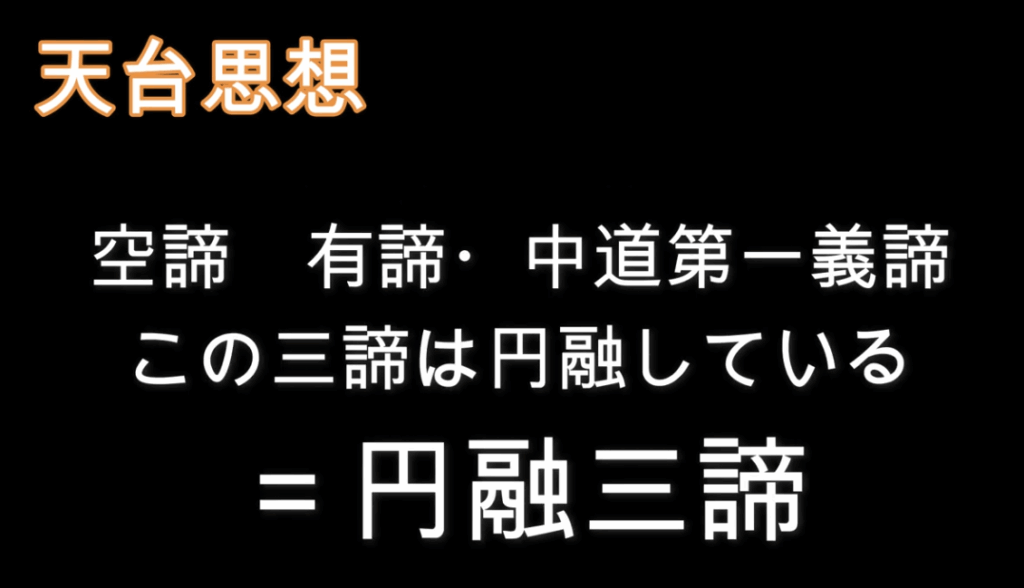
出典:サブタイトル/華厳経と華厳思想 No.2(法界縁起)~吉田叡禮(臨済宗妙心寺派牟禮山観音寺住職)転記~
<参考情報:Google chrome AI回答>
三諦(さんだい)
天台宗で説かれる「空諦(くうたい)」、「仮諦(けたい)」、「中諦(ちゅうたい)」の三つの真理を指します。
- 空諦:一切のものは実体がない、空であるという真理です。
- 仮諦:一切のものは、因縁によって仮に存在しているという真理です。
- 中諦:空でもなく、仮(有)でもない、空と仮を共に受け入れる中道の実相を示す真理です。
天台宗では、これらの三つの真理はそれぞれ別々に存在するのではなく、互いに融け合い、一念の中に全てが顕現している「円融三諦(えんゆうさんだい)」として説かれます。
<参考情報>
概念(戯論)からの解放
また空の立場からは、ものごとは役割に応じて名前が変わるので、いま仮に「空」ということばで「ものごとは空である、すなわち固有の本質を持たない」と表現しているが、「空」という表現そのものが究極(=勝義)であるわけでもない、とも言います。
つまり、本来は言語表現されえない、いいかえれば、概念によって間接的に指し示すことはできても、「空であること」は直接に体得されることが期待されるということです。
とはいえ、ブッダの悟りであるその勝義的な真理(第一義諦)が人々に理解されるためには、「空」などの世間の言語表現が必要不可欠で、それを世俗真理(世俗諦)とも呼びました。
もとより、事物に固有の本質はないが、そこに固有の本質があるかのような錯覚はある。それが錯覚にすぎないこと気づかせるために、「空」という否定的な響きのある言葉が選びとられたとナーガールジュナは言います。
ただし、空が正しく理解されるというのは、錯覚を錯覚であると気づくこと、それによって煩悩の根源に巣くう概念化(戯論)という心のはたらきから解放されることを意味しています。
出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~中項目:■空とは何でしょう? ―中観派(ちゅうがんは)の教えを学ぶ/第16回 愛宕薬師フォーラム(東京大学教授 斎藤 明 先生)
<参考情報>
■時間概念が否定
因果論や縁起論はもちろんのこと、カントの認識論も、ヘーゲルの自己展開する弁証法も崩壊させるような根本的問題を突きつけることになる。
まず、観時品では直接的に「時相の不可得」と言い、「時有るべきや」と反語的に時間把握の不可能を言っているが、このことをもう少し具体的に展開している去来品で検討してみよう。
時間論と言えば多くの論者がこの去来品を取り上げるものの、已去(過去)と未去(未来)については明快に否定できるのだが、「去時」、即ち「去りつつある時」の「現在」については、どれもこれもその説明に難渋している。ところが先の思考の次元化を適用すると、これについての次のような解き方が可能となる。
過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、
概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。
しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。
同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。
つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。
これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。
つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。それ故。「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。
出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学講師)~
■ 三観の名義
玄疏は続けていう(五二五b)、
三観の名を釈すれば、三観の名は瓔珞経に出づ。云わく、仮より空に入るを二諦観と名づけ、空より仮に入るを平等観と名づく。是の二観は方便道なり。是の二空観に因りて中道第一義観に得入し、二諦を双照して心心寂滅し、自然に薩婆若海に流入す、と。
瓔珞経は大正大蔵経の第二十四巻に収められており、巻上(一〇一四b)にほぼこのとおりの文言を見ることができる。以下玄疏の解説である。
言う所の従仮入空観なる者は、無にして虚設する、之を謂いて仮と為す。仮を観じて無なること如幻如化にして但だ名字有るのみと知るは、即ち入空なり。而も説きて二諦観と為す者は、或いは是れ情智の二諦、或いは隨智の二諦に約するなり。
まず「無にして虚設する」というのは、一切法空の立場から「今ま四句もて境を検(しら)ぶるに不可得にして、而も説きて境と為す者は即ち是れ仮境なり。亦た是れ不思議境なり」(五二五b)ということである。
次に従空入仮観を釈すれば、若し空に住せざれば、還た幻化に入る。仮りに世諦と名づけ、分別して滞ること無き、即ち是れ従空入仮観なり。
而して平等と言う者は、前の若(ごと)きは俗を破して眞を用いるのみなれば平等と名づけず。此の観は破用等しければ平等と名づくるなり。(五二五b)
「従仮入空観」を二諦観と称し、「従空入仮観」を平等観と呼ぶ。これはなぜからいえば前者が俗諦を破して、一方的に眞諦だけを用いるのに対して、後者は俗諦を破すると同時に俗諦を立てるからである。
「従仮入空観」とは、「仮境をふまえて空諦に悟入する観法」ということであるが、二諦観に即していうと、俗諦観を破棄して眞諦観を用いることである。摩訶止観三上(大46―二四b)にいう、
言う所の二諦なる者は、仮を観じて入空の詮と為す、空は詮に由りて会するなり。能所合論す、故に二諦観と言う。
「詮」とは「言詮」「言筌」のことで、言葉という道具。仏性論四に「一切諸法は並びに是れ空を説くの方便なり」(大31―八〇九a)という。摩訶止観は続ける、
又た俗は是れ所破にして、眞は是れ所用なり。若し所破に従えば応に俗諦観と言うべし。若し所用に従えば応に眞諦観と言うべし。破用合論す、故に二諦観と言う。
止観輔行伝弘決三之二に次のように解説する(大46―二二五c)、
又た俗はの下は、第三に破用に約して説くなり。若し所破有らば必ず能破有らん。能破は即ち是れ所用の眞諦なり。能所は孤ならず、是の故に倶立す。
「従空入仮観」とは、「空諦をふまえて仮諦に悟入する観法」ということであり、眞諦観を破棄して俗諦観を用いることである。摩訶止観(同前二四c)はいう、
従空入仮をば平等観と名づくる者は、若し是れ空に入らば、尚お空の有とす可きすら無し、何の仮か入る可けん。当に知るべし、此の観は衆生を化せんが為なることを。眞は眞には非ずと知りて、方便として仮に出づ、故に従空と言う。薬病を分別して而して差謬無し、故に入仮と言う。
平等なる者は、前に望んで平等と称するなり、前観は仮病を破して仮法を用いず、但だ眞法を用いるのみ。一を破して一を破せざれば未だ平等とは為さず。後観は空病を破して還た仮法を用う。破用既に均しければ異時に相い望む、故に平等と言うなり。
入空観は「仮病を破する」ことを狙いとし、入仮観は「空病を破する」ことを目的とするが、前観が眞諦観を用いるのみなのに対して、後観は前観のあとを受けつつ「空病を破する」ために「還た仮法を用う」、すなわち俗諦観をも用いることになるので、「破」と「用」とを等しく用いるという意味で平等観と言うのである。
■ 中道観
維摩玄疏は続ける(五二五c)、
次に中道観を釈すれば、中は不二を以て義と為し、道は是れ能通をば名と為す。一実諦を照らし、虚通して滞ること無き、中道観と名づくるなり。
故に経に云わく、前の二観を方便道と為す。是の二空観に因りて中道に得入し、二諦を双照して心心寂滅し、自然に薩婆若海に流入す、
「一実諦」とは、玄疏が「此の三は通じて観と名づくる者は、観は観穿を以て義と為し、亦た是れ観達を能と為す」(五二五c)と説明するとろで涅槃経の文を引き、「金剛に至るとは、即ち一実諦なる仏性の理に達するなり」と解説するように、仏性のことである。玄疏は続ける、
問うて曰わく、三観は倶に二諦を照らすに、何等の殊有りや。
答えて曰わく、前観は二諦を照らすと雖も、破用不等なり。
次観は亦た二諦を照らして破用平等なるも、既に中道を見ざれば、但だ是れ異時に平等なるのみ。
第三観なる者は、中道を見るを得て二諦を双照すれば、即ち是れ一時に平等なるなり。
「破用不等」というのは、入空観が「仮病を破する」ために眞諦観を用いるだけなのでこう言うのである。
「破用平等」というのは、入仮観が、入空観が「破俗用眞」するのを承けて、「空病を破する」ためにさらに「破眞用俗」して俗諦観をも用いるから、つまり二諦を平等に用いるのでこう言うのである。「但だ是れ異時に平等なるのみ」というのは、その事情を説明するのが次の文章である。玄疏はいう(五二八a)、
中道第一義観を明らむれば即ち三意と為す。
一に所観の境を明らむれば、前の二観は是れ方便なり。二諦を照らすの智有りと雖も、未だ無明を破して中道を見ざれば、眞俗別照す、即ち是れ智障なり。
「眞俗別照す」というのが「異時平等」、つまり眞諦と俗諦とを平等に観照するけれども別々の時に行うということであるが、それはいまだ無明を破して中道を見ていないからだという。そこで「一時平等」へと進むことが要請される。玄疏は続ける(五二八b)、
二に修観の心を明らむれば、若し此の観を修せば、還た前の二観を用いて双忘双照の方便とす。
双忘の方便なる者は、初観に俗は俗に非ずと知る、即ち是れ俗空なり。
次観に眞は眞に非ずと知る。即ち是れ眞空なり。
俗を忘ずるは非俗、眞を忘ずるは非眞にして、非眞非俗なる即ち是れ中道なり。
是の二空観に因りて中道第一義諦に入るなり。
「俗は俗に非ず(俗非俗)」というのは、智度論九五(大25―七二七b)に示すところの、
色如非色非離色
色の如は、色に非ず(=色即是空)、色を離れず(=空即是色)という図式にもとづくもので、空の表明である。これを「俗空」と呼ぶが、これは「破俗用眞」である。
同様に、「眞は眞に非ず」というのは「眞空」の謂いであり、これは「破眞用俗」である。
「 双忘」とは、「双遮」ともいうが、「忘俗」つまり「破俗用眞」すると同時に、「忘眞」つまり「破眞用俗」することであり、眞俗二辺を忘ずるので「二空観」と呼ばれる。
これが「破用平等」のうちの「一時平等」にほかならないが、その時、眞俗二諦は共に「所破」である。しかるに前に見たように、「若し所破有れば必ず能破有り」(止観輔行弘決三之二)であるから、眞俗の二諦は同時に「能破」でもある。そこを見とどけるのが「双照」である
(9)。