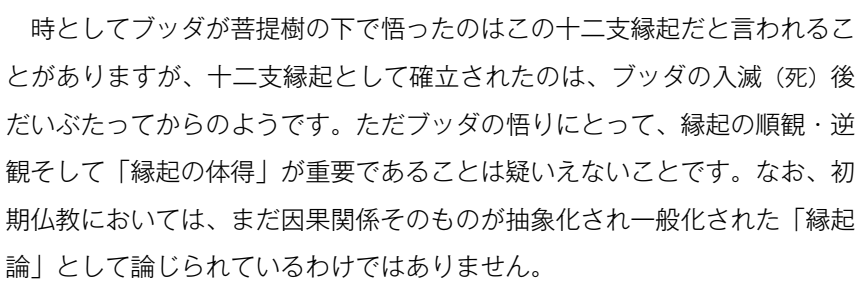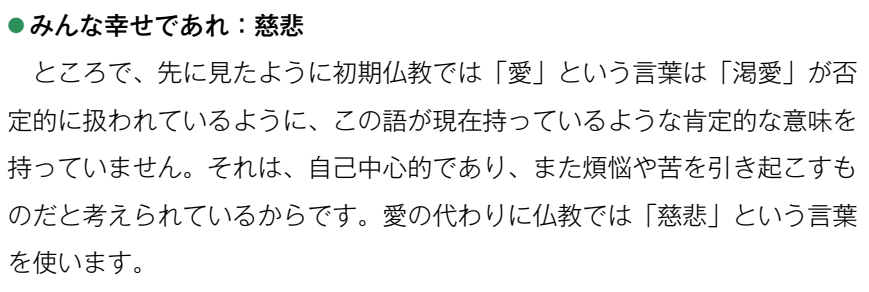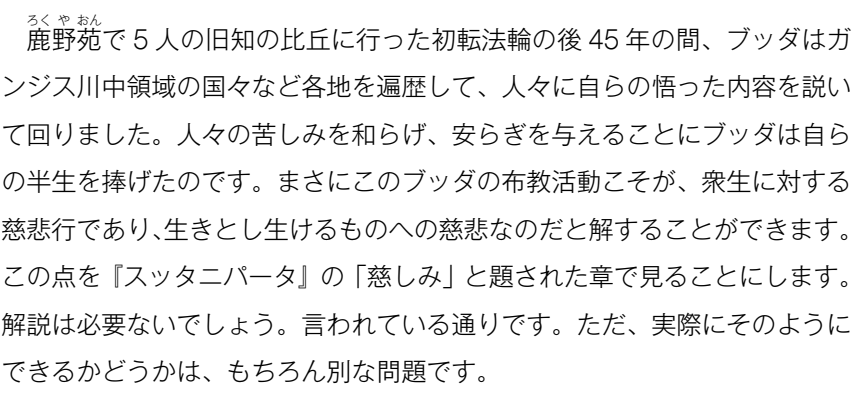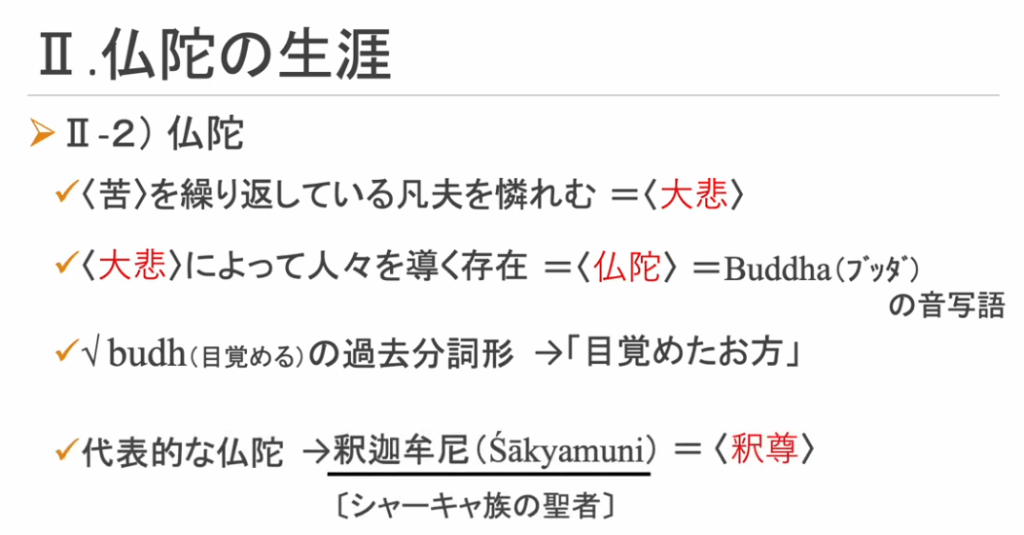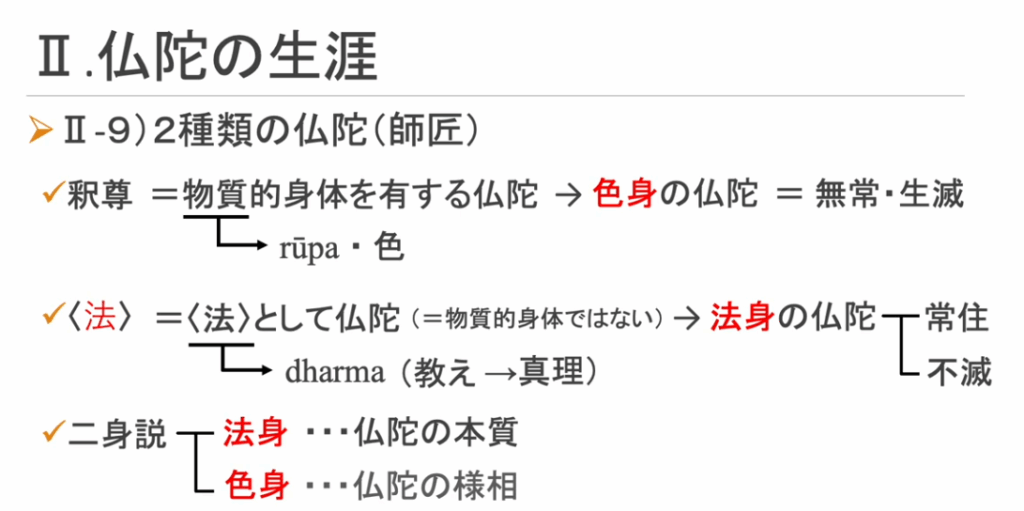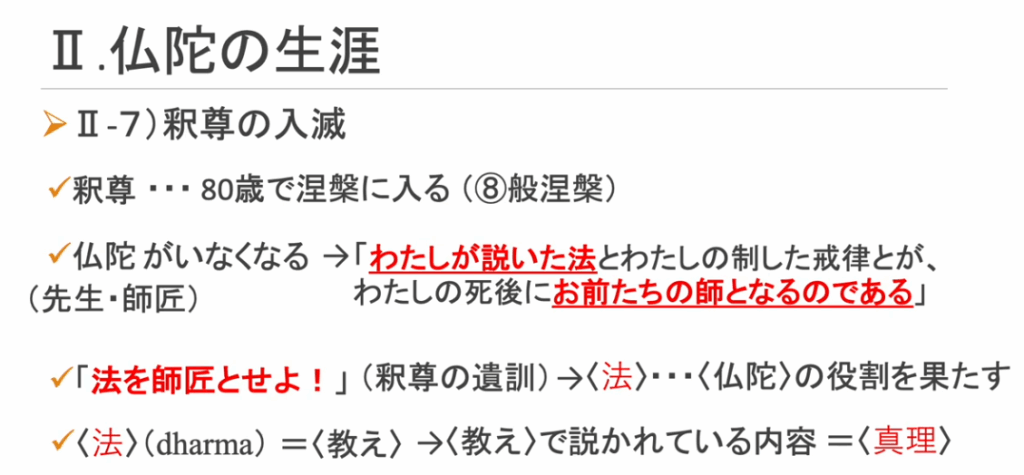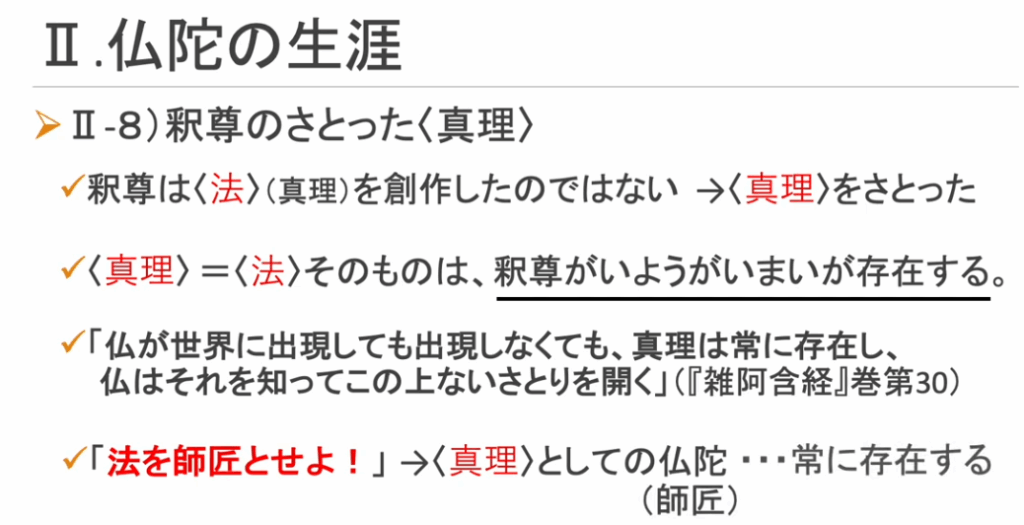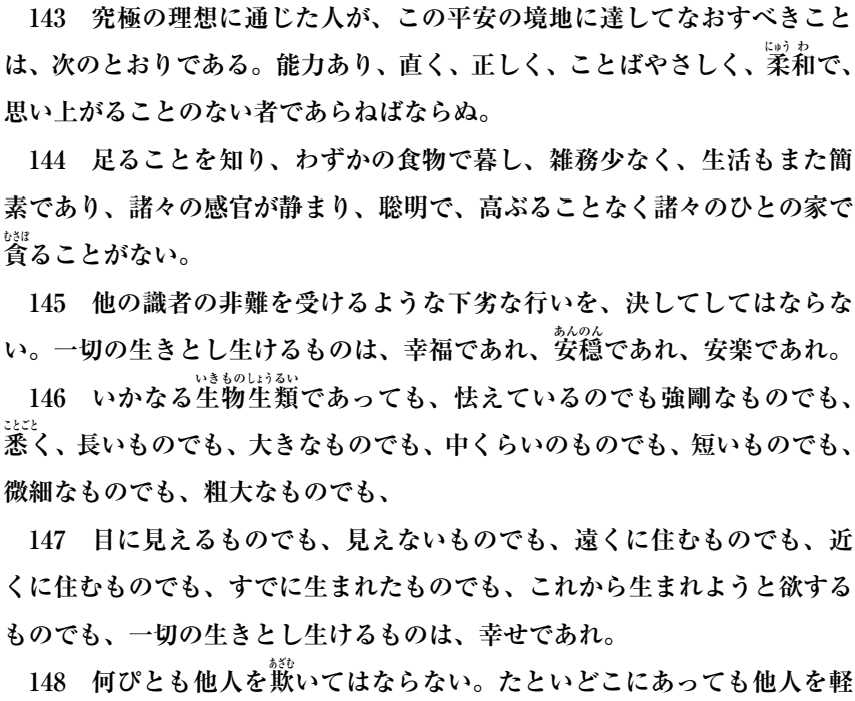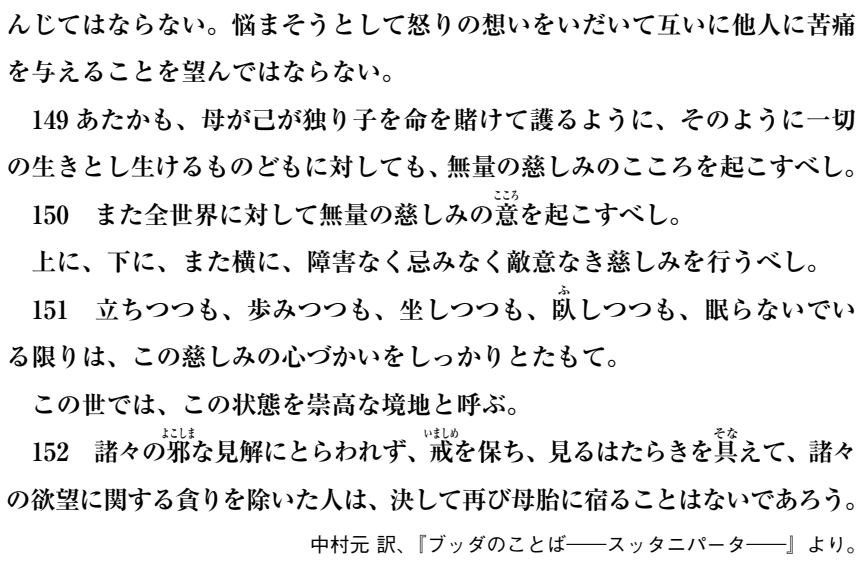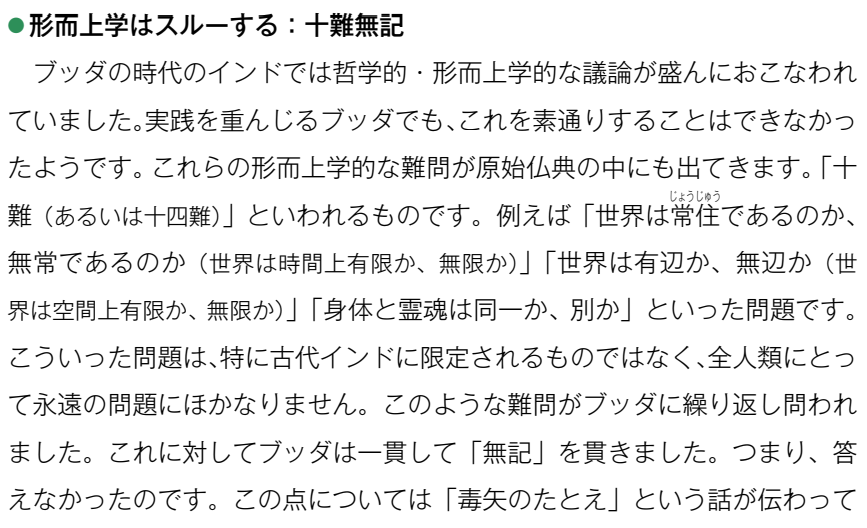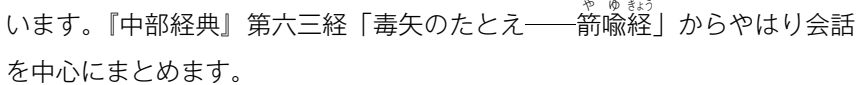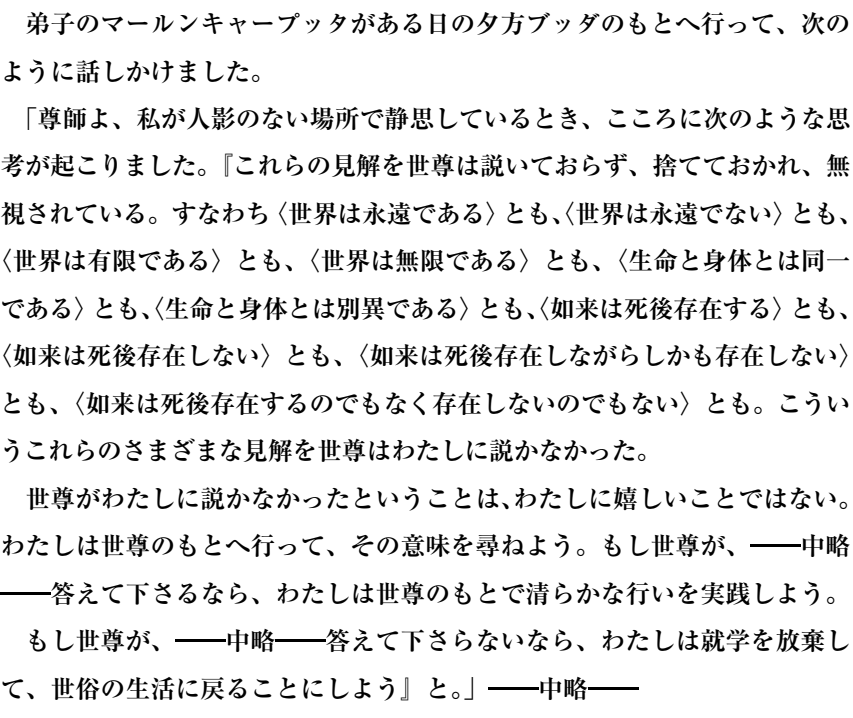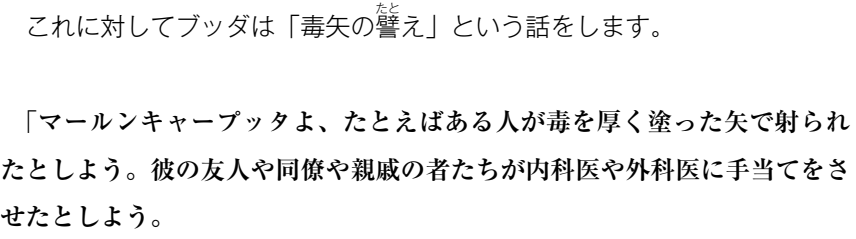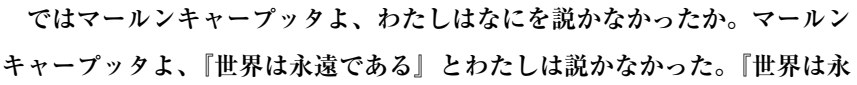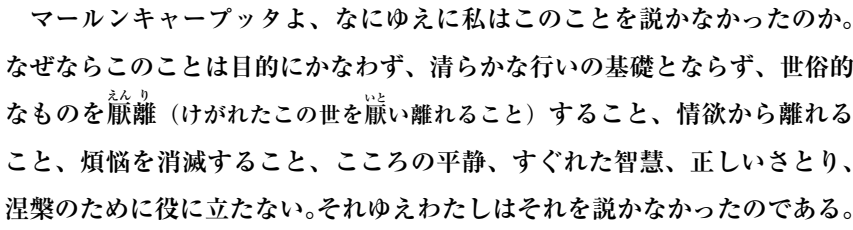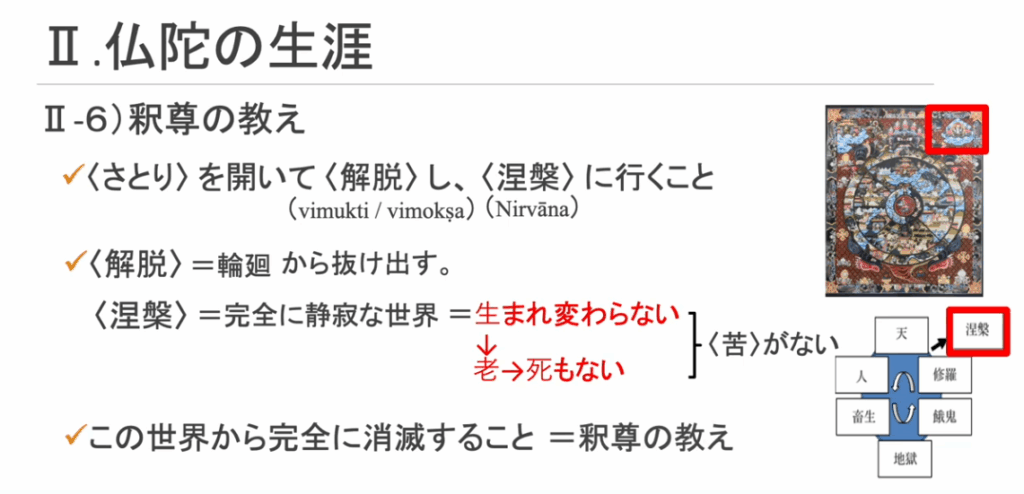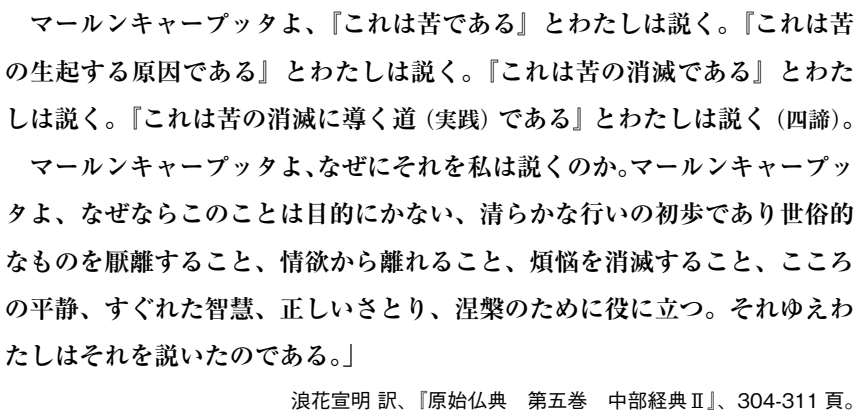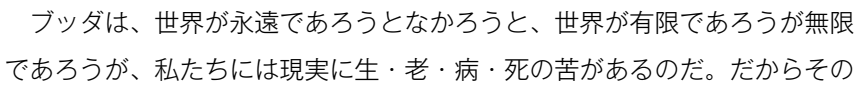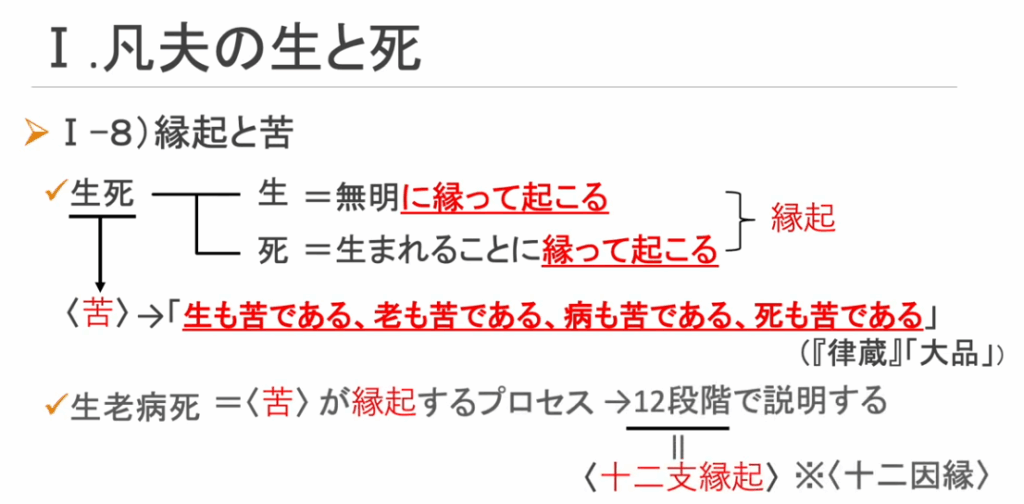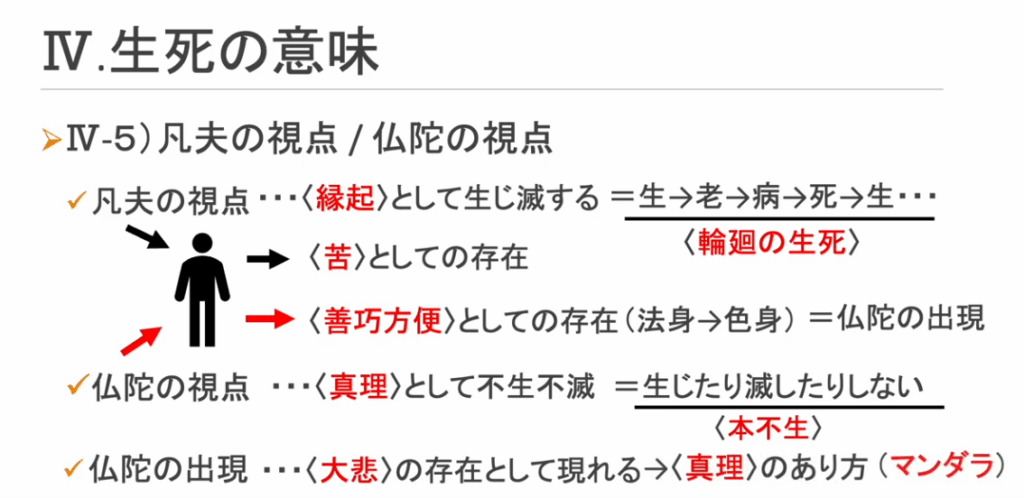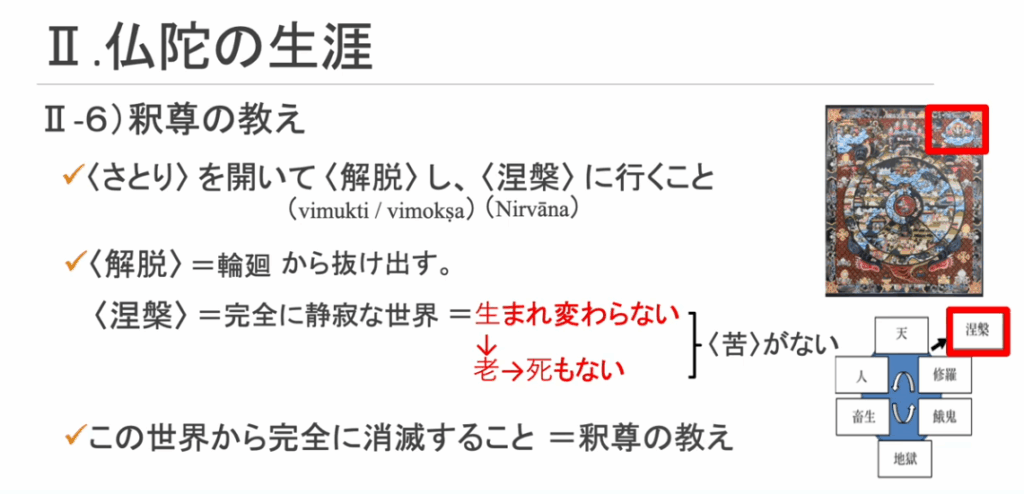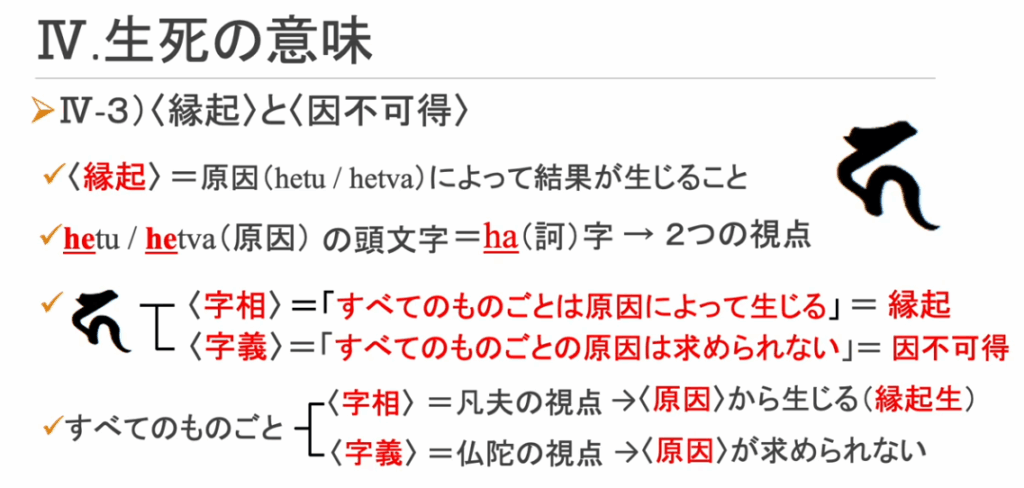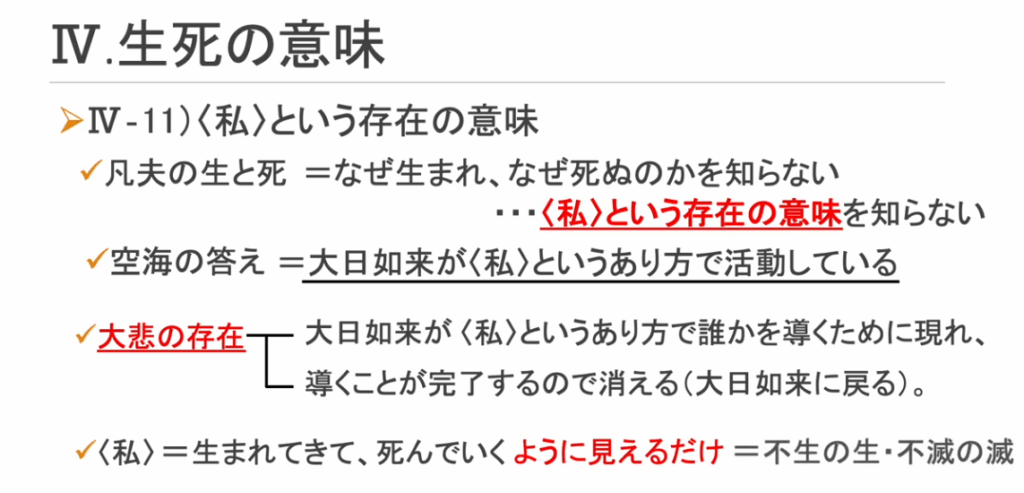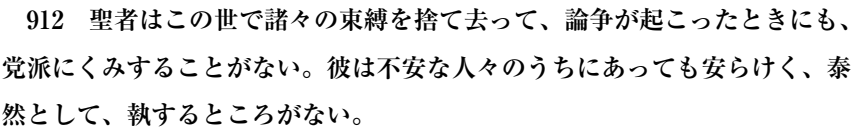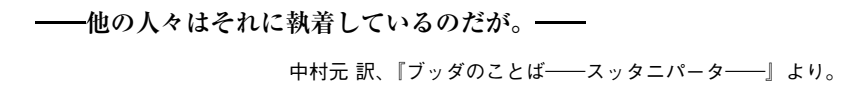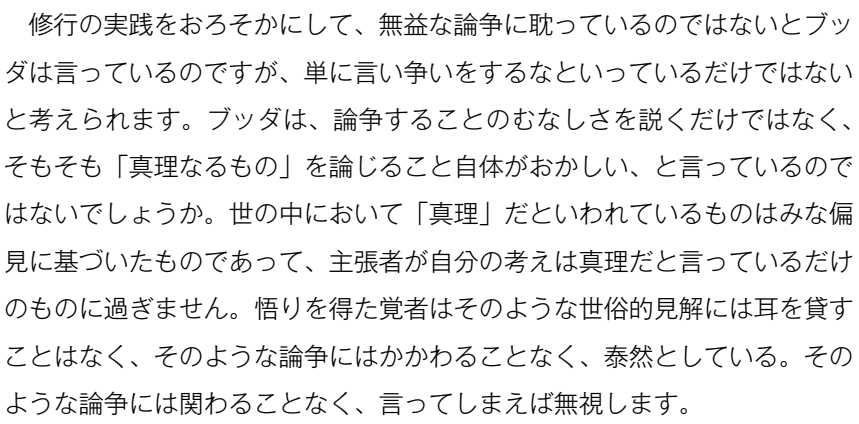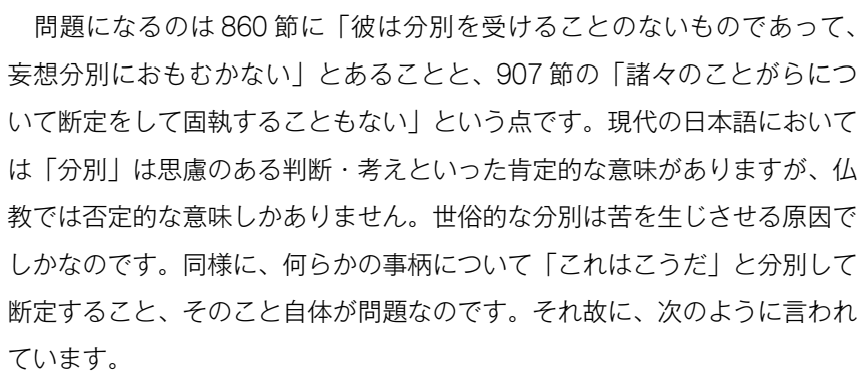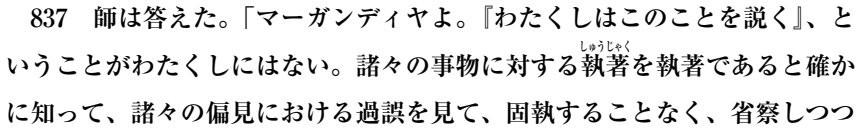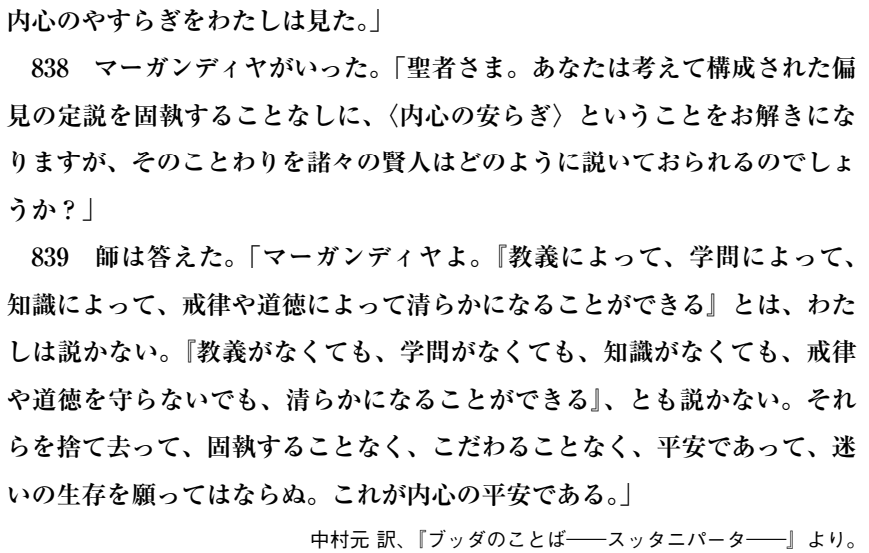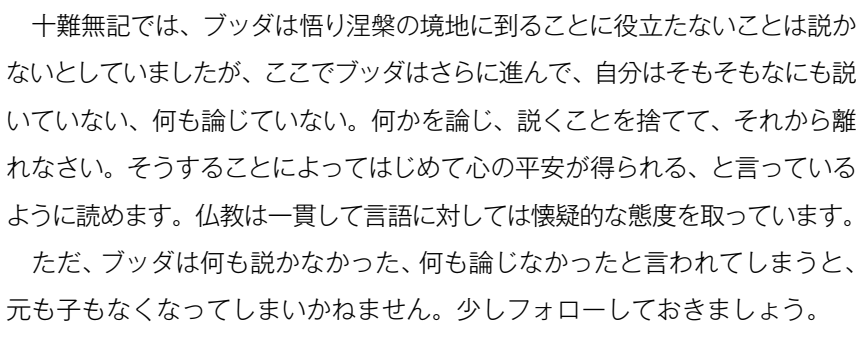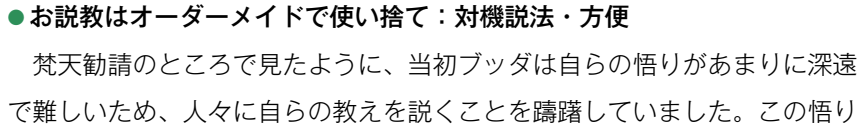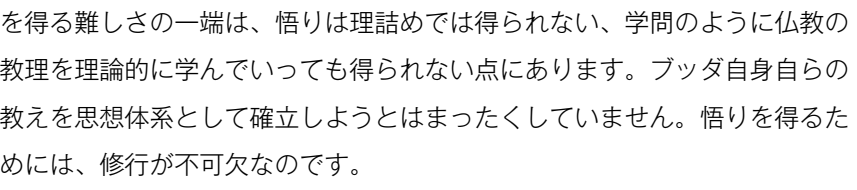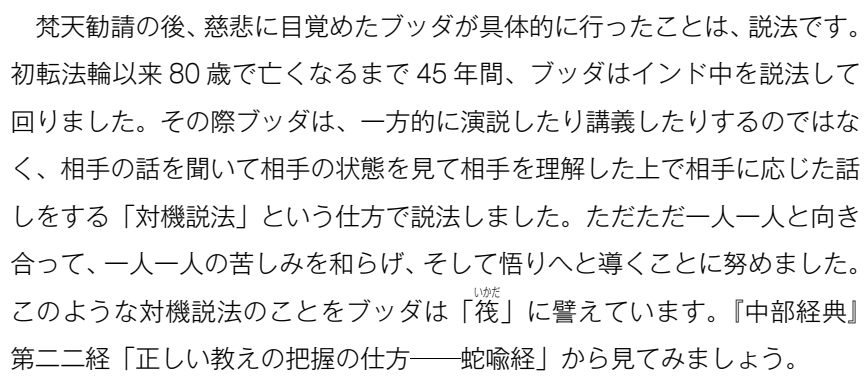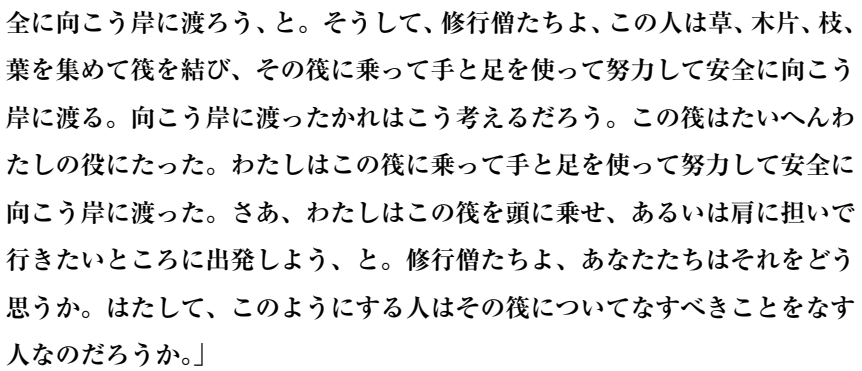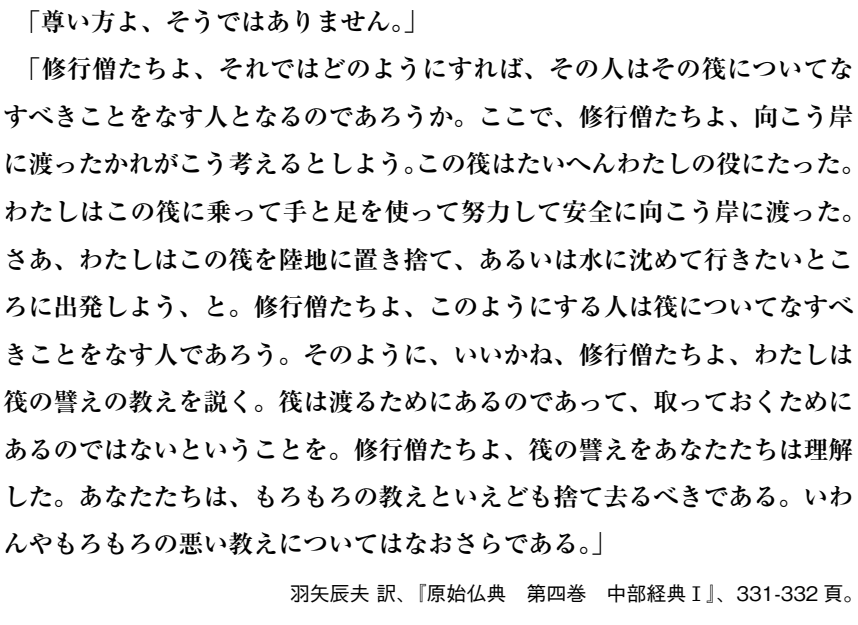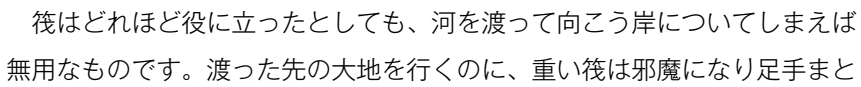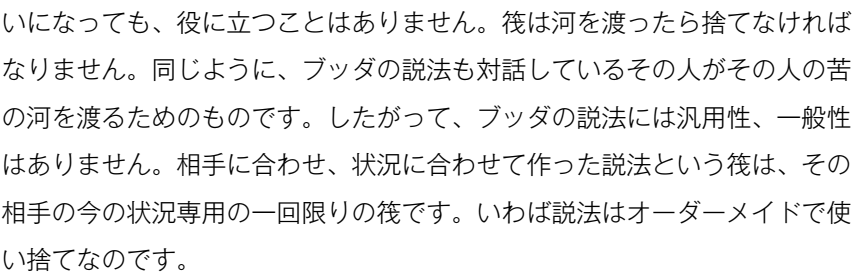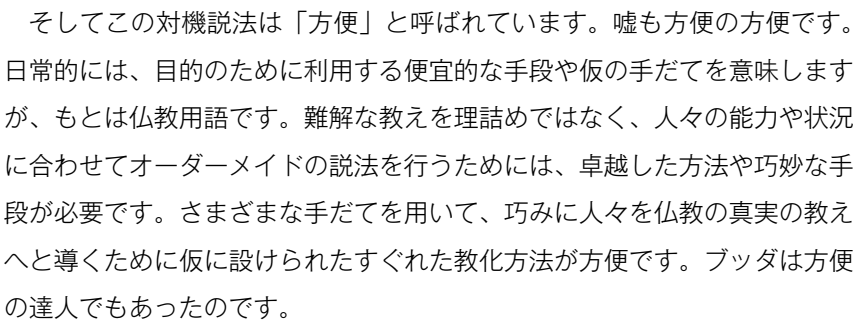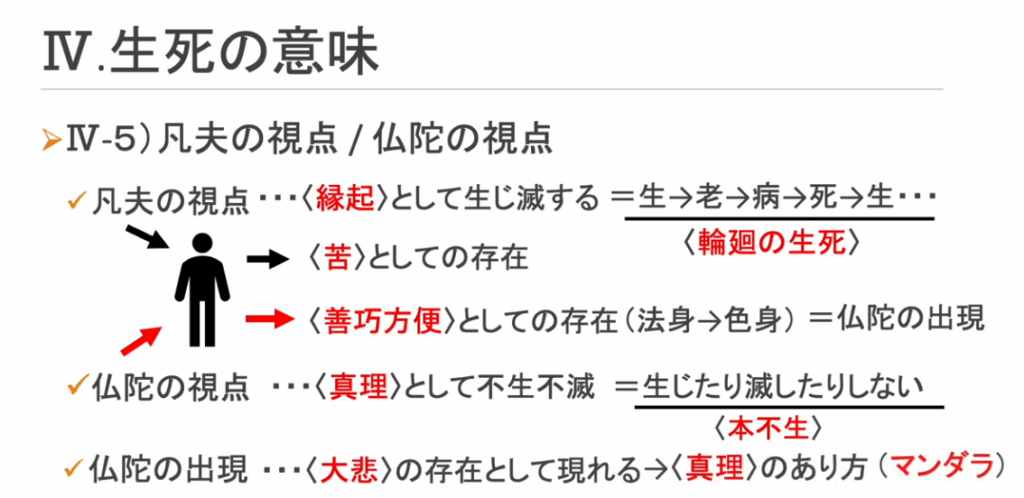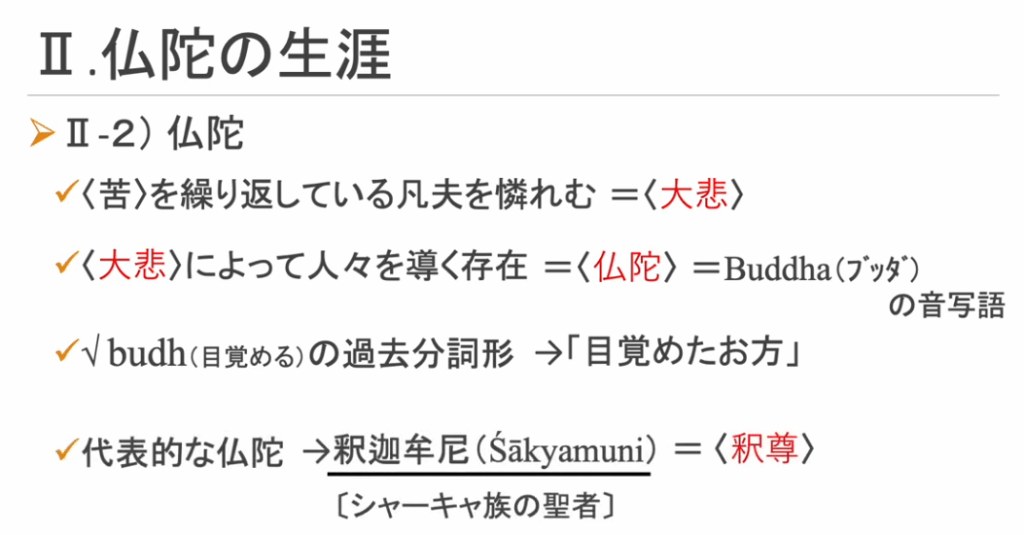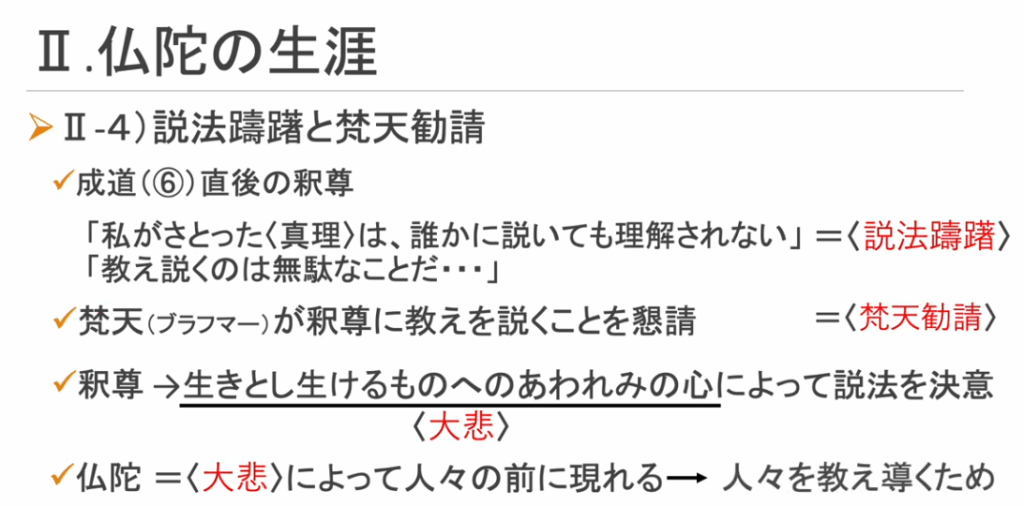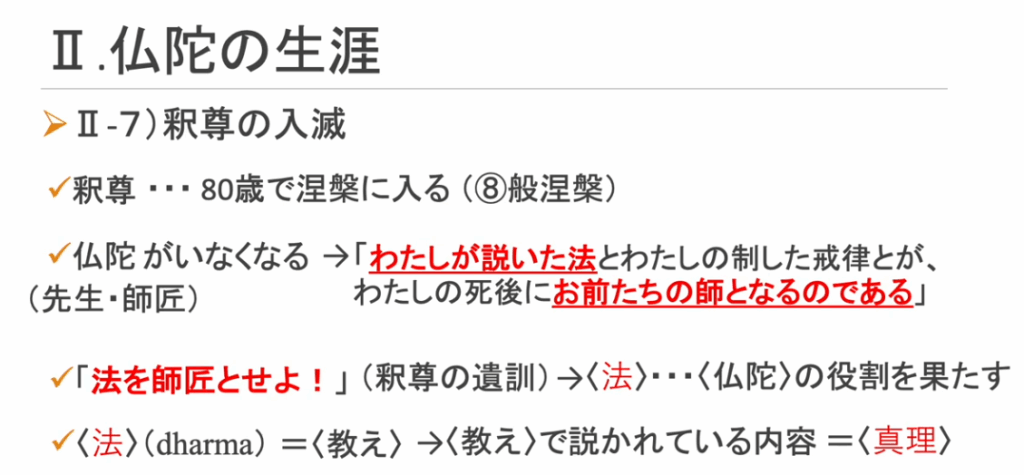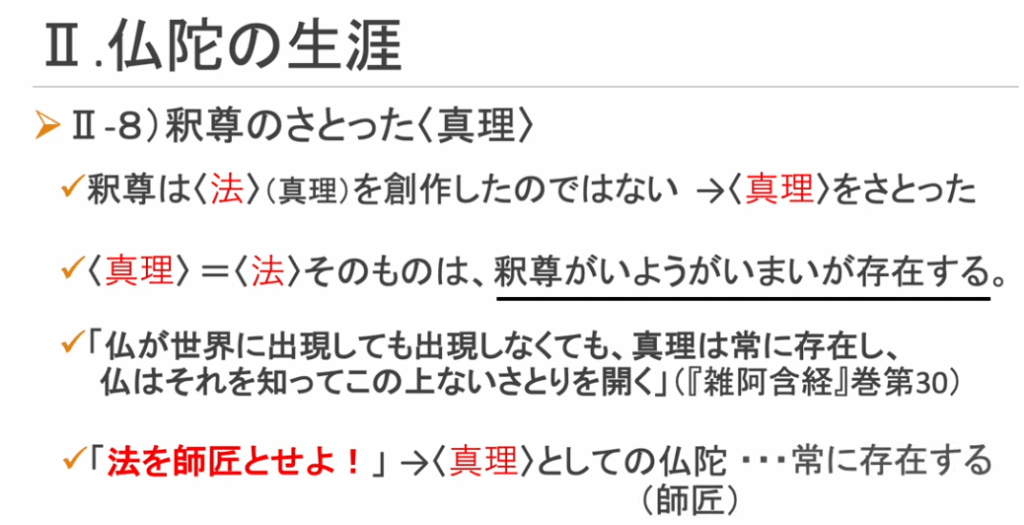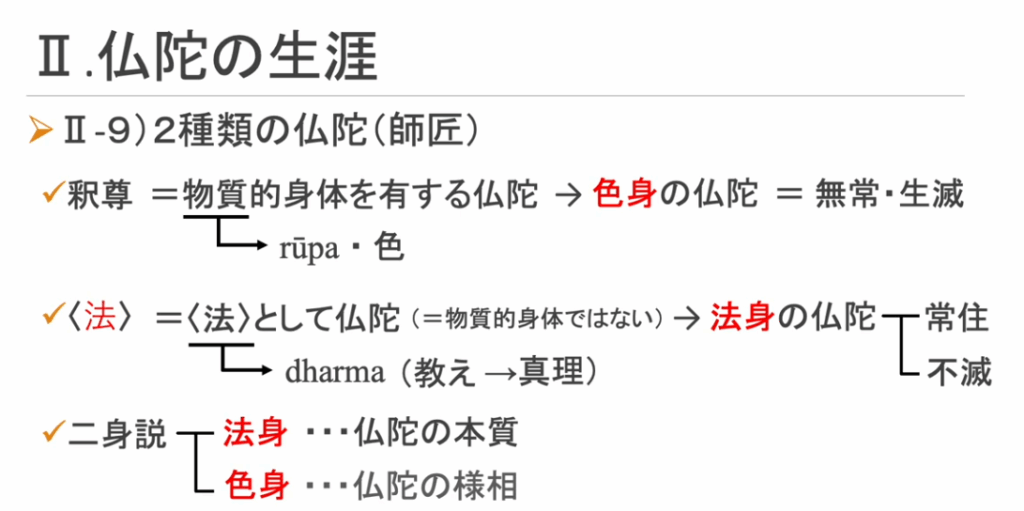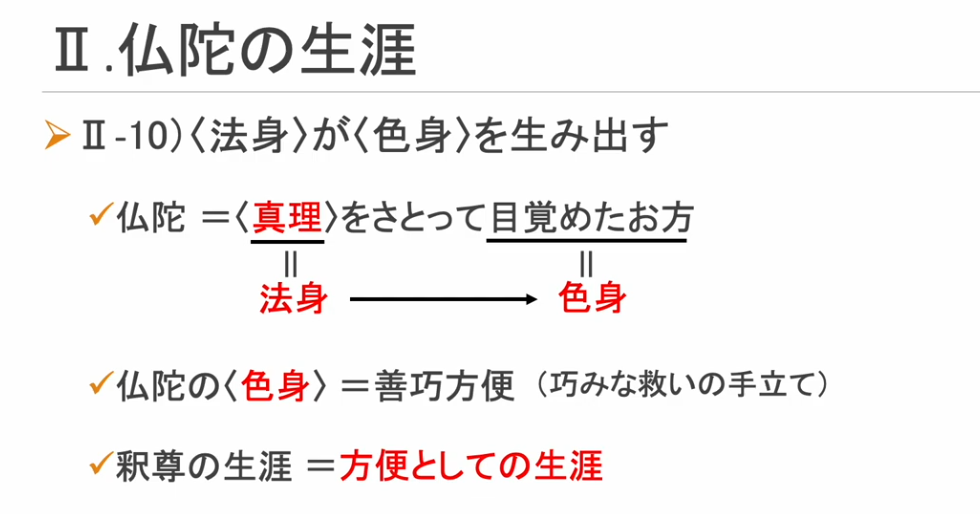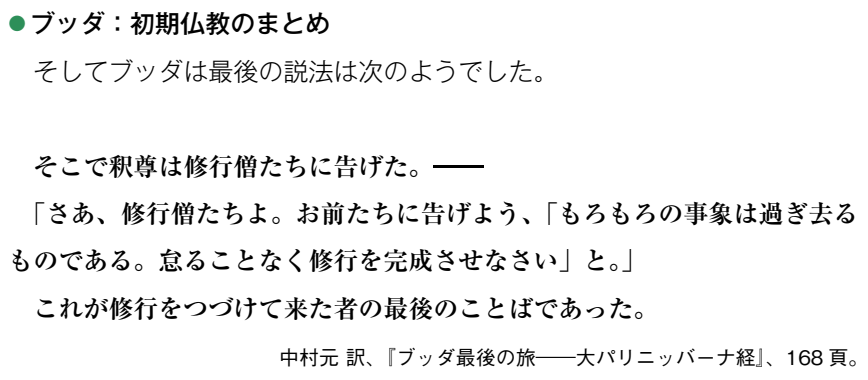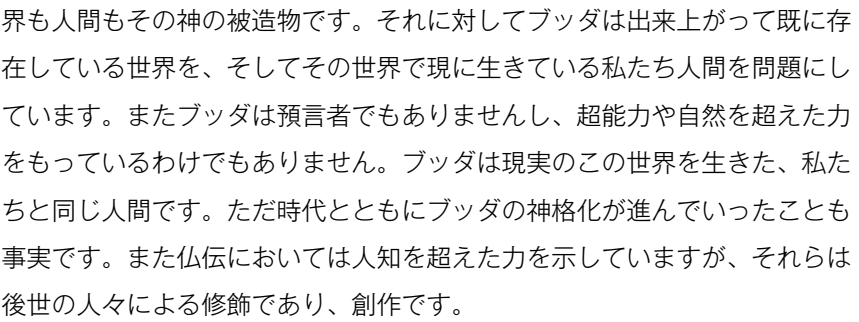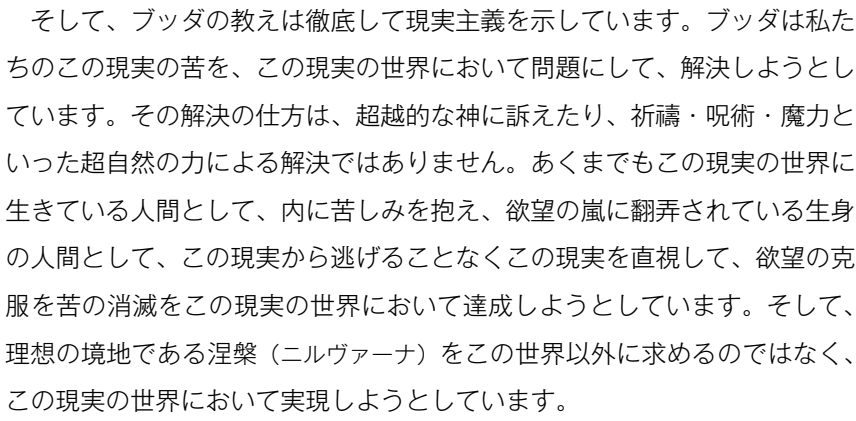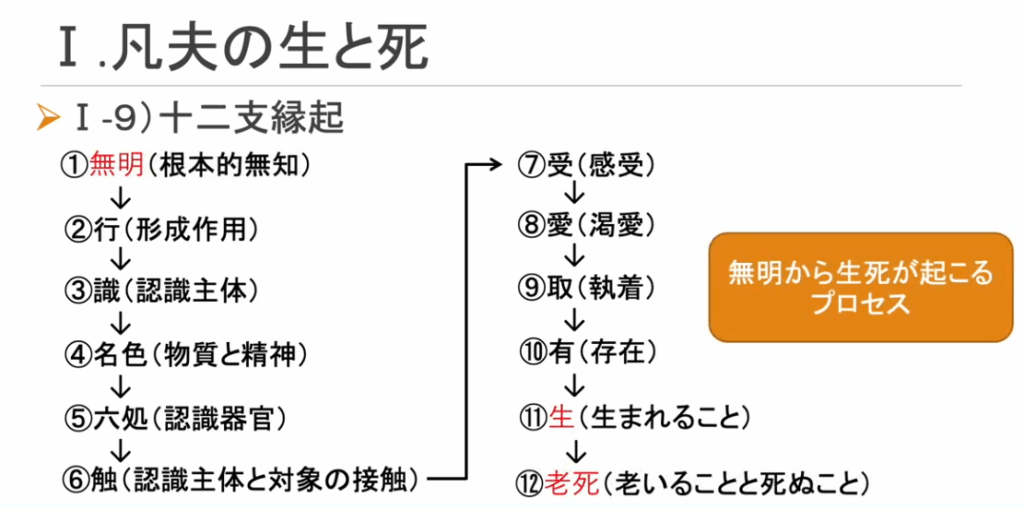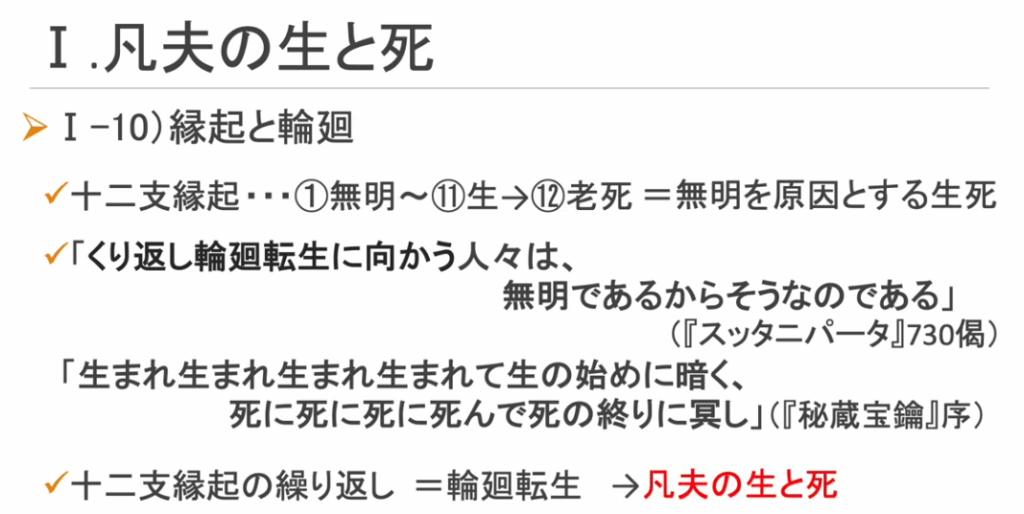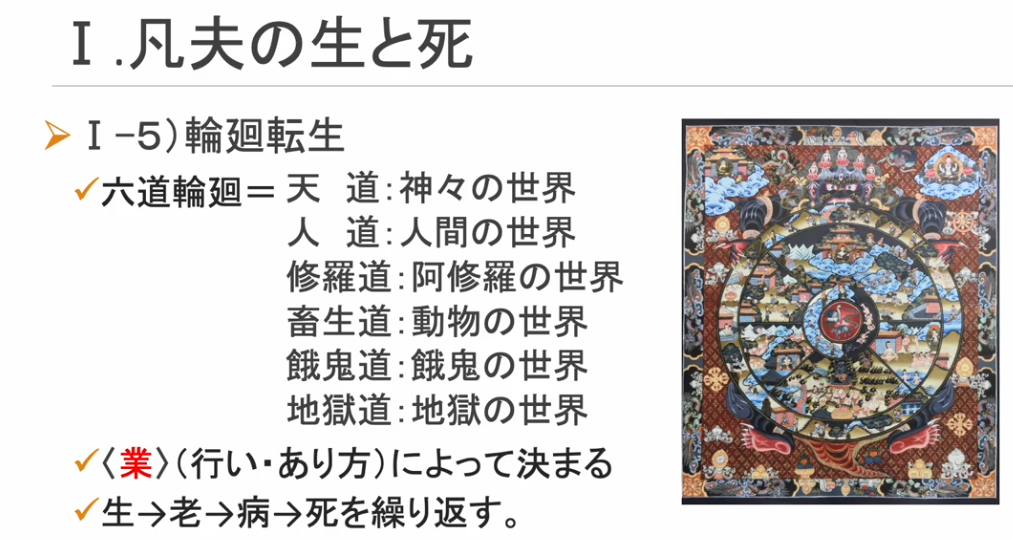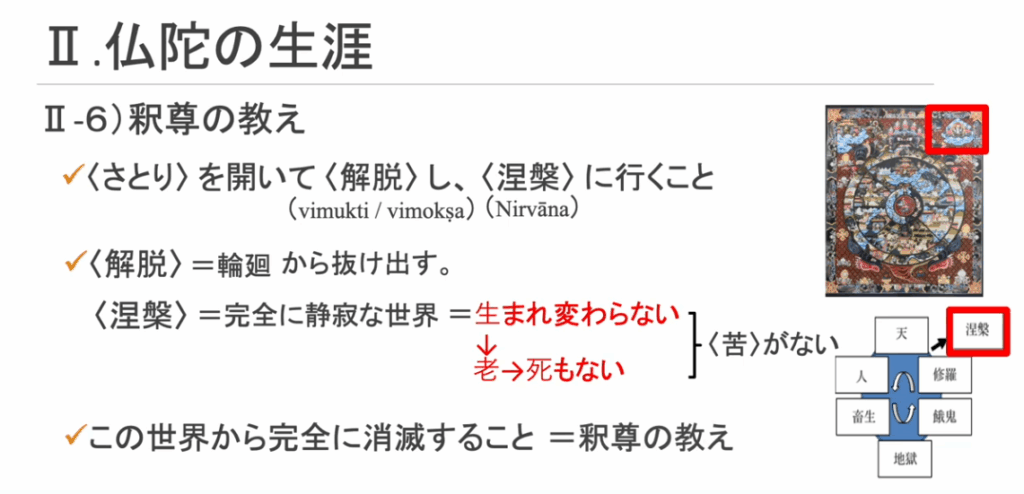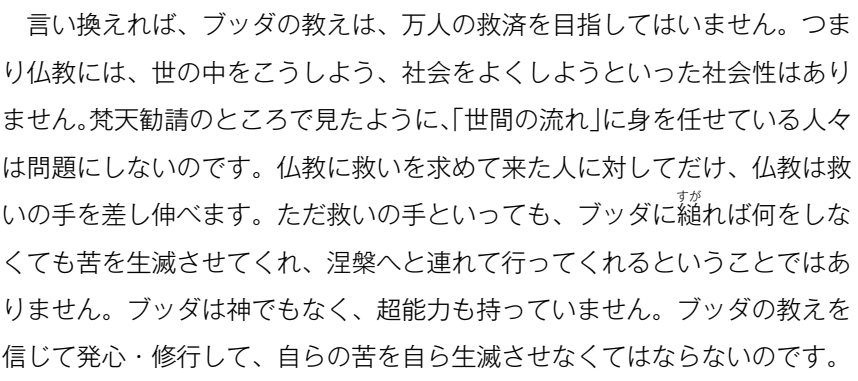出典:https://www.fpu.ac.jp/news/d153809_d/fil/booklet_2.pdf
は じ め に
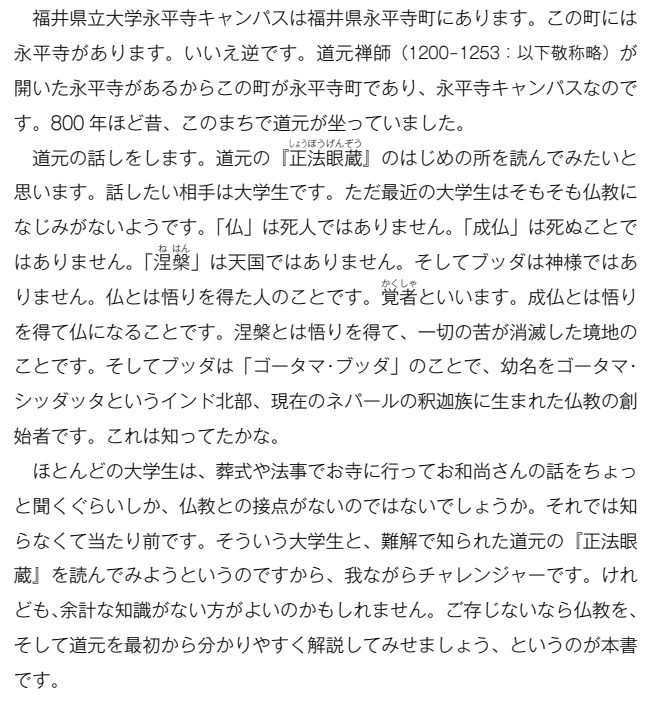
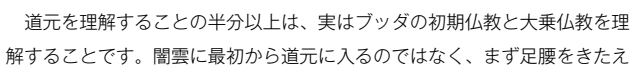
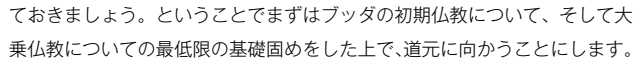
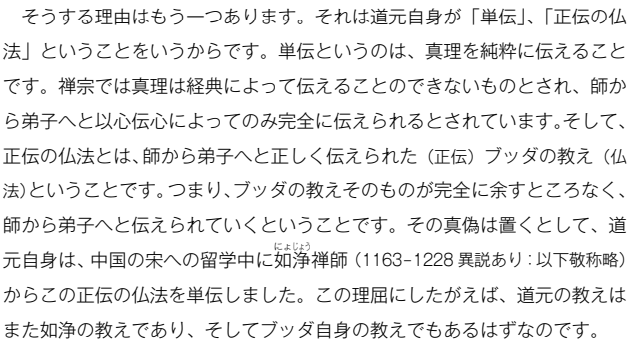
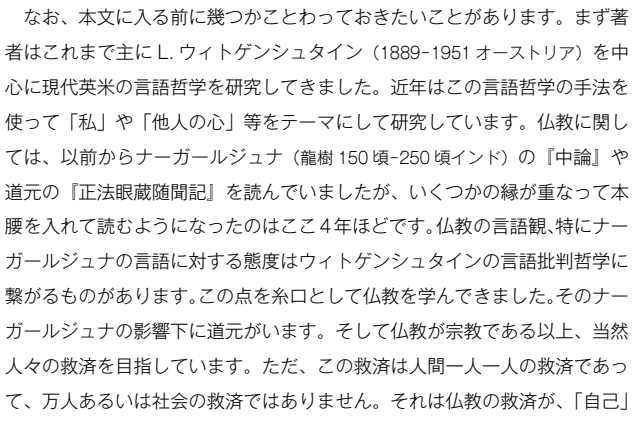
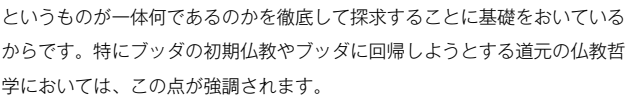
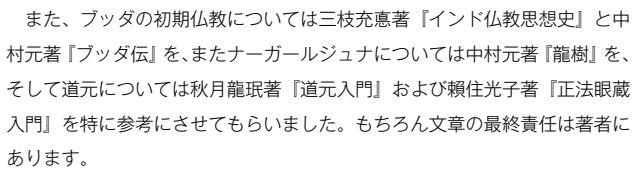
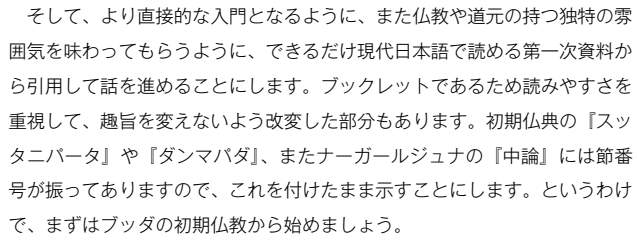
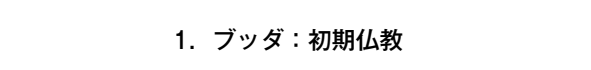
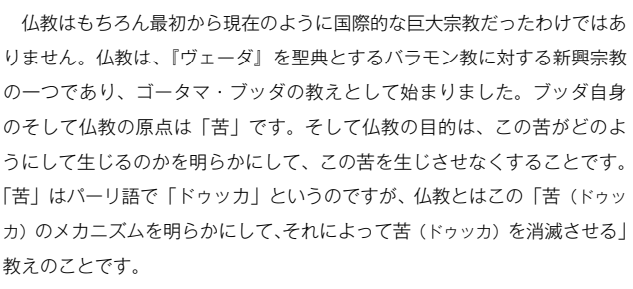
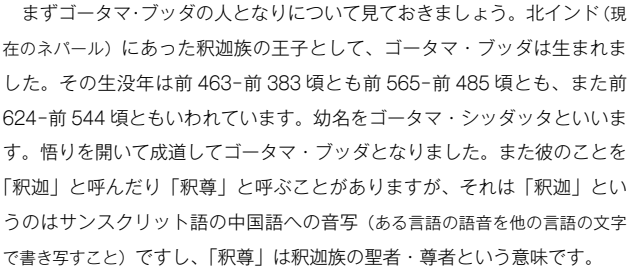
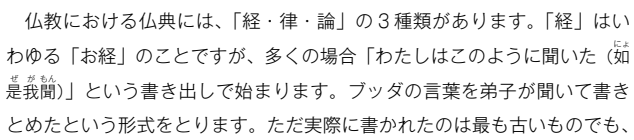
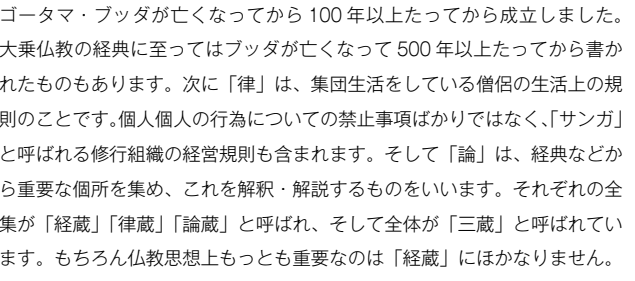
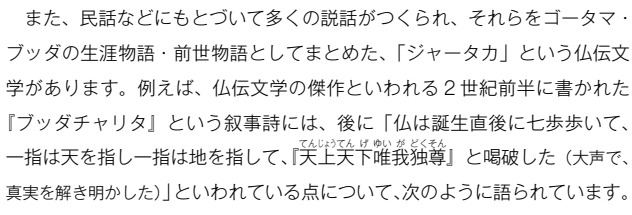
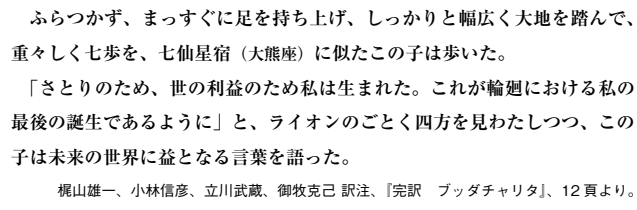
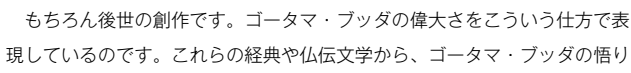
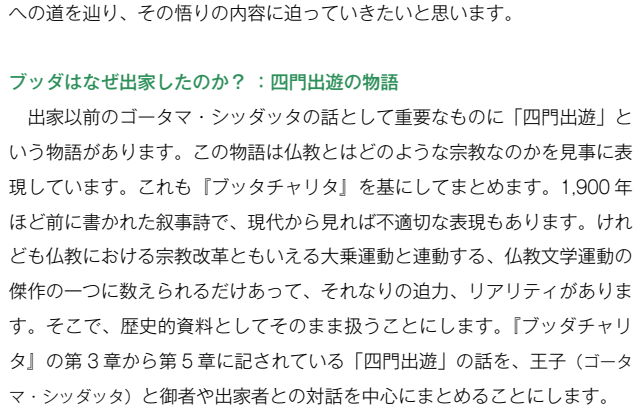
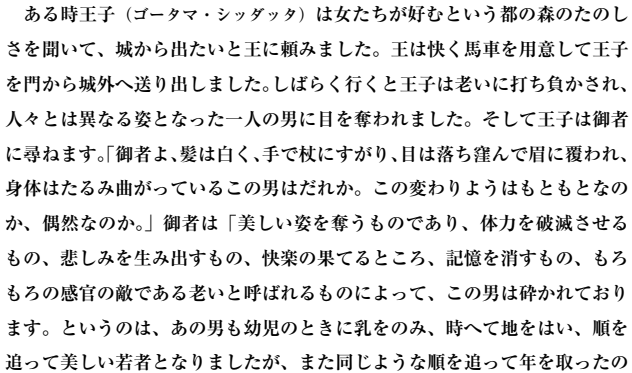
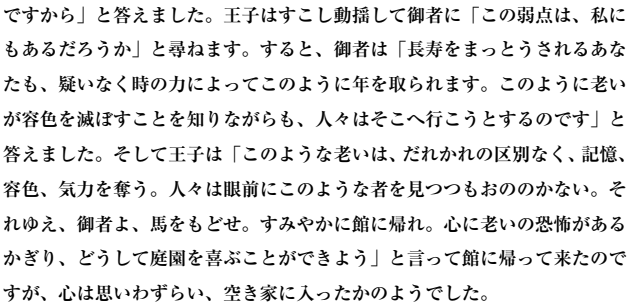
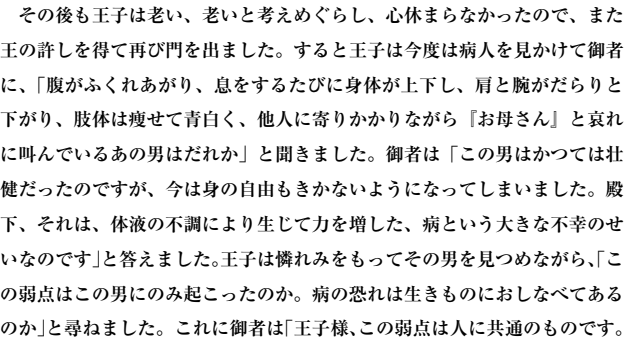
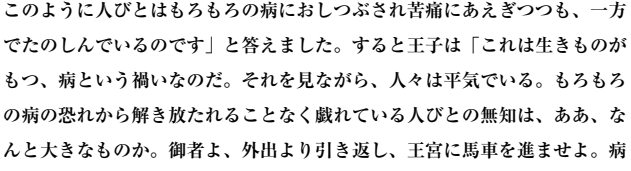
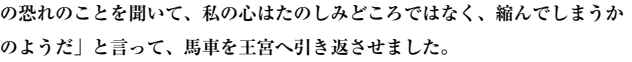
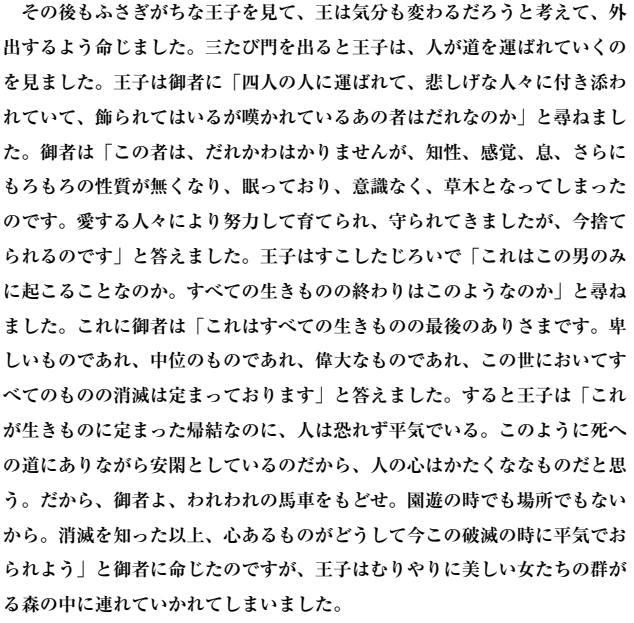
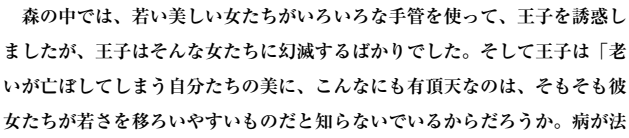
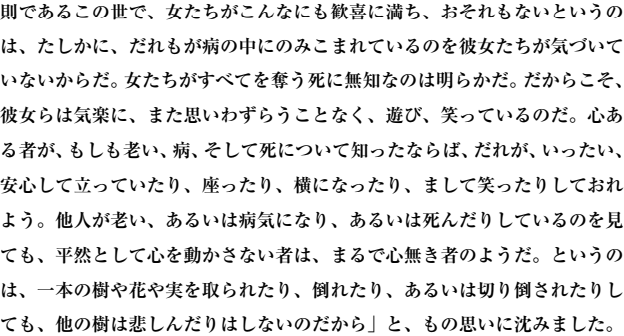
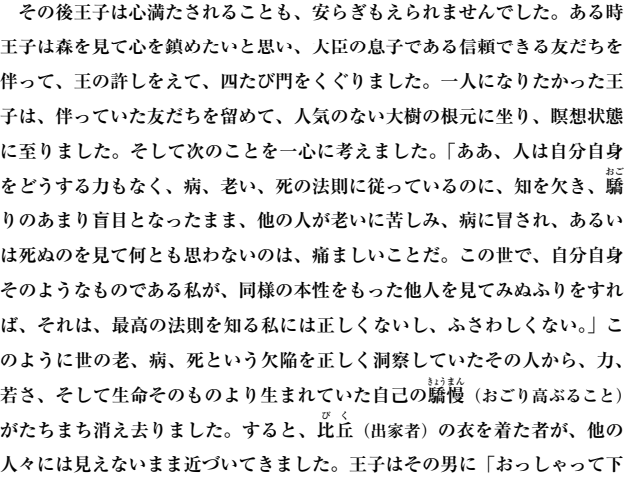
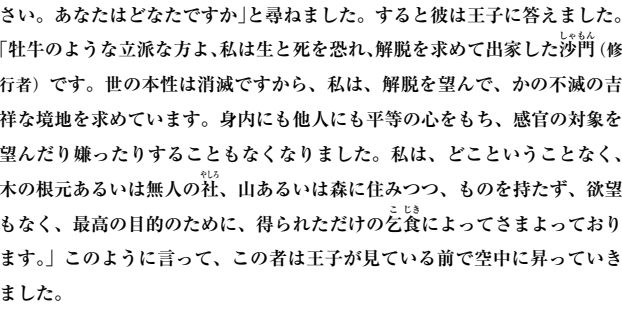
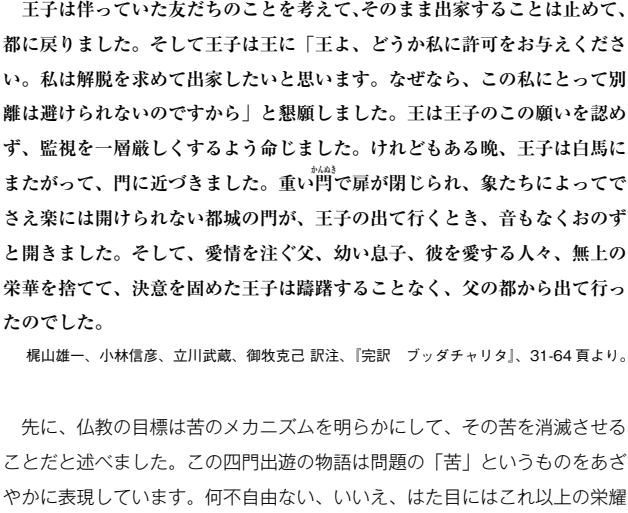
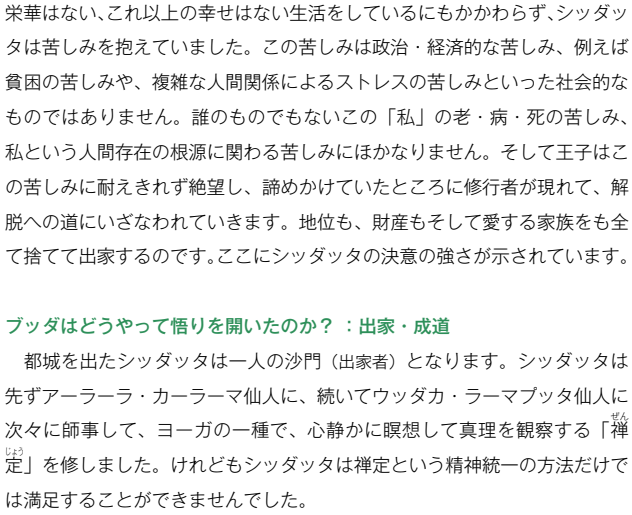
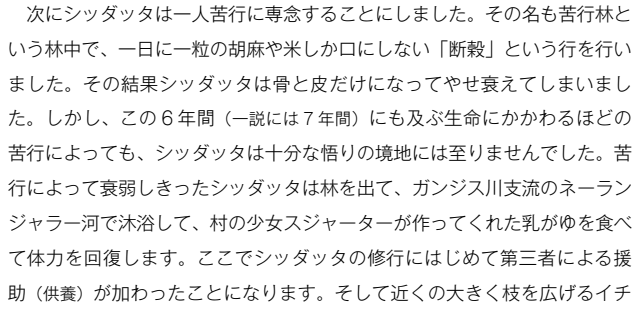
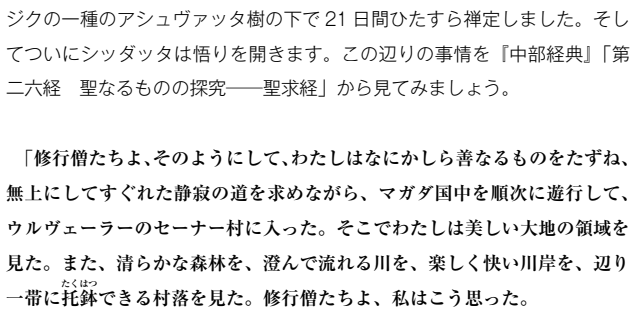
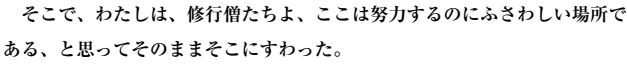
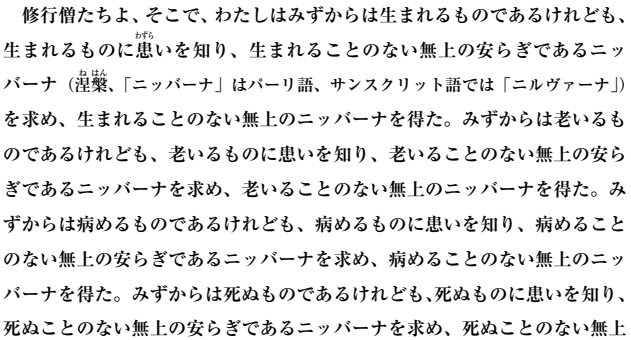

<参考情報>
■釈尊の悟り
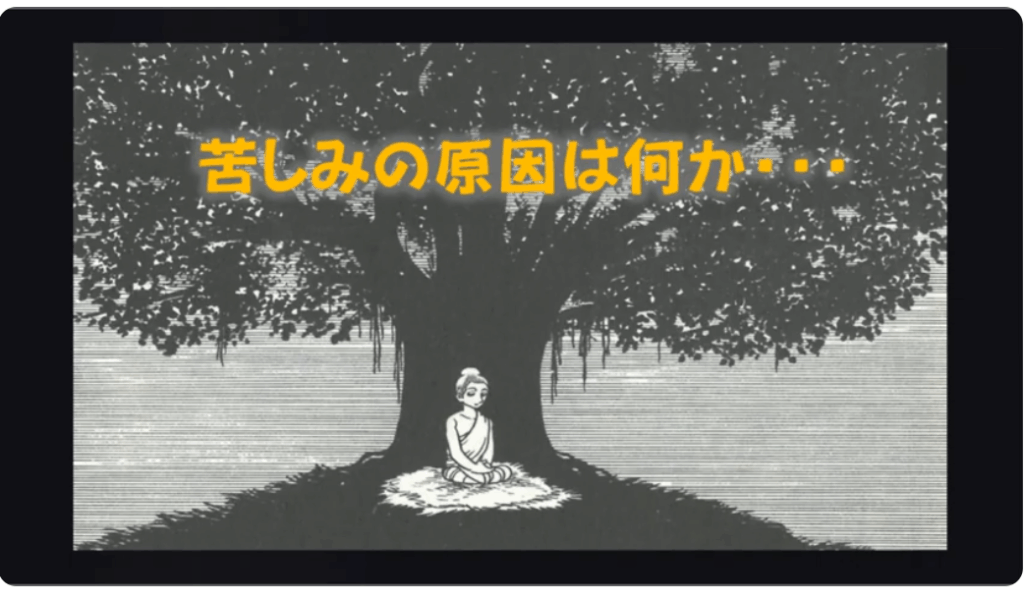
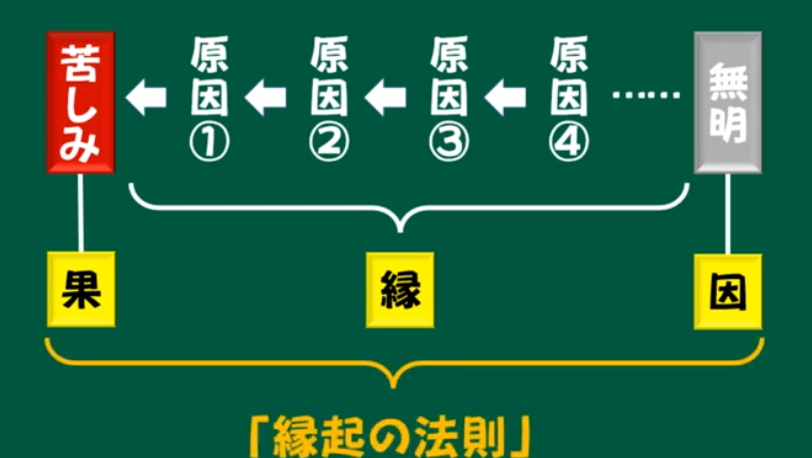
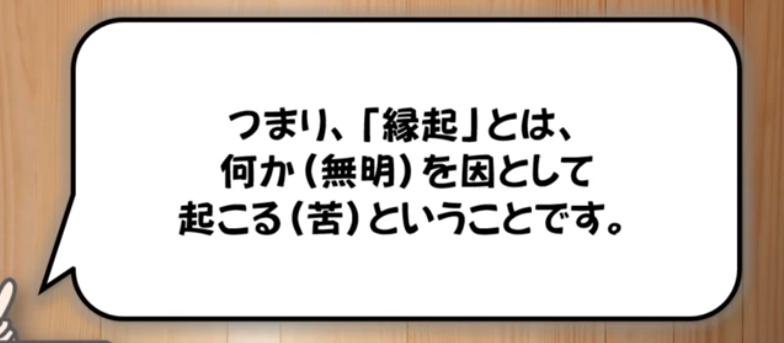
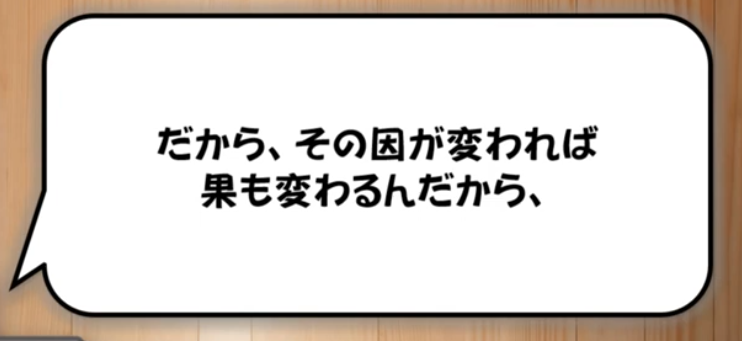
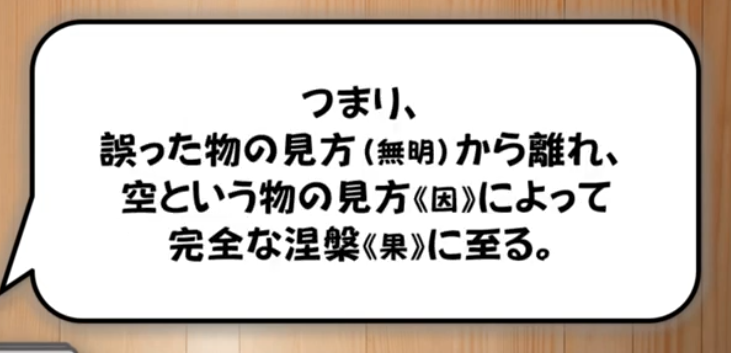
出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~
<参考情報>
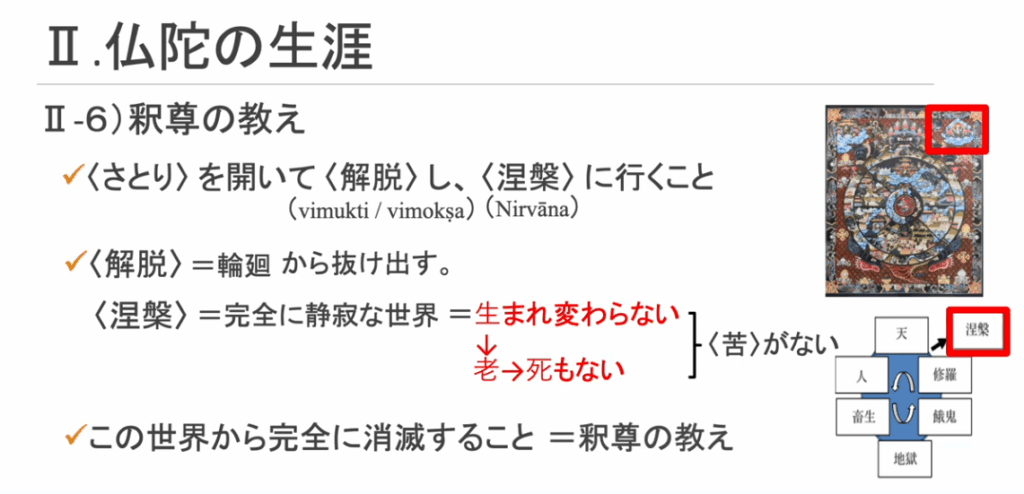
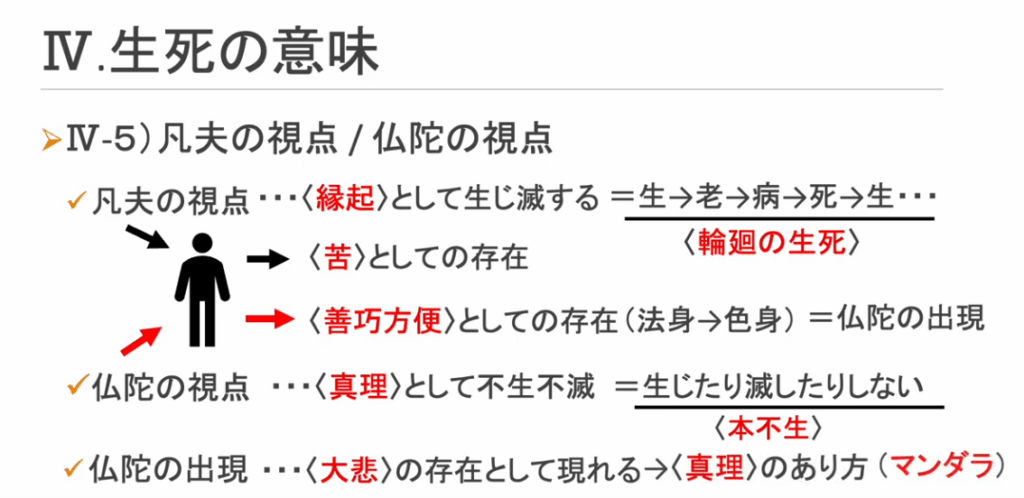
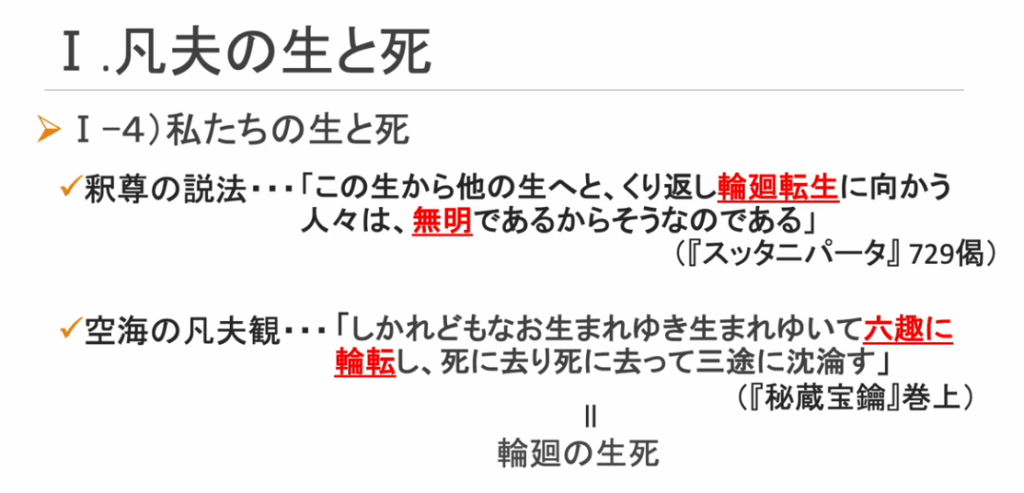
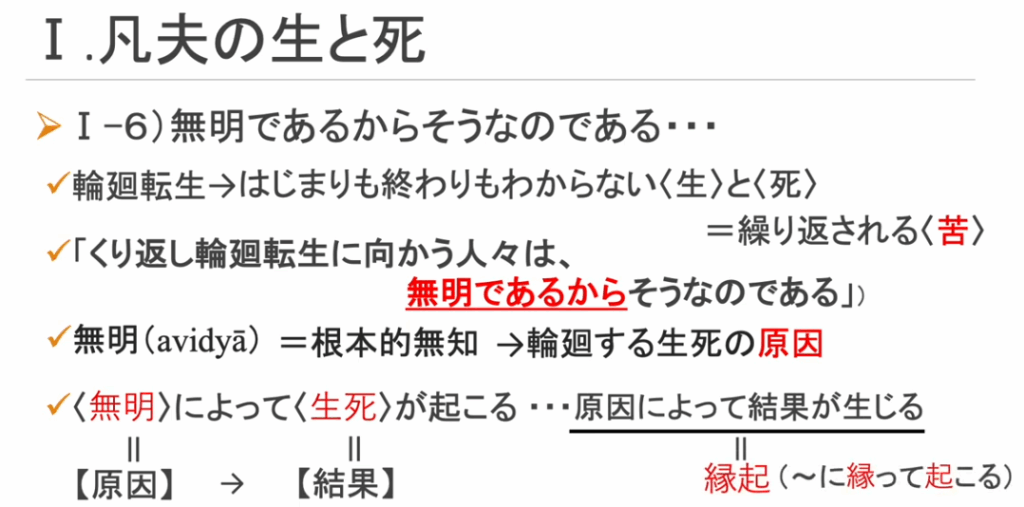
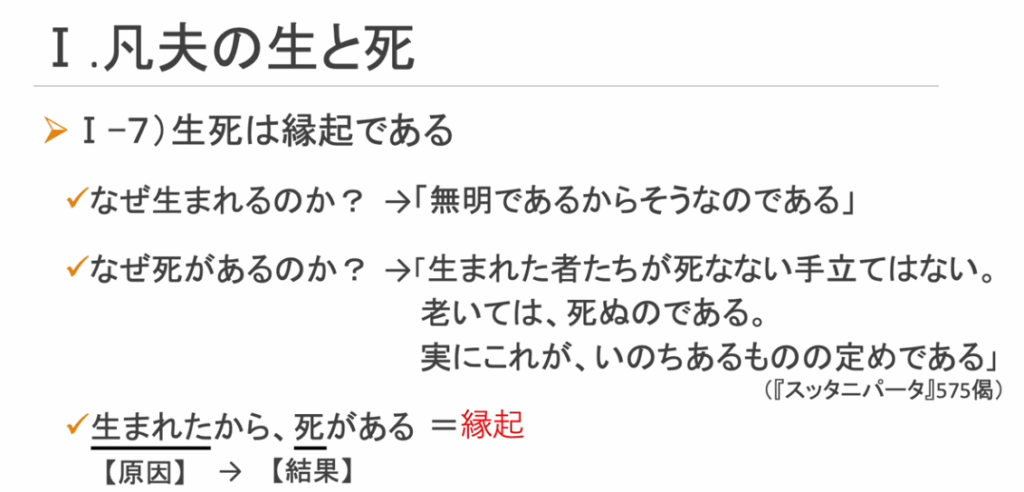
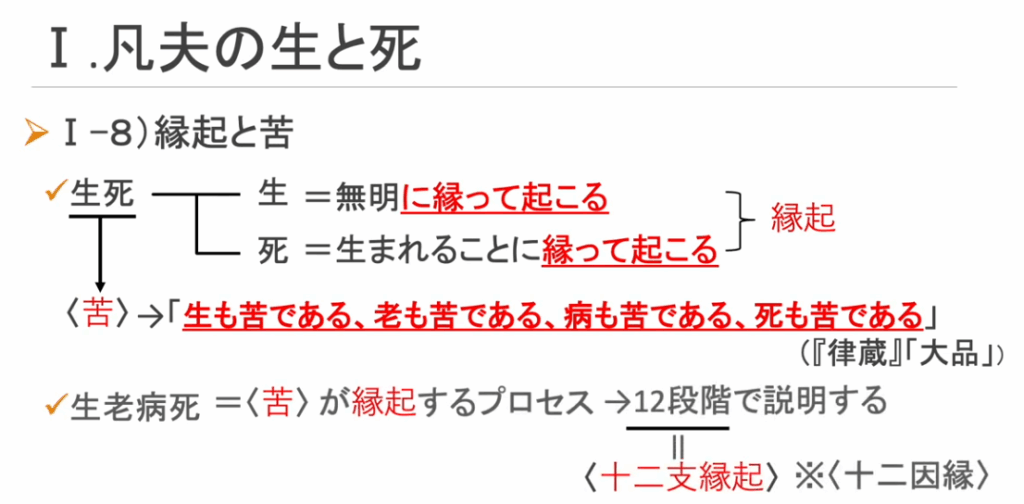
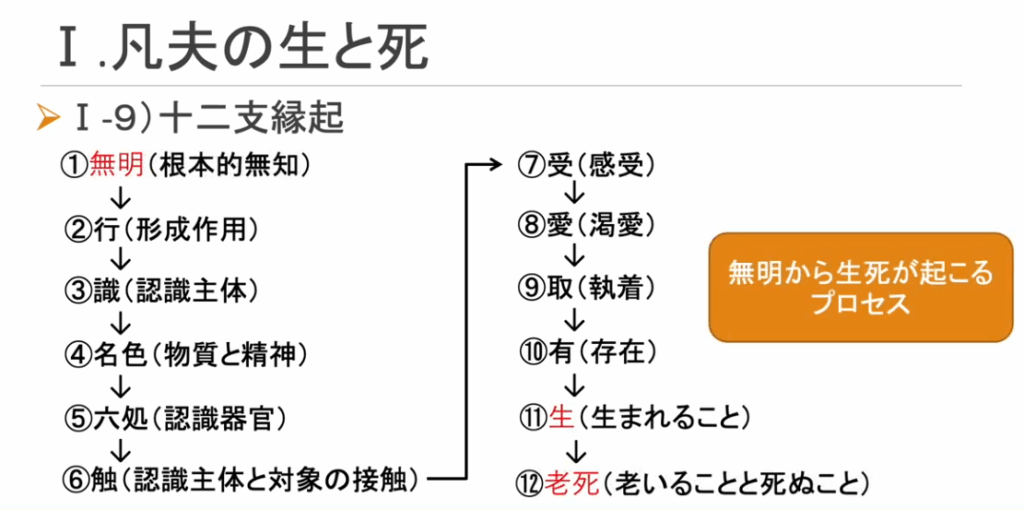
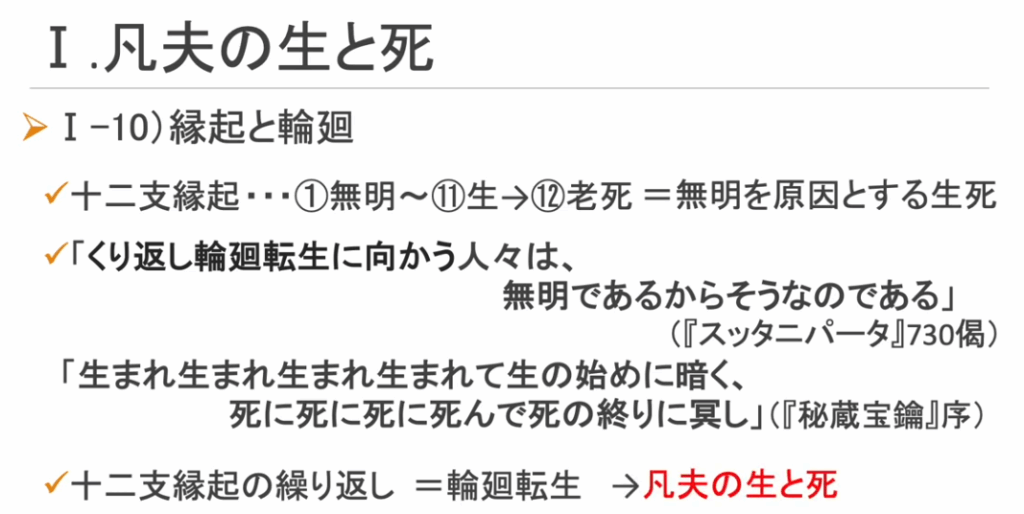
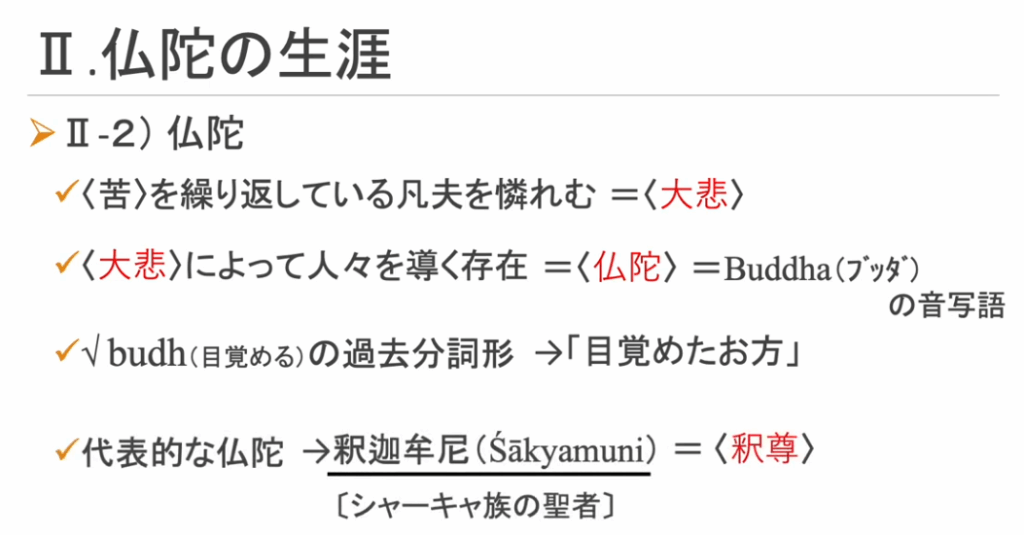
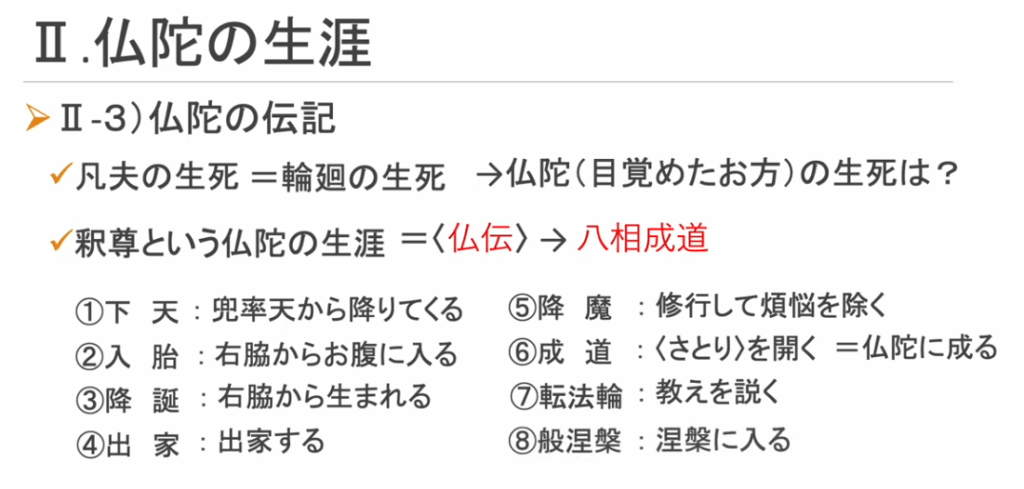
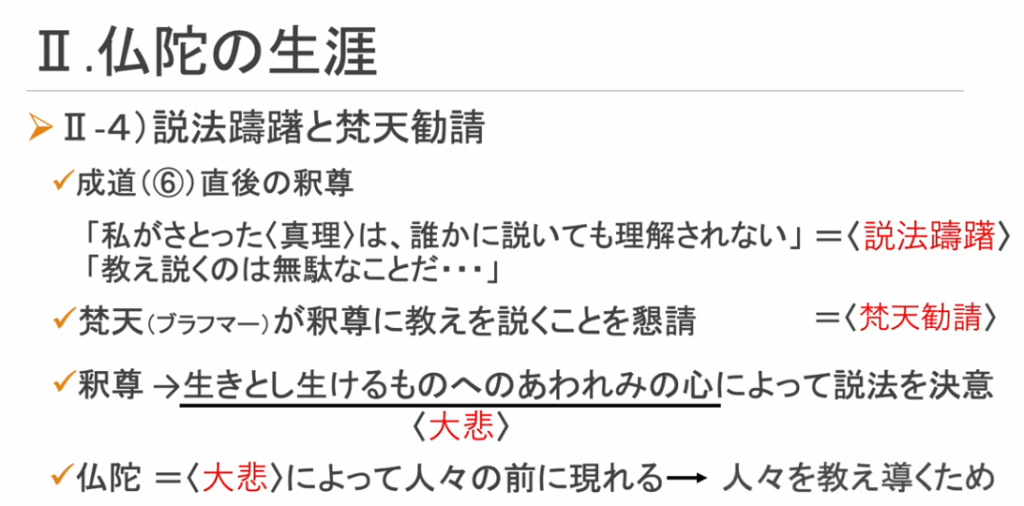
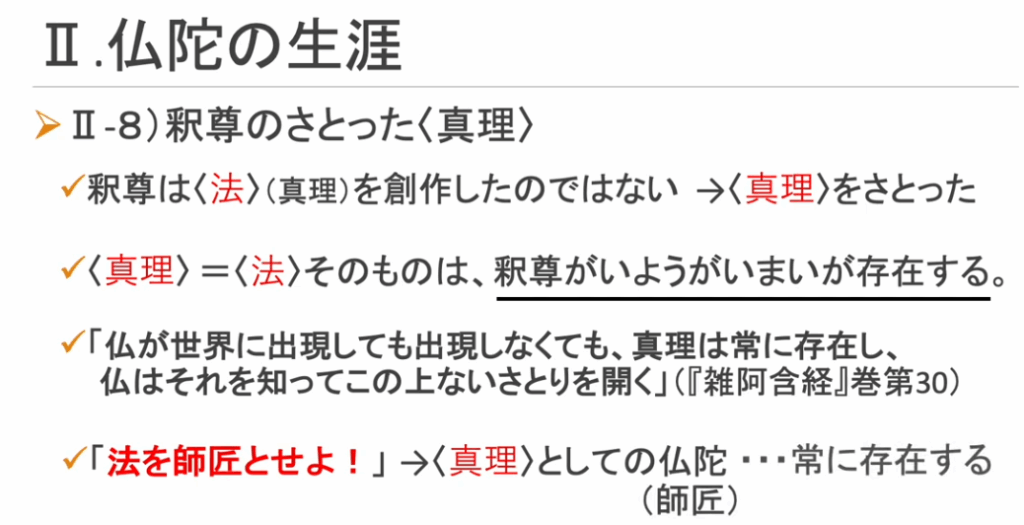
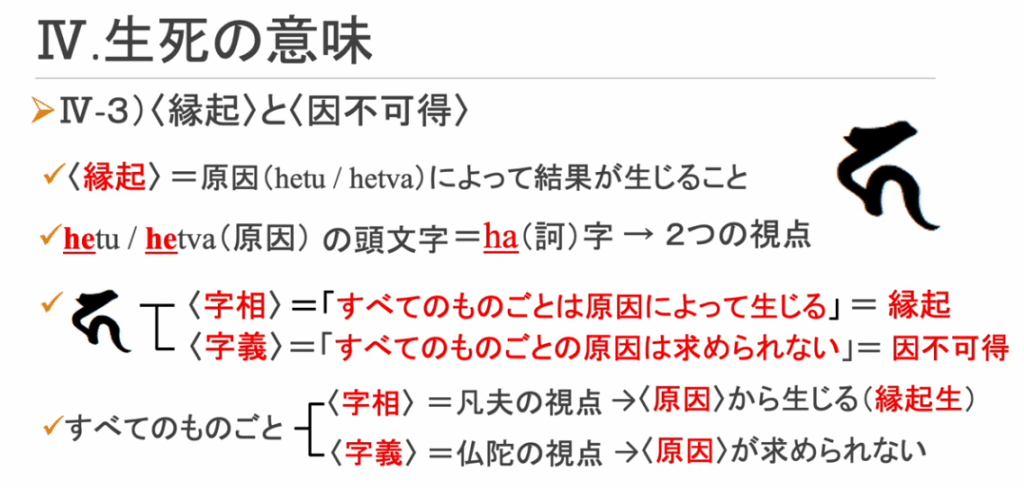
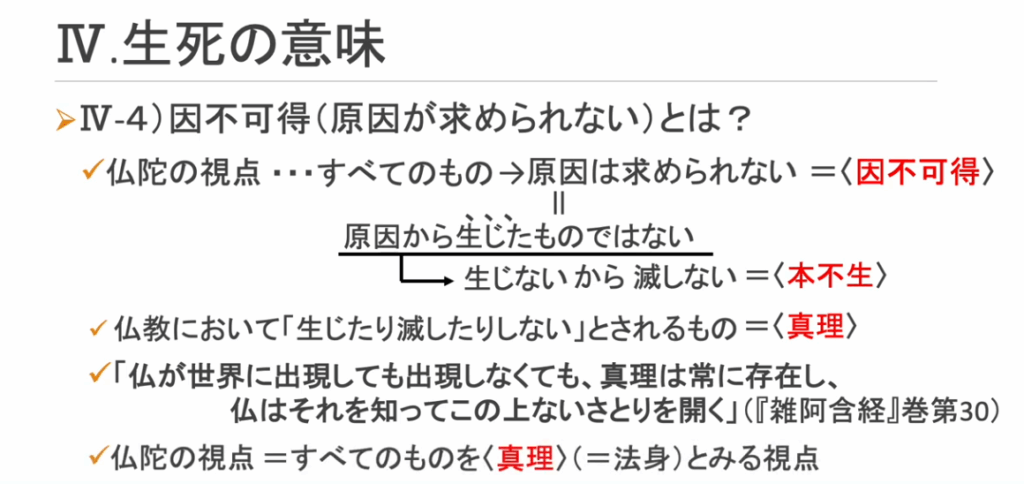
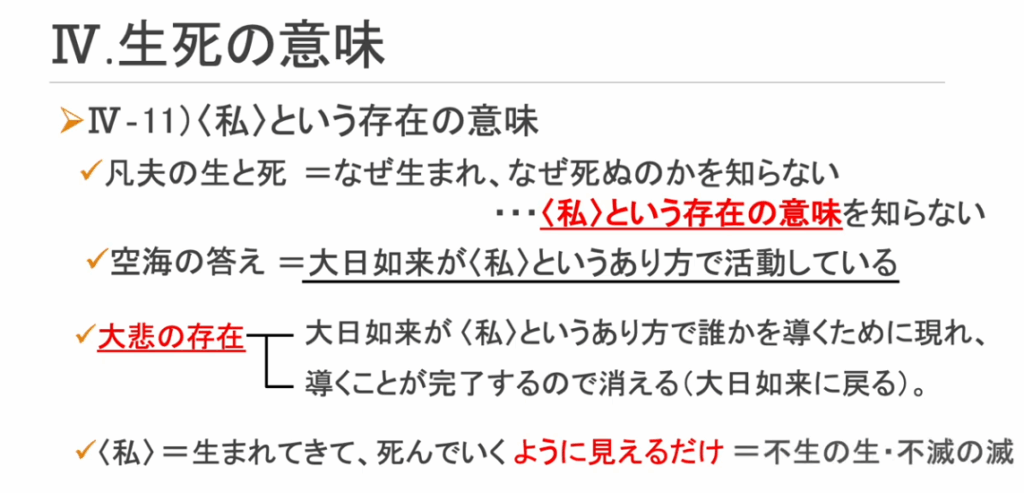
出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)




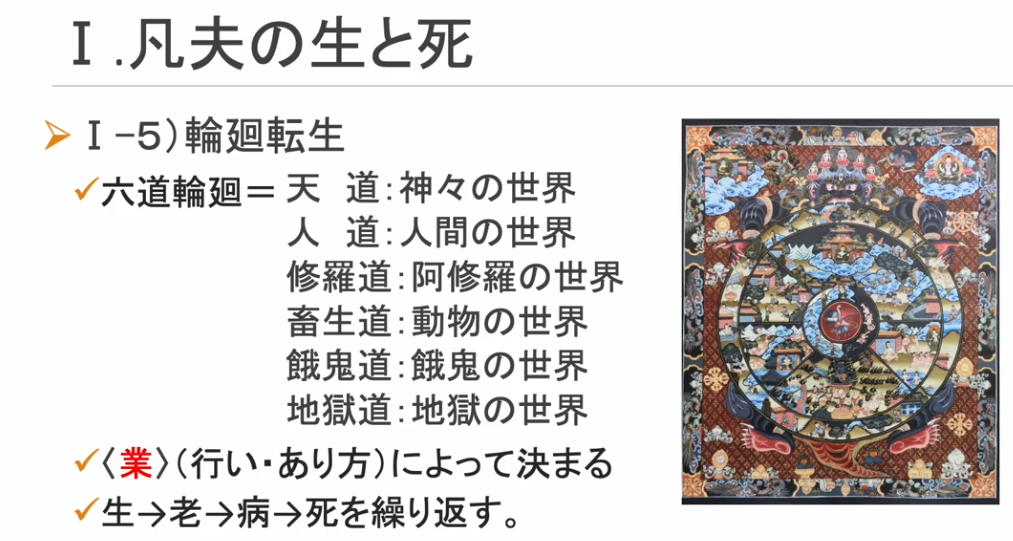
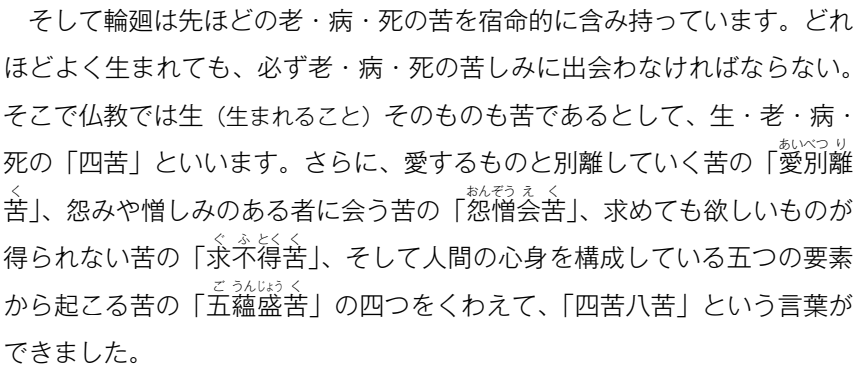
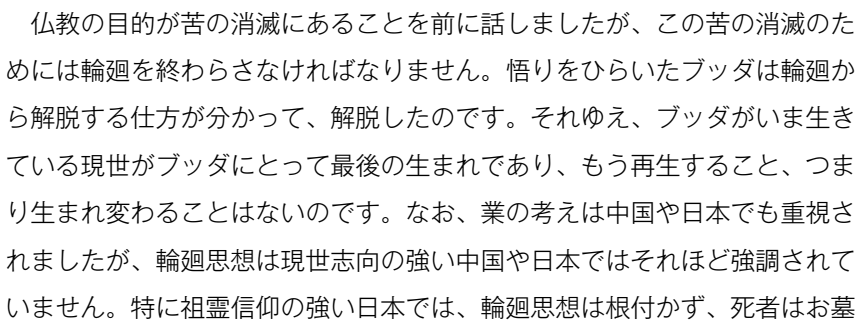
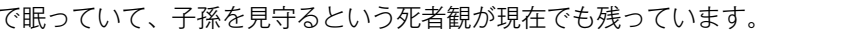
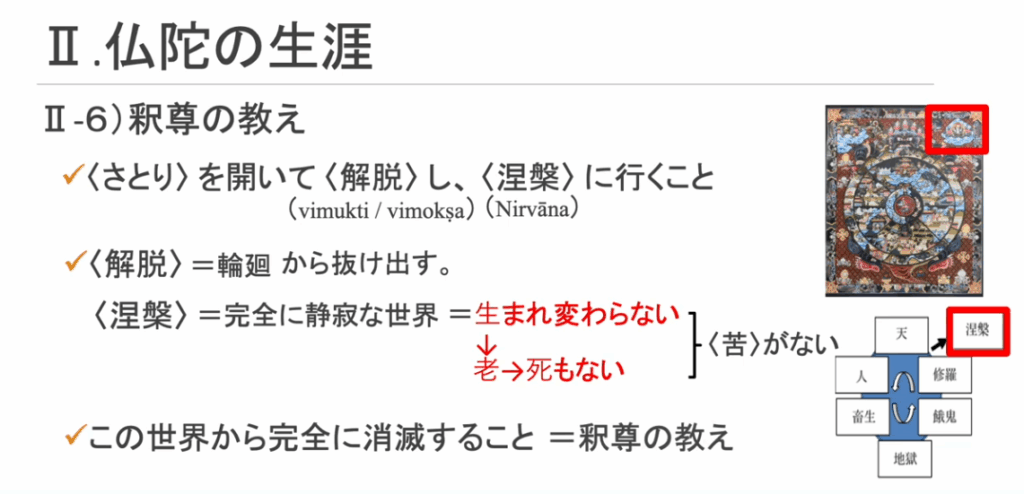
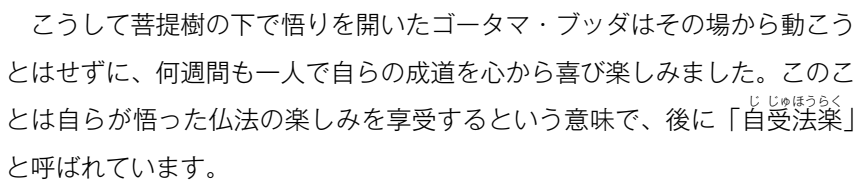
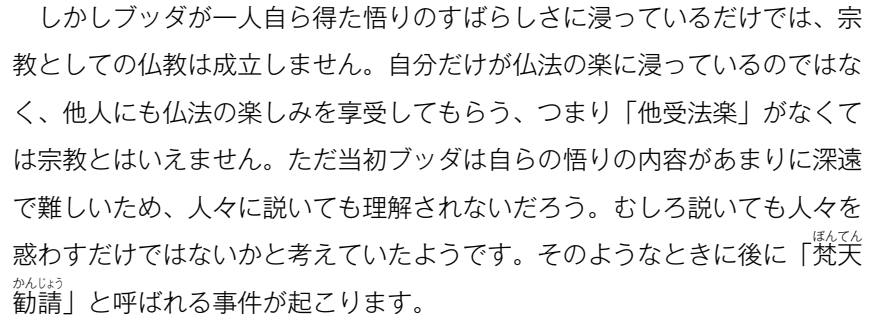
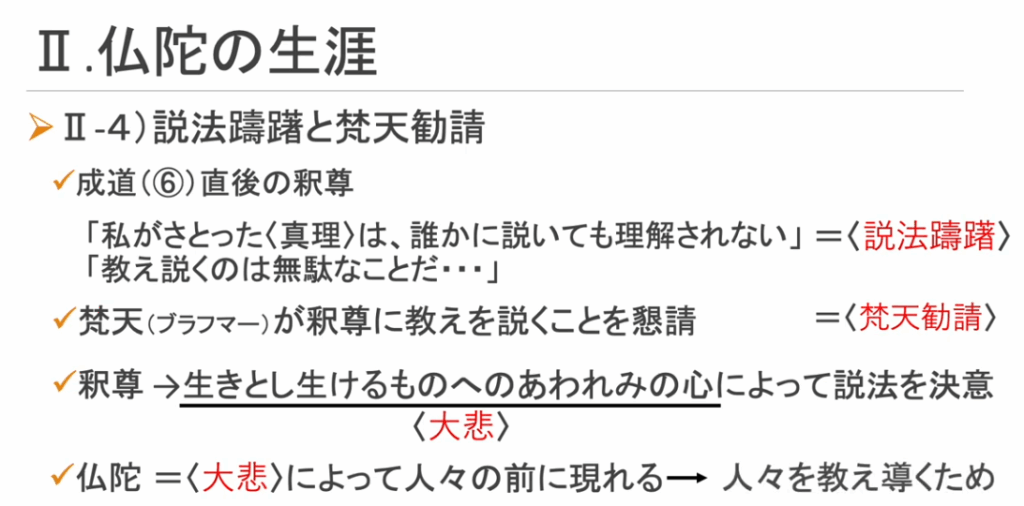
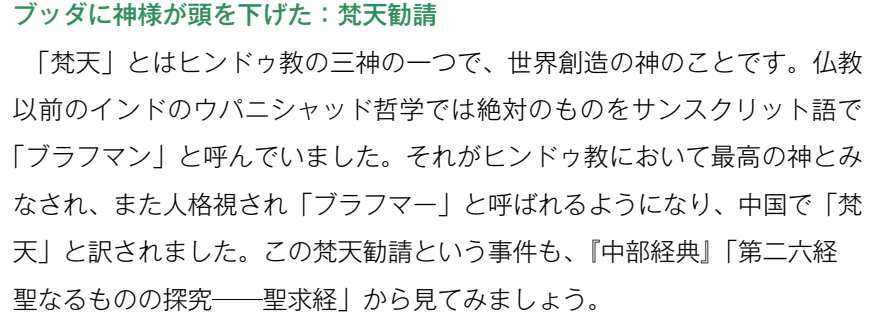
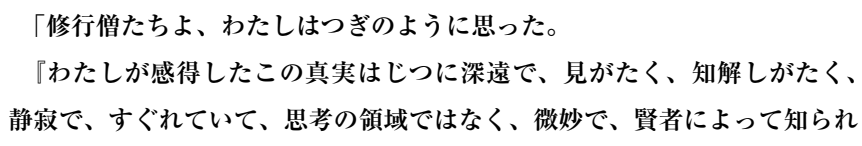
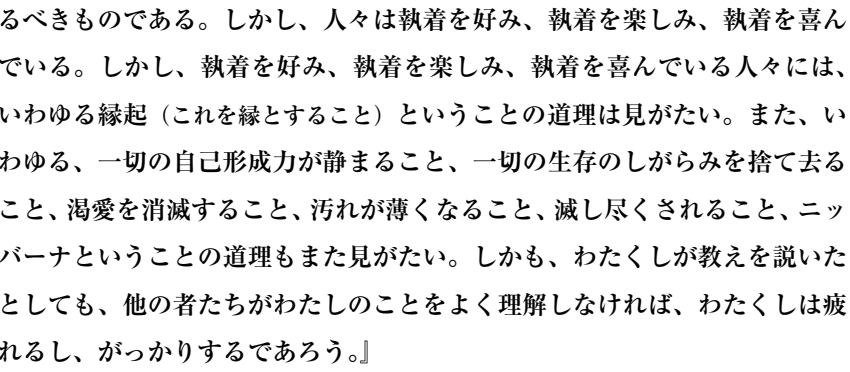
<参考情報>
■龍樹が重要視した原始経典の一説
・中道によって法を説くのである
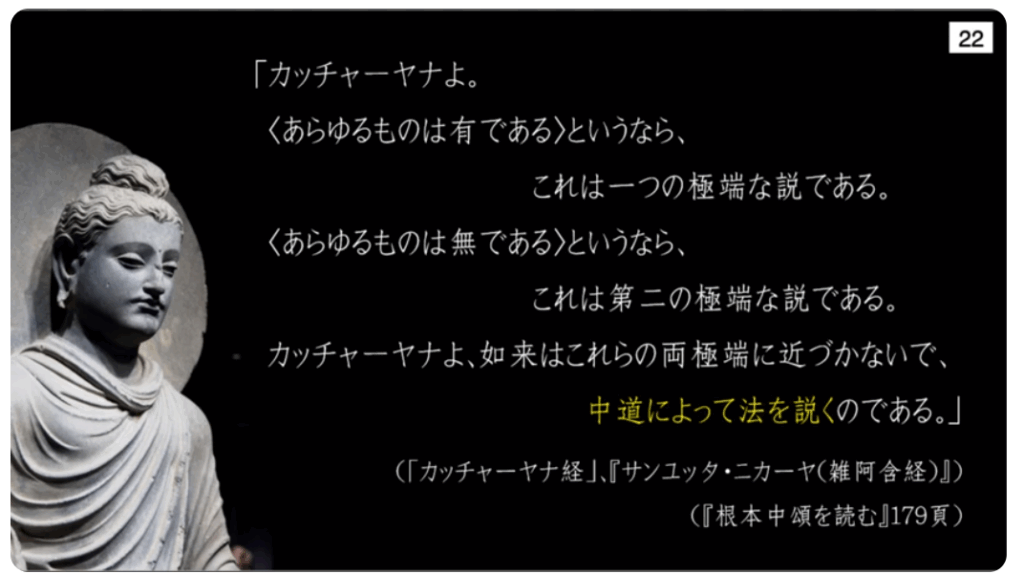
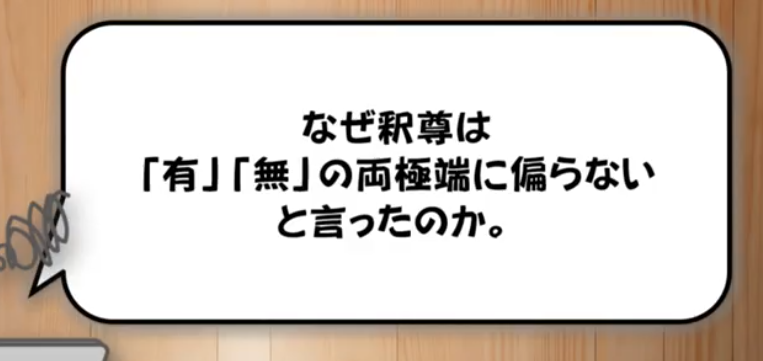
■空の教え
・すべての執われを離れる
⇒空の教えが仏教として真実(仏説)であることを証明することであった
・龍樹がした証明
⇒釈尊が説いた「縁起」と「中道」から明らかにしていく
◆縁起=空=中道
・縁起は
⇒何かを因として
⇒何かが概念設定(=名前付けられる:汚いツバ等)されること
⇒そういうものを「因施設」と呼んでいる
・空
⇒名付けられた諸々が「空」
・中道
⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない
⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)
⇒つまり実体がない=空
⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)
⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが
⇒それが中道である
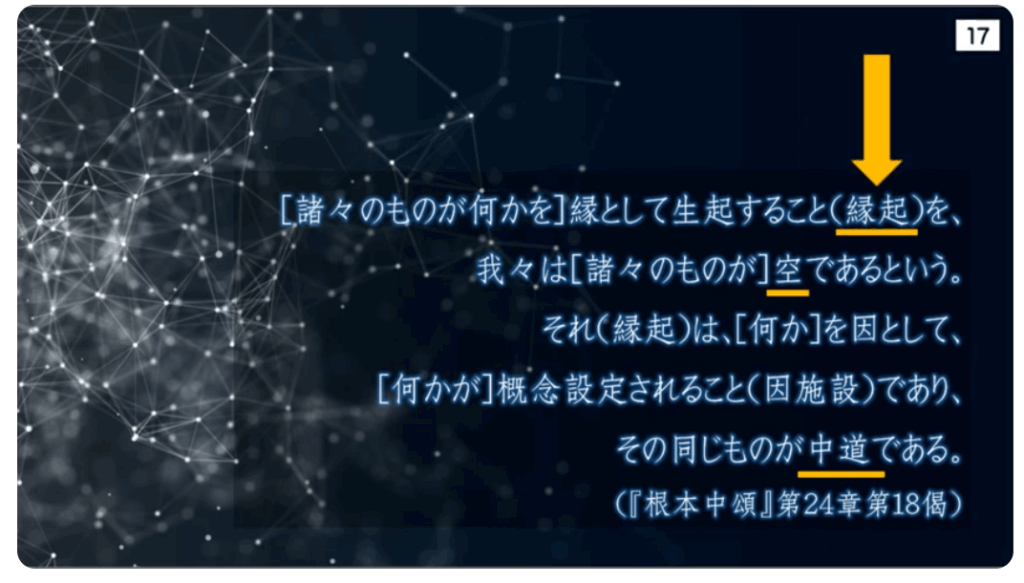
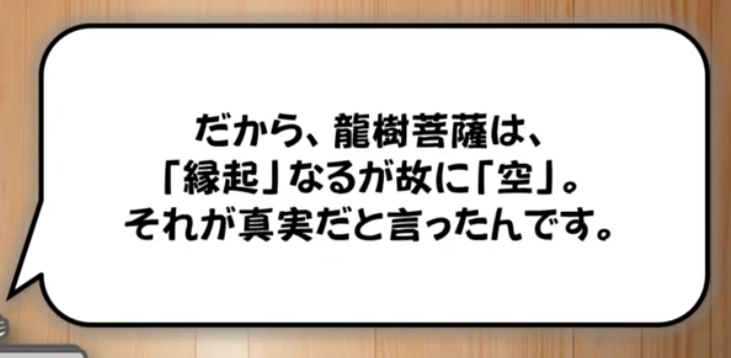

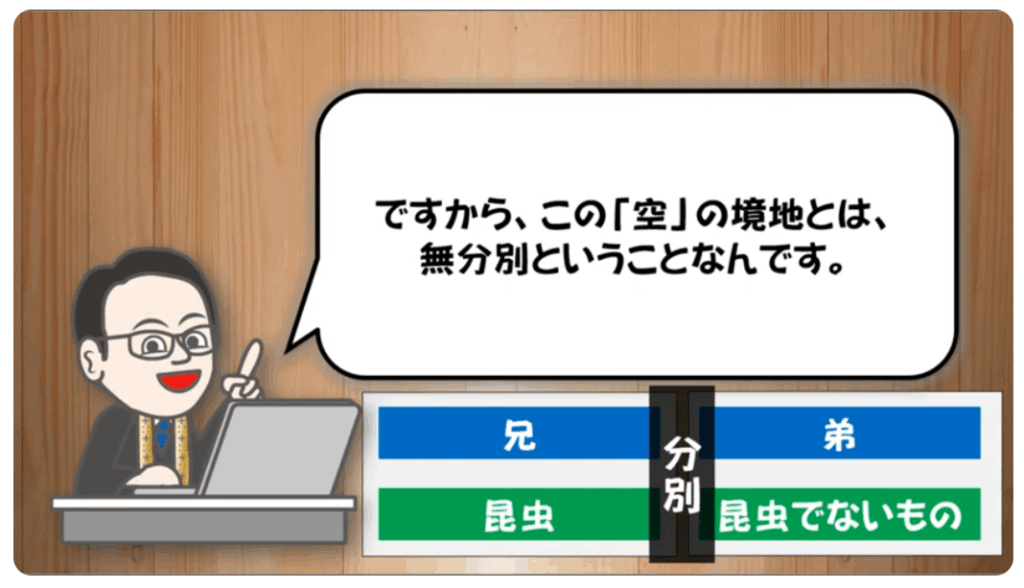
↓
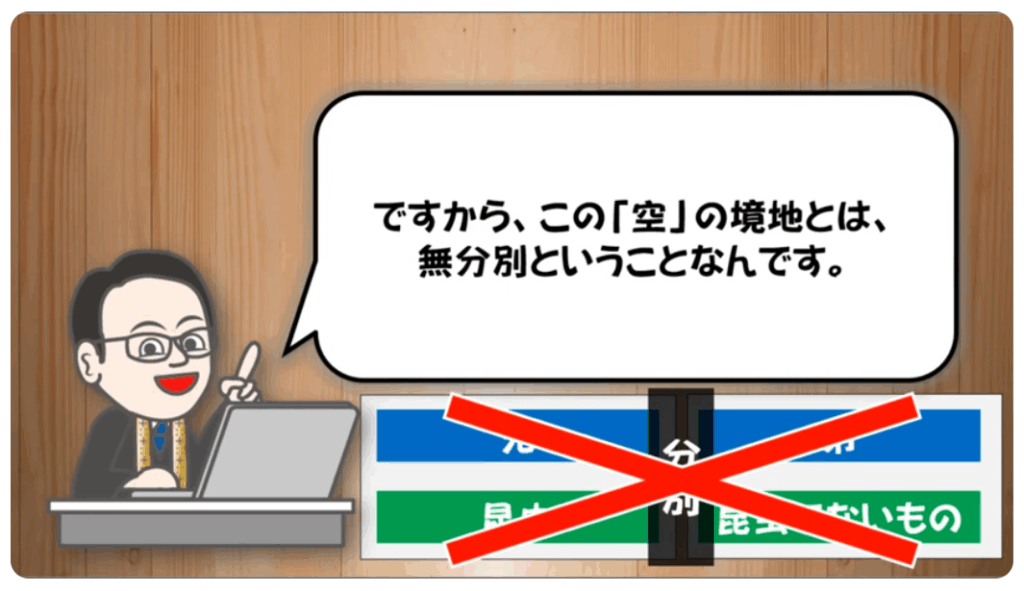
出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~
<参考情報>
概念(戯論)からの解放
また空の立場からは、ものごとは役割に応じて名前が変わるので、いま仮に「空」ということばで「ものごとは空である、すなわち固有の本質を持たない」と表現しているが、「空」という表現そのものが究極(=勝義)であるわけでもない、とも言います。
つまり、本来は言語表現されえない、いいかえれば、概念によって間接的に指し示すことはできても、「空であること」は直接に体得されることが期待されるということです。
とはいえ、ブッダの悟りであるその勝義的な真理(第一義諦)が人々に理解されるためには、「空」などの世間の言語表現が必要不可欠で、それを世俗真理(世俗諦)とも呼びました。
もとより、事物に固有の本質はないが、そこに固有の本質があるかのような錯覚はある。それが錯覚にすぎないこと気づかせるために、「空」という否定的な響きのある言葉が選びとられたとナーガールジュナは言います。
ただし、空が正しく理解されるというのは、錯覚を錯覚であると気づくこと、それによって煩悩の根源に巣くう概念化(戯論)という心のはたらきから解放されることを意味しています。
出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~中項目:■空とは何でしょう? ―中観派(ちゅうがんは)の教えを学ぶ/第16回 愛宕薬師フォーラム(東京大学教授 斎藤 明 先生)
<参考情報>
■時間概念が否定
因果論や縁起論はもちろんのこと、カントの認識論も、ヘーゲルの自己展開する弁証法も崩壊させるような根本的問題を突きつけることになる。
まず、観時品では直接的に「時相の不可得」と言い、「時有るべきや」と反語的に時間把握の不可能を言っているが、このことをもう少し具体的に展開している去来品で検討してみよう。
時間論と言えば多くの論者がこの去来品を取り上げるものの、已去(過去)と未去(未来)については明快に否定できるのだが、「去時」、即ち「去りつつある時」の「現在」については、どれもこれもその説明に難渋している。ところが先の思考の次元化を適用すると、これについての次のような解き方が可能となる。
過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、
概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。
しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。
同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。
つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。
これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。
つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。それ故。「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。
出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学講師)~
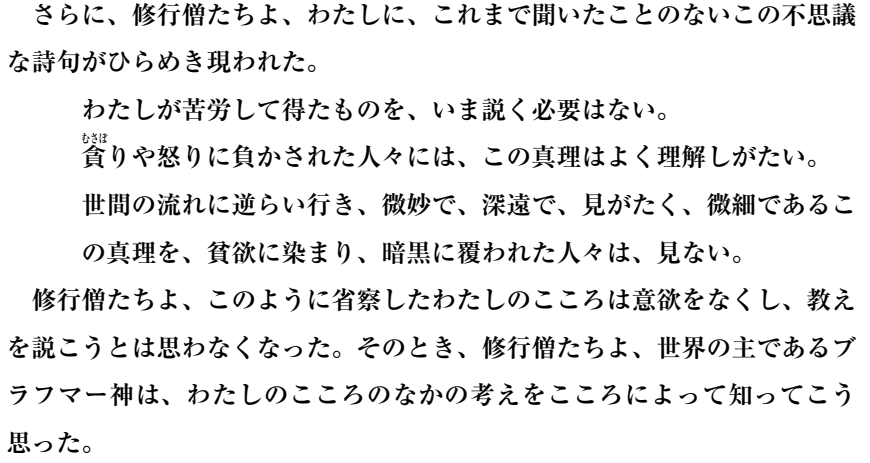
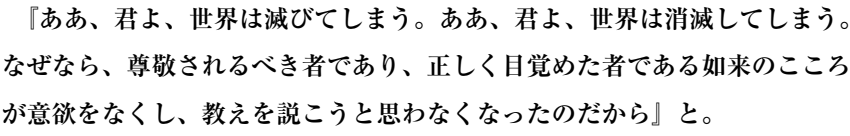
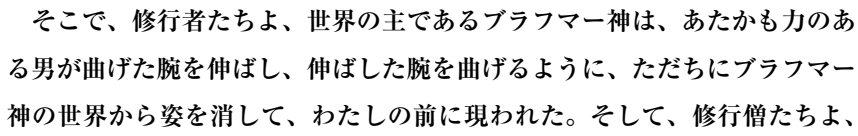
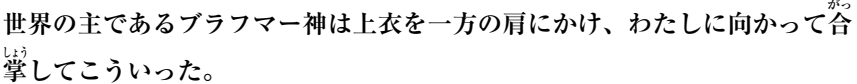
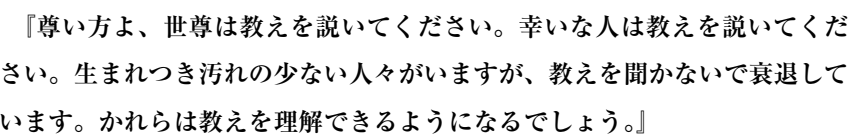
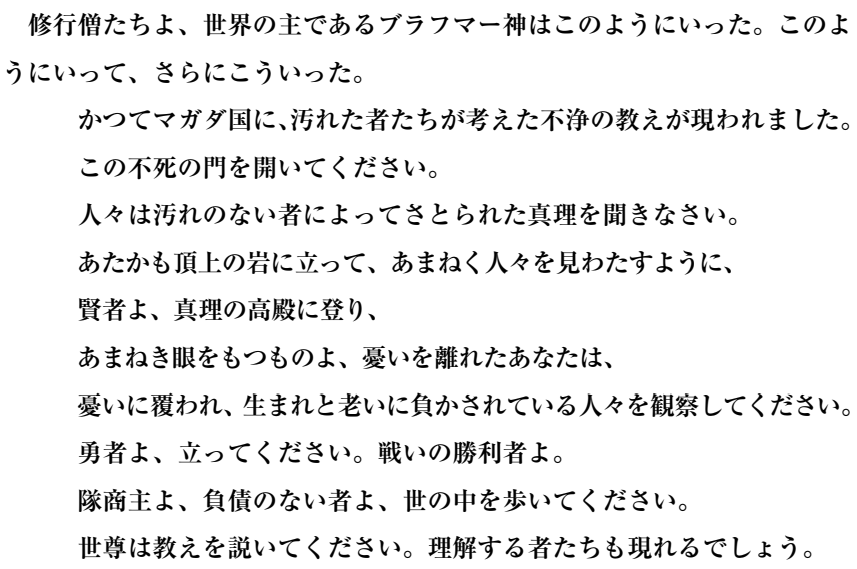
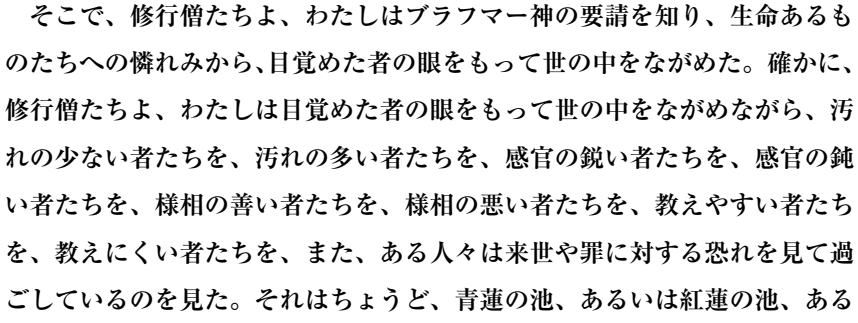
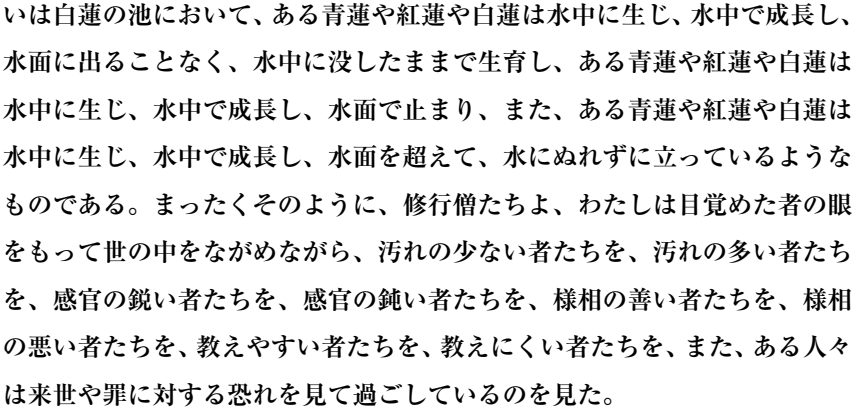
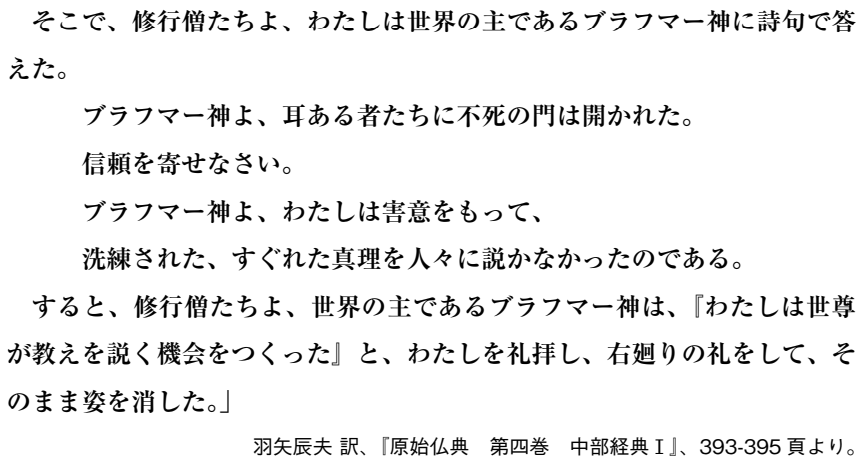
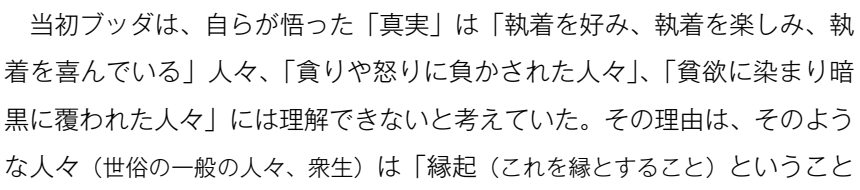
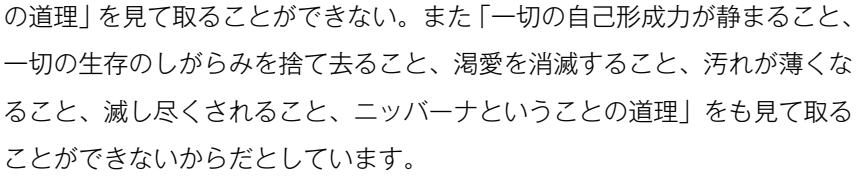
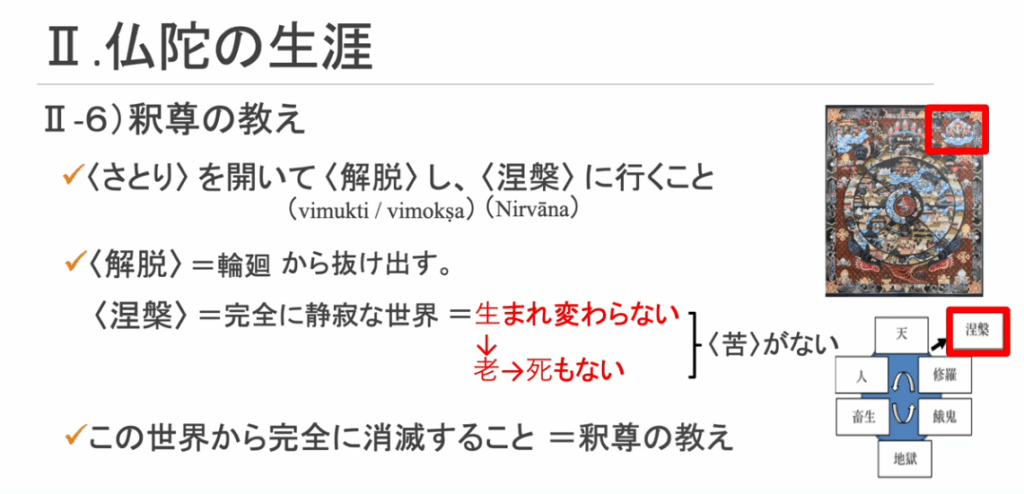
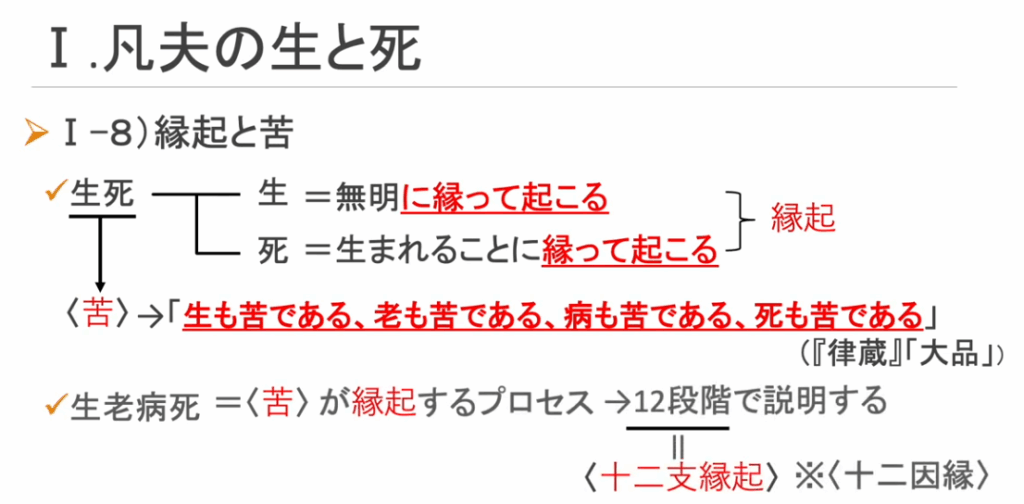

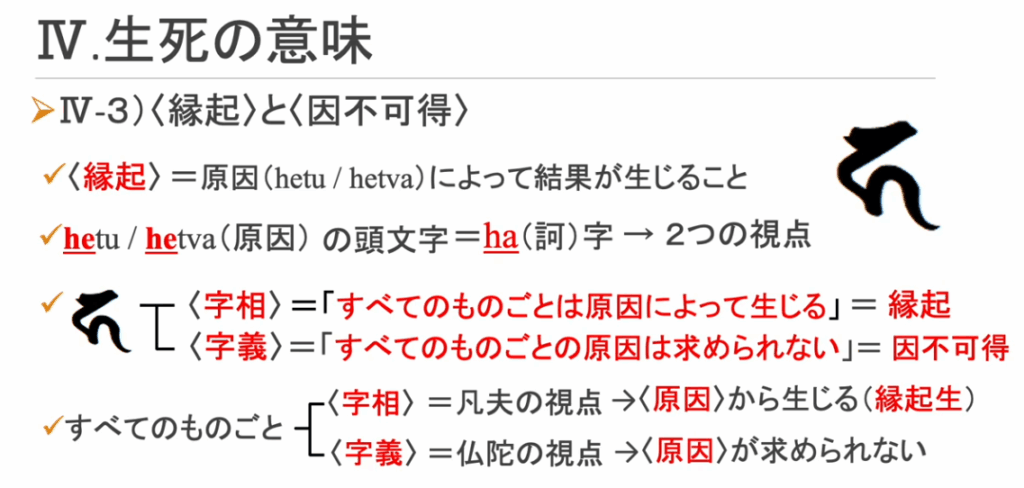
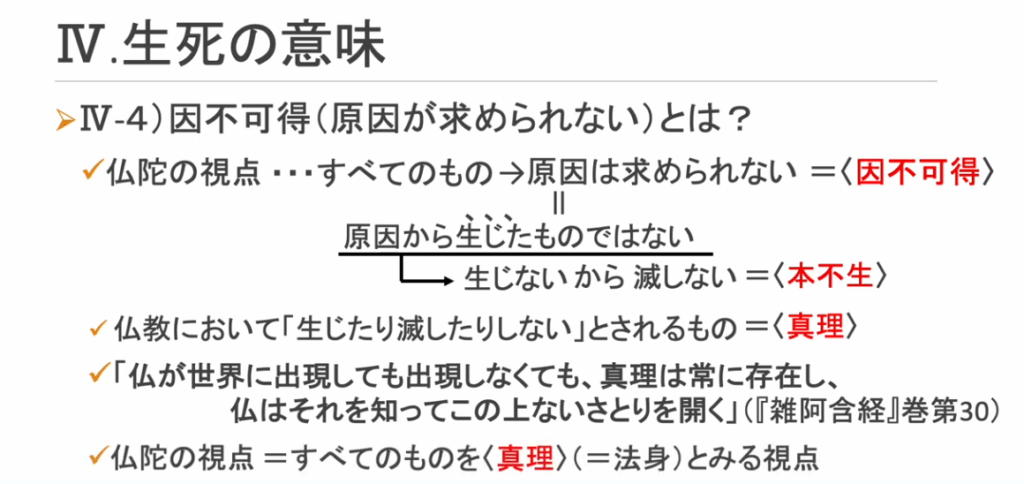
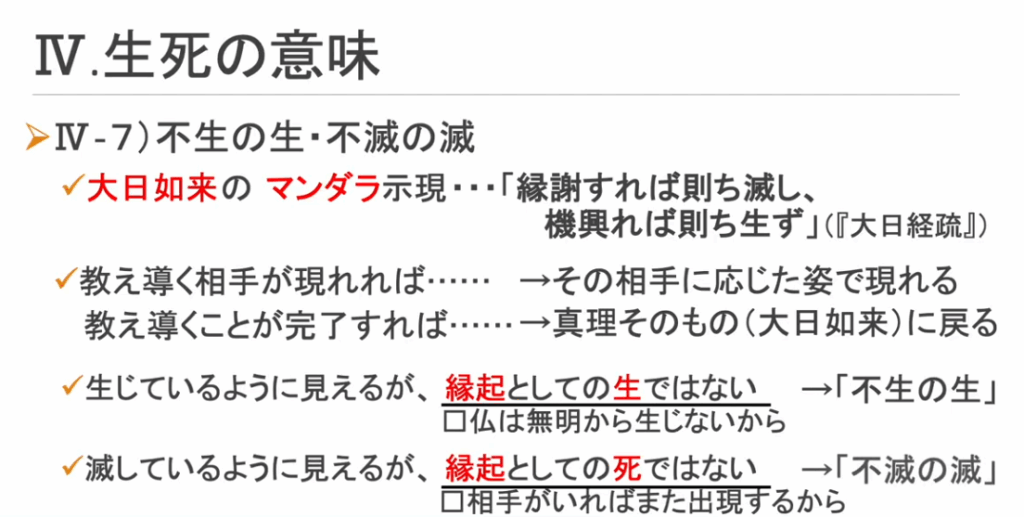
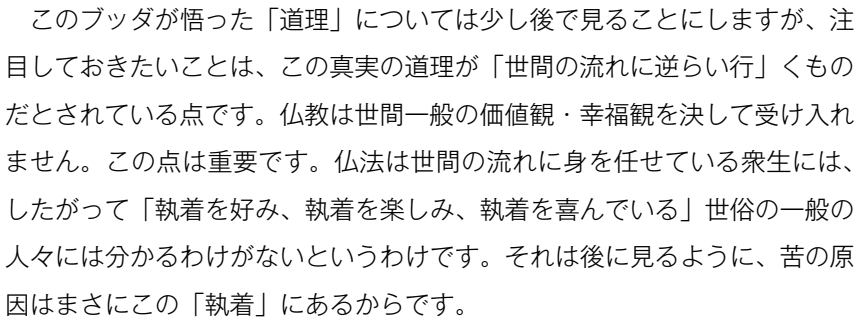

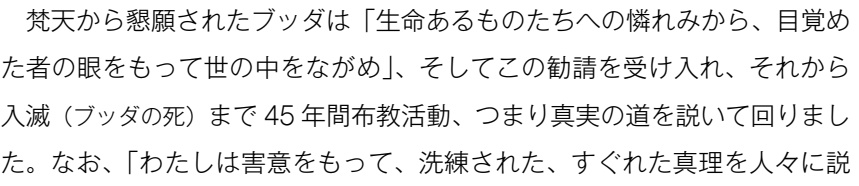
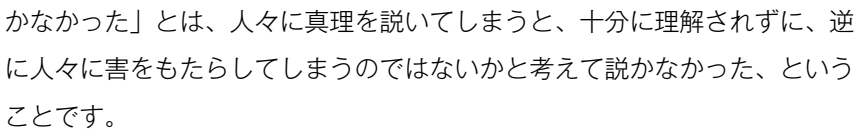
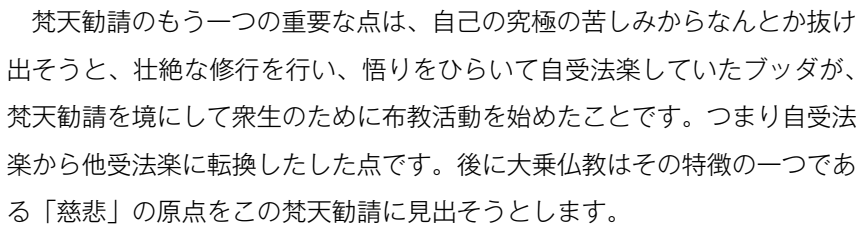


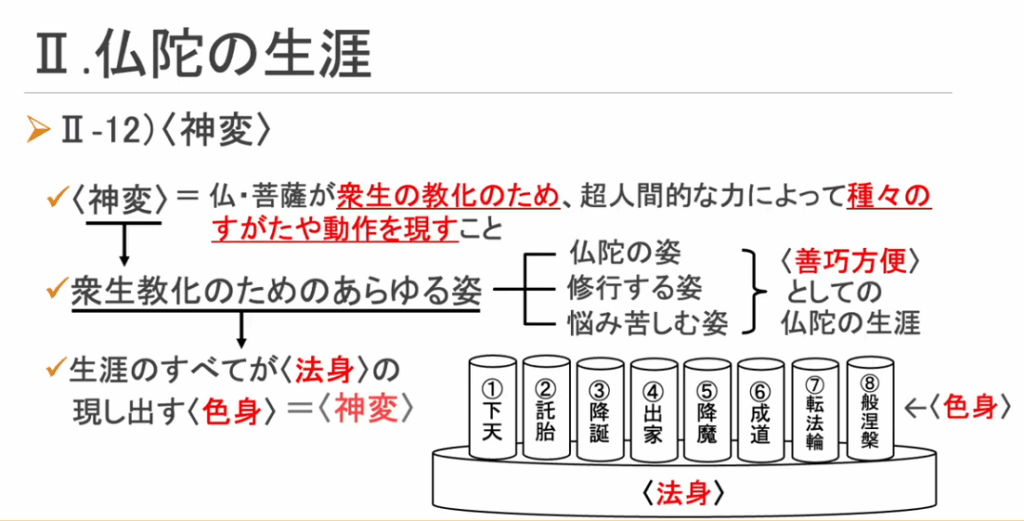
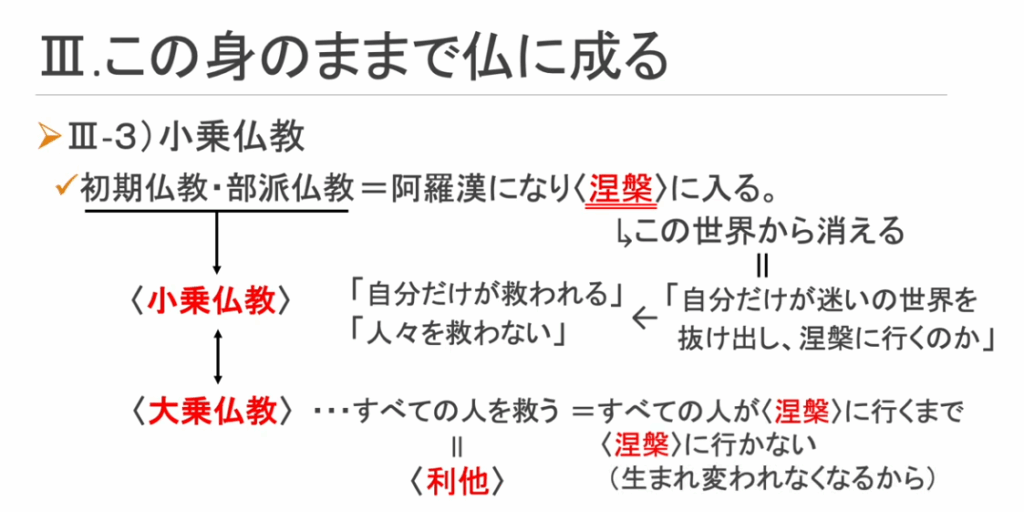
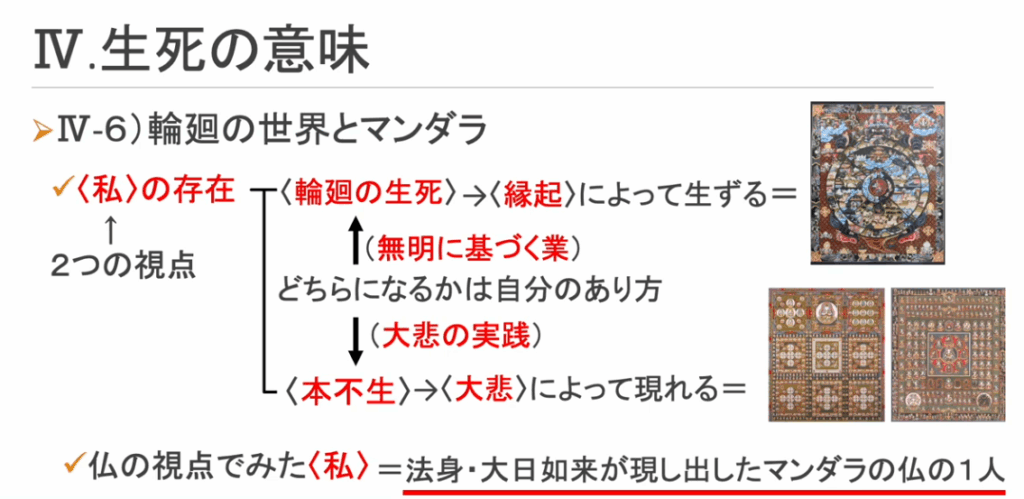

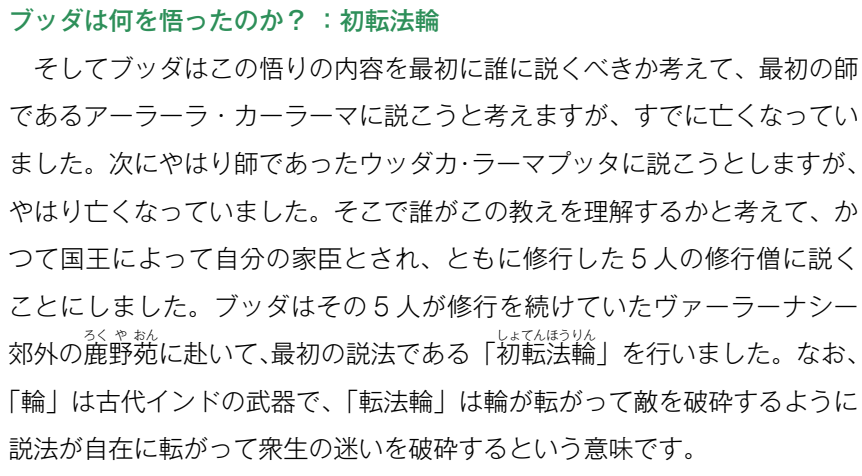
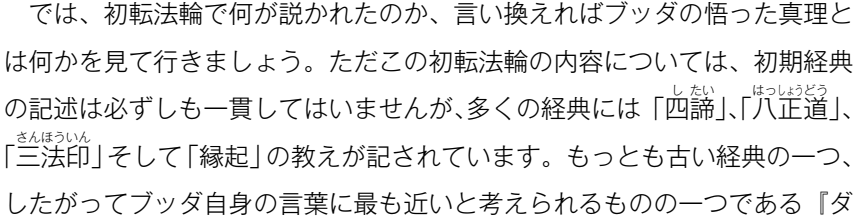
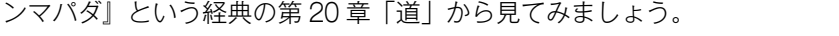
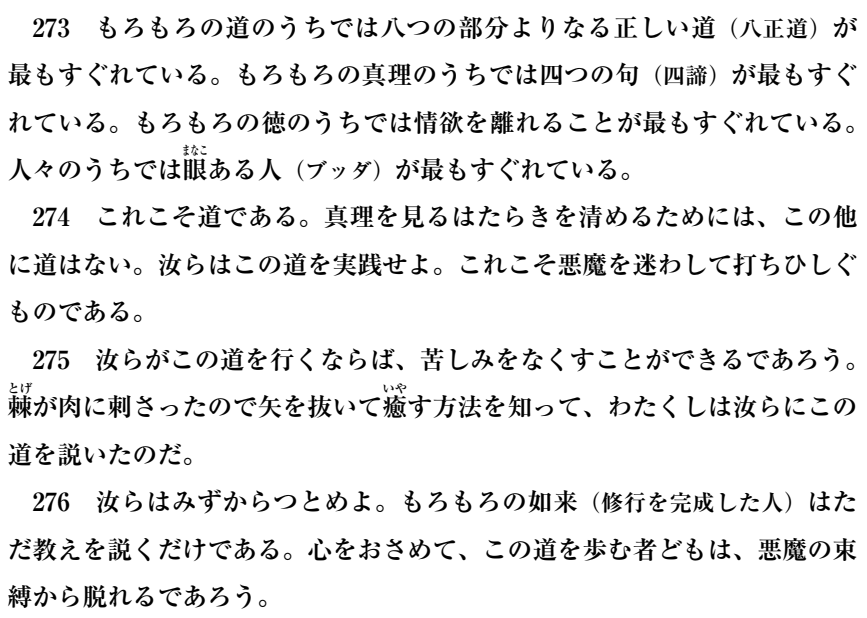

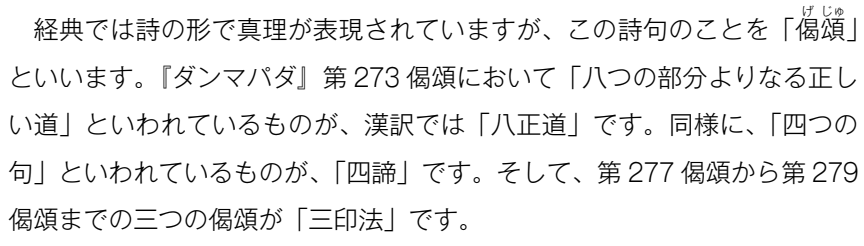
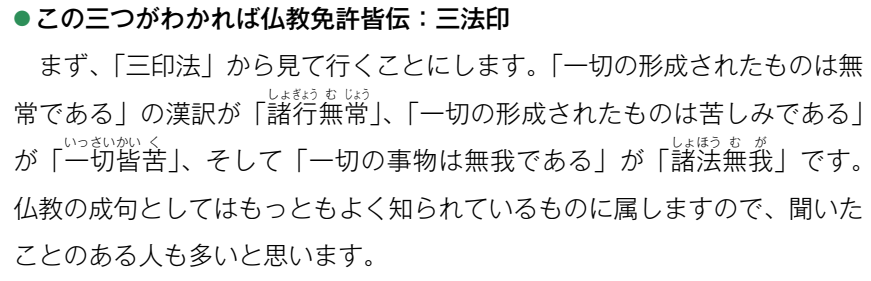
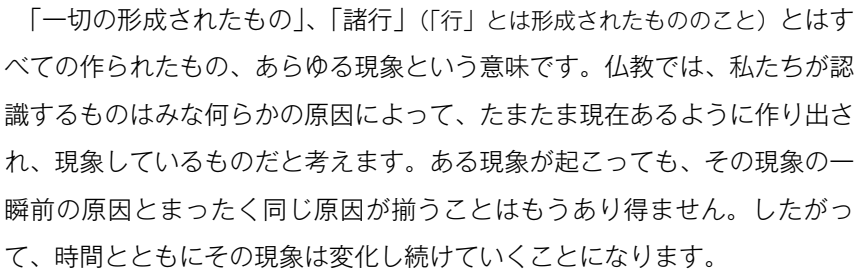

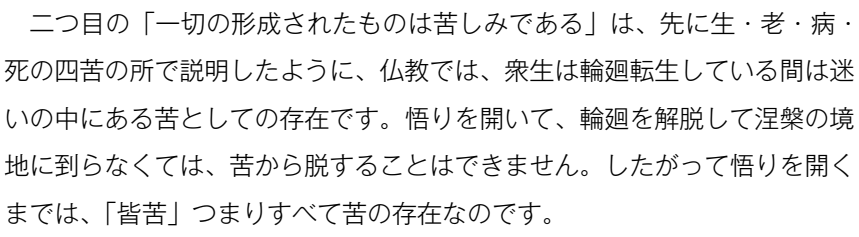
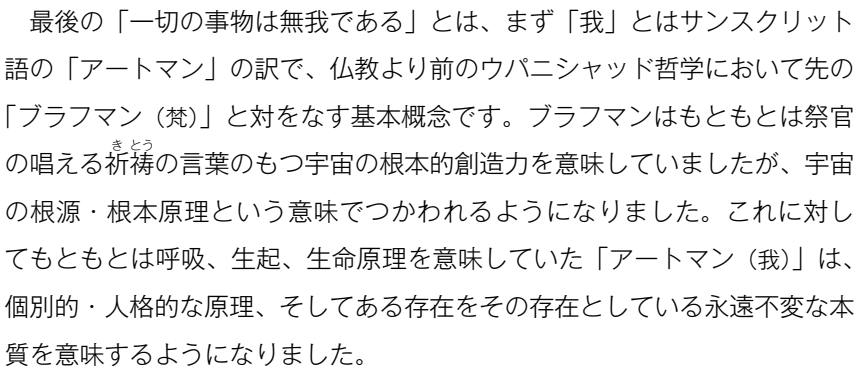
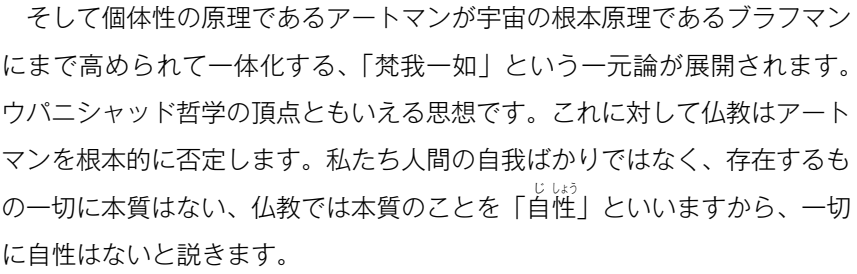
<参考情報>
・八千頌(はちせんじゅ)般若経
⇒本体がない
⇒固定的に永遠に存在する本体はない
⇒無自性=空

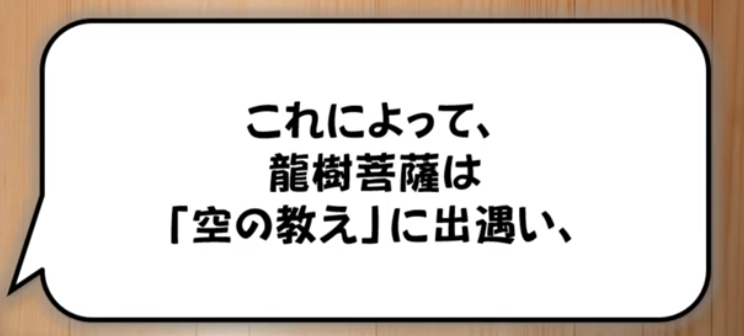
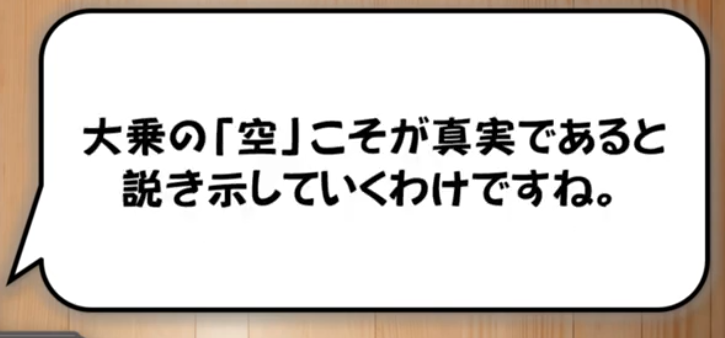
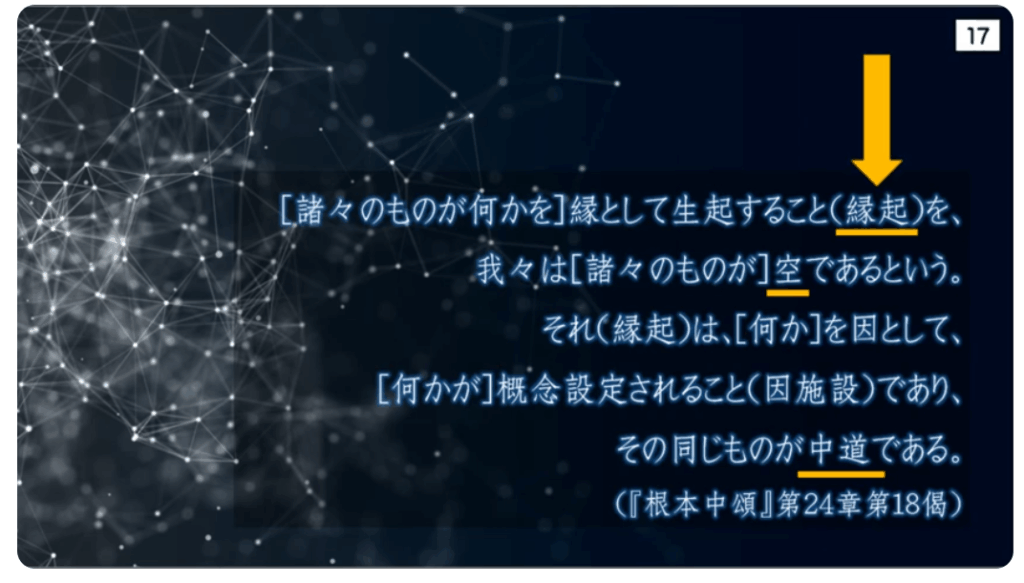
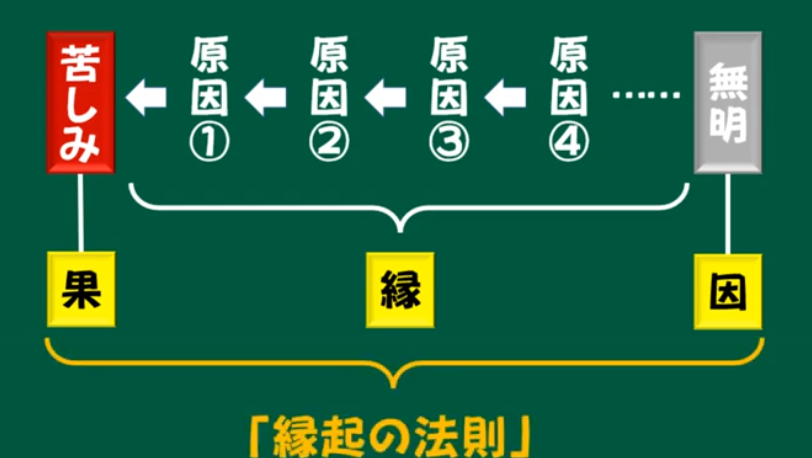
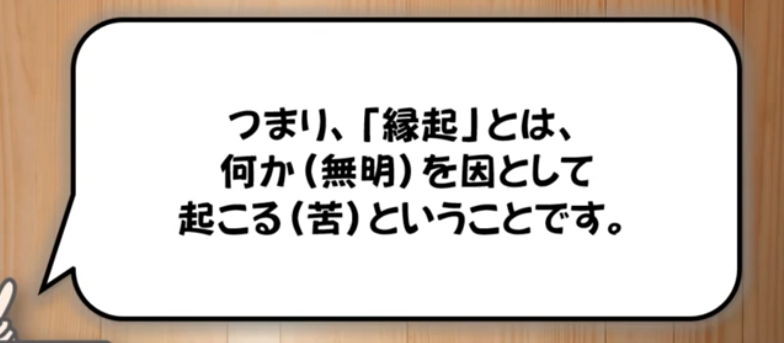


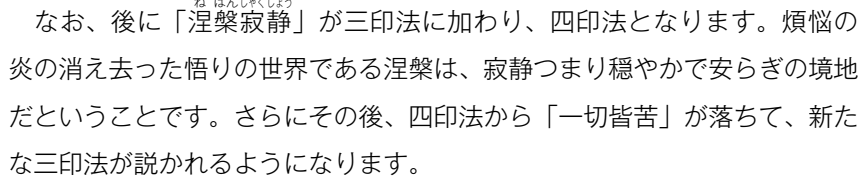
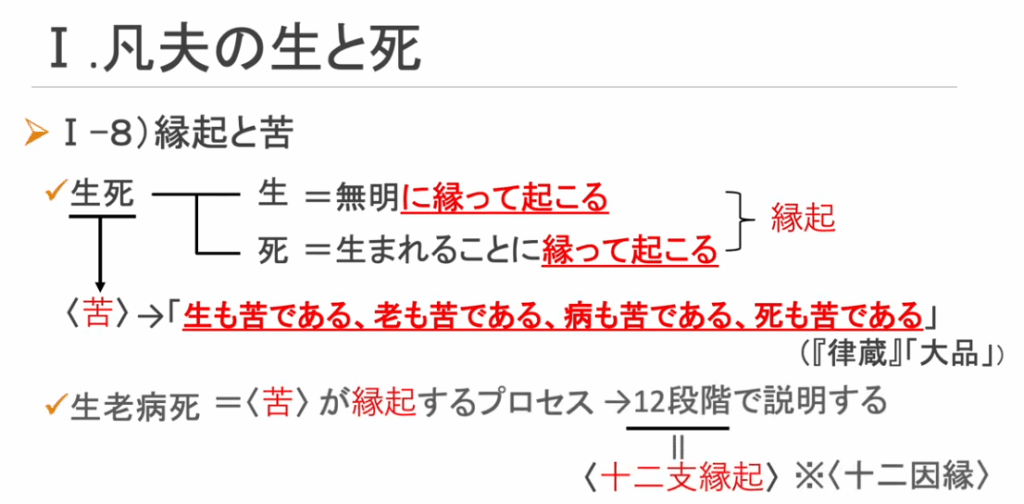
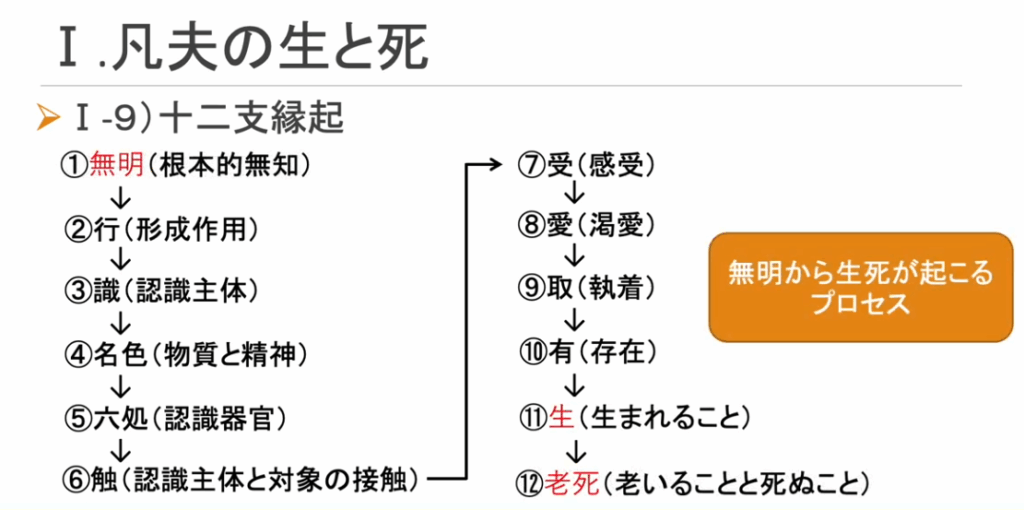

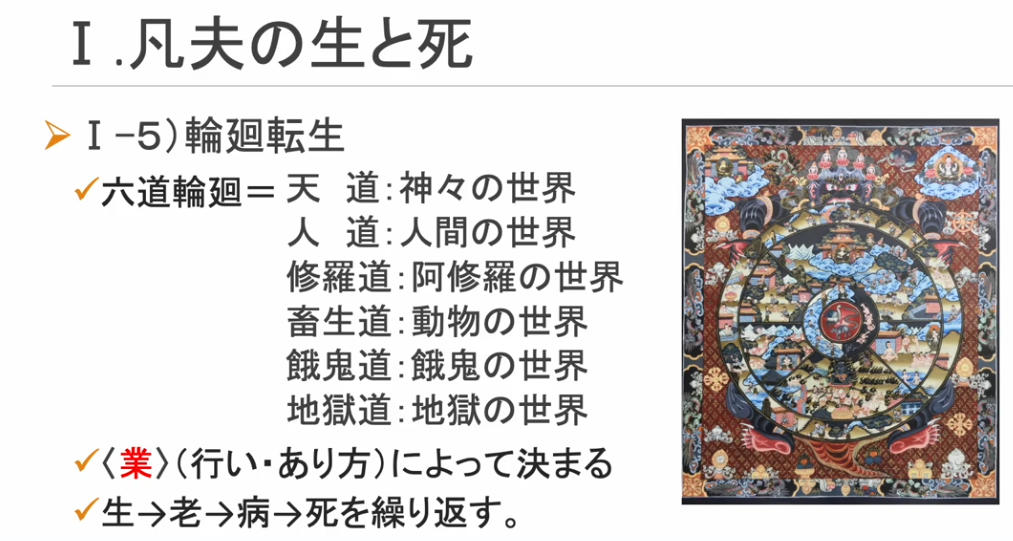
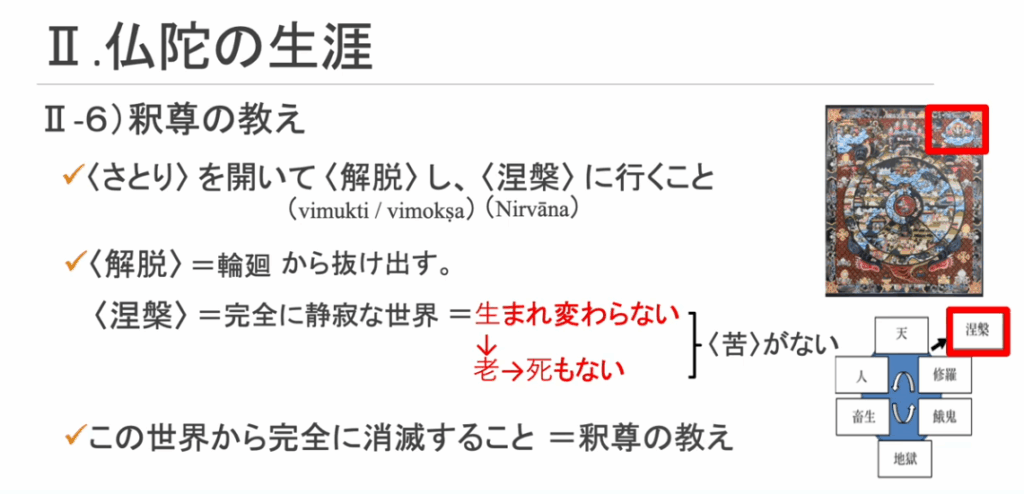
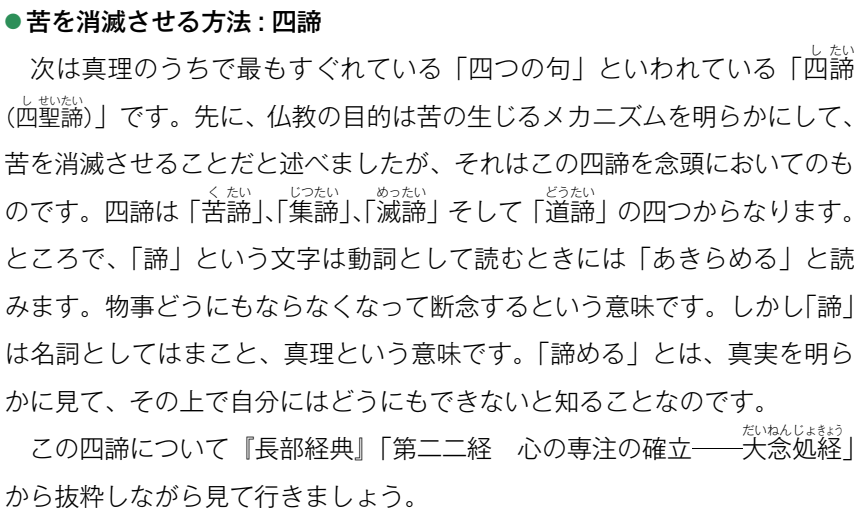
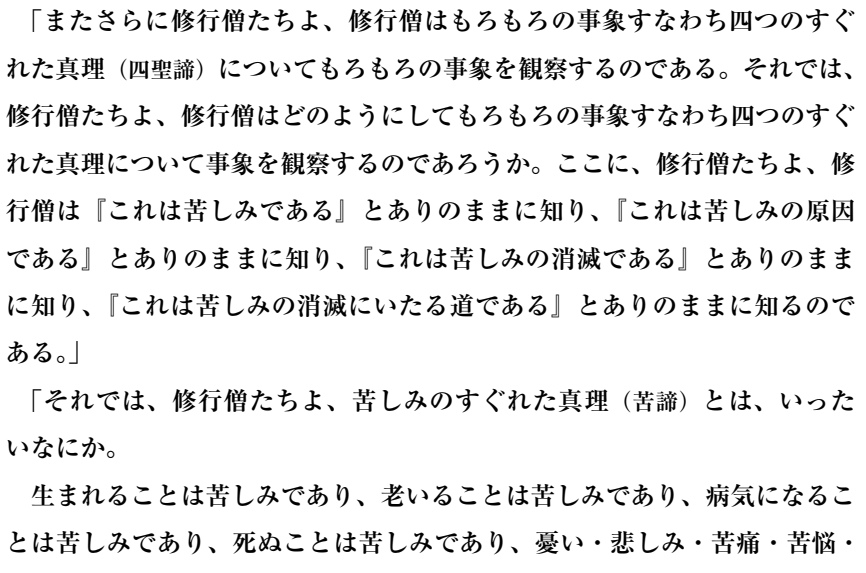
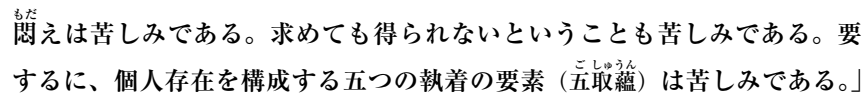
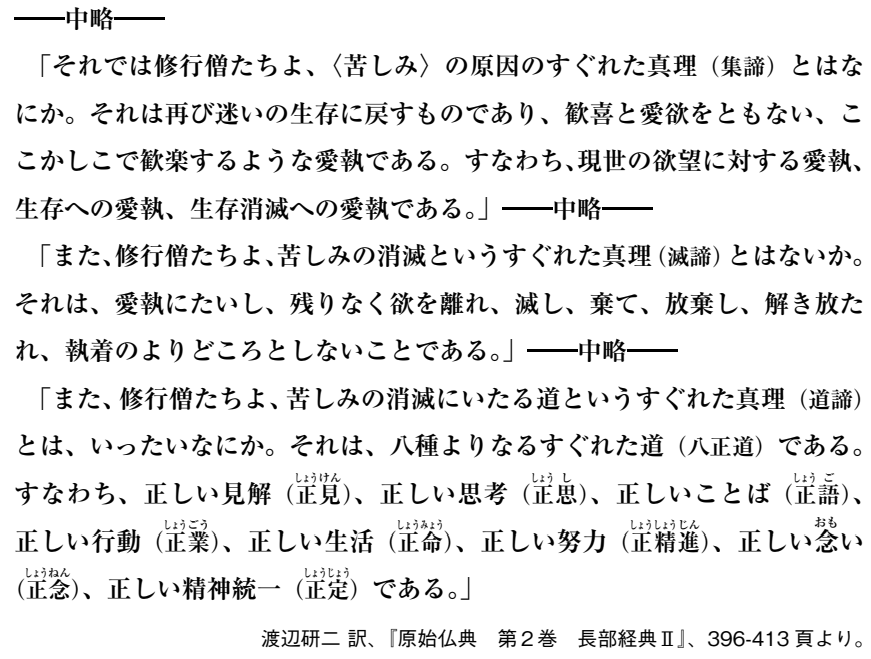
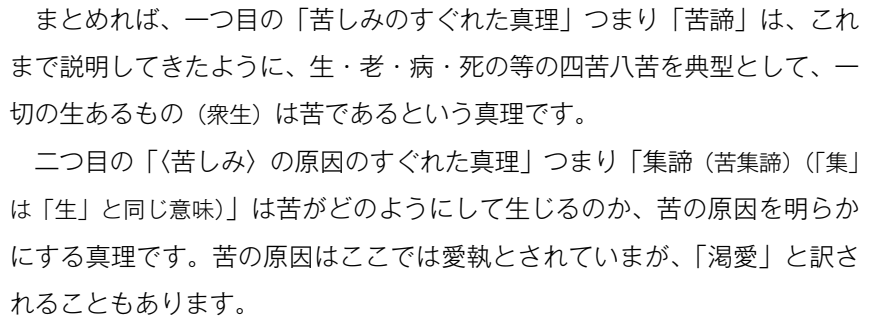
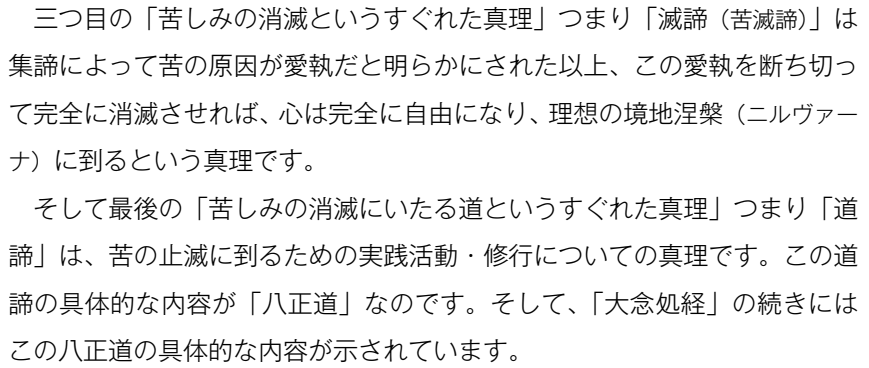
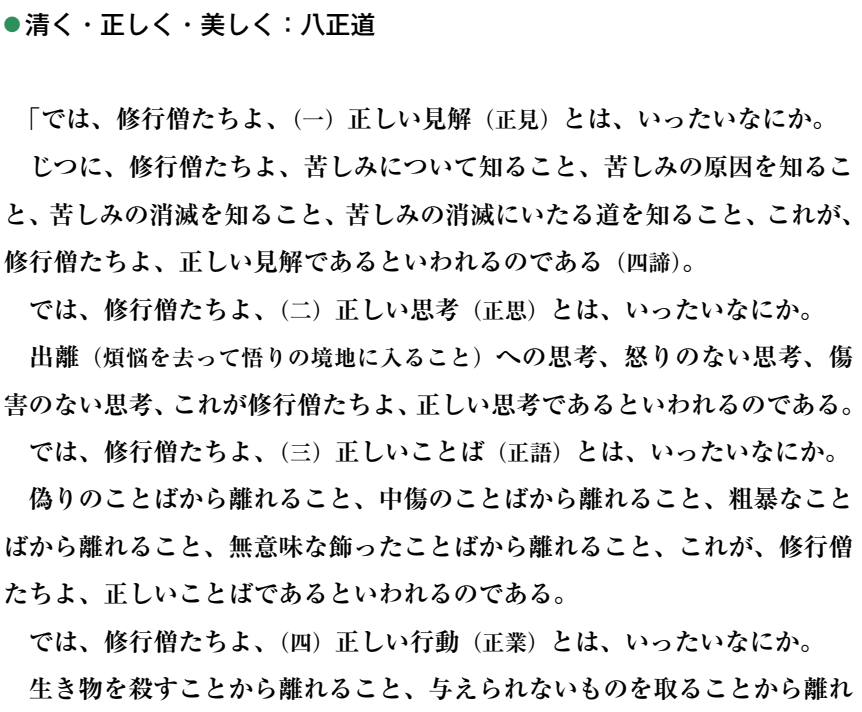
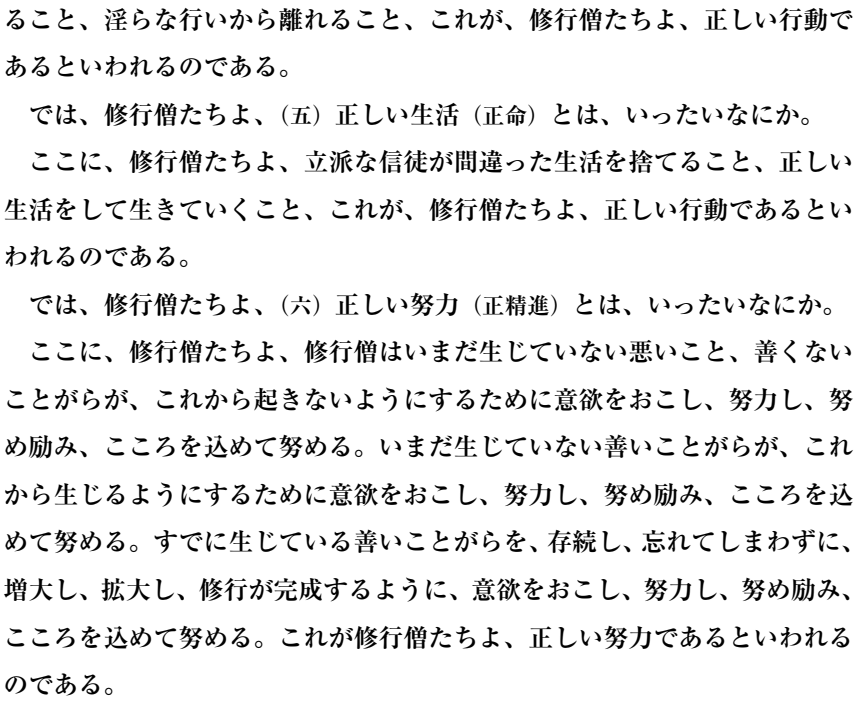
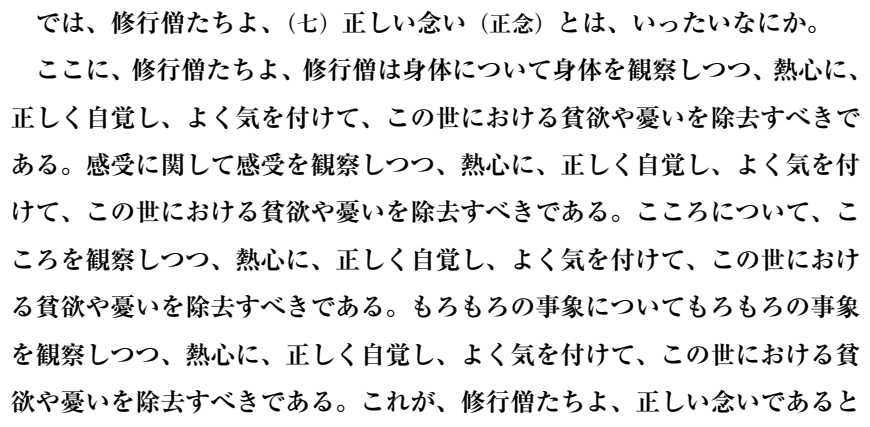
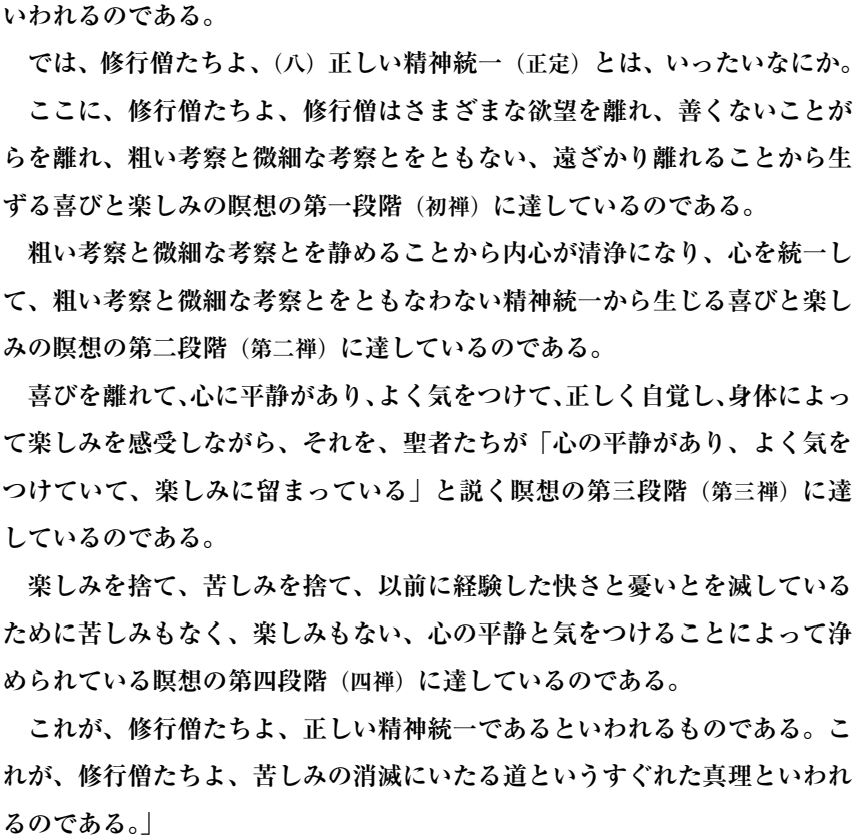
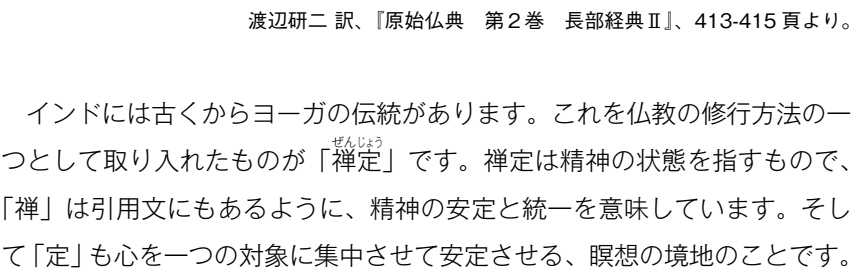
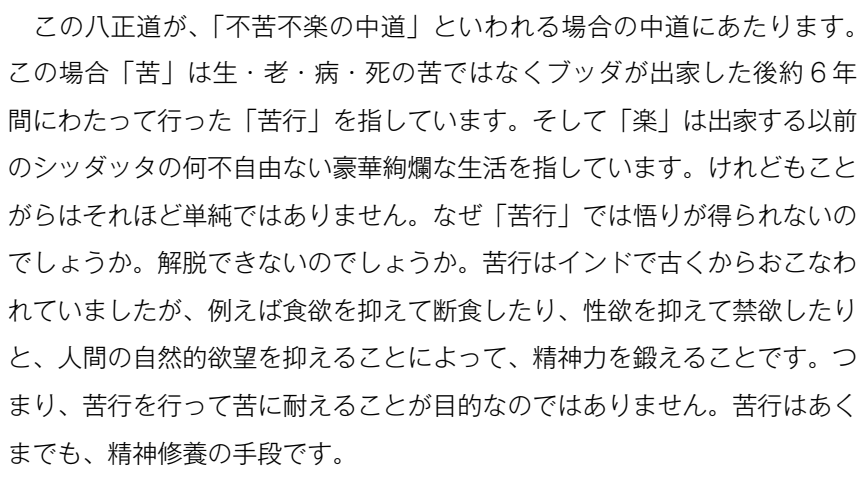
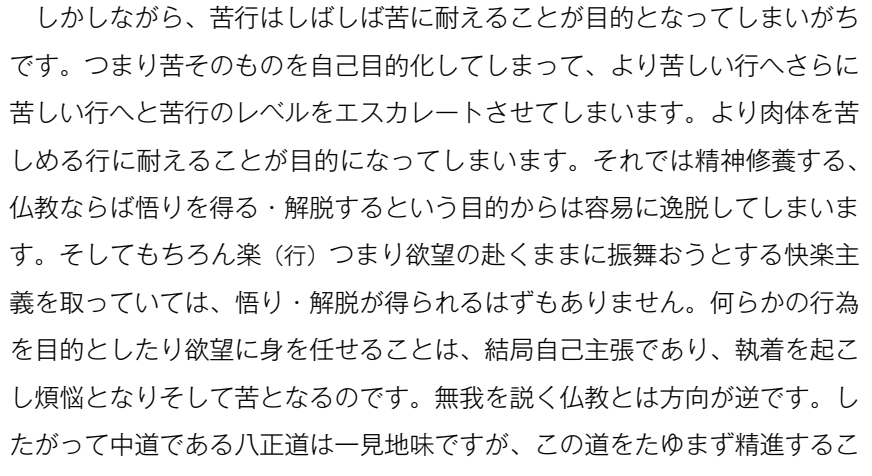
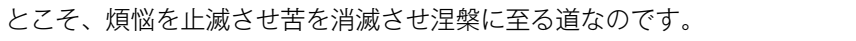
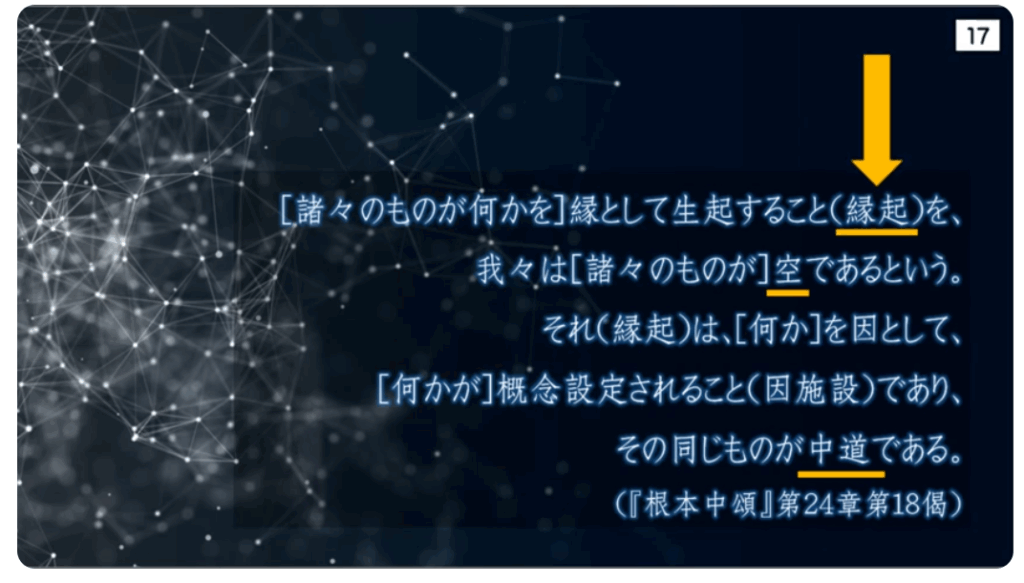
■釈尊の悟り=中道
・両極を排する中道
⇒「有」と「無」のどちらにも実体を見ない
⇒「空の教え」こそが
⇒釈尊の真意である中道
◆縁起による「空の教え」=中道における「空の教え」
・縁起=中道
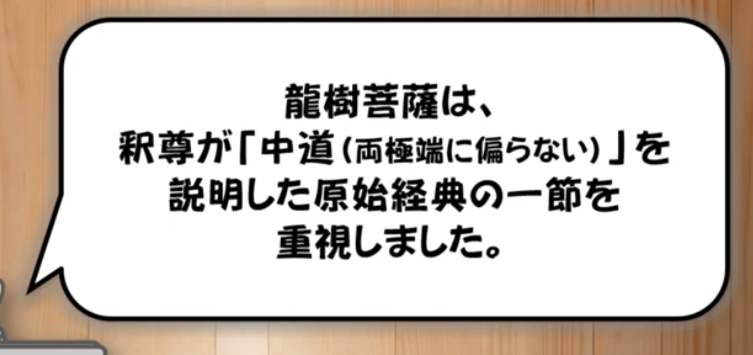
■龍樹が重要視した原始経典の一説
・中道によって法を説くのである
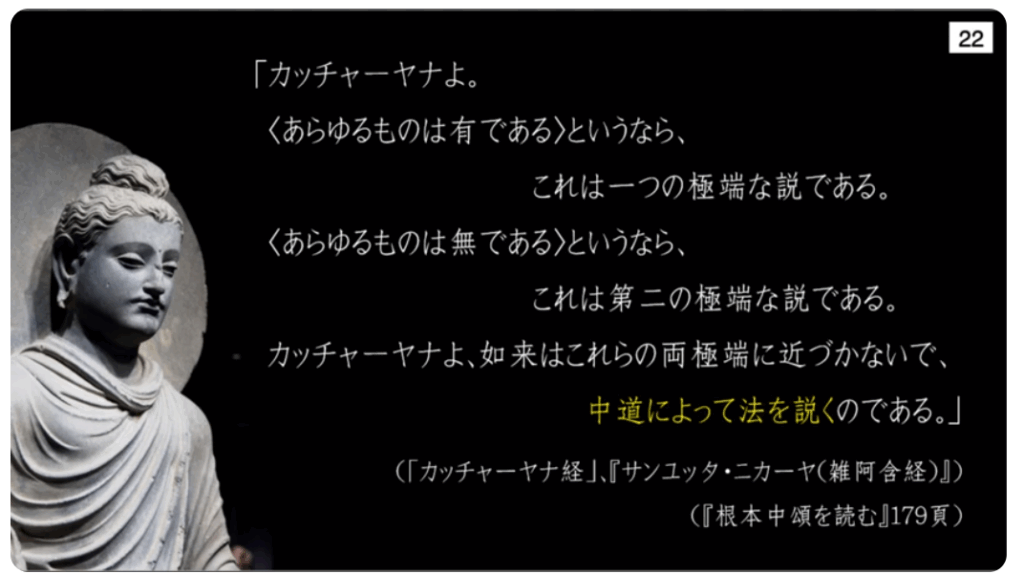
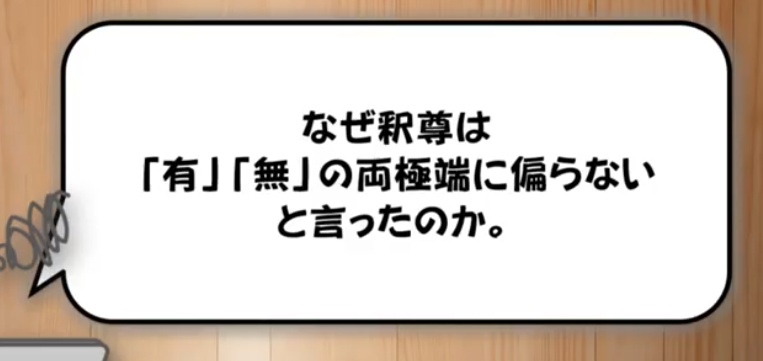
・中道
⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない
⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)
⇒つまり実体がない=空
⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)
⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが
⇒それが中道である
⇒無自性=空
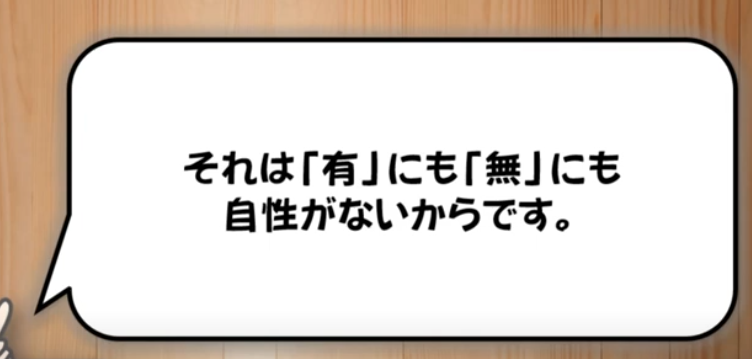
■大乗仏教において慈悲が登場する根拠
・「善」「悪」の両方を包含していくことができる
⇒善人・悪人を救う事ができる悟りの境地
⇒空を根底にしているから
⇒慈悲が可能になる
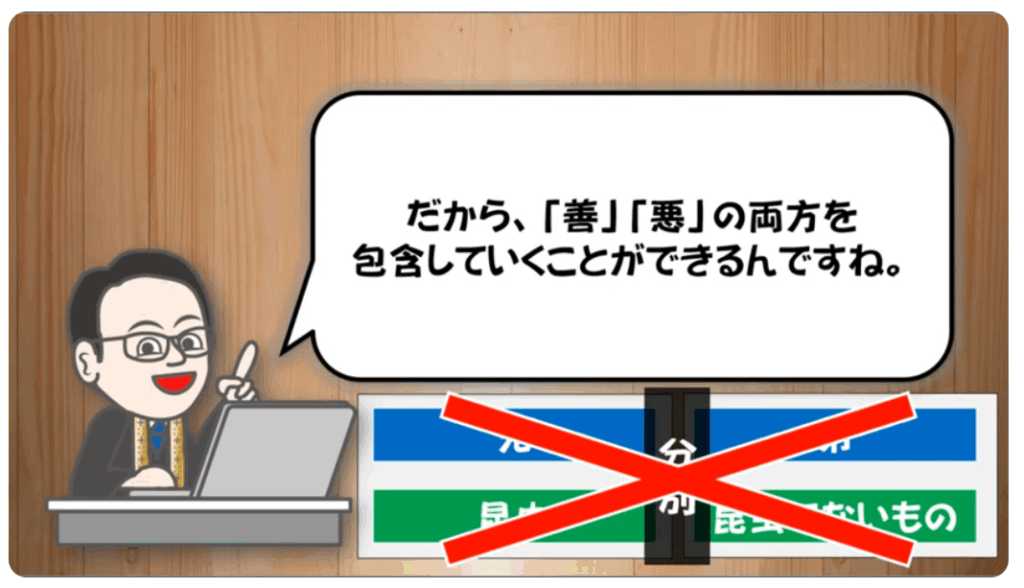
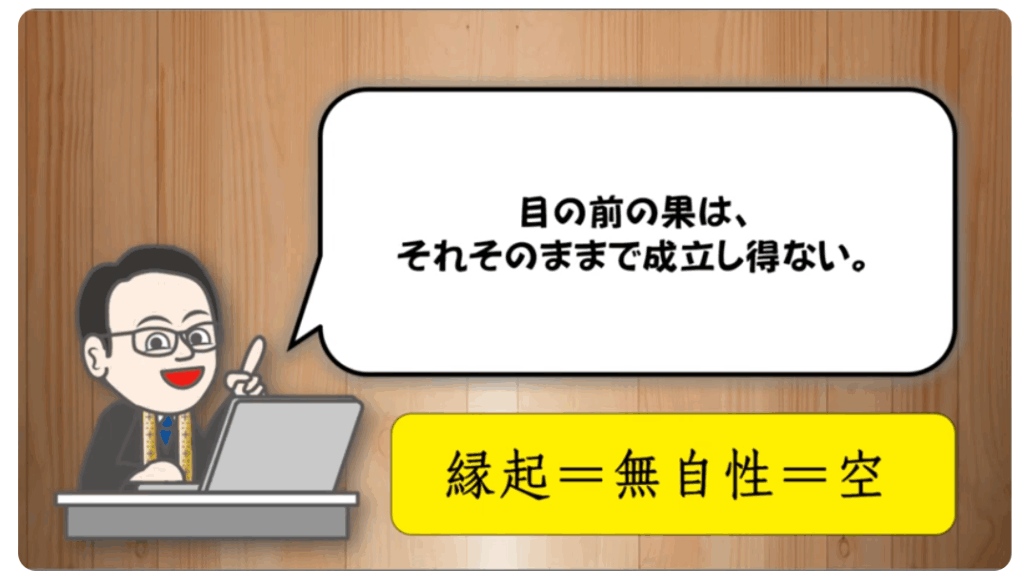
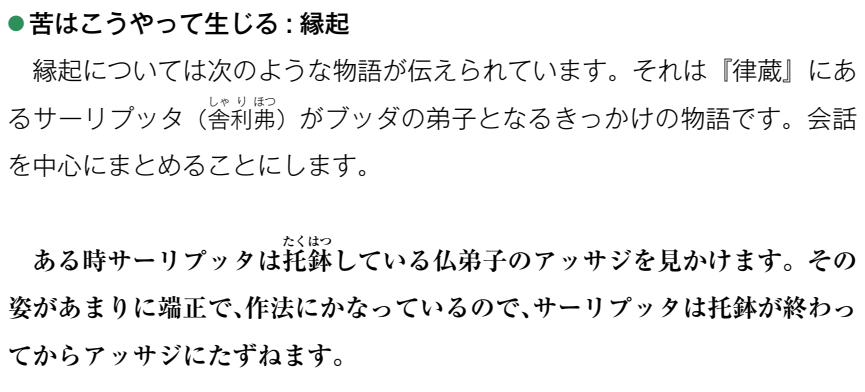
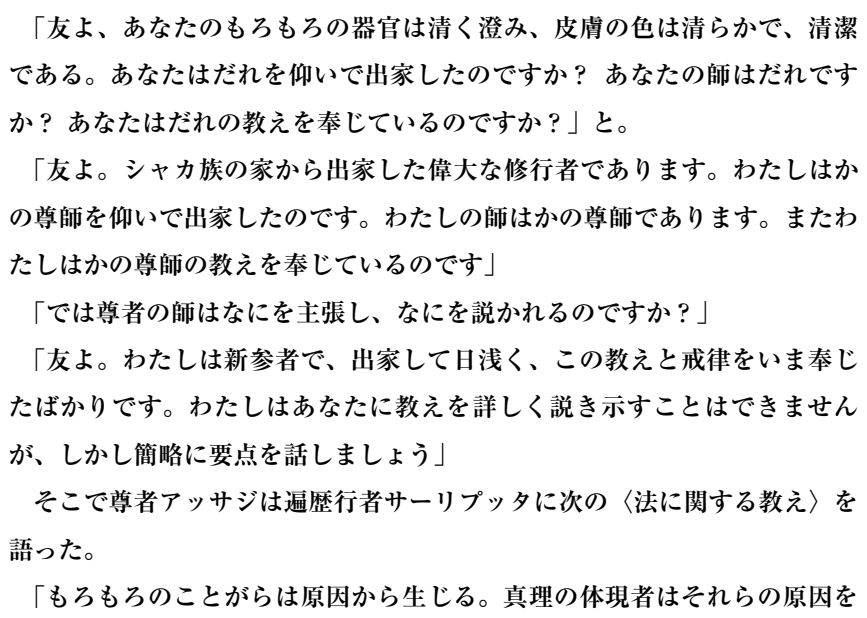
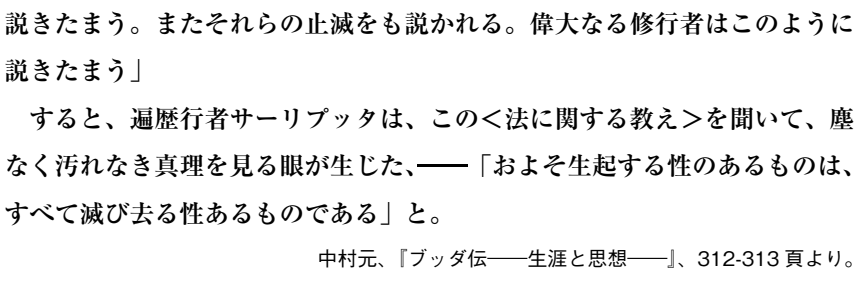
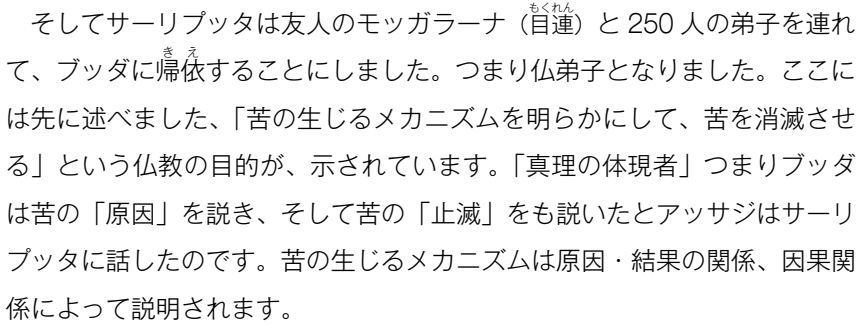
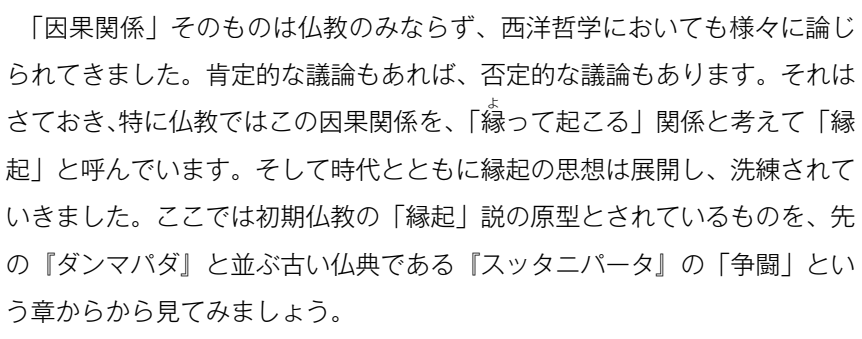
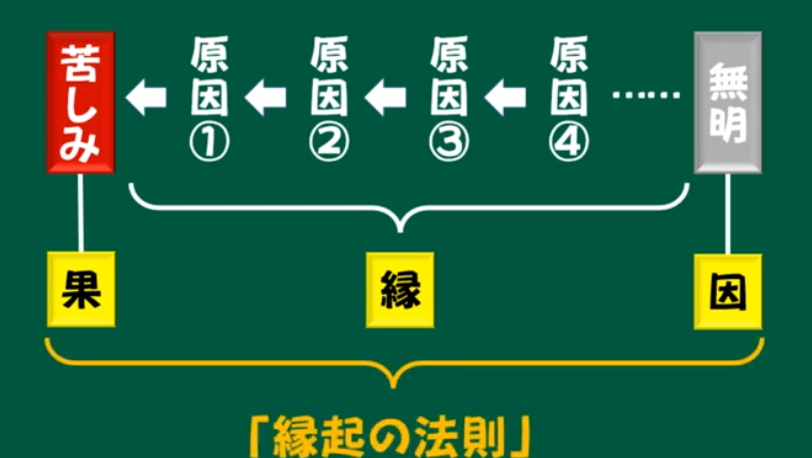
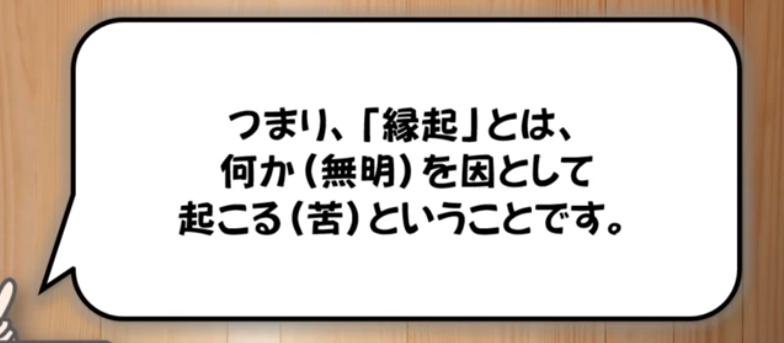
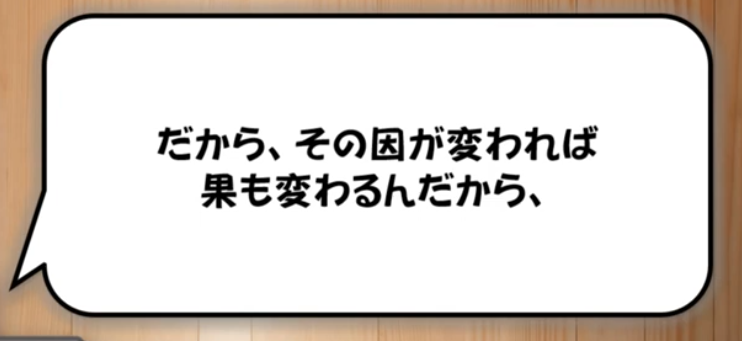
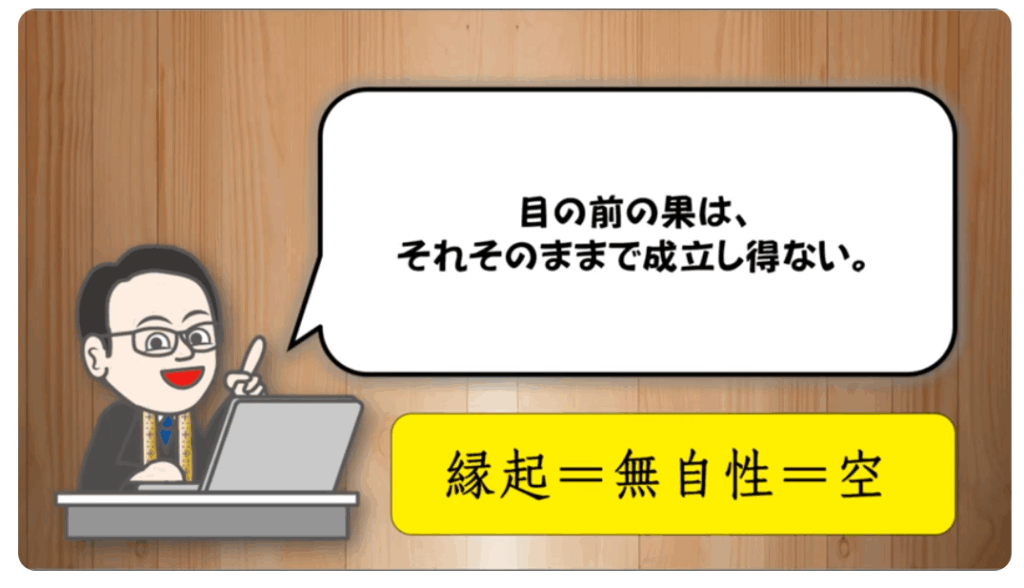
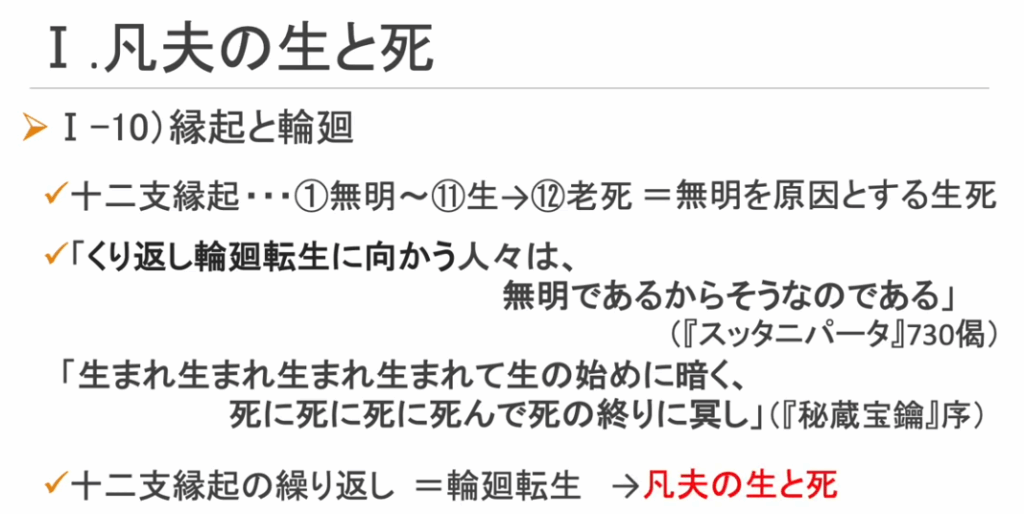
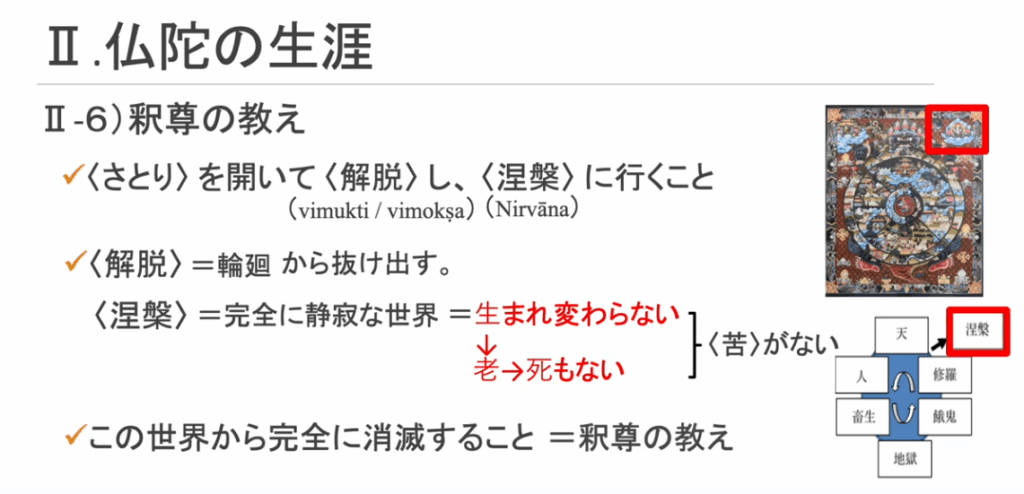
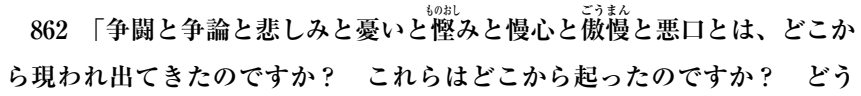
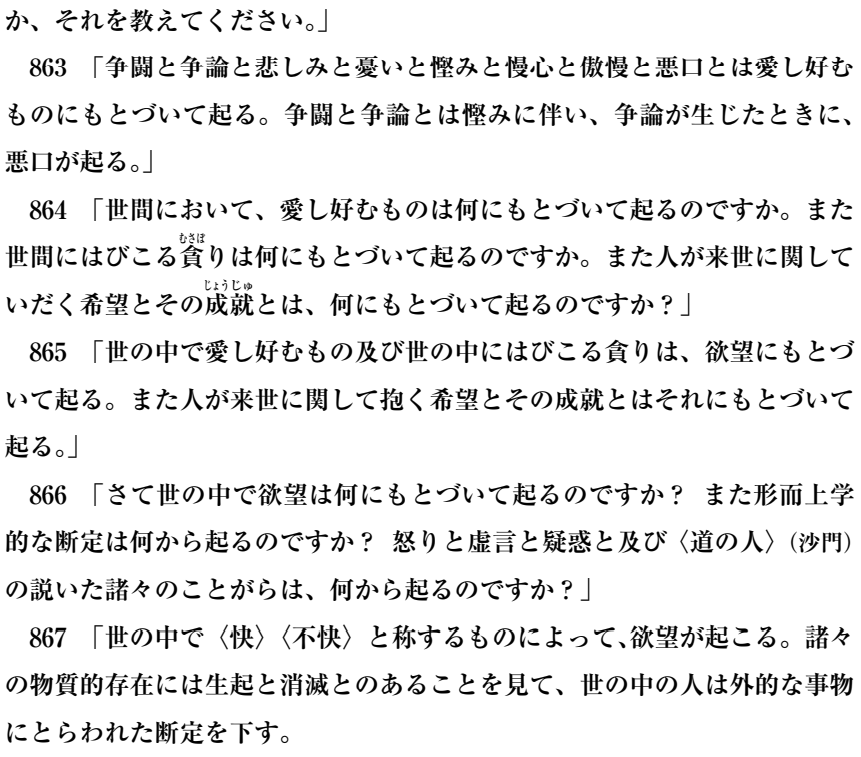
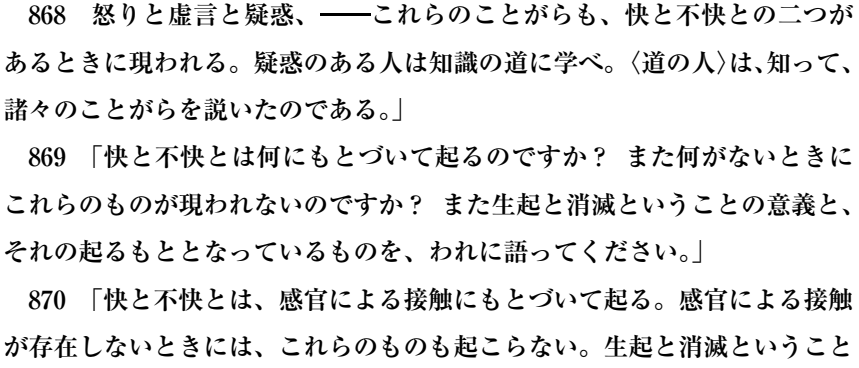
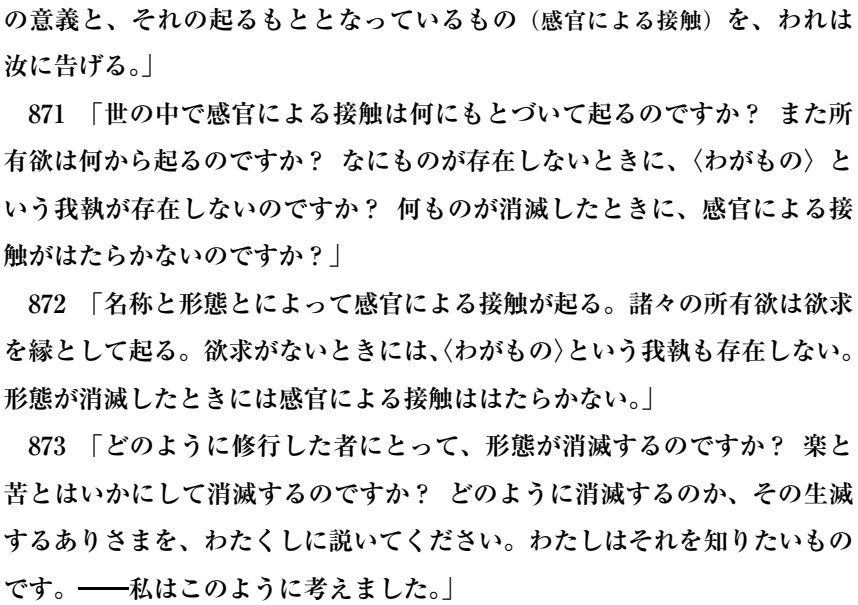
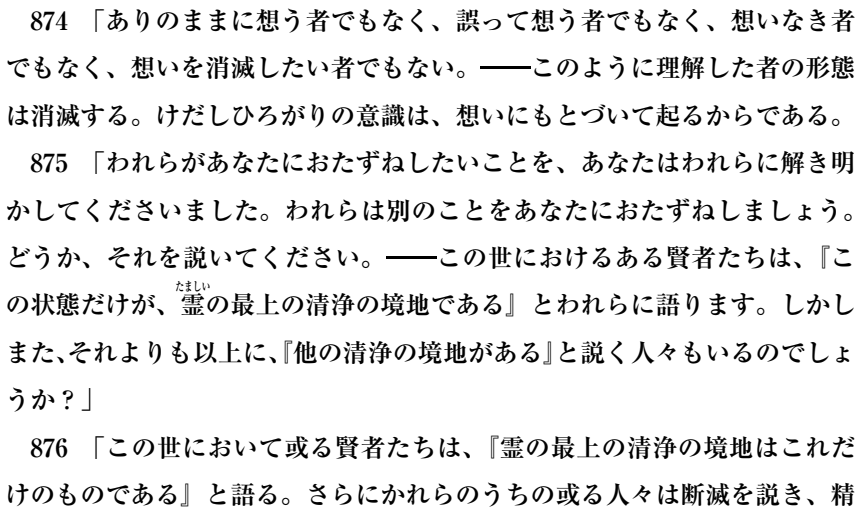
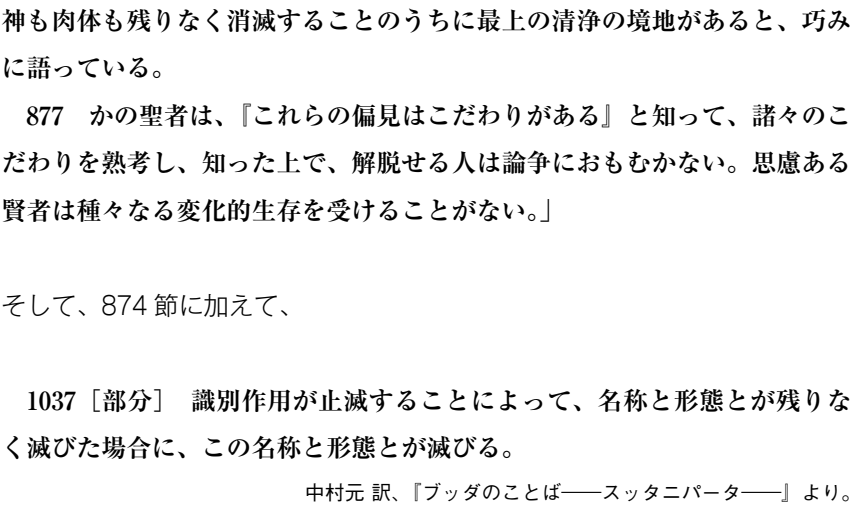
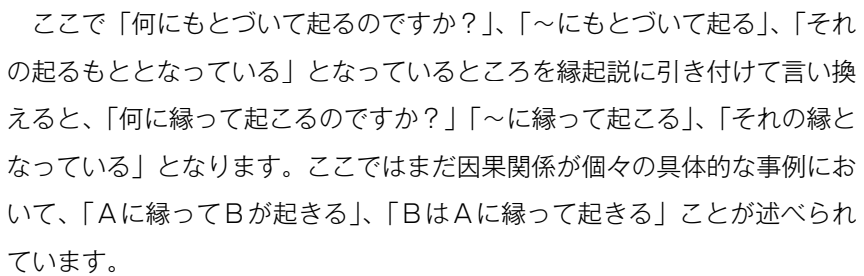
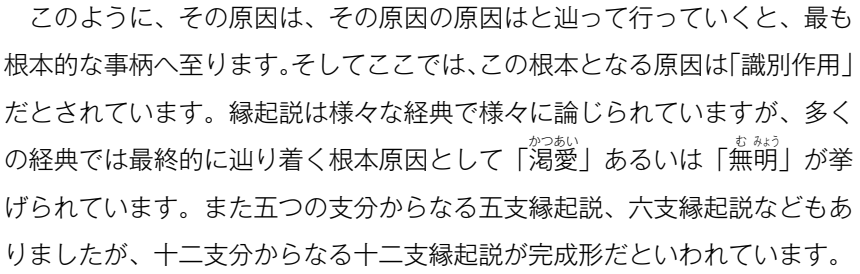
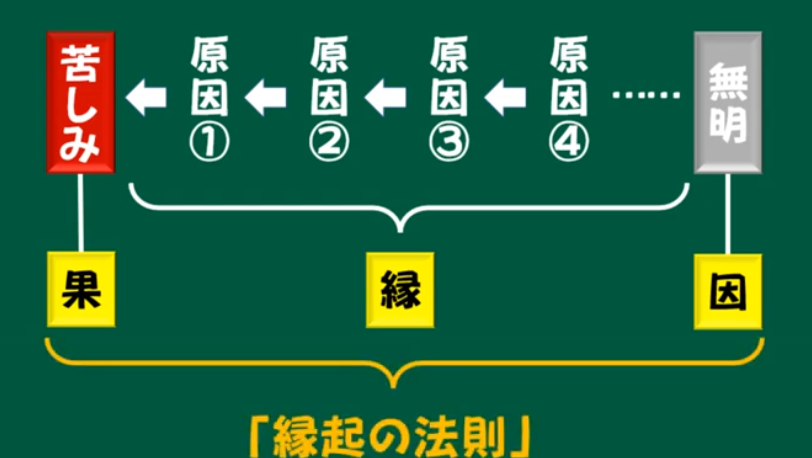
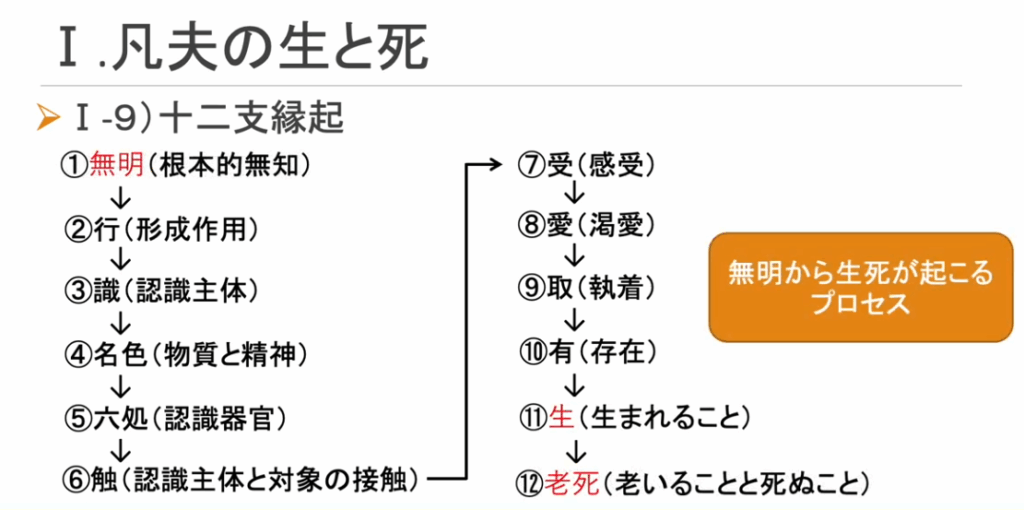
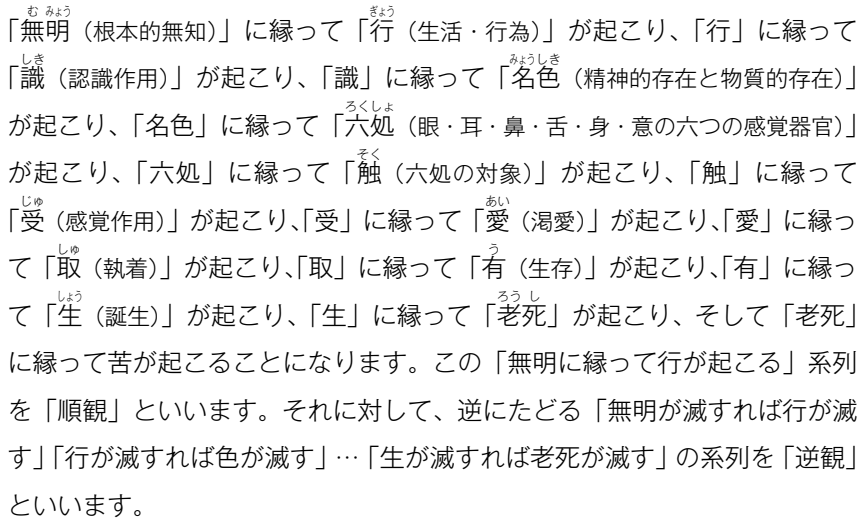
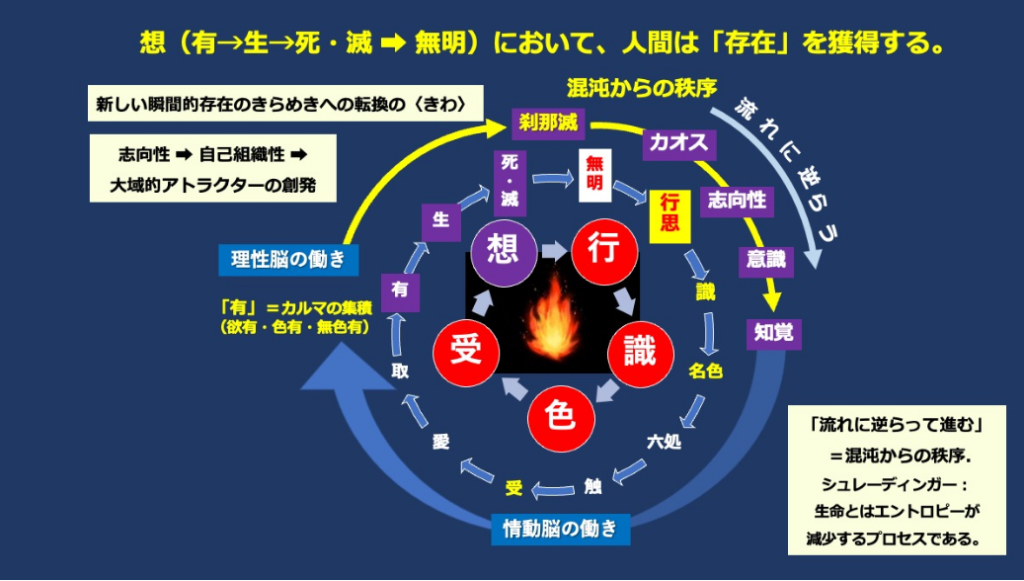
出典:https://www.eel.co.jp/aida/lectures/s4_4/ Season 4 第4講「脳科学×ブッダ」から見えて来たもの 2024.1.13 編集工学研究所