■伝統社会も含めて現代における空間の構造は二元的である
伝統社会における空間の構造は二元的である。現世と他界があり、地上と天上の世界がある。娑婆と極楽といってもよい。二つの世界は表と裏のように背中合わせになっていて、たがいに顔をあわせることができない。二つの世界は断絶しているのである。二つの世界をつなぐ橋はない。
しかし、だからといって二つの世界が永久に断絶したままであったら、そこに住む人間のこころに究極のやすらぎはないであろう。
世界の分裂が人間の分裂をひきおこすからである。そこで人間は何とかして、おのれ自身のうちに、同時に、二つの世界を映そうとする。二つの世界のただなかで一元的に生きようとする。そういう一つのねがい、一つの祈りをもっている。
その点ではキリスト教といい、原始宗教といっても少しも相違はない。人間のこころの出所は一つである。万法帰一である。万教帰一である。(岩田慶治、「カミの人類学――不思議の場所をめぐって」『岩田慶治著作集』3巻、106頁)
■一元的に変換する仕掛けのイメージ(悩みの解消を模索して)
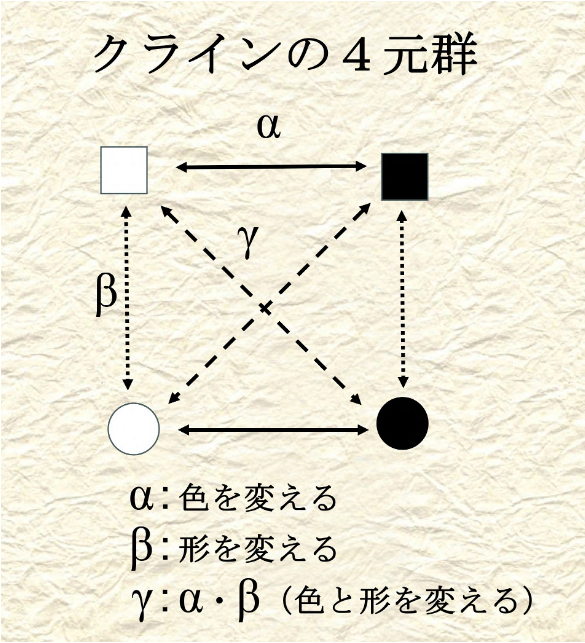
■身近な事例を収集する
◆バブル絶頂期に“苗場の1LDK”を買った〈年収1,200万円〉エリートの後悔。35年後「1円でも買い手はつきません」夢の別荘は“負動産”と化して詰みかけの年金生活
出典:THE GOLO ONLINE編集部 2026.1.30
https://gentosha-go.com/articles/-/75122
バブル絶頂期の当時、年収1,200万円を超えていた元エリート会社員の田中さん(仮名・75歳)は、1990年に苗場のリゾートマンションの一室を3,200万円で現金で一括購入。しかし、年金生活に入った現在、月々4万5,000円の維持費が家計を激しく圧迫しています。老朽化して1円でも売れない「負動産」と化したかつての成功の証が、穏やかに過ごすはずだった老後を奪った事例を紹介します。
かつては成功の象徴だった「苗場のリゾートマンション」
「当時の自分は、人生の勝者だと本気で信じていたんです。でも、誰もいない部屋に毎月4万5,000円。私の老後は、この『負動産』に壊されました」
田中耕作さん(仮名・75歳)は、新潟県・苗場エリアに建つリゾートマンションの一室で、色褪せたソファに腰掛けながら力なく語ります。
田中さんは現役時代、大手電機メーカーの営業部長を務めていました。年収は1,200万円を超え、都内に構えた自宅ローンの返済も順調。将来の役員候補のエリート会社員として、まさに人生の絶頂期にありました。
今から36年前の1990年、そんな彼がバブル絶頂期に手に入れたのが「苗場の別荘」です。
苗場スキー場まで徒歩圏内という一等地にそびえ立ち、館内には豪華な温泉大浴場や本格的なレストランを備えた、当時憧れの的だったリゾートマンション。そのなかでも、家族4人がゆったりと寛げる「55平米の1LDK」という広々とした一室を、3,200万円という今では考えられないような高値で現金一括で購入しました。
「当時は空前のスキーブーム。関越自動車道は大渋滞でしたが、それでも週末になれば家族を連れて、この山へ向かうのが誇らしかった。冬はスキー、夏は涼しい高原でテニス。専業主婦として家を守ってきた妻も『素敵な退職後の住まいができた』と、この華やかな買い物を誰よりも喜んでいました。現役を退いたあとは、ここを拠点に悠々自適な二拠点生活を送る。それが自分たち夫婦への“最高のプレゼント”になるはずだったんです」
管理費・修繕積立金に固定資産税や住民税を合わせた月々約4万5,000円の維持費は、趣味の経費として現役時代には気にも留めない金額でした。
しかし、月々20万円(手取り約17万円)の年金生活に入った今、状況は一変しました。
手取り額の4分の1以上を強制的に飲み込んでいくこの「4万5,000円」という固定費は、一日も滞在しなくとも容赦なく口座から引き落とされます。
かつての「成功の象徴」は、今や彼の老後をじわじわと蝕む負動産へと姿を変えていました。
年金の4分の1を削り取る「年間54万円の呪縛」
「滞在していなくても、毎月4万5,000円が引き落とされる。ここへ来るたびに高速代やガソリン代を計算してしまい、ちっとも楽しくないんです」
田中さんの手取り17万円に加え、妻の年金を合わせても、世帯の受取額は月23万円ほど。そこから別荘の維持費を引けば、手元に残るのは18万円強です。そこからさらに都内の自宅の固定資産税や夫婦の医療費を支払えば、家計の余裕はほとんどありません。
さらに、かつて成功の象徴だったリゾートマンションは、静かに崩壊していました。 立体駐車場は故障したまま放置され、エントランスにはカビ臭い空気が漂っています。
「昔は避暑地として最高でしたが、今は窓を開けても不快な熱気がこもるだけ。古い設計でエアコンもつけられず、ただじっと耐えるしかありません」
生活の足も、75歳の身体には重くのしかかります。 近隣の個人商店は軒並みシャッターを下ろし、食料品の買い出しには車で30分かけて越後湯沢の市街地まで山道を下らなければなりません。
「30年以上の思い出はあります。でも、死ぬまで続く年間54万円の支払いや、この不便な暮らしがその代償だなんて。夢の終わりが、こんなに惨めだとは思わなかった……」
手放したくても手放せない「負動産」
妻からは、顔を合わせるたびに「もう手放して。誰かに譲って」と懇願されています。
しかし、どれほど手放したくとも、もはや出口は見つかりません。仲介業者に相談した際、担当者は冷淡にこう告げました。
「田中さん、正直にいいますよ。ここは1円でも買い手はつきません。むしろ、今すぐ手放したいなら、処分費用としてあなた自身が数十万円を支払う必要がある。それくらい、今の苗場は厳しいんです」
かつて「資産」と呼んでいた55平米の空間は、今やマイナスの価値しか持たない厄介者となりました。管理組合は滞納者であふれ、修繕の目処も立たないまま、建物の資産価値はゼロに向かって突き進んでいます。
「全盛期の自分の判断を、今の自分が否定し続ける。これほど惨めなことはありません。この支払いを抱えたまま、残りの人生を過ごしていくしかないのでしょうか」
田中さんの手元に残ったのは、もはや誰も羨まない古びた鍵の束と、終わりの見えない維持費の請求書だけ。かつての「夢の別荘」は、今や穏やかな老後を脅かす、重い負担へと姿を変えています。
リゾートマンションに潜む「所有の罠」
田中さんのように、かつての「夢」が老後の家計を圧迫する「負動産」と化すケースは、決して他人事ではありません。バブル期にリゾート物件を購入した多くの世代が、同様の現実に直面しています。
国土交通省が2024年に公表した「令和5年度 マンション総合調査」によれば、築30年超の物件では修繕積立金の不足や滞納が深刻化しています。特に共用施設が豪華なリゾートマンションは維持費が高額になりやすく、たとえば年間30万円の維持費を要する物件であれば、30年間で計900万円もの固定費が家計を圧迫します。買い手にとっては「資産」よりも「将来の支払い義務」という負担が勝るため、1円でも売れない「資産価値の逆転」が起きています。
さらに、2023年に開始された相続した不要な土地を一定の条件で国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」も、建物がある土地やマンションの区分所有権は対象外です。不用品のように「廃棄」することができず、手放せないまま管理費を払い続けるしかありません。
物件ごとに異なる「維持費の不透明さ」と「出口のなさ」が、老後資金を枯渇させる致命的なリスクとなっています。
■ChatGPTサム・アルトマンが警告「一部投資家は大金失う」AIバブルの”理性なき崩壊”はすぐそこだ…95%は未だリターンなし
出典:MINKABUマガジン 2025.10.19
https://mag.minkabu.jp/politics-economy/36890/?membership=1
市場は実体より資本の流れに敏感だーーその前提に立てば、足元は「AIバブル」とみる見方が優勢である。メガテックのデータセンター投資は桁違いに拡大し、他方で企業のAI導入は収益化が遅れ、機関投資家は「AI株のバブル」かつ「最大のテールリスク」と判断を強めている。技術が本物でも、制度設計が遅れれば価格は物語に先導されやすい。歴史の力学(過剰投資、崩壊、制度整備、黄金期)を踏まえ、何を先に整えるべきか。その本質と実務的含意を、日経新聞編集委員・小平龍四郎氏が分析するーー。
目次
- 生成AI関連株高は「プラザ合意型バブル」の再演か
- 危機は機会に反転──現地生産・買収・再編が一気に進行
- 証券が生んだ「ウォーターフロント相場」──臨海再開発の幻想
- 制度の不在が熱狂を許した…バブルは「人災」だった
- 「一部の投資家は大金を失う」現場トップも認める過熱リスク
- 制度が追いつかなければ、行き着く先は「理性なき崩壊」
- 歴史は韻を踏むのかーーAIバブルと1985年の残響
生成AI関連株高は「プラザ合意型バブル」の再演か
1985年9月22日、ニューヨークのプラザホテル。先進5カ国(G5)の蔵相と中央銀行総裁が顔をそろえ、ドル高是正のための協調介入に合意した。いわゆる「プラザ合意」である。米国の巨額な経常赤字、貿易不均衡、金利格差が世界経済の歪みを生み、通貨秩序を立て直すために結ばれた国際的な合意だった。
だがこの一日は、日本経済にとって単なる為替政策の転換点ではなかった。後に「バブル経済」と呼ばれる資産価格の狂騰の起点であり、制度の未整備な資本市場がいかに熱狂を生み出すかを示す実験でもあった。市場に理性を求めても、それを支える制度がなければ、流動性は「物語」と結びつき、容易に肥大化する。40年後の今日、AIという新たな技術革命の下で、世界は同じ構図を再演しようとしている。
危機は機会に反転──現地生産・買収・再編が一気に進行
1985年9月22日、ニューヨークのプラザホテル。先進5カ国(G5)の蔵相と中央銀行総裁が顔をそろえ、ドル高是正のための協調介入に合意した。いわゆる「プラザ合意」である。米国の巨額な経常赤字、貿易不均衡、金利格差が世界経済の歪みを生み、通貨秩序を立て直すために結ばれた国際的な合意だった。
だがこの一日は、日本経済にとって単なる為替政策の転換点ではなかった。後に「バブル経済」と呼ばれる資産価格の狂騰の起点であり、制度の未整備な資本市場がいかに熱狂を生み出すかを示す実験でもあった。市場に理性を求めても、それを支える制度がなければ、流動性は「物語」と結びつき、容易に肥大化する。40年後の今日、AIという新たな技術革命の下で、世界は同じ構図を再演しようとしている。
危機は機会に反転──現地生産・買収・再編が一気に進行
プラザ合意以前、1ドル=240円台だった為替は、1年あまりで150円台にまで急騰。円高は輸出企業の採算を直撃し、トヨタや松下電器、川崎製鉄など、戦後日本を支えた輸出主導型の産業構造が根底から揺らいだ。
しかし企業は、この危機をむしろ機会に変えようとした。現地生産への転換、海外企業の買収、事業再編と人員整理。こうしたリストラクチャリングが「円高に勝つ経営改革」というストーリーを市場に供給した。投資家はそれを未来の成長物語として受け止め、株価はうなぎ登りとなる。
1985年9月の日経平均1万2733円は、1989年末には3万8915円に達した。わずか4年で3倍である。PERは50倍、PBRは4倍を超え、常識的な企業価値評価の範疇を超えていた。だが「成長ストーリー」があれば、どんな価格にも理屈をつけられた。理性が熱狂の手先になったのである。
証券が生んだ「ウォーターフロント相場」──臨海再開発の幻想
1988年、日本証券経済研究所がまとめた「株価水準研究グループ報告書」は、日本株はまだ割安だと主張した。理由は、大企業が抱える不動産などの含み益を反映していないから。東京大学の経済学者や大手証券エコノミストが名を連ねたこの報告書は、「トービンのQ(Qレシオ)」を日本的に再解釈し、資産再調達価格に照らせば株価の上昇余地は大きいと説いた。
同じ時期に証券会社が打ち出したのが「ウォーターフロント相場」だった。臨海部に工場を持つ重厚長大産業が、再開発を通じて都市型企業に変貌するという幻想である。
川崎製鉄の八木靖浩社長は株価が1000円を突破した際にこう語った。「血みどろの努力でリストラを進め、ようやく株価も世間並みに。土地に担保力があるし、自社ビルでも持っていたらもっと評価されたかもしれないね」(日経産業新聞、1988年10月26日付)
企業努力と土地神話が混然一体となり、資産価値の膨張が「成長の証拠」と錯覚された。市場の熱狂には、常に「根拠らしきもの」がある。そしてその根拠は、後から制度が否定するしかなくなる。
制度の不在が熱狂を許した…バブルは「人災」だった
この時期、日本の株式市場の規模は世界最大級に膨らんでいた。だが、市場を監視し透明性を担保する法制度は驚くほど遅れていた。
本格的なインサイダー取引規制が導入されたのは1989年4月、株価がすでに頂点を迎えていた頃だ。大量保有報告制度(5%ルール)の導入は1990年、証券取引等監視委員会の設立は1992年。いずれも熱狂の後始末に過ぎなかった。
野村証券元副社長の橘田喜和氏はこう回想する。「日本の市場は巨大だったが制度は新興国並みだった。熱狂を抑える仕組みが存在しなかった」。バブルは自然現象ではなく、制度の不在という人災だった。
そして今、舞台は通貨市場からテクノロジー市場へと移った。AI(人工知能)という「汎用技術」をめぐり、巨額のマネーが渦を巻いている。
この点で、8月21日に英フィナンシャル・タイムズのイノベーション・エディター、ジョン・ソーンヒル氏が発表した論考「AI黄金時代の前に訪れる危機に備えよ」(“Brace for a crash before the golden age of AI”)は示唆に富む。以下、要約、引用する。
「一部の投資家は大金を失う」現場トップも認める過熱リスク
*****
米グーグル、アマゾン、マイクロソフト、メタの4社だけで、2025~26年の2年間にAI向けデータセンターへ計7500億ドル(約110兆円)を投じる計画だ。モルガン・スタンレーは、世界全体のAIインフラ投資が2029年までに3兆ドルに達すると予測している。
だが、その投資は本当に回収できるのか。マサチューセッツ工科大学(MIT)の報告書によれば、AI関連投資を行った企業の95%が、いまだリターンを得られていない。オープンAIのサム・アルトマンCEOも「一部の投資家は大金を失うだろう」と述べ、AIバブルのリスクを暗に認めている。
経済史家カルロタ・ペレスは『技術革命と金融資本』( Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages)で、18世紀以降の5つの技術革命がすべて「過剰投資→バブル→崩壊→制度整備→黄金時代」というサイクルを繰り返してきたと説く。AIはIT革命に続くものであり、現在は「バブル→制度未整備→不安定化」の最中にある。
「暴落なしに黄金時代を迎えるのを見たことがない。金融市場が機能不全に陥っている以上、AIバブルの崩壊はさらに大きな混乱を引き起こすだろう」。ペレス氏はソーンヒル氏にこともなげに語ったという。
AI革命の特徴は、鉄道や電力のような「物理インフラ」ではなく、ソフトウエアとデータが中心にあることだ。ネットワーク効果によって一気にスケールし、法制度や規制が追いつく暇もない。ChatGPTは公開から3年足らずで週7億人のユーザーを獲得し、AIモデルの高度化は国家主導でも追いつけないスピードで進んでいる。
そして今、そのスピードは地政学の領域すら揺さぶる。中国発の低価格AIモデル「DeepSeek」が登場した途端、米国市場では投資家心理が冷え込み、ハイテク株が大きく調整した。
ペレスは言う。「革命を社会の利益にするには、市民社会が制度によってそれを形づくらねばならない」。19世紀の独占資本には反トラスト法、20世紀の大量生産社会には社会保障と労働規制が整備された。AI時代にも、アルゴリズムの透明性、データの所有権、そして国家と企業の責任分担を明確にする制度が求められている。
***
制度が追いつかなければ、行き着く先は「理性なき崩壊」
現場の投資家も、このリスクを肌で感じ始めている。
バンク・オブ・アメリカ(BofA)が2025年10月に公表したグローバル機関投資家調査(3~9日実施)によれば、投資家は一段と強気に傾く一方で、AI関連株に対して「バブル期にある」との見方が過去最高の54%に達した。世界の株式全体が割高とする回答も記録を更新した。
「AI株のバブル」が「テールリスク(想定外の大きな下振れ要因)」とされた割合は33%と、インフレ再燃やFRBの独立性喪失を上回って初の1位となった。実際、AI企業を中心としたハイテク株に集中投資が続く中、ちょっとした悪材料で数兆ドルが吹き飛ぶ脆弱な相場構造が露呈しつつある。
2020年代のAIバブルも、同じ轍を踏む危険をはらむ。もし制度の整備が追いつかず、倫理と公共性のない資本の暴走が続けば、その果てにあるのは再び「理性なき崩壊」である。
歴史は韻を踏むのかーーAIバブルと1985年の残響
現下の米株式市場は自国第一主義のトランプ大統領の言動に振り回されるばかりで、新しい現実への制度面での備えは覚束ない。その混乱の外縁にある日本も政治的な安定性を大きく欠き、金融市場への目配りは不十分と言わざるをえない。
1985年のプラザ合意は、通貨秩序を整えるはずだった。だが制度なき株式市場に資金が集中し、日本経済はバブルと崩壊を体験した。もし歴史がまた韻を踏むのならば、AIバブルの帰結は、40年前の日本が体験した「制度なき繁栄」の再演になるかもしれない。
市場が再び「根拠ある熱狂」に支配される前に、我々は問い直さねばならない。制度とは何か。理性とは何か。そして、誰がそれを築くのか。そうでなければ、私たちは熱狂の迷宮から抜け出すことはできない。